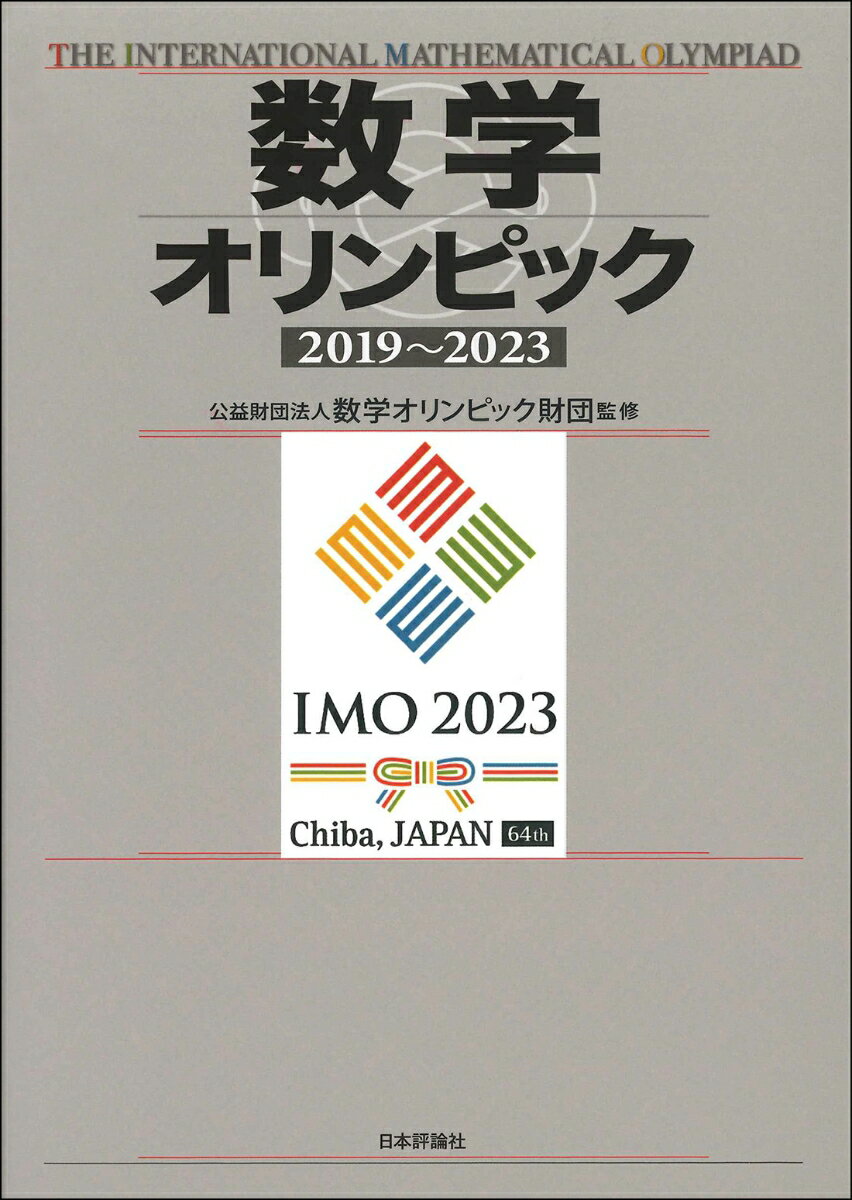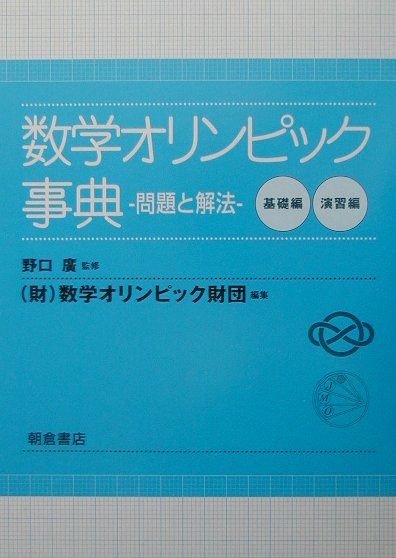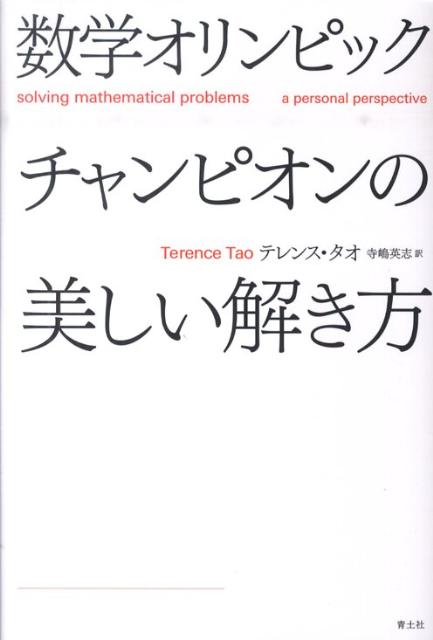今回は、日本数学オリンピック2016年予選第5問を取り上げ、解説します。
面積が等しいという条件があるときに、面積の差が0と読み替えて、面積の差を求める手法を利用するのは、中学入試問題を解く際によくあることです。
この問題は面積が等しいという条件はありませんが、合同な図形→面積が等しい→面積が0という発想ができれば、小学生でも容易に解くことができるでしょう。
なお、合同な図形という条件がなくても、自分で面積が等しい図形を見つけて、上の流れの発想をすることも可能な場合もあります(東海中学校2008年算数第9問の(解答・解説)の(解法2)などを参照)。
この東海中学校の問題の場合、(解法2)で解くよりも(解法1)で解くほうが楽だと思いますが、最難関中学校の受験生であれば、(解法2)のような解法もマスターしておいてほしいと考えてあえてやっているわけです。
さて、JMOの問題を解いてみましょう。
若干図がかきにくいので、とりあえず適当な図をかいて、その後調整すればよいでしょう。

合同な三角形があるので、等しい辺の長さと等しい角の大きさをチェックします。
三角形ABCと三角形APDは頂角が等しい二等辺三角形となり、相似(相似比はAB:AP(AD)=20:16=5:4)となるから、面積比は(5×5):(4×4)=25:16となります。
三角形APDの面積が28だから、三角形ABCの面積は28×25/16=175/4となります。
図のようにそれぞれの部分の面積をア、イ、ウ、エ、オとします。
ウ=28、ア+エ=175/4ですね。
三角形ABPと三角形ACDが合同だから、
ア+イ=イ+ウ+オ
ア=ウ+オ (イを取り除きました。)
ア+エ=ウ+オ+エ (エをつけたしました。)
したがって、三角形BCPの面積(エ+オ)は
175/4-28
=63/4
となります。
若干答えが汚い数値になりましたね。
JMOの出題者なら、きれいな数値となるように当然コントロールできるはずですが、20、16、28という数値を使いたかったのでしょうね。
この問題が出されたのが西暦2016年、言い換えれば平成28年ですからね。
灘中が同じようなことを時々やっていますね(灘中学校2017年算数1日目第1問、灘中学校2019年算数1日目第1問など)。
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策ならプロ家庭教師のPTへ
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策のお申込み・ご相談