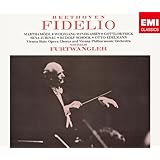(写真左がSHM-SACD/UCGG-9021、右がESOTERIC盤/ESSG-90053)
なぜ、同じ音源から異なるマスタリングで二社から発売になったんでしょうか?
某オーディオ・ショップで、「ESOTERICから聞いた話では・・・・」と語る店員さんがいましたが、真偽のほどは定かではありません。従って、ここではその話題には触れないことにします。
このブラームスの交響曲第1番は、古くから名演と定評のある演奏ですので、演奏については簡単に感想を書いてみます。
ベーム指揮のブラ1と言えば、1975年5月に録音されたウィーン・フィルとの演奏が有名です。このベルリン・フィルとのブラ1は1956年に録音された交響曲だ2番ニ長調に続く、ベーム/ベルリン・フィルのブラームスでした。交響曲第2番は録音があまりさえない事もあってか、最近では話題になりませんが、1959年録音の交響曲第1番はウィーン・フィルとの1975年録音よりも筋肉質のドイツ音楽を体現していると言われています。
今回発売された2種類のSACDですが、どちらも既存のCDと比べれば音質の改善効果は大きいと断言してよいでしょう。ただし、再生した印象は多少異なりますし、リスナーによって好みが分かれる音です。
まず、ESOTERIC盤ですが、ピラミッド・バランスをうまく再現したようなマスタリングがされています。高域(ヴァイオリンなど)は鮮明度を失わない程度に適度な木鳴りを感じる様なサウンドに仕上がっています。
一方、ユニヴァーサルミュージック盤はワイドレンジを感じさせる音響空間の広さとストレートさが特色です。ぱっと聴いた感じではESOTERIC盤よりも硬めの音に聴こえます。
おそらく、ディスクをぱっと再生した感じではESOTERIC盤がウェルバランスに聴こえるでしょう。しかし、これがイエス・キリスト教会でのベルリン・フィルの音か?というと少し違うような気がします。ダーレムのイエス・キリスト教会は全面石造りの教会で、透明感がある音響が高い評価を受けていました。1960年前後のカール・ベームはまさに全盛期、長年の職人芸で築き上げた重厚かつ引き締まった硬質な力強い表現が特色でした。ESOTERIC盤では、イエス・キリスト教会が木造の教会に化けてしまったような印象です。
ユニヴァーサルミュージック盤では高域にやや刺激的な部分もありますが、おそらくこれがマスター・テープに入っていた音に近いものだと思います。
つまり、作り物だけれどバランスよく仕上げたESOTERIC盤、再生機器などの調整が必要になることがあるがオリジナルに近い(と思う)ユニヴァーサル盤、といった違いになると思います。