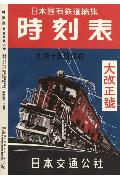https://ameblo.jp/pon-chape/entry-12834577450.html
2024年1月1日にアップしましたこちらの記事について訂正と補足です。
記事内で日ノ出駅が仮乗降場だった時代の時刻表が復刻版の対象から漏れているので仮乗降場時代のダイヤの情報がつかみにくいという旨の記述をしましたが、冒頭にリンクを張った商品、JTBの「時刻表復刻版 戦後編 5」というセットに昭和23(1948)年から30(1955)年までの計6冊が収録されていることが分かり、早速取り寄せてみました。
私の商品のリサーチ不足はお恥ずかしい限りです。
お詫びして訂正致します。
件の復刻版は2002年に初版が発行されたものですが、2024年現在でも入手可能なようです。
この年代の時刻表はさすがに貴重で、復刻版で発行されていることは非常に有り難いところです。
それもほぼ毎年分が収録されているのは資料的価値が高いと思われます。
というのも、日ノ出駅だけに留まらず、昭和20年代に開設された仮乗降場は早い時期に正駅に昇格したものが多く、さらにこの時代の北海道内版の時刻表がほとんど出回っていないので、それらの実態を探るには当時の全国版の時刻表が数少ない手がかりとなるためです。
同じくJTB刊の「停車場変遷大辞典」巻末によると、昭和24年5月、24年7月、26年10月号はJTB出版事業局にも残っていないそうで、「停車場変遷大辞典」巻末の「時刻表に見る 国鉄時代の臨時駅」を執筆された水谷昌義氏は交通博物館(当時)所蔵の同月号を参照されたと記されています。
ともあれ、昭和20年代の時刻表というのはそれほど貴重なもので、これが一部でも復刻版として我々一般人にも比較的手軽に見られるようになったということがいかに大きな一歩かということがお分かり頂けたら嬉しいです。
今回の日ノ出駅についても、昭和22年仮乗降場として開設、昭和25年正駅化という、仮乗降場時代が短くしかも古い時代というケースでは、資料がどうしても少ないので、全国版時刻表があるのとないのとでは雲泥の差です。
のちに池北線となった区間については、昭和20年代(1945〜54年)に設置されたと考えられる仮乗降場として、
・様舞(さままい)
・愛冠(あいかっぷ)
・笹森(ささもり)
・釧北(せんぽく)
・日ノ出(ひので)
・北光社(ほっこうしゃ)
があります。
加えて、豊住、西富、広郷が昭和30(1955)年、西訓子府が昭和31(1956)年、穂波が昭和32(1957)年に仮乗降場として開設されているということで、しかもこれらの大部分が昭和34(1959)年までに正駅に昇格しています。
笹森のみ国鉄民営化まで仮乗降場のまま、そして昭和43(1968)年に大森仮乗降場が新たに加わっています。
釧北は開設期日ははっきりと分かっていませんが、昭和32(1957)年に一応は正式に廃止されたことにはなっていますので、昭和20年代の開設の可能性が高いかと思われます。
昭和32年の廃止以後もしばらくは利用者がいれば乗り降りができるという取り扱いになっていたらしく、実態としての廃止がいつなのか、あるいは胆振線尾路園のように自然消滅したのか、よく分かりません。
さてここから本題となりますが、日ノ出仮乗降場はどのような停車パターンでしたでしょうか?
まずこの「時刻表復刻版 戦後編 5」の中で最も古い号、昭和23年7月号から見てみます。
昭和23(1948)年7月1日に網走本線の池田〜網走間(のちに池田〜北見間は池北線、北見〜網走間は石北本線に編入)ではダイヤの改正が行われており、この号はそのダイヤを掲載しています。
日ノ出仮乗降場は驚くことに巻頭の索引地図にも掲載されており、もちろん本文中にも掲載があります。
また仮乗降場であることを匂わせる(乗)(臨)(仮)などの付記もなく、他の正駅と同等の表記方となっています(ただしキロ程が空欄になっているので、分かる人には分かります)。
停車列車ですが、この区間を走行する4往復の普通列車の全てが停車ということになっています。
網走本線として池田〜北見〜網走が一体となった時刻表になっていますが、北見を超えて走破する列車はなく、日ノ出仮乗降場について見ると、池田〜北見間の運用がほとんどで、1往復だけ置戸〜北見間の区間列車があります。
このあたりは以前の記事でご紹介した正駅化後のダイヤと大きな違いはないですね。
ちなみに北見〜網走間の列車は北見から石北線(当時は新旭川〜北見間を指す路線名)に直通するものが多く、旭川、上川ないし小樽発着という列車が設定されていました。
また、この網走本線の時刻表には日ノ出のほか、愛冠、旭野(正駅化に際して西女満別に改称)の2か所の仮乗降場が索引地図にも時刻表本文にも掲載されていました。
様舞仮乗降場は未開業、笹森仮乗降場はこの翌月の開業、釧北仮乗降場もおそらく未開業(運転時刻表中には釧北線路班の記載があり、旅客扱いのための停車列車が定められていましたが、線路班表記なので、仮乗降場としては未開業と推定)で、昭和23年5月(日付は不詳)に開設されたとされる北光社仮乗降場だけが非掲載でした。
その北光社ですが、続く昭和24年9月号でも非掲載のままである一方、日ノ出、愛冠、旭野の3仮乗降場は変わらずに掲載されています。
日ノ出仮乗降場については置戸〜北見間の区間列車が1日2往復に増え、計5往復が通行するようになりましたが、相変わらず全列車停車でした。
愛冠仮乗降場には通過する列車が現れ、昭和23には4往復全列車停車だったのが、24年には4往復中2往復が通過、2往復のみ停車となります。
「時刻表復刻版 戦後編 5」では次の収録号が昭和27年5月号に飛んでしまいますが、まず目を引くのが、網走本線の掲載が北見駅を境に分割され、石北線と網走本線北見〜網走間のを一体とした、現在の石北本線の形態と同様の時刻表になり、池田〜北見間で単独の時刻表の形に掲載方法が改められています。
日ノ出仮乗降場は昭和25(1950)年に正駅になっているので、この昭和27年5月号では当然、正駅としてキロ程も記入された状態で記載されています。
置戸〜北見間の区間列車は1往復となり、池田〜北見間を走破する列車が4往復に増えたので、日ノ出駅停車列車も1日5往復で変わらず、愛冠も全列車停車に戻っており、池田〜陸別間の区間列車1往復を加えて1日5往復停車となっています。
ただ、愛冠はこの年の3月に正駅に昇格しているはずなので、全列車停車はそれに伴うものかも知れませんが、キロ程だけは、まだ間に合っていなかったのか、空欄のままでした。
(27年3月25日訂補、と書かれており、愛冠が駅に昇格したのも同日であるので、愛冠の正駅化と同時に改定された時刻表のため、キロ程が空欄なのも致し方ないものと考えられます。)
またこの時点では様舞、笹森、北光社の各仮乗降場が開業済みであり、おそらく釧北も開業しているであろうという時期にあたりますが、いずれも掲載されていません。
この他の変化としては、この間に淕別(りくんべつ)駅が陸別(りくべつ)駅に改称した、旭野仮乗降場が西女満別駅に昇格した、などが挙げられます。
これ以降は日ノ出については正駅として歩んでいきますので、時刻表での扱いについては割愛させて頂きます。
「時刻表復刻版 戦後編 5」収録の中で最後の号となる昭和30年8月号では仮乗降場である証となる「キロ程空欄」の停車場はすっかり姿を消し、様舞と北光社は結局非掲載のままでした。
またこの8月から9月にかけては豊住、西富、広郷が相次いで仮乗降場として開設、昭和31(1956)年には西訓子府、昭和32年には穂波が仮乗降場として開設していきます。
昭和34年には既に述べたように様舞(5月1日)、豊住、西訓子府、西富、穂波、広郷、北光社(11月1日)が正駅に昇格します。
昭和32年には書類上、釧北仮乗降場が廃止となり、上記の各仮乗降場が正駅となってからは、池田〜北見間の仮乗降場は笹森のみとなります。
昭和35(1960)年に西一線、昭和36年に塩幌がいずれも正駅として開業し、昭和43(1968)年に大森仮乗降場が開設されるまで、網走本線池田〜北見間改め池北線には仮乗降場が笹森の1か所のみという状態が続きます。
大森は昭和40年代に開設された数少ない仮乗降場であると共に、仮乗降場の設置が少ない釧路鉄道管理局管内の仮乗降場という点で異色の存在です。
そして、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、笹森、大森は共に道内版の時刻表にすら掲載されない仮乗降場として知られるところとなります。
白糠線共栄仮乗降場や士幌線新士幌仮乗降場、標津線多和仮乗降場など、釧路鉄道管理局管内の仮乗降場は時刻表に掲載されにくい傾向があるような気がするのは私だけでしょうか…?