みなさんこんにちは。
今回は環境保全についてちょっと看過しがたい行為を見かけたのでそのことについて語っていきます。
少しベニシオマネキ氏@kani_farm
今後、私が少ない給料を投げ打って、東北の保全地で必死に外来種駆除や環境整備をしても、そこに戻ってきたナミゲンはこの人が勝手に撒いた国内外来種との交雑個体かもしれないという疑念は一生晴れないこういう人が国内外来種を撒く懸念をゼロ… https://t.co/NaGMizl3WK
2019年07月31日 01:15
これですね。
勘違いされると困るので最初に書いておきますけど、私が批判しているのはこのツイートでも批判している画像の文章についてであり、少しベニシオマネキ氏さんを批判しているわけではまったくもってございませんのでね😅
むしろこの方のおっしゃっていることをもう少し掘り下げていこうというのが今回のテーマです。
それでは久々に長くなりそうですがお付き合いください🙇♂️
ゲンゴロウ(ナミゲンゴロウ)は大型の水性甲虫の一種で、かつては全国の水田や小川などに広く生息していた昆虫でしたが、農薬の使用や開発による環境の変化によって個体数が激減し、現在では限られた地域でしかその姿を見ることができません。
というより、ゲンゴロウに限らず水生昆虫は環境の変化に弱いものが多く、他にも多くの種が年々数を減らしています。
そんな中での冒頭のこれ。
自家繁殖をさせたゲンゴロウの放流、たしかに一見素晴らしい活動のように見えます。
しかし先に言ってしまうとこの行為、むしろ生態系の破壊に繋がる恐れがあります。
それについて説明するためのキーワードは『生物多様性』です。
生物多様性(Biodiversity)とは保全生物学における重要な用語の一つで、生態系の多様性・種の多様性・遺伝的多様性の3つのレベルから生物の多様性について示す概念のことです。
生態系の多様性は、湿地や草原など多様な環境があってそれぞれに多様な生態系が存在することを示しています。
種の多様性は、1つの生態系の中で食物連鎖やその他なんらかの関わりを持ちながら共に生息している多様な生物種を示しています。
そして遺伝的多様性は、同じ種であっても遺伝子はそれぞれの生息場所によって微妙に異なっており、その多様な遺伝子のことを示しています。
難しいようですが、ザックリ言うといろんな特徴を持ったいろんな生き物を守っていこうねって感じです。
さて話を戻すと、繁殖させたゲンゴロウを野外(しかも不特定多数の場所)に放流する行為は、この生物多様性を構成する3つの多様性全てにおいてアウトなんです。
生態系というものは絶妙なバランスの上で成り立っていて、例えばある一種の生物が増えすぎた時には捕食者が増えるなどして元の数に戻るなど、常に変化しながらも均衡を保っています。
しかし人為的に生物を放流するとそのバランスが大きく崩れ、酷い場合には生態系そのものの破壊にも繋がる可能性があります。
そうでなくても放流した生物の作用によって、放流した生態系がどこも似たようなものになってしまうことでしょう。
生態系の多様性を損なうということですね。
さらに文章からは元々その場所にゲンゴロウがいるかどうかに関係なく放流するといったように読み取れるため、ゲンゴロウが元々いなかった場所に放っている可能性があります。
それはもう立派な外来種です。
外来種というとアメリカザリガニやブラックバスを思い浮かべるかもしれませんが、本来その生物がいなかった環境に新しく放流された生物というのは国内や都道府県内、市町村内であっても外来種となります。
特にゲンゴロウは肉食であり他の水性生物を捕食することから、ダイレクトに他の生物に影響を及ぼす生物です。
元々いなかったゲンゴロウに対する防衛策を持っていない小型生物などはなすすべも無く個体数を減らすことになるでしょう。
種の多様性が損なわれるということですね。
そして意外と知られていないのが、生物は同じ種であっても様々な遺伝子をそれぞれの個体が保有しており、生息場所によって多様な特徴を別々に持っているということです。
分かりやすい例が人種です。
我々ヒトはホモ・サピエンス(Homo sapiens)という一つの種ですが、地域によって様々な人種がいます。
肌の色や骨格など多種多様な特徴を持った人種が一つの種に内包されているわけです。
それと同じで、全ての生物にもそういった人種のようなものがあり、亜種として分けられているものはもちろんのこと、学名上でもまったくの同一種が地域によって異なる形質を持つことは当たり前のようによくあることです。
人間だと苗字でイメージするといいかもしれません。
そのことを無視して色々な場所に別の遺伝子をばら撒くことは大変危険です。
遺伝子がどんどん均一化していって、どこのゲンゴロウも同じ遺伝子を持つことになります。
言うなれば日本人全員が田中さんになるみたいなものです(全国の田中さんゴメンナサイm(_ _)m)
そうなると種の存続に関わってきます。
例えばゲンゴロウにおいて寒さに強い遺伝子と暑さに強い遺伝子が別々にあったとしましょう。
もしも気候が変動して極端に寒くなったり暑くなったりした時に、それぞれの遺伝子を持ったゲンゴロウは生き残ることができます。
結果ゲンゴロウという種としては絶滅を免れることができるわけです。
しかし遺伝子が均一化すると、環境が変化した際にそれに対応できる個体群がいなくなった結果、種が絶滅する可能性があります。
ハーフは優秀なイメージがあるかもしれませんが、遺伝子の数が決まっている以上全てに対応することはできないのです。
これが遺伝的多様性の損失です。
長くなりましたが、以上がゲンゴロウ放流活動を批判する根拠となります。
本人はバクテリアやウイルスレベルでの討論をお望みのようですが、風に乗って拡散するようなものの運搬リスクについて議論するのはナンセンス極まりないし、なんなら正しい知識を持った保全活動家は活動の際にきちんと殺菌消毒を行っていますよ?
自然からかけ離れてしまった人々の関心をもう一度自然に向けたいという思いには共感しますが、正しい知識を持って正しい保全活動をしてもらいたいものです。
今回はゲンゴロウの放流を例に述べてきましたが、その他にも全国で行われているメダカやマス類の放流にも同様のことが言えます。
その場所でとった卵や稚魚を育てた上でその場所に放流するならばよいのですが(これもある一種の個体数だけ増加させることになり、100%正しい行為だと言えるかは微妙な所)、元々いた場所と異なる場所に放流することは絶対にしてはいけません。
長くなりましたが、この記事を読まれた方によって少しでも間違った放流活動がなくなれば幸いです。
最後まで読んでくださってありがとうございます😊
 | ゲンゴロウ・ガムシ・ミズスマシハンドブック (水生昆虫1) 1,944円 Amazon |
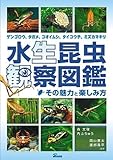 | 水生昆虫観察図鑑―その魅力と楽しみ方 ゲンゴロウ、タガメ、コオイムシ、タイコウチ、ミズカマキリ 2,500円 Amazon |

