国債の60年間召喚ルールって
バラマキでいい顔して使うだけ使って後は頼むってこと
おはようございます みなさん
3月2日2024年度の政府の予算案が
衆議院の本会議で可決されました
今回決まった予算では
1年間で政府が使うお金
歳出額は112兆5717億円と大変な多額に登っています
これは昨年度に継ぐ
過去2番目の規模となっています
現在政府の収入にあたる税収は
およそ70兆円です
歳出額は110兆円ですからその差は
40兆円
政府はこの差額40兆円を借金
すなわち
国債で賄っているのです
俯瞰的に見て
およそ30年は税収がそれほど増えない中
歳出額は拡大を続け毎年多額の借金を生み出してきました
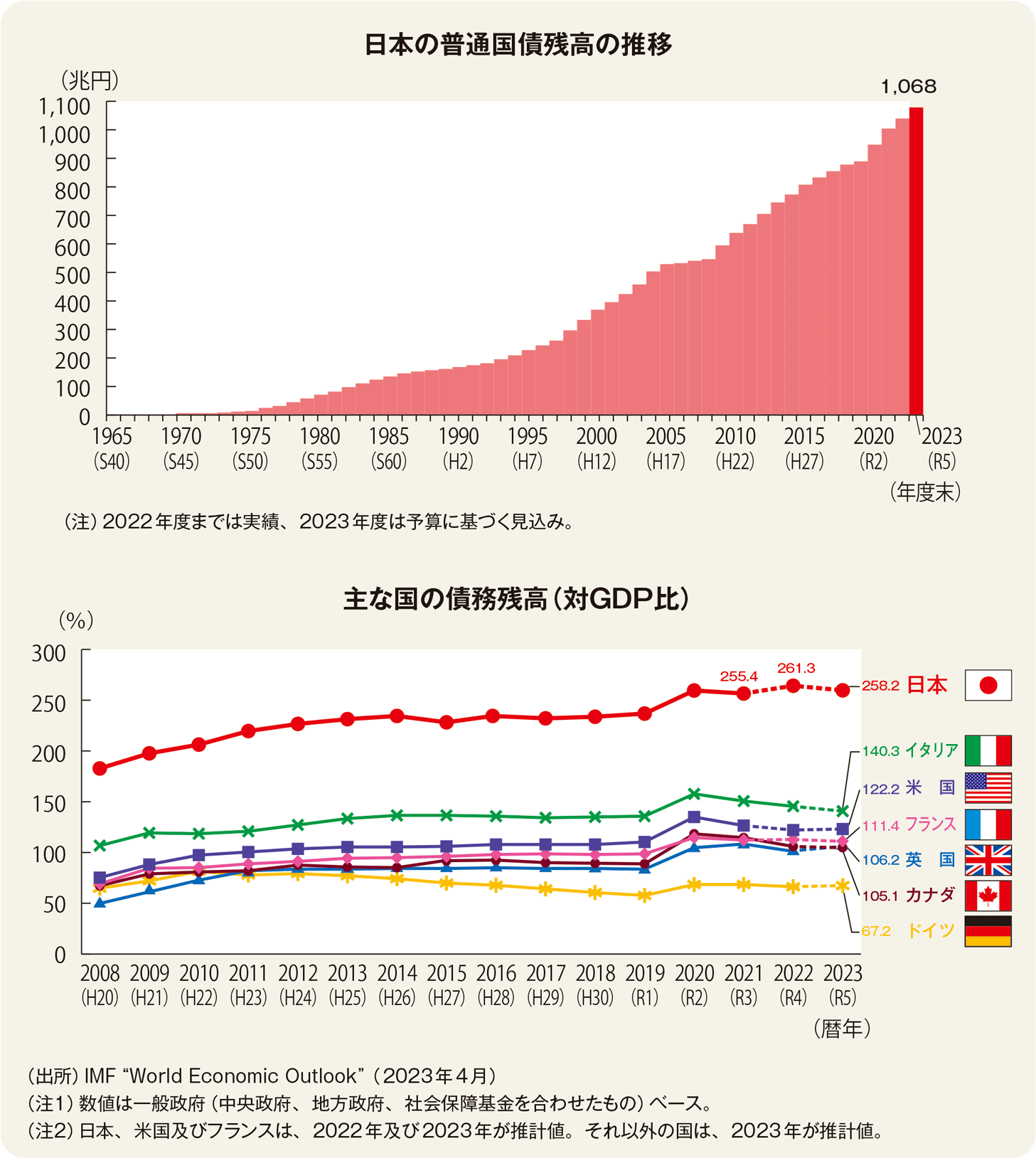
そして
その国債は60年かけて返していくという
いわゆる60年召喚ルールの元で
今の若い世代またこれから生まれる世代が
そのツケを払うことになります
政府が歳出を拡大することは
実は将来世代への負担の押し付けで成り立っているのです
この状況をなくしていくためには
そもそも
財政の構造を変えなければなりません
政府が使うお金の最大の項目は社会保障費です
年金や医療などの社会保障給付の財源は社会保険料です
私たちの収入から社会保険料が天引きされています
それだけでは巨額の社会保障給付を賄えきれないために
政府が社会保障費に多額の税金を投じているのです
今
少子高齢化が急速に進んでいるため
今後
社会保障給付は拡大し続けていくと予想されています
社会保障のあり方を今抜本的に見直さなければ
今後さらに国際を発行する
あるいは大増税社会保険料の大幅な上げに
迫られることになります
年金制度を例に見てみると
年金制度では将来自分たちが
高齢者になって受ける年金は
自分たちが現役の時に積み立てる積み立て方式が
採用されていたのですが
1970年代に
年金給付の大盤振る舞いを始めて
積み立方式が成り立たなくなり
付加方式の高齢者が受けている世代の金は
今働いている現役層がこしらえるという方式に
移行したのです
現役層の人口が拡大する局面では
付加方式は成り立つのですが
今はまさに
少子高齢化が進んで支えられる高齢者層が増える一方
それを支える現役層が減少の一途をたどっています
1950年には
12人の現役層で高齢者1人を支える構造でしたが
現在は
現役層2人で高齢者1人を支える状況となっています
そして
およそ40年後の2065年には
1人の高齢者を1人の現役層で支える状況となるのです
それは例えば
自分の給料が30万円だとすると
30万円で自分や家族を支えるとともに
社会保障制度の元で
見知らぬ誰か分からない
高齢者1人を同時に養うということにするのです
このように社会保障の付加方式が採用されている中で
少子高齢化が急速に進むという日本では
今
最悪のコンビネーションが成り立っているのです
鈴木渡教授による試算では
厚生年金を会社のどに勤務している人が加入する年金について
若者と高齢者層など世代間でどのくらいの格差があるか
年金の大盤振る舞いの恩恵を受けた世代は
年金の支払う額よりももらう額の方が多い
「もらい得」となっている
一方
若い世代はもらう額よりも支払う額の方が多い
「払い損」となっています
今
23歳前後の2000年生まれの方を見てみますと
2610万円の「払い損」になるという試算となっています
3460万円の「もらい得」となっている
1940年生まれの方と比べますと
実に
6000万円ほどの開きがあるのです
そもそも
保険というのは加入者同士がお金を出し合い
将来のリスクに備えるという性質のものです
年金も年金保険というぐらいですから
本来は保険の1つであり
長生きし過ぎて資産がなくなって
飢え死ににするというリスクを
社会全体でカバーしようとするものです
決して年金は世代間での
所得再分配を行うための道具ではないはずです
若者はいわば加入すれば
必ず損する保険に
強制的に入らされている状況にあると言えます
このような
年金制度の歪みを無視し続けけるわけには参りません
年金をあるべき姿に戻すために
本来の年金制度のあり方について
徹底的な議論を行わなければなりません
幸福実現党
大川隆法党総裁は
少子高齢化が進むことによって起きる問題について
次のように述べています
今後シルバー民主主義と言って
高齢者たちが選挙民として増えてきます
高齢者の場合
投票率が高く
大体60%の人が投票します
一方
若者は30%しか投与しません
2倍ぐらい違うわけです
そうすると政治家としては
「年を取った方の票を集めたい」
という気持ちになるのです
団塊の世代を含め年配の世代は人口が多く
若い世代の方が少子高齢化で有権者数が少ないという中で
若者の方が投票率が少ないというのが実態です
実は
これこれまで政治の場でも
さすがに社会保障のあり方を
見直さなければならないのではないかという
動きが何度か出てはいたものの
結局のところ
その場のぎとしての制度の微修正にとまってしまい
制度を根本的に変えるというところまでは
至っていないというのが実情です
なぜ
根本改革に踏み込むことができなかったかと言えば
有権者の多くを占めるのがシルバー層であり
シルバー層の利益を優先する政治がが
行われたからに他なりません
臭いものには蓋をし
制度改革の先送りを続けてきた
これまでの政治こそ
シルバー民主主義が横行してきたことの証明と
言えるのではないでしょうか
島沢論教授(関東学院大学)が
最近の書籍でも述べています
政治学の中でえシルバー民主主義の脱却に向けて
若者の声を政治に届けるための
新しい選挙制度のアイデアが様々提案されています
例えば
投票権をまだ持たない子供を持つ親に
子供の人数分の選挙権を付与する
ドメイン投票制度
7
20代選挙区60代選挙区など
年代別の選挙区を設ける年齢別選挙区制度
あるいは
人間の限界余命を125歳とした時に
90歳なら125-90で35票
20歳なら125-20で105票を保有するとして
若い人ほどえ自分が持つ標数が増えるという
余名投票制度というものがあります
こうした奇なアイデアがあるわけですが
どのようなえ選挙制度改革をするとしても
結局のところえ高齢者が多数を占める
シルバー民主主義の元では
高齢者が損をするような制度改革の実現は
難しいと言えるでしょう
選挙制度改革とまではいかないまでも
最低限年金などのあり方を
真っ当なものに変えることは必要です
また
これからの世代にツケを回すバラマキを
政治からなくさなければなりません
そのためにも若い世代
特にZ世代の皆さんの政治参加が必要不可決です
今まで日本を作り上げてくれた世代の方から
日本を若い世代に引き継ぎ
若い人たちが政治に参加したくなるような
政策提言を行うことを
幸福実現党は志してまいります
【Truth Z(トゥルースゼット)】
選挙制度の改革も大事ですが
何より政府の借金が増え続けることを止めなければなりません
社会保障の美名のもと湯水のごとく借金を増やし続けています
政府が大きくなり過ぎている
政府に金が掛り過ぎているのです
参議院は必要ですか
文科省・厚生省・デジタル庁・復興庁・農林水産省必要ですか
総務省でやってください
金のかかる政治家を減らし
不要な省庁を徹底的に集約して民間に移行し
小さな政府にして政府をスリム化して
減税してください
今日の光の言霊は【仏陀と共に歩む人生】です
本当に大事なことを残し
不要な部分は捨てることでしょう
生きて行く上において必要なことだけにする
そして
心の法則を究めること
八正道に則って生きること
四弘誓願で生きること
厳しい道にこそ本物がある
できるかできないかは自分次第です
バラマキでいい顔して使うだけ使って後は頼むってこと
おはようございます みなさん
3月2日2024年度の政府の予算案が
衆議院の本会議で可決されました
今回決まった予算では
1年間で政府が使うお金
歳出額は112兆5717億円と大変な多額に登っています
これは昨年度に継ぐ
過去2番目の規模となっています
現在政府の収入にあたる税収は
およそ70兆円です
歳出額は110兆円ですからその差は
40兆円
政府はこの差額40兆円を借金
すなわち
国債で賄っているのです
俯瞰的に見て
およそ30年は税収がそれほど増えない中
歳出額は拡大を続け毎年多額の借金を生み出してきました
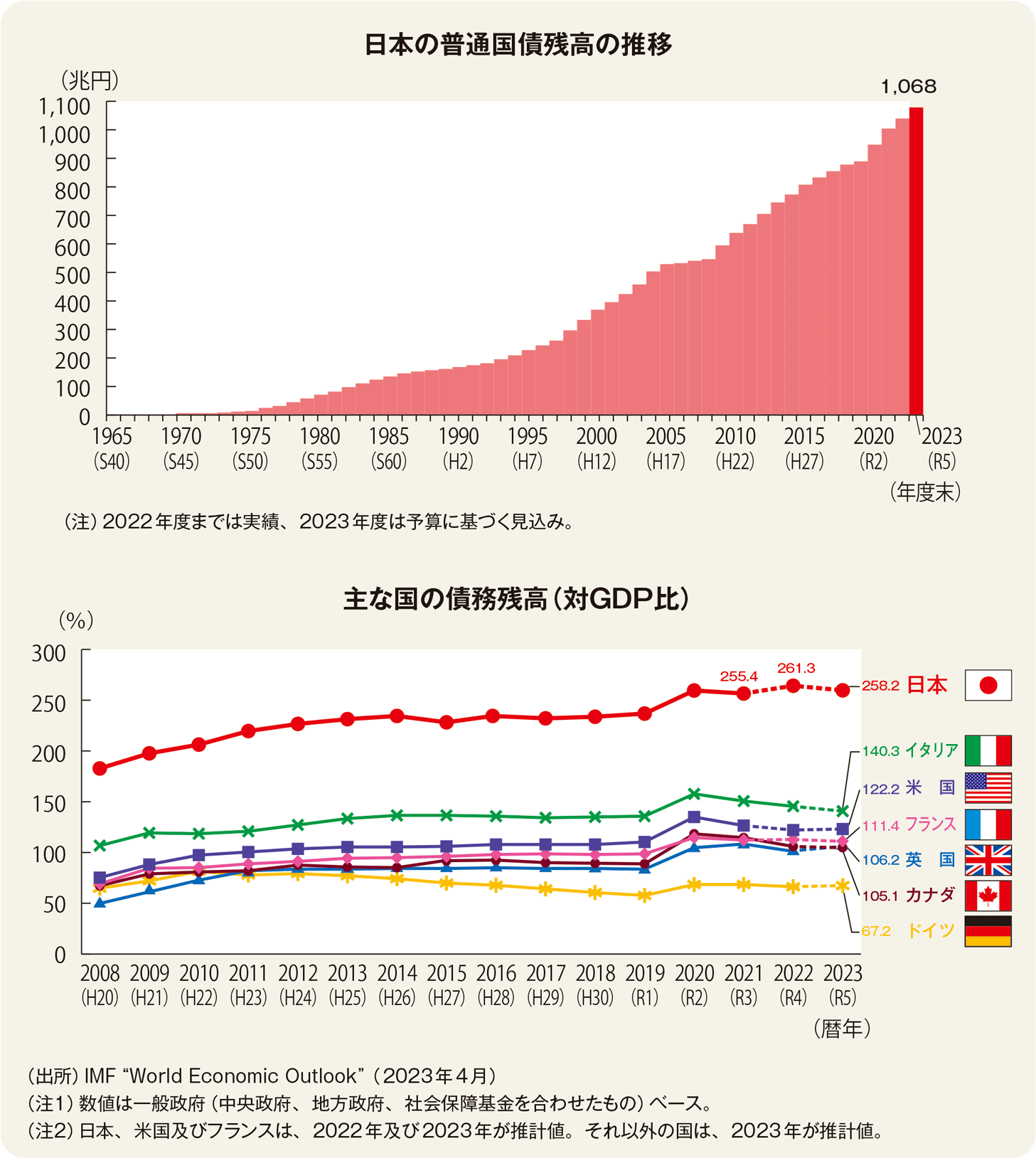
そして
その国債は60年かけて返していくという
いわゆる60年召喚ルールの元で
今の若い世代またこれから生まれる世代が
そのツケを払うことになります
政府が歳出を拡大することは
実は将来世代への負担の押し付けで成り立っているのです
この状況をなくしていくためには
そもそも
財政の構造を変えなければなりません
政府が使うお金の最大の項目は社会保障費です
年金や医療などの社会保障給付の財源は社会保険料です
私たちの収入から社会保険料が天引きされています
それだけでは巨額の社会保障給付を賄えきれないために
政府が社会保障費に多額の税金を投じているのです
今
少子高齢化が急速に進んでいるため
今後
社会保障給付は拡大し続けていくと予想されています
社会保障のあり方を今抜本的に見直さなければ
今後さらに国際を発行する
あるいは大増税社会保険料の大幅な上げに
迫られることになります
年金制度を例に見てみると
年金制度では将来自分たちが
高齢者になって受ける年金は
自分たちが現役の時に積み立てる積み立て方式が
採用されていたのですが
1970年代に
年金給付の大盤振る舞いを始めて
積み立方式が成り立たなくなり
付加方式の高齢者が受けている世代の金は
今働いている現役層がこしらえるという方式に
移行したのです
現役層の人口が拡大する局面では
付加方式は成り立つのですが
今はまさに
少子高齢化が進んで支えられる高齢者層が増える一方
それを支える現役層が減少の一途をたどっています
1950年には
12人の現役層で高齢者1人を支える構造でしたが
現在は
現役層2人で高齢者1人を支える状況となっています
そして
およそ40年後の2065年には
1人の高齢者を1人の現役層で支える状況となるのです
それは例えば
自分の給料が30万円だとすると
30万円で自分や家族を支えるとともに
社会保障制度の元で
見知らぬ誰か分からない
高齢者1人を同時に養うということにするのです
このように社会保障の付加方式が採用されている中で
少子高齢化が急速に進むという日本では
今
最悪のコンビネーションが成り立っているのです
鈴木渡教授による試算では
厚生年金を会社のどに勤務している人が加入する年金について
若者と高齢者層など世代間でどのくらいの格差があるか
年金の大盤振る舞いの恩恵を受けた世代は
年金の支払う額よりももらう額の方が多い
「もらい得」となっている
一方
若い世代はもらう額よりも支払う額の方が多い
「払い損」となっています
今
23歳前後の2000年生まれの方を見てみますと
2610万円の「払い損」になるという試算となっています
3460万円の「もらい得」となっている
1940年生まれの方と比べますと
実に
6000万円ほどの開きがあるのです
そもそも
保険というのは加入者同士がお金を出し合い
将来のリスクに備えるという性質のものです
年金も年金保険というぐらいですから
本来は保険の1つであり
長生きし過ぎて資産がなくなって
飢え死ににするというリスクを
社会全体でカバーしようとするものです
決して年金は世代間での
所得再分配を行うための道具ではないはずです
若者はいわば加入すれば
必ず損する保険に
強制的に入らされている状況にあると言えます
このような
年金制度の歪みを無視し続けけるわけには参りません
年金をあるべき姿に戻すために
本来の年金制度のあり方について
徹底的な議論を行わなければなりません
幸福実現党
大川隆法党総裁は
少子高齢化が進むことによって起きる問題について
次のように述べています
今後シルバー民主主義と言って
高齢者たちが選挙民として増えてきます
高齢者の場合
投票率が高く
大体60%の人が投票します
一方
若者は30%しか投与しません
2倍ぐらい違うわけです
そうすると政治家としては
「年を取った方の票を集めたい」
という気持ちになるのです
団塊の世代を含め年配の世代は人口が多く
若い世代の方が少子高齢化で有権者数が少ないという中で
若者の方が投票率が少ないというのが実態です
実は
これこれまで政治の場でも
さすがに社会保障のあり方を
見直さなければならないのではないかという
動きが何度か出てはいたものの
結局のところ
その場のぎとしての制度の微修正にとまってしまい
制度を根本的に変えるというところまでは
至っていないというのが実情です
なぜ
根本改革に踏み込むことができなかったかと言えば
有権者の多くを占めるのがシルバー層であり
シルバー層の利益を優先する政治がが
行われたからに他なりません
臭いものには蓋をし
制度改革の先送りを続けてきた
これまでの政治こそ
シルバー民主主義が横行してきたことの証明と
言えるのではないでしょうか
島沢論教授(関東学院大学)が
最近の書籍でも述べています
政治学の中でえシルバー民主主義の脱却に向けて
若者の声を政治に届けるための
新しい選挙制度のアイデアが様々提案されています
例えば
投票権をまだ持たない子供を持つ親に
子供の人数分の選挙権を付与する
ドメイン投票制度
7
20代選挙区60代選挙区など
年代別の選挙区を設ける年齢別選挙区制度
あるいは
人間の限界余命を125歳とした時に
90歳なら125-90で35票
20歳なら125-20で105票を保有するとして
若い人ほどえ自分が持つ標数が増えるという
余名投票制度というものがあります
こうした奇なアイデアがあるわけですが
どのようなえ選挙制度改革をするとしても
結局のところえ高齢者が多数を占める
シルバー民主主義の元では
高齢者が損をするような制度改革の実現は
難しいと言えるでしょう
選挙制度改革とまではいかないまでも
最低限年金などのあり方を
真っ当なものに変えることは必要です
また
これからの世代にツケを回すバラマキを
政治からなくさなければなりません
そのためにも若い世代
特にZ世代の皆さんの政治参加が必要不可決です
今まで日本を作り上げてくれた世代の方から
日本を若い世代に引き継ぎ
若い人たちが政治に参加したくなるような
政策提言を行うことを
幸福実現党は志してまいります
【Truth Z(トゥルースゼット)】
選挙制度の改革も大事ですが
何より政府の借金が増え続けることを止めなければなりません
社会保障の美名のもと湯水のごとく借金を増やし続けています
政府が大きくなり過ぎている
政府に金が掛り過ぎているのです
参議院は必要ですか
文科省・厚生省・デジタル庁・復興庁・農林水産省必要ですか
総務省でやってください
金のかかる政治家を減らし
不要な省庁を徹底的に集約して民間に移行し
小さな政府にして政府をスリム化して
減税してください
今日の光の言霊は【仏陀と共に歩む人生】です
本当に大事なことを残し
不要な部分は捨てることでしょう
生きて行く上において必要なことだけにする
そして
心の法則を究めること
八正道に則って生きること
四弘誓願で生きること
厳しい道にこそ本物がある
できるかできないかは自分次第です
【仏陀と共に歩む人生】
心の法則を究めて
生きようとすること
心の法則を学び
それを実践して
生きることが
すなわち
「仏陀と共に歩む」
ということなのです
HS
『大悟の法』P.276


