20代の投票率が9割!?
おはようございます みなさん
Truth Z(トゥルースゼット)より
《台湾現地リポート》

20代の投票率が9割!?
なぜ台湾の選挙は日本とケタ違いに盛り上がるのか?
日本人が現地で感じた台湾総統選
私自身
海外の選挙を経験するのは初めてのことだったんですけれども
台湾総統選に関してはこの盛り上がり
事前にあの聞いていたんですけれども
その予想をはるかに超えるすごい熱気でありました
1月13日の日直前の大規模集会には
3日間通いました
現地で指示者のインタビューを収録したり
選挙直後には台湾の2人の有識者に
今後の来政権における台湾はどうなっていくのか
外交安全保障
そして
内政の両面で幅広くお話を聞くことができました
さて
今回は日本人が現地で感じた台湾総統選というテーマで
その盛り上がりの背景にあるもの
そして
日本との大きな違いについて考えていきたいと思います
まず1つ目にあげられるのがえ投票率です
日本では台湾総統選に当たるような
国家元首を国民が直接得システムというのはありませんので
単純な比較は禁物なんですけれども
日本で投票率が最も高い国政選挙である
衆院選挙と比較してみてもその差は歴然としております
ここ10年で日本の衆院戦においては
約50%から55%投票率
国民の半数強なのに対して
台湾においては
今回7割を超えています
毎回ほぼこの70%ラインを超えています
過去最も低かった2016年の台湾総統選でも
66.3%となって
毎回国民のほぼ三分の2以上が投票している計算になります
しかも現地で聞いてみますと
台湾には期日前投票や在外投票といった制度がありません
要するに戸籍のあるところで
当日しか投票できないというから驚きです
投票日が近づく2日前頃から
大平駅周辺は本来から多いんですけれども
キャリーケースを持ち歩く人が格段に増えたように思いました
そして
実際に
「帰省して投票するから
今日は早めにお店を閉めるからごめんね」という
飲食店の方ともお会いしました
また
投票前日のインタビューにおいても
この投票のために
アメリカのボストンから戻ってきたという人にもお会いできました
そして
その高い投票率に続いてもう1つ顕著だったのが
若者たちの政治参加の姿です
日本だと若者イコール政治に無関心というイメージが
どうしても先行してしまいますけれども
台湾では真逆です
20代の投票率は9割と平均を有に超えている
という統計も出ています
この若者たちの政治参加が活発な1つの要因として
確かに若者たちが参加しやすい
集会の雰囲気作りも1つあるかもしれません
まさにこのライブとかフェスのような雰囲気が演出されています
そして
同時に驚いたのが
小学校に上がるか上がらないかぐらいの子供たちの姿が
やたら目立ったということです
お祭り感覚で家族みんなで行ってみるかという感覚で
参加している感じです
中にはバギーを引きながらえ赤ちゃんを連れて
来場してるご夫婦にもインタビューhしました
向うで出会った日本のの方にも確かに
台湾では親が意識して
政治に触れさせていくという教育スタンスが
日本よりもはるかに強いんじゃないかという
お話も聞きました
そして
何より実感したのは
選挙という枠を超えて
この国のかじ取りをどうしていくのか
人々の考え方思想がこのある種の集合想念として
ぶつかり合っている印象を体感しました
この選挙を現代の戦争と例えることもありますけれども
日本の選挙に比べると
はるかにこの実際の戦争に近い
「三国志」「項羽と劉邦」だった時代が
現代に蘇ったかのような気分にもさせられたのを
覚えております
さて
この聞きしに勝る台湾の凄まじい熱気
4年に1度の選挙にかける国民の情熱に触れてみて
日本人として純粋に
この根底にあるものを知りたくて
現地で取材させていただいた
台湾教授協会会長
の陳博士にお聞きしてみました
ここで陳先生がおっしゃっていたのは
台湾の先人たちが多くの血を流して
民主化を手にしてきたという歴史があるからだと
歴史的背景を台湾人は
決して忘れないんだということでありました
例えば
1947年に起こりましたえ2:28事件を
見てみたいと思うんですけれども
1992年の李登輝政権での調査によりますと
犠牲者の数は1万8000人から2万8000人とも言われる規模で
推定されております
その後の国民党制権によって敷かれた
戒厳令が40年近く続きました
民主化を目指して処刑された人は
3000人とも4000人とも言われております
そうした先人たちの犠牲のもとに
ようやく勝ち取った民主主義であるという意識が
台湾人の精神に根付いていると言えるのではないでしょうか
やはり何と言っても
日本との大きな違いの中では
自分たちのリーダーを直接自分たちの手で
選ぶことができる大統領性が導入されている
日本では議員内閣制ですけれども
この点の違いも非常に大きいのではないかなと感じました
では
この大統領性と議員内閣制の違いとは何なのか
ここで簡単に考えてみたいと思います
まず
議員内閣制とは
国民に選出された
国会議員選挙で選ばれた国会議員たちが
行政の長としてふさわしい人物を
彼らの中から選んでいくというプロセスでありまして
立法権としての国会と行政権としての内閣が
大きく重なり合っていて
これが混然一体となっている形であります
それに対して
大統領制においては
直接国民たちの手で選ばれるという点から
この国会と行政が完全に独立している形になります
日本に置き換えて
この議員内閣制を見てみますと
まず
選挙で勝たなくては
自分たちの党から総理大臣を出すことができない
選出することができない
だからどうしても
選挙で勝つことが最優先となる
選挙至上主義となる
そうすると
総理大臣に求められるのは
この「行政の長」としての手腕や
経営能力といったものよりも
選挙の顔として使えるかどうかという
別の要素が求められてしまうわけです
そしてまた
あいつは引きずり下ろしてやれとか次は俺がやるんだとか
国会議員同士また派閥の間で嫉妬が渦巻きま
足の引っ張り合いが起こりやすいわけです
こうした政争を内部に多数抱えることで
本来国の宰相として
最優先で取り組まなくてはならない
国家運営において多々非効率が起きてしまうわけです
この点立法権と行政権が切り離された
大統領制においては
こうした煩わしさからは少なからず解放され
強いリーダーシップを発揮することが可能となるわけです
また
今
自民党の派閥の政治資金パーティーを巡る問題が
日本を騒がせていますけれども
こうした問題が起こる1つの要因こそ
議員内閣制において国会議員の中から
総理大臣を排出するという
仕組み事態にあるのではないでしょうか
幸福実現党の大川隆法党総裁は
2009年立党の段階で「新・日本国憲法試案」を発表し
その「第3条」には既に
大統領性の導入を提唱されていました
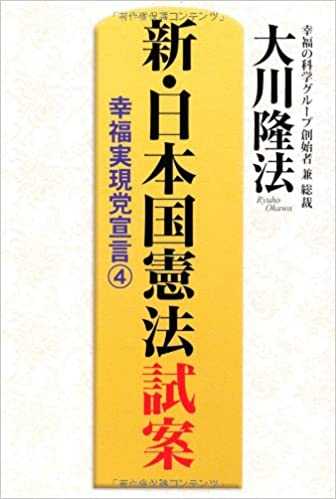
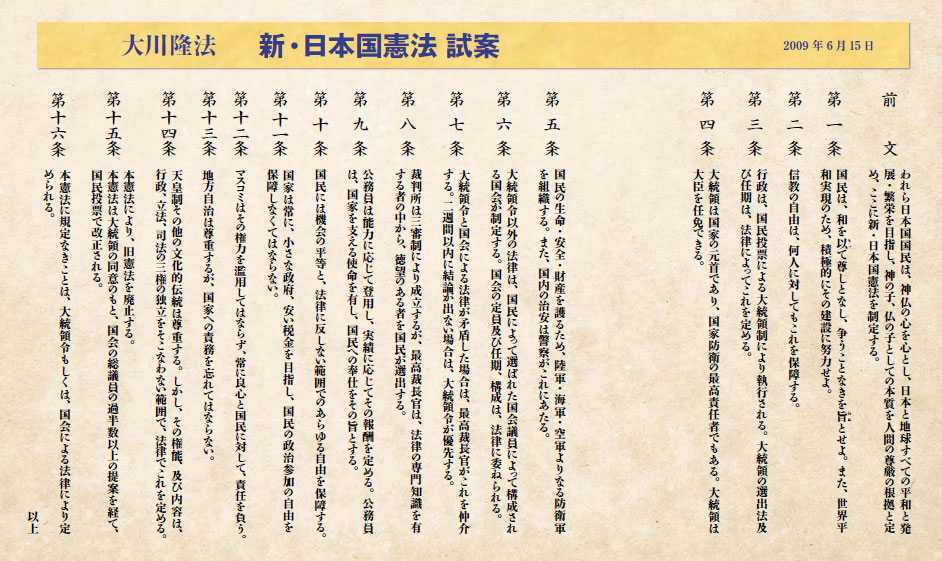
そして
「新・日本国憲法試案の講義」においては
「議院内閣制」の弊害について
このように言及されています
「例えば『国会で多数派を形成できるものが
行政の長になれる』ということであれば
派閥のボス的な人
金権政治家などが
非常に生まれやすい状況になると思われますし
そうした
長田町で人気や権力のある人
権謀術数にたけた人が行政の長になることもあると言えます」
また
議院内閣制に代表される間接民主性について
「これは
現代のように
テレビや
新聞
ラジオ
インターネットなどの媒体が発達することを
予想していない時代
また
交通期間も限られていて
その人のあり方を
それほど知ることのできない時代の産物だと思います」
と述べられています
確かに
日本の衆院戦の投票率を遡ってみますと
台湾並の70%を超える時代あったんです
1980年代前の昭和期においては
投票率衆院戦においては
60%後半から80%に近づく年もあったようです
その時代はまだ議員内閣制がある程度機能していて
国民が政治を信頼していた
政治家を信頼していた時代なのかもしれません
その後インターネットの台頭など
メディアの発達と相反して
この低い投票率から見ますと国民の政治への関心は
一気に下がっていると言えるのではないでしょうか
バブル崩壊から
日本経済は失われた30年と言われて久しいですけれども
日本の政治にとって
いわば国民からの信頼が失われた30年だったと
言えるのではないでしょうか
人口が国力の基なのはもちろんでありますけれども
台湾の人々が情熱を持って政治に参加する姿を垣見ることで
政治参加する人がどれだけいるのかということも
国力に直結しているということを今回体感させられました
今の日本政治は誰がどう見ても
深い機能不全に陥っていると言えます
国民から信頼を挽回し
日本政治の失われた30年を取り戻すためには
国家の宰相が強いリーダーシップを発揮することができる
大統領制こそが必要な一手であると確信し
日本は本気でこの大統領制の導入を
検討すべき時期に来ているのではないでしょうか
政治パーティー券での裏金作りは大問題です
政治制度や政治家本人たちが時代おくれであることが
露呈した形となったのではないでしょうか
国防の問題や選挙制度の問題など憲法を早急に改正するべきです
その際
ぜひ大川隆法総裁が作られた
「新・日本国憲法試案」を参考にしてもらいたいものです
今日の光の言霊は【心があなた自身】です
心が自分自身である
今思っていることが自分自身である
ということは日本と言う国にとっては
憲法が日本であるということ
戦後GHQの監修で作られた「借り物憲法」では
「借り物の日本」であるということでしょう
本来の日本の姿に戻すのであれば
憲法を一から作り直すべきではないでしょうか
Truth Z(トゥルースゼット)より
《台湾現地リポート》

20代の投票率が9割!?
なぜ台湾の選挙は日本とケタ違いに盛り上がるのか?
日本人が現地で感じた台湾総統選
私自身
海外の選挙を経験するのは初めてのことだったんですけれども
台湾総統選に関してはこの盛り上がり
事前にあの聞いていたんですけれども
その予想をはるかに超えるすごい熱気でありました
1月13日の日直前の大規模集会には
3日間通いました
現地で指示者のインタビューを収録したり
選挙直後には台湾の2人の有識者に
今後の来政権における台湾はどうなっていくのか
外交安全保障
そして
内政の両面で幅広くお話を聞くことができました
さて
今回は日本人が現地で感じた台湾総統選というテーマで
その盛り上がりの背景にあるもの
そして
日本との大きな違いについて考えていきたいと思います
まず1つ目にあげられるのがえ投票率です
日本では台湾総統選に当たるような
国家元首を国民が直接得システムというのはありませんので
単純な比較は禁物なんですけれども
日本で投票率が最も高い国政選挙である
衆院選挙と比較してみてもその差は歴然としております
ここ10年で日本の衆院戦においては
約50%から55%投票率
国民の半数強なのに対して
台湾においては
今回7割を超えています
毎回ほぼこの70%ラインを超えています
過去最も低かった2016年の台湾総統選でも
66.3%となって
毎回国民のほぼ三分の2以上が投票している計算になります
しかも現地で聞いてみますと
台湾には期日前投票や在外投票といった制度がありません
要するに戸籍のあるところで
当日しか投票できないというから驚きです
投票日が近づく2日前頃から
大平駅周辺は本来から多いんですけれども
キャリーケースを持ち歩く人が格段に増えたように思いました
そして
実際に
「帰省して投票するから
今日は早めにお店を閉めるからごめんね」という
飲食店の方ともお会いしました
また
投票前日のインタビューにおいても
この投票のために
アメリカのボストンから戻ってきたという人にもお会いできました
そして
その高い投票率に続いてもう1つ顕著だったのが
若者たちの政治参加の姿です
日本だと若者イコール政治に無関心というイメージが
どうしても先行してしまいますけれども
台湾では真逆です
20代の投票率は9割と平均を有に超えている
という統計も出ています
この若者たちの政治参加が活発な1つの要因として
確かに若者たちが参加しやすい
集会の雰囲気作りも1つあるかもしれません
まさにこのライブとかフェスのような雰囲気が演出されています
そして
同時に驚いたのが
小学校に上がるか上がらないかぐらいの子供たちの姿が
やたら目立ったということです
お祭り感覚で家族みんなで行ってみるかという感覚で
参加している感じです
中にはバギーを引きながらえ赤ちゃんを連れて
来場してるご夫婦にもインタビューhしました
向うで出会った日本のの方にも確かに
台湾では親が意識して
政治に触れさせていくという教育スタンスが
日本よりもはるかに強いんじゃないかという
お話も聞きました
そして
何より実感したのは
選挙という枠を超えて
この国のかじ取りをどうしていくのか
人々の考え方思想がこのある種の集合想念として
ぶつかり合っている印象を体感しました
この選挙を現代の戦争と例えることもありますけれども
日本の選挙に比べると
はるかにこの実際の戦争に近い
「三国志」「項羽と劉邦」だった時代が
現代に蘇ったかのような気分にもさせられたのを
覚えております
さて
この聞きしに勝る台湾の凄まじい熱気
4年に1度の選挙にかける国民の情熱に触れてみて
日本人として純粋に
この根底にあるものを知りたくて
現地で取材させていただいた
台湾教授協会会長
の陳博士にお聞きしてみました
ここで陳先生がおっしゃっていたのは
台湾の先人たちが多くの血を流して
民主化を手にしてきたという歴史があるからだと
歴史的背景を台湾人は
決して忘れないんだということでありました
例えば
1947年に起こりましたえ2:28事件を
見てみたいと思うんですけれども
1992年の李登輝政権での調査によりますと
犠牲者の数は1万8000人から2万8000人とも言われる規模で
推定されております
その後の国民党制権によって敷かれた
戒厳令が40年近く続きました
民主化を目指して処刑された人は
3000人とも4000人とも言われております
そうした先人たちの犠牲のもとに
ようやく勝ち取った民主主義であるという意識が
台湾人の精神に根付いていると言えるのではないでしょうか
やはり何と言っても
日本との大きな違いの中では
自分たちのリーダーを直接自分たちの手で
選ぶことができる大統領性が導入されている
日本では議員内閣制ですけれども
この点の違いも非常に大きいのではないかなと感じました
では
この大統領性と議員内閣制の違いとは何なのか
ここで簡単に考えてみたいと思います
まず
議員内閣制とは
国民に選出された
国会議員選挙で選ばれた国会議員たちが
行政の長としてふさわしい人物を
彼らの中から選んでいくというプロセスでありまして
立法権としての国会と行政権としての内閣が
大きく重なり合っていて
これが混然一体となっている形であります
それに対して
大統領制においては
直接国民たちの手で選ばれるという点から
この国会と行政が完全に独立している形になります
日本に置き換えて
この議員内閣制を見てみますと
まず
選挙で勝たなくては
自分たちの党から総理大臣を出すことができない
選出することができない
だからどうしても
選挙で勝つことが最優先となる
選挙至上主義となる
そうすると
総理大臣に求められるのは
この「行政の長」としての手腕や
経営能力といったものよりも
選挙の顔として使えるかどうかという
別の要素が求められてしまうわけです
そしてまた
あいつは引きずり下ろしてやれとか次は俺がやるんだとか
国会議員同士また派閥の間で嫉妬が渦巻きま
足の引っ張り合いが起こりやすいわけです
こうした政争を内部に多数抱えることで
本来国の宰相として
最優先で取り組まなくてはならない
国家運営において多々非効率が起きてしまうわけです
この点立法権と行政権が切り離された
大統領制においては
こうした煩わしさからは少なからず解放され
強いリーダーシップを発揮することが可能となるわけです
また
今
自民党の派閥の政治資金パーティーを巡る問題が
日本を騒がせていますけれども
こうした問題が起こる1つの要因こそ
議員内閣制において国会議員の中から
総理大臣を排出するという
仕組み事態にあるのではないでしょうか
幸福実現党の大川隆法党総裁は
2009年立党の段階で「新・日本国憲法試案」を発表し
その「第3条」には既に
大統領性の導入を提唱されていました
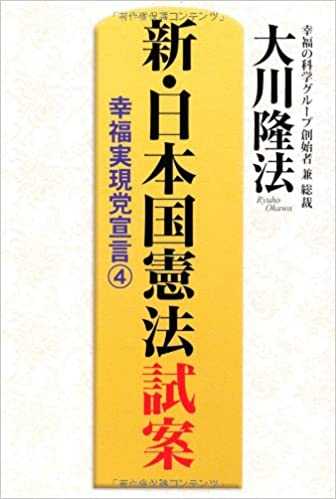
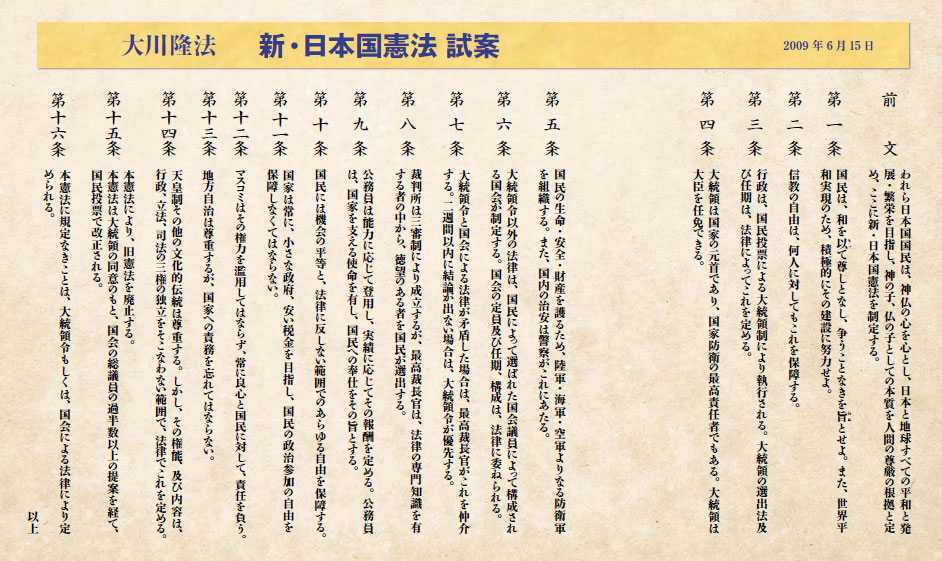
そして
「新・日本国憲法試案の講義」においては
「議院内閣制」の弊害について
このように言及されています
「例えば『国会で多数派を形成できるものが
行政の長になれる』ということであれば
派閥のボス的な人
金権政治家などが
非常に生まれやすい状況になると思われますし
そうした
長田町で人気や権力のある人
権謀術数にたけた人が行政の長になることもあると言えます」
また
議院内閣制に代表される間接民主性について
「これは
現代のように
テレビや
新聞
ラジオ
インターネットなどの媒体が発達することを
予想していない時代
また
交通期間も限られていて
その人のあり方を
それほど知ることのできない時代の産物だと思います」
と述べられています
確かに
日本の衆院戦の投票率を遡ってみますと
台湾並の70%を超える時代あったんです
1980年代前の昭和期においては
投票率衆院戦においては
60%後半から80%に近づく年もあったようです
その時代はまだ議員内閣制がある程度機能していて
国民が政治を信頼していた
政治家を信頼していた時代なのかもしれません
その後インターネットの台頭など
メディアの発達と相反して
この低い投票率から見ますと国民の政治への関心は
一気に下がっていると言えるのではないでしょうか
バブル崩壊から
日本経済は失われた30年と言われて久しいですけれども
日本の政治にとって
いわば国民からの信頼が失われた30年だったと
言えるのではないでしょうか
人口が国力の基なのはもちろんでありますけれども
台湾の人々が情熱を持って政治に参加する姿を垣見ることで
政治参加する人がどれだけいるのかということも
国力に直結しているということを今回体感させられました
今の日本政治は誰がどう見ても
深い機能不全に陥っていると言えます
国民から信頼を挽回し
日本政治の失われた30年を取り戻すためには
国家の宰相が強いリーダーシップを発揮することができる
大統領制こそが必要な一手であると確信し
日本は本気でこの大統領制の導入を
検討すべき時期に来ているのではないでしょうか
政治パーティー券での裏金作りは大問題です
政治制度や政治家本人たちが時代おくれであることが
露呈した形となったのではないでしょうか
国防の問題や選挙制度の問題など憲法を早急に改正するべきです
その際
ぜひ大川隆法総裁が作られた
「新・日本国憲法試案」を参考にしてもらいたいものです
今日の光の言霊は【心があなた自身】です
心が自分自身である
今思っていることが自分自身である
ということは日本と言う国にとっては
憲法が日本であるということ
戦後GHQの監修で作られた「借り物憲法」では
「借り物の日本」であるということでしょう
本来の日本の姿に戻すのであれば
憲法を一から作り直すべきではないでしょうか
【心があなた自身】
あなたの心が
あなた自身であり
あなた自身の真なる姿です
つまり
あなたの考えていることが
「あなた」なのです
一日中
あなたの考えていることが
「あなた自身」なのです
HS
『救世の法』 P.201】


