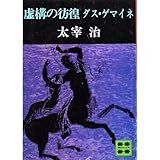グレーテルのかまど (2月21日放送)
太宰治の甘酒
太宰治の甘酒
主人公の私は、叶わぬ恋の相手に似た、一人の
女の子が働く、甘酒屋に通っていました。
女の子が働く、甘酒屋に通っていました。
(略)
その甘酒屋の縁台に腰をおろし、
一杯の甘酒をゆるゆると啜り乍ら、
その菊という女の子を、
私の恋の相手の代理として眺めて、
我慢していたものであった。
「ダス・ゲマイネ」より
しかし、この甘酒屋で出会ったある男によって、主人
公、私の人生が、思わぬ方向に転んでいくのです。
公、私の人生が、思わぬ方向に転んでいくのです。
今夜は、甘酒が登場する太宰の不思議な作品と共に、
日本で長~く愛されてきた、甘酒の魅力に迫ります。
**********
39歳という若さで、命を絶った作家…太宰治。
「走れメロス」「人間失格」など、数々の名作を残し、
今も熱烈な支持を受けています。その中の一つ、
友人への手紙に、こう書き残した作品があります。

私自身でさへ、他の作家に氣の毒なくらゐに、(略)
ずば抜けてゐると思ってゐます。
(昭和十年九月二十二日 三浦正次宛)
昭和10年、デビュー間もなく発表された、
「ダス・ゲマイネ」です。


主人公は、上野の大学で、フランス文学を学ぶ、25歳
の私こと、佐野次郎(じろ)。悩みを抱えながらも、お目
当ての女の子が働く、上野公園の甘酒屋に通ってい
ました。ある日、そこで怪しい一人の男に出会います。
その男が、赤毛氈の縁台のまんなかに、
あぐらをかいて坐ったまま、
大きい碾茶の茶碗で、
たいぎそうに甘酒をすすりながら、
ああ、片手あげて、
私へおいでおいでをしたでないか。(略)
馬場と名乗るその男は、また甘酒をすすりながら…。
「僕はそこの音楽学校にかれこれ八年います。なかな
か卒業できない。まだいちども試験というものに出席し
ないからだ。ひとがひとの能力を試みるなんてことは、
君、容易ならぬ無礼だからね。」「そうです。」「と言って
みただけのことさ。つまりは頭がわるいのだよ。(略)」
**********
甘酒屋から始まるこの物語について、
専門家はこう語ります。

(東京大学教授 安藤宏)
太宰治っていうと、普通は、お酒の話が多いんですよ
ね。本物のお酒じゃなくて甘酒を、昼間から、大学生
達が飲んで、議論するっていうね。芸術家を目指して
るんだけれども、どうも偽物くさいぞっていう。甘酒を
偽物にしてはいけませんけれど、本物のお酒に対し
て、やっぱり甘酒なんだっていうところがね、凄く、ユ
ーモア、醸し出してるところだと思うんです。
その後、一緒に同人誌を作ろうという馬場を信じ、私は
誘いに乗ります。更に馬場は、絵描きの佐竹、新進作
家の太宰治という人物を、私に紹介。芸術家気取りの
4人の若者が集まります。ところが、バイオリニストを
自称する馬場に対して、太宰は…。
「(略) なんだか、君たちは芸術家の伝記だけを知っ
ていて、芸術家の仕事をまるっきり知っていないような
気がします。」
…と皮肉るのです。
自意識ばかりが高く、中身の伴わない若者たち。彼ら
は皆、太宰自身の分身だといいます。
同じ年、太宰は「逆行」を発表。それは、数多く小説を
書いた男が、売れずに終わってしまうという物語でした。

この作品が、第1回芥川賞の候補となり、注目を集め
ます。「ダス・ゲマイネ」は、そんな自分自身を、風刺し
た作品だというのです。

(東京大学教授 安藤宏)
一つも売れなかった、小説家の物語っていうのを作っ
た後に、(太宰自身が)売れ始めちゃった時に、もう書
いちゃったから、自分何もないんだよっていう。自分が
いかに空っぽかと言うことを、風刺して、ユーモラスに
書いて見せたっていう。どっか本物らしく見せようとす
るんだけれども、中身は空っぽだっていう。それが何
か、甘酒に託されているような気がするんですよね。

酒ではなく、甘酒を登場させた、「ダス・ゲマイネ」。
理想とかけ離れた、中身の伴わない空っぽの若者
を描いたお話は、驚きの結末を迎えます。
**********

やさしい甘みの甘酒。
その味は、こうじによって生み出されます。
こうじは、どんな力を持っているのでしょう?
40年にわたり、発酵の研究をする、
小泉先生に教えて頂きました。

(東京農業大学名誉教授 小泉武夫)
こうじってのは、蒸した米に、こうじ菌というかびが生え
る。それがもの凄い力を持っているのね。米のでんぷ
んを分解してブドウ糖にするとか、だからとても甘くな
るわけですよね。
こうじ菌の中でも、ブドウ糖を作る、強い力を持つのが、
アスペルギルス・オリゼ。日本特有のかびです。

オリゼの生み出す天然の甘みは、1000年以上前から
日本人にとって、欠かせないものでした。

(東京農業大学名誉教授 小泉武夫)
日本の歴史の中で、一番最初の甘酒というのは、奈良
時代。砂糖なんてなかったわけですからね。もの凄い
甘味料ですね。
**********
また、甘酒には、
甘いだけじゃないパワーが秘められていました。
夏、疫病がはやり、命を落とす人が多かった江戸時代。
この季節になると、町に現れたのが、甘酒売り。
人々は、甘酒を飲んで、栄養を取ったというのです。

(東京農業大学名誉教授 小泉武夫)
全てのビタミンは、甘酒の中にみんな入ってるんです。
なぜかといったら、こうじ菌が、蒸した米の上で増殖す
る時に、大量のビタミンをいっぱい作ってくれる。甘酒っ
ていうのは、米をよく食べる民族にとっては、素晴らし
いスタミナ源だった、栄養源だったと思いますね。

栄養にも恵まれた甘酒。
それは、古くから日本人の命を守ってきた、
ソウルスイーツなのです。
**********
太宰治の故郷、青森五所川原市。
古くから暮らしの中で、こうじを使ってきました。
ここは、明治14年から続く、町のこうじ屋さん。
昔から米どころであるこの地域では、
米とこうじを、物々交換していました。
もちろん、こうじを使った甘酒もなじみ深いものです。
(こうじ屋 角田信さん)
冬になればよく作って飲んでいる。(子どもの頃は)
年上の人が作ってくれるから、飲む時はこうしてかき
混ぜて、茶碗に入れて飲んだ。
**********

五所川原市金木町に残る太宰の生家でも、
よく、甘酒が作られていたといいます。

津軽屈指の大地主の家に、六男として生まれた太宰。
多くの使用人がいて、彼らが食事作りを任されていま
した。ある記録によれば…

(略)大釜では一年中毎朝湯を沸かし、
ほかのカマドも、糯米をふかしたり、大豆をふかしたり、
納豆や甘酒、水飴作り、(略)何でも自家製だから、
小さな工場くらいこの釜場を使った。
津島美知子著
「増補改訂版・回想の太宰治」(人文書院)より
病弱な母や、権威ある父に、親しめなかったという
太宰。彼の面倒は、使用人が見ていました。
(金木太宰会会長 木下巽)
使用人との交流が、非常に他の兄弟と違って、機会が
多くありましたね。ですから、太宰もここ(釜場)を遊び
場にしながら、女の人たちが、甘酒を飲んでいる時に、
そういう時は、子どもも飲んでいたと思うので、太宰も
やっぱり、甘酒を飲んでいるだろうと。
**********
家が裕福な事に、引け目を感じて育った太宰。
上京後、自殺未遂や、薬中毒を起こし、故郷との間に
溝が出来ていきます。

この家系で、人からうしろ指を差されるような
愚行を演じたのは、私ひとりであった。
「苦悩の年鑑」より

故郷、そして、自らの家系を批判しながらも、津軽、
という土地には、特別な想いを抱いていました。

私は津軽の人である。(略)
だから少しも遠慮無く、
このように津軽の悪口を言うのである。
他国の人が、
もし私のこのような悪口を聞いて、
そうして安易に津軽を見くびったら、
私はやっぱり不愉快に思うだろう。
なんと言っても、
私は津軽を愛しているのだから。
「津軽」より
故郷に、愛憎入り乱れた複雑な想いを抱いていた
太宰。使用人たちが造る甘酒は、愛しい津軽の、
一部分だったのかもしれません。
**********
【Tea Break】
甘酒の今風の楽しみ方をどど~んとご紹介!
女性が流行のオシャレを求めて集う街、自由が丘に
なんと、甘酒専門店があるのよ~。

●古町糀製造所
こちらは、
甘酒に梅果汁とハチミツを合わせた甘酒ドリンク。
酸っぱさと甘さの絶妙なハーモニー。

抹茶風味や、みかん果汁と混ぜたものなど、
いろんな味が楽しめちゃうの。

甘酒は、飲むだけじゃないの。
アイスクリームにもなっちゃいました~。
甘酒がほ~んのり。癖になる~!

和菓子にも甘酒をどうぞ。こちらは、おまんじゅう。
ふわふわの皮の中に、甘酒さんが、入ってますよ。

最後は、
甘酒をこよなく愛する小泉先生のとっておき~!

甘酒ぜんざいです。
小豆と甘酒。そこにみりんで甘さをプラス!
(東京農業大学名誉教授 小泉武夫)
こりゃ~いいですよ、体にも。
それを食べて、元気はつらつと。
こうじパワー全開の甘酒! あなたもぜひ、
そのバリエーションをお試しあれ~!
**********
もち米とこうじだけで造った天然の甘さの甘酒。
津軽出身の太宰にあやかり、りんごチップスを添えて。

甘酒ゼリーには、黒糖シロップでコクをプラスして。

寒い季節、優しく深~い味わいの甘酒で、
身も心も、癒してみて。

**********
甘酒屋が登場する、「ダス・ゲマイネ」。
ドイツ語で、卑俗。
卑しく下品であることを、意味しています。
それと似たような言葉が、太宰の故郷、
津軽にもありました。
(金木太宰会会長 木下巽)
津軽弁で「まいね」。「まいね」、「駄目だ」というんで
すね。「そんなことまいね、まいね」って言うんです。
「だすね、まいね」。「だから、駄目なんだよ」という、
津軽弁的に、解釈もできるっていうのがね、
「ダス・ゲマイネ」なんですよね。
「ダス・ゲマイネ」の最後、何を信じればいいか
わからなくなった私は、町に飛び出します。
私はいったい誰だろう、
と考えて、慄然とした。
私は私の影を盗まれた。
そして、ぶつぶつと呟くのです。
走れ、電車。
走れ、佐野次郎。
(略)
出鱈目な調子をつけて
繰り返し繰り返し歌っていたのだ。
あ、これが私の創作だ。
私の創った唯一の詩だ。
なんというだらしなさ!
頭がわるいから駄目なんだ。
だらしがないから駄目なんだ。
電車にはねられて、私は死んでしまうのです。
理想と現実のはざまで、空回りする若者を描いた、
「ダス・ゲマイネ」。
彼らを風刺するために、太宰は、甘酒を登場させたの
でしょうか?自分自身を追い込み、太宰が綴った物語。
それは、生きるとは何かを、
今も私たちに、問いかけています。

**********
恥ずかしながら、昔太宰にはまった者として、今回の
グレーテルのかまどは外せません。とはいえ、ダス・
ゲマイネも読んでいるはずなのに、思い出せないとい
う、すっかり文学少女だった頃の記憶は、遥か遠くに。
甘酒は、嫌いじゃないけど、それほど好きでもないと
いうか、本物のお酒の方が断然好きと言いますか…。
ただ、江戸時代には甘酒が栄養源だったり、大量の
ビタミンが含まれるスタミナ源だったことを知って、こ
れからは、甘酒も飲まなければと思う、単純な私です。
甘酒を作るこうじ菌「オリゼー」が、漫画「もやしもん」
でお馴染みのキャラだったのも親しみが増した理由。
昔読んだ文学作品と、好きな漫画が繋がる瞬間。ちょ
っと何だか面白いなあと、何が何に繋がるか、わから
ないものだなあと、変なところで感心したりしたりして。
最近では、本当に手にする事がなくなった、太宰作品。
今回、紹介されたダス・ゲマイネが、今でも十分通じる
青春のグダグダ感といいますか、いつの世も、若者は
空回りしながら悩むのだと、今さらながら、青臭かった
自分の姿と重なって、何とも気恥ずかしく。やっぱり太
宰は面白いなあと、彼の才能に恐れ入るといいますか。
だって・・・
「グレーテルのかまど」関連ブログはこちら↓
**********
39歳という若さで、命を絶った作家…太宰治。
「走れメロス」「人間失格」など、数々の名作を残し、
今も熱烈な支持を受けています。その中の一つ、
友人への手紙に、こう書き残した作品があります。

私自身でさへ、他の作家に氣の毒なくらゐに、(略)
ずば抜けてゐると思ってゐます。
(昭和十年九月二十二日 三浦正次宛)
昭和10年、デビュー間もなく発表された、
「ダス・ゲマイネ」です。


主人公は、上野の大学で、フランス文学を学ぶ、25歳
の私こと、佐野次郎(じろ)。悩みを抱えながらも、お目
当ての女の子が働く、上野公園の甘酒屋に通ってい
ました。ある日、そこで怪しい一人の男に出会います。
その男が、赤毛氈の縁台のまんなかに、
あぐらをかいて坐ったまま、
大きい碾茶の茶碗で、
たいぎそうに甘酒をすすりながら、
ああ、片手あげて、
私へおいでおいでをしたでないか。(略)
馬場と名乗るその男は、また甘酒をすすりながら…。
「僕はそこの音楽学校にかれこれ八年います。なかな
か卒業できない。まだいちども試験というものに出席し
ないからだ。ひとがひとの能力を試みるなんてことは、
君、容易ならぬ無礼だからね。」「そうです。」「と言って
みただけのことさ。つまりは頭がわるいのだよ。(略)」
**********
甘酒屋から始まるこの物語について、
専門家はこう語ります。

(東京大学教授 安藤宏)
太宰治っていうと、普通は、お酒の話が多いんですよ
ね。本物のお酒じゃなくて甘酒を、昼間から、大学生
達が飲んで、議論するっていうね。芸術家を目指して
るんだけれども、どうも偽物くさいぞっていう。甘酒を
偽物にしてはいけませんけれど、本物のお酒に対し
て、やっぱり甘酒なんだっていうところがね、凄く、ユ
ーモア、醸し出してるところだと思うんです。
その後、一緒に同人誌を作ろうという馬場を信じ、私は
誘いに乗ります。更に馬場は、絵描きの佐竹、新進作
家の太宰治という人物を、私に紹介。芸術家気取りの
4人の若者が集まります。ところが、バイオリニストを
自称する馬場に対して、太宰は…。
「(略) なんだか、君たちは芸術家の伝記だけを知っ
ていて、芸術家の仕事をまるっきり知っていないような
気がします。」
…と皮肉るのです。
自意識ばかりが高く、中身の伴わない若者たち。彼ら
は皆、太宰自身の分身だといいます。
同じ年、太宰は「逆行」を発表。それは、数多く小説を
書いた男が、売れずに終わってしまうという物語でした。

この作品が、第1回芥川賞の候補となり、注目を集め
ます。「ダス・ゲマイネ」は、そんな自分自身を、風刺し
た作品だというのです。

(東京大学教授 安藤宏)
一つも売れなかった、小説家の物語っていうのを作っ
た後に、(太宰自身が)売れ始めちゃった時に、もう書
いちゃったから、自分何もないんだよっていう。自分が
いかに空っぽかと言うことを、風刺して、ユーモラスに
書いて見せたっていう。どっか本物らしく見せようとす
るんだけれども、中身は空っぽだっていう。それが何
か、甘酒に託されているような気がするんですよね。

酒ではなく、甘酒を登場させた、「ダス・ゲマイネ」。
理想とかけ離れた、中身の伴わない空っぽの若者
を描いたお話は、驚きの結末を迎えます。
**********

やさしい甘みの甘酒。
その味は、こうじによって生み出されます。
こうじは、どんな力を持っているのでしょう?
40年にわたり、発酵の研究をする、
小泉先生に教えて頂きました。

(東京農業大学名誉教授 小泉武夫)
こうじってのは、蒸した米に、こうじ菌というかびが生え
る。それがもの凄い力を持っているのね。米のでんぷ
んを分解してブドウ糖にするとか、だからとても甘くな
るわけですよね。
こうじ菌の中でも、ブドウ糖を作る、強い力を持つのが、
アスペルギルス・オリゼ。日本特有のかびです。

オリゼの生み出す天然の甘みは、1000年以上前から
日本人にとって、欠かせないものでした。

(東京農業大学名誉教授 小泉武夫)
日本の歴史の中で、一番最初の甘酒というのは、奈良
時代。砂糖なんてなかったわけですからね。もの凄い
甘味料ですね。
**********
また、甘酒には、
甘いだけじゃないパワーが秘められていました。
夏、疫病がはやり、命を落とす人が多かった江戸時代。
この季節になると、町に現れたのが、甘酒売り。
人々は、甘酒を飲んで、栄養を取ったというのです。

(東京農業大学名誉教授 小泉武夫)
全てのビタミンは、甘酒の中にみんな入ってるんです。
なぜかといったら、こうじ菌が、蒸した米の上で増殖す
る時に、大量のビタミンをいっぱい作ってくれる。甘酒っ
ていうのは、米をよく食べる民族にとっては、素晴らし
いスタミナ源だった、栄養源だったと思いますね。

栄養にも恵まれた甘酒。
それは、古くから日本人の命を守ってきた、
ソウルスイーツなのです。
**********
太宰治の故郷、青森五所川原市。
古くから暮らしの中で、こうじを使ってきました。
ここは、明治14年から続く、町のこうじ屋さん。
昔から米どころであるこの地域では、
米とこうじを、物々交換していました。
もちろん、こうじを使った甘酒もなじみ深いものです。
(こうじ屋 角田信さん)
冬になればよく作って飲んでいる。(子どもの頃は)
年上の人が作ってくれるから、飲む時はこうしてかき
混ぜて、茶碗に入れて飲んだ。
**********

五所川原市金木町に残る太宰の生家でも、
よく、甘酒が作られていたといいます。

津軽屈指の大地主の家に、六男として生まれた太宰。
多くの使用人がいて、彼らが食事作りを任されていま
した。ある記録によれば…

(略)大釜では一年中毎朝湯を沸かし、
ほかのカマドも、糯米をふかしたり、大豆をふかしたり、
納豆や甘酒、水飴作り、(略)何でも自家製だから、
小さな工場くらいこの釜場を使った。
津島美知子著
「増補改訂版・回想の太宰治」(人文書院)より
病弱な母や、権威ある父に、親しめなかったという
太宰。彼の面倒は、使用人が見ていました。
(金木太宰会会長 木下巽)
使用人との交流が、非常に他の兄弟と違って、機会が
多くありましたね。ですから、太宰もここ(釜場)を遊び
場にしながら、女の人たちが、甘酒を飲んでいる時に、
そういう時は、子どもも飲んでいたと思うので、太宰も
やっぱり、甘酒を飲んでいるだろうと。
**********
家が裕福な事に、引け目を感じて育った太宰。
上京後、自殺未遂や、薬中毒を起こし、故郷との間に
溝が出来ていきます。

この家系で、人からうしろ指を差されるような
愚行を演じたのは、私ひとりであった。
「苦悩の年鑑」より

故郷、そして、自らの家系を批判しながらも、津軽、
という土地には、特別な想いを抱いていました。

私は津軽の人である。(略)
だから少しも遠慮無く、
このように津軽の悪口を言うのである。
他国の人が、
もし私のこのような悪口を聞いて、
そうして安易に津軽を見くびったら、
私はやっぱり不愉快に思うだろう。
なんと言っても、
私は津軽を愛しているのだから。
「津軽」より
故郷に、愛憎入り乱れた複雑な想いを抱いていた
太宰。使用人たちが造る甘酒は、愛しい津軽の、
一部分だったのかもしれません。
**********
【Tea Break】
甘酒の今風の楽しみ方をどど~んとご紹介!
女性が流行のオシャレを求めて集う街、自由が丘に
なんと、甘酒専門店があるのよ~。

●古町糀製造所
こちらは、
甘酒に梅果汁とハチミツを合わせた甘酒ドリンク。
酸っぱさと甘さの絶妙なハーモニー。

抹茶風味や、みかん果汁と混ぜたものなど、
いろんな味が楽しめちゃうの。

甘酒は、飲むだけじゃないの。
アイスクリームにもなっちゃいました~。
甘酒がほ~んのり。癖になる~!

和菓子にも甘酒をどうぞ。こちらは、おまんじゅう。
ふわふわの皮の中に、甘酒さんが、入ってますよ。

最後は、
甘酒をこよなく愛する小泉先生のとっておき~!

甘酒ぜんざいです。
小豆と甘酒。そこにみりんで甘さをプラス!
(東京農業大学名誉教授 小泉武夫)
こりゃ~いいですよ、体にも。
それを食べて、元気はつらつと。
こうじパワー全開の甘酒! あなたもぜひ、
そのバリエーションをお試しあれ~!
**********
もち米とこうじだけで造った天然の甘さの甘酒。
津軽出身の太宰にあやかり、りんごチップスを添えて。

甘酒ゼリーには、黒糖シロップでコクをプラスして。

寒い季節、優しく深~い味わいの甘酒で、
身も心も、癒してみて。

**********
甘酒屋が登場する、「ダス・ゲマイネ」。
ドイツ語で、卑俗。
卑しく下品であることを、意味しています。
それと似たような言葉が、太宰の故郷、
津軽にもありました。
(金木太宰会会長 木下巽)
津軽弁で「まいね」。「まいね」、「駄目だ」というんで
すね。「そんなことまいね、まいね」って言うんです。
「だすね、まいね」。「だから、駄目なんだよ」という、
津軽弁的に、解釈もできるっていうのがね、
「ダス・ゲマイネ」なんですよね。
「ダス・ゲマイネ」の最後、何を信じればいいか
わからなくなった私は、町に飛び出します。
私はいったい誰だろう、
と考えて、慄然とした。
私は私の影を盗まれた。
そして、ぶつぶつと呟くのです。
走れ、電車。
走れ、佐野次郎。
(略)
出鱈目な調子をつけて
繰り返し繰り返し歌っていたのだ。
あ、これが私の創作だ。
私の創った唯一の詩だ。
なんというだらしなさ!
頭がわるいから駄目なんだ。
だらしがないから駄目なんだ。
電車にはねられて、私は死んでしまうのです。
理想と現実のはざまで、空回りする若者を描いた、
「ダス・ゲマイネ」。
彼らを風刺するために、太宰は、甘酒を登場させたの
でしょうか?自分自身を追い込み、太宰が綴った物語。
それは、生きるとは何かを、
今も私たちに、問いかけています。

**********
恥ずかしながら、昔太宰にはまった者として、今回の
グレーテルのかまどは外せません。とはいえ、ダス・
ゲマイネも読んでいるはずなのに、思い出せないとい
う、すっかり文学少女だった頃の記憶は、遥か遠くに。
甘酒は、嫌いじゃないけど、それほど好きでもないと
いうか、本物のお酒の方が断然好きと言いますか…。
ただ、江戸時代には甘酒が栄養源だったり、大量の
ビタミンが含まれるスタミナ源だったことを知って、こ
れからは、甘酒も飲まなければと思う、単純な私です。
甘酒を作るこうじ菌「オリゼー」が、漫画「もやしもん」
でお馴染みのキャラだったのも親しみが増した理由。
昔読んだ文学作品と、好きな漫画が繋がる瞬間。ちょ
っと何だか面白いなあと、何が何に繋がるか、わから
ないものだなあと、変なところで感心したりしたりして。
最近では、本当に手にする事がなくなった、太宰作品。
今回、紹介されたダス・ゲマイネが、今でも十分通じる
青春のグダグダ感といいますか、いつの世も、若者は
空回りしながら悩むのだと、今さらながら、青臭かった
自分の姿と重なって、何とも気恥ずかしく。やっぱり太
宰は面白いなあと、彼の才能に恐れ入るといいますか。
だって・・・
なんというだらしなさ!
頭がわるいから駄目なんだ。
だらしがないから駄目なんだ。
ですよ? 頭が悪いから駄目なんだ。だらしがないから
駄目なんだ。なんというだらしなさ!と感嘆するセリフ。
面白いなあ。面白すぎる。でも、きっと昔はもっと、その
面白さに気づかないまま、夢中で読んでいた気がする。
それもそのはず。あの頃は、空回りしてる若者そのもの
だったのだから。駄目なんだ!…な、若者なんだもの。
青春スーツを再装着して、もう一度、太宰作品を読んで
みようかと、照れてる自分もまた恥ずかしいと思いつつ、
甘酸っぱい青春の一ページをめくってみようと思います。
「ダス・ゲマイネ」は、青空文庫のHPで読めます。↓
「ダス・ゲマイネ」(太宰治)
ですよ? 頭が悪いから駄目なんだ。だらしがないから
駄目なんだ。なんというだらしなさ!と感嘆するセリフ。
面白いなあ。面白すぎる。でも、きっと昔はもっと、その
面白さに気づかないまま、夢中で読んでいた気がする。
それもそのはず。あの頃は、空回りしてる若者そのもの
だったのだから。駄目なんだ!…な、若者なんだもの。
青春スーツを再装着して、もう一度、太宰作品を読んで
みようかと、照れてる自分もまた恥ずかしいと思いつつ、
甘酸っぱい青春の一ページをめくってみようと思います。
「ダス・ゲマイネ」は、青空文庫のHPで読めます。↓
「ダス・ゲマイネ」(太宰治)
「グレーテルのかまど」関連ブログはこちら↓
- 読んでおきたいベスト集! 太宰 治 (宝島社文庫)/宝島社

- ¥720
- Amazon.co.jp