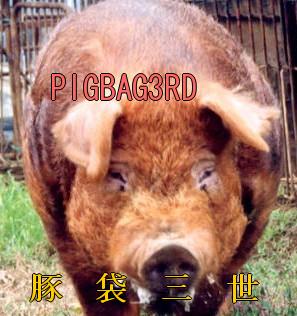豚袋でございます。
世間的には3連休が終わりまた明日が祝日ですね。昨年までの豚と違って、今年は世間のお休みの時に休む生活を送っております。それはいいのですが、そんな時に限って風呂が壊れたりなんだかんだと家でやることが多く、外出したりできておらず無為に時間を過ごしているような気がします。気候も秋めいてきましたし、そろそろ秋物を着る楽しみが出てきた頃ではないでしょうか?アパレル業界救済のためにも「書を捨てよ街へ出よう(そして洋服買ってね)」もしくは「書を捨てよネットに没頭しよう(そして洋服買ってね)」でよろしくお願い申し上げます(笑)
新しい書庫を立ち上げてしまいました。気軽に「曲単位で取り上げる」記事を書くことにしました。アルバム単位で書いていくとなかなかスポットを当てたくても当てられないものを取り上げたくなったのと、ちょっと気分転換も兼ねてツィッターとの中間くらいの感覚もいいのかな、と^^。いえ、決して手抜きとかそういうことではないんですけどね(笑)まぁ自分のブログは文字数が多くて、ついだらだらうだうだ書いてしまうので、もう少し書く側もブログを覗いていただく側にももっと気軽さがあっていいのかと思いました。よろしくお付き合いください。
さて本編の記事ですが、今回はダーク&コールドファンクの雄、ア・サートゥン・レシオを取り上げたいと思います。ブログを始めた頃にサードアルバム「SEXTET」を記事にしましたが、今回は事実上のデヴューアルバムでもある「TO EACH...」にスポットを当てようと思います。(事実上の、というのは最初のアルバム「The Graveyard and the Ballroom」はカセットのみの限定販売だった為)
ア・サートゥン・レシオ(以下ACRと表記します)はジョイ・デヴィジョンの所属レーベルとして有名な「ファクトリー・レコーズ」の代表的なバンドのひとつでありました。ジョイ・デヴィジョンがイアンの死もあっていやが応でも注目を浴び、ニュー・オーダーに繋がるなか、特に日本ではかなり相対的に地味なポジションを強いられたバンドではないかと思います。
とにかくこのバンドは「クール」でした。ラテンやファンクの音楽的ベースから「躍動感」や「陽気さ」「熱」というものを全て削ぎ落とした後に残る、極めて冷たく、ひりひりするような触感のリズムと音塊。それがACRの特徴でした。その音楽性は「コールド・ファンク」という言葉で言い表すしかないものでした。そしてそれは他に類をみない、かなり独自の音楽として昇華されたように思います。初めてその音に触れた時は衝撃的でした。
1980年初頭の英国はポスト・パンクの時代でした。パンクのサウンド背景でもあった単純な8ビート、3コードがひとつの役目を終え、精神性を残しながらより複雑化するか解体するかにみな躍起になっていた時代。ジョン・ライドンがPILでパンクを葬り去り、ポップ・グループがリズムの分断と継ぎはぎによる再構築で攻撃的に尖鋭化し、キリング・ジョークが呪術的要素をビートに持ち込んだりした時代。ACRはパンクの攻撃性とラテンやファンクのグルーヴ感を融合させた上でその双方の特徴的な部分を無力化して新しいサウンドにするという、非常にオルタナティヴな音楽を志向することにより頭角をあらわしたバンドだったのだと思います。
ファンクとパンクの融合を図った最初は前出のポップ・グループでした。ジャズ、ファンク等複数オリジンの音楽を背景にもち、ダブ処理によるサウンドエフェクトと剥き出しのギター音等々、ACRも共通する部分を多く持っていると思います。ただ、ACRとポップ・グループの間の圧倒的な違いは、「踊れるビートか否か」であると思います。ポップ・グループのビートはわざと「踊れない」ように分断した音塊でありました。一方ACRはあくまで「ダンス・ミュージック」である事にこだわり、パーカッシヴなビートとエコーバリバリのホーン、チョッパーなベースによって延々と続くかのようなループ感を特徴としています。そのループ感が独自のトランス感覚やクールなグルーヴを生んでいるように思います。
また、このアルバムはボーカルの体温のなさと何を言ってるかわからないつぶやきも、より無機的な印象を強くするのに役立っていると思います。この次のアルバムでは女性ボーカルを導入しましたが、ボーカルの役目は一緒です。歌詞で何かを伝える、というよりも、声という楽器に特化したような単なるサウンドとしての一部構成要素。そうした割り切り方もたまらなく妖しくクールだと思っていました。
残念ながらこのバンドは次第にポップ・ファンク化していき、後期のアルバムは本当につまらない凡作となっていってしまうのですが、初期のACRは本当に素晴らしい作品を残してくれたと思います。ファクトリーというインディーレーベルの気炎というか、そうした背景もあったのでしょうけど。冒頭の方に書きましたが、ある意味恵まれないバンドでもあったのではないでしょうか。ジョイ・デヴィジョンというトップもいましたが、その後のマッドチェスター・ブームまでには間があり、ファクトリーを離れ、ブームの頃には主役はハッピー・マンデーズにとって代わられ、と結構タイミングもよくないバンドだったと思います。そのあたりのポジショニングとしても好きなんですけど(笑)
ファクトリーというと、映画「24アワー・パーティ・ピープル」でその内幕を描かれているようですが、実はまだこの映画を見ておりません。レヴュー等を読んでもACRのAの字も出てこないので、きっととりあげられる事もないのだろうと半ばあきらめておりますが、やっぱり見ておかねばならないだろうなとは思っています。
最後にもう一曲聴いて本日は締めたいと思います。それでは、また。