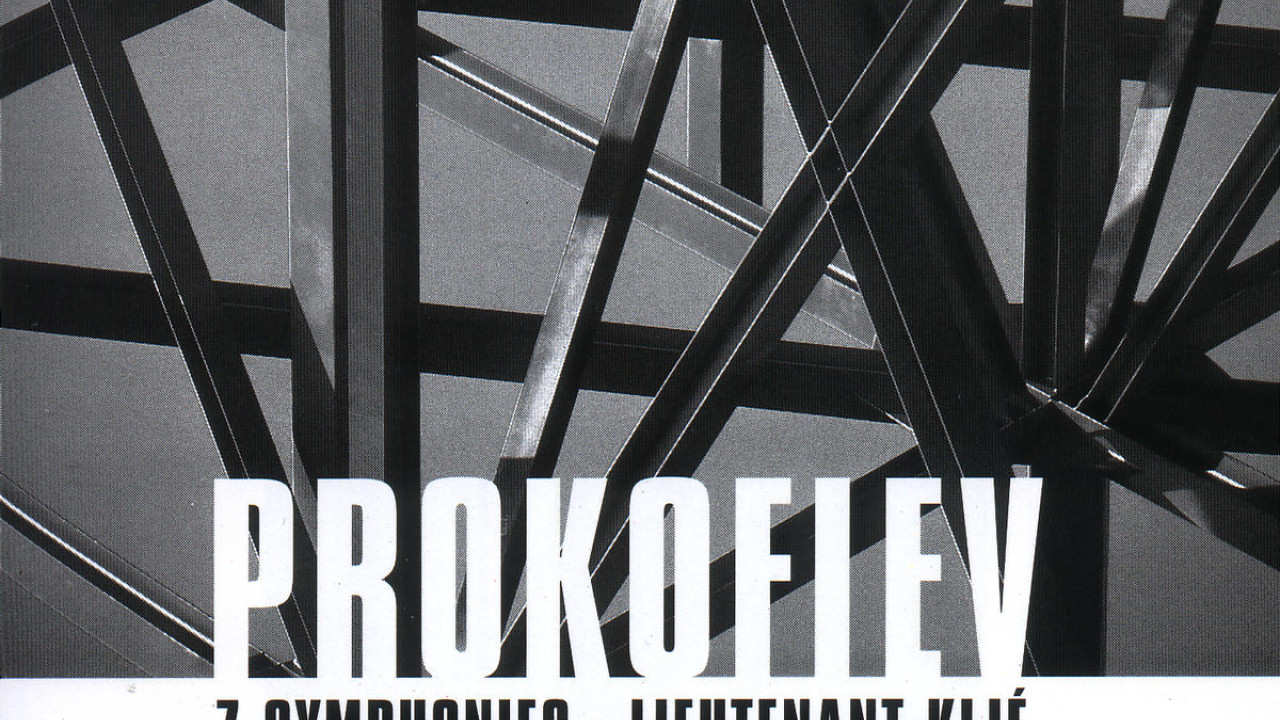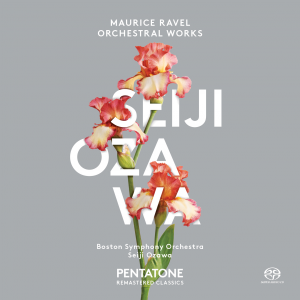小澤征爾さんの訃報に接して以来、ずっとその録音に耳を傾けています。
実演に接したのは2002年松本での第九だけでしたが、小澤さんが作る音楽と小澤さんの生き方から、これまで何度も励ましと勇気をもらってきたように思います。
一昨年、桐朋学園大学に宗教学の講義ができて、自分がそれを担当することになったとき、ああ、小澤さんが学び教えた学校の教育に携わることができるのだな…と、かつて母校で教鞭を執ることが決まったときよりも悦びを感じたのは事実です。
以後二年間、毎週仙川に教えに行き、学生の皆さんや先生方と言葉を交わすうちに、小澤さんへの尊敬の念はいっそう大きなものとなりました。
そして、それまでとは異なる心持ちで、サイトウ・キネンを聴きに松本へ、水戸室内管を聴きに水戸へ、新日フィルを聴きに錦糸町へ足を運ぶようになりました。
2022年11月25日、アンドリス・ネルソンス指揮サイトウ・キネン、マーラー「交響曲第9番」の終演後、ステージ上に現れた小澤さんの姿を忘れることはないでしょう。
ここでは、これまでも頻繁に聴いてきたし、これからも折に触れて聴くであろう録音を記して、小澤さんを追悼いたします。
(アルバム・ジャケットを載せたいところですが、著作権の関係で叶わないので、レコード会社の公式サイトへのリンクを記しておきますね。)
●リヒャルト・シュトラウス「オーボエ協奏曲」
宮本文昭、水戸室内管弦楽団、1999年録音、SONY
今月9日、小澤さんのことを知った夜、最初に聴いたのがこの録音です。
湿気が多い日の夕陽をみるかのようで、とても胸にしみます。
しかも、年齢を重ねるごとによりいっそう。
宮本さんのオーボエが絶品なのはもちろんですが、なんという弦のざわめき!
大好きな演奏です。
●武満徹「カトレーン」
TASHI、ボストン響、1977年録音、Deutsche Grammophon
「Quatrain」とは「四行詩」のこと。
この曲を耳にするたびに、平安期の宮廷人を思い浮かべます。
減退し消えゆく音の美しさを教えてくれた録音です。
以下はアルバムを。
●バルトーク「弦楽器・打楽器とチェレスタのための音楽」&「管弦楽のための協奏曲」
サイトウ・キネン・オーケストラ、2004年録音、PHILIPS
悲しいことや面白くないことがあったとき、僕はこのアルバムを大音量で聴きます。
聴き終わると、たいていのことは何でもなくなります。
サイトウ・キネンって抜群に弦がクリアで豊穣ですよね。
おそらく欧米のどのオケよりも楽器の質がよいのだと勝手に思っています(演奏者と指揮者が優れているからこそなのは言うまでもありません)。
最高に気持ちのいいアルバムです。
(現役盤はCDですが、かつてPHILIPSからSACDが出ていました。素晴らしい音質ですので、中古店で見つけたら即買いしてください。)
●プロコフィエフ『交響曲全集』+組曲「キージェ中尉」
ベルリン・フィル、1989~92年録音、Deutsche Grammophon
小澤さんの強みは、卓越したリズム感と、音楽の見通しのよさにあるのではないでしょうか。
(そういえば2002年のヴィーン・フィル「ニューイヤーコンサート」においても、ヘルメスベルガー「悪魔の踊り」が最も光っていたように感じます。)
そうした美点が最も発揮されるのは、やはり19世紀後半以降の音楽においてです。
これはオケがベルリン・フィルですし、全集としてのまとまりもありますので、何度聴いても飽きません。
●ラヴェル『管弦楽曲集』
ボストン響、1974~75年録音、Deutsche Grammophon
LPで四枚分あります。音質的に最も気に入っているのは、オランダのPENTATONEが出しているSACDで、「クープランのトンボー」、「古風なメヌエット」、「マ・メール・ロワ」、「高雅で感傷的なワルツ」、「海原の小舟」が収められています。
「香り」というものは、部分が全体のなかに位置付けられ、ただ音が鳴っているというような曖昧な箇所が無くなって初めて発生するものなのですね。
僕にとって最も小澤さんを感じる一枚です。
ヴィーン・フィル、ベルリン・フィル、ロイヤル・コンセルトヘボウ管といった欧州トップ・オブ・ザ・トップのオケの定期公演に、毎年のように呼ばれた日本人指揮者は小澤さんしかいません。
僕は、いや僕たちは、小澤さんの後に続く人をずっと待ち望んでいます。
いつの日か山田和樹さんや沖澤のどかさんが、もしくは(これは贔屓が入っていますが)いま/これから桐朋学園で学ぶ若者が、僕たちの夢をきっと叶えてくれるはず、そう信じています。