学校卒業後何十年経っても、担任を呼んで定期的にクラス会をやり、「○○先生にまた会いたい。」
と言っている人の話を聞くと、非常に意外であり、羨ましくもある。
自分の担任だった人には、今でも会いたいと思える人物はいない。いや、実はそれに値する人は二人居たが、一人は病弱のため途中で任を解かれ、一人は自ら教職を辞したらしく、いずれも今現在音信不通である。二人の共通項は、真っ正直で、生き方が下手そうだったということ。この評価の底流には自分の姿が投影しているようだ。この基準が妥当かどうかは諸説あるだろうが、鈍感、日和見、打算、猜疑、妄信、傲慢、そして事なかれ主義がにじみ出ているその他の担任よりは自分にとっては非常に信頼できる存在であったことは確かなことだ。
前回書いたごとく、劣等生の自分が意外な才能を垣間見せた時、暗鬱とした黒い気持ちを陰湿な嫌がらせとして吐露してきた同級生たちの仕打ちを、教師たちは授業を行うことで手一杯で余裕がなく、誰もそれらを見抜く教師は居なかった。
今日、イジメのあるやなしやの問いに、「分からぬ。」あるいは「なかった。」と答える学校側が多い事をよくマスコミが批判しているのを見るが、自分はこれに嘘はないと見ている。彼等は授業や雑務に手一杯で、学生個々の動向まで把握できていないのが実情だろうと思えるからだ。教師はそこまで求め得るほどの人格者ではない。というのが、私の経験上の考え方なのだ。
しかしながら、もちろん、ひどい教師ばかりではない。自分にブンガクの光を与えてくれた現代国語の教師のことを記してみたいと思う。
教師の名前はSと云った。160センチ前後の小柄でずんぐりとした体格。着古しよれよれの背広に底が磨り減ったぼろサンダルという出で立ちは、どう見ても最果ての地からやって来た田舎教師然としており、当時でもすでに珍しいタイプだった。しかし、S教師は下膨れの頬にいつも微かな笑みを浮かべていて、なんとなく安心感を持たせる風貌でもあった。
その彼が教科書を朗読した時のことだった。やや甲高くしゃがれ気味な声は決して上質なものとは云い難かったが、その読み上げる"間”と抑揚は絶妙で、その心地よさに自分は教科書の中では初めて、その物語の情景を思い浮かべてしまったのだ。
この時の教材は梶井基次郎の『闇の絵巻』。自分は物干し竿のような棒を身体の前に突き出しながら闇の中を全速力で疾走する泥棒の姿をありありと見たのである。実はこの時まで梶井基次郎を知っていたのは名前のみで、作品には触れたことがなかった。いつか写真資料で見た梶井のゴリラのような風貌が、作品から遠ざけていたのだと思う。自分はこの日、紀伊國屋へ走り、新潮文庫を買い求めた。
この日以来、梶井基次郎は自分の愛する作家のひとりとなったのである。
後に知ったことだが、S教師は演劇の指導で定評があり、前任の学校では演劇部の顧問をしていて、いくつも権威ある賞を受賞させていたと聞いた。あの朗読の魅力はこの辺にあるのではと思ったものだ。
ある日、自分は例によって、教科書に掲載された文章を独特な解釈で紐解いて発表させられていた。この内容は今となっては気恥ずかしく、稚拙そのものので、よく人前で発表したものだと思うようなものだが、S教師はそれを否定せず、内容は尊重しつつも細かい誤りを正してゆき、結局自分の反れていた解釈をかなり修正してくれたのだ。これ以降自分はちょっとした解釈法のコツを摑み、授業や試験では突拍子もない異説を唱えることは稀となった。
当時の自分はすでに生活の大部分が"Rock”に埋もれてしまっており、演劇をやってみるという方向には行かなかったわけだが、今は部活としてやってみても面白かったのではないかと少々後悔の念も起こる。わが校が優秀な演劇を見せると評判になり、高い評価を得るようになるのは自分が卒業して間もなくのことである。
細かなことを書くときりがないが、教科書に時々短歌が掲載されていた釈迢空が民俗学者折口信夫 だということを教えてくれたのもS教師だった。この後、今に続く民俗への興味の切っ掛けになったこともまた彼の私への貢献である。S教師と私的な交流は全くなかったが、彼の授業を受けた二年間が自分の世界を広げてくれたことは間違いなく、今でも大変感謝している。
S教師は今改めて逢ってみたいと思う、数少ない存在である。
[今回はえらそうに書いてるなぁ、と思いながらも]
檸檬 (新潮文庫)/梶井 基次郎

¥420
Amazon.co.jp
歌集 倭をぐな (短歌新聞社文庫)/釈 迢空

¥700
Amazon.co.jp
初稿・死者の書/折口 信夫

¥3,570
Amazon.co.jp
私の折口信夫 (中公文庫)/穂積 生萩
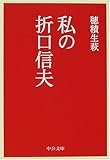
¥840
Amazon.co.jp
と言っている人の話を聞くと、非常に意外であり、羨ましくもある。
自分の担任だった人には、今でも会いたいと思える人物はいない。いや、実はそれに値する人は二人居たが、一人は病弱のため途中で任を解かれ、一人は自ら教職を辞したらしく、いずれも今現在音信不通である。二人の共通項は、真っ正直で、生き方が下手そうだったということ。この評価の底流には自分の姿が投影しているようだ。この基準が妥当かどうかは諸説あるだろうが、鈍感、日和見、打算、猜疑、妄信、傲慢、そして事なかれ主義がにじみ出ているその他の担任よりは自分にとっては非常に信頼できる存在であったことは確かなことだ。
前回書いたごとく、劣等生の自分が意外な才能を垣間見せた時、暗鬱とした黒い気持ちを陰湿な嫌がらせとして吐露してきた同級生たちの仕打ちを、教師たちは授業を行うことで手一杯で余裕がなく、誰もそれらを見抜く教師は居なかった。
今日、イジメのあるやなしやの問いに、「分からぬ。」あるいは「なかった。」と答える学校側が多い事をよくマスコミが批判しているのを見るが、自分はこれに嘘はないと見ている。彼等は授業や雑務に手一杯で、学生個々の動向まで把握できていないのが実情だろうと思えるからだ。教師はそこまで求め得るほどの人格者ではない。というのが、私の経験上の考え方なのだ。
しかしながら、もちろん、ひどい教師ばかりではない。自分にブンガクの光を与えてくれた現代国語の教師のことを記してみたいと思う。
教師の名前はSと云った。160センチ前後の小柄でずんぐりとした体格。着古しよれよれの背広に底が磨り減ったぼろサンダルという出で立ちは、どう見ても最果ての地からやって来た田舎教師然としており、当時でもすでに珍しいタイプだった。しかし、S教師は下膨れの頬にいつも微かな笑みを浮かべていて、なんとなく安心感を持たせる風貌でもあった。
その彼が教科書を朗読した時のことだった。やや甲高くしゃがれ気味な声は決して上質なものとは云い難かったが、その読み上げる"間”と抑揚は絶妙で、その心地よさに自分は教科書の中では初めて、その物語の情景を思い浮かべてしまったのだ。
この時の教材は梶井基次郎の『闇の絵巻』。自分は物干し竿のような棒を身体の前に突き出しながら闇の中を全速力で疾走する泥棒の姿をありありと見たのである。実はこの時まで梶井基次郎を知っていたのは名前のみで、作品には触れたことがなかった。いつか写真資料で見た梶井のゴリラのような風貌が、作品から遠ざけていたのだと思う。自分はこの日、紀伊國屋へ走り、新潮文庫を買い求めた。
この日以来、梶井基次郎は自分の愛する作家のひとりとなったのである。
後に知ったことだが、S教師は演劇の指導で定評があり、前任の学校では演劇部の顧問をしていて、いくつも権威ある賞を受賞させていたと聞いた。あの朗読の魅力はこの辺にあるのではと思ったものだ。
ある日、自分は例によって、教科書に掲載された文章を独特な解釈で紐解いて発表させられていた。この内容は今となっては気恥ずかしく、稚拙そのものので、よく人前で発表したものだと思うようなものだが、S教師はそれを否定せず、内容は尊重しつつも細かい誤りを正してゆき、結局自分の反れていた解釈をかなり修正してくれたのだ。これ以降自分はちょっとした解釈法のコツを摑み、授業や試験では突拍子もない異説を唱えることは稀となった。
当時の自分はすでに生活の大部分が"Rock”に埋もれてしまっており、演劇をやってみるという方向には行かなかったわけだが、今は部活としてやってみても面白かったのではないかと少々後悔の念も起こる。わが校が優秀な演劇を見せると評判になり、高い評価を得るようになるのは自分が卒業して間もなくのことである。
細かなことを書くときりがないが、教科書に時々短歌が掲載されていた釈迢空が民俗学者折口信夫 だということを教えてくれたのもS教師だった。この後、今に続く民俗への興味の切っ掛けになったこともまた彼の私への貢献である。S教師と私的な交流は全くなかったが、彼の授業を受けた二年間が自分の世界を広げてくれたことは間違いなく、今でも大変感謝している。
S教師は今改めて逢ってみたいと思う、数少ない存在である。
[今回はえらそうに書いてるなぁ、と思いながらも]

¥420
Amazon.co.jp
歌集 倭をぐな (短歌新聞社文庫)/釈 迢空

¥700
Amazon.co.jp
初稿・死者の書/折口 信夫

¥3,570
Amazon.co.jp
私の折口信夫 (中公文庫)/穂積 生萩
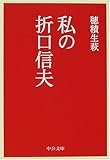
¥840
Amazon.co.jp