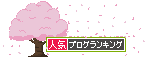復興構想は、「慣れ親しんだもの」は一度失われたら、復旧することはあり得ないという冷厳な現実から出発するものでなければならない。そうでなければ、いかなる復興構想も空虚なものとなる。
震災後、政府の復興構想会議をはじめとして、新聞、雑誌、テレビ、あるいは書籍など、あちこちから、復興構想の提案が乱発されている。
だが、それらのいずれもオークショットの言う「見知らぬもの」「試されたことのないもの」「神秘」「可能なもの」「無限のもの」「遠いもの」「過剰なもの」「完璧なもの」そして「理想郷における至福」で埋め尽くされているのだ。
例えば、四月十四日の復興構想会議において、菅直人首相は「ただ元に戻す復旧ではなく、創造的な復興案を示してほしい」と述べた。
震災によって打ちひしがれている被災者には、明るい未来を約束しさえすればよいとでも思っているのだろう。確かに、世論もそれを要求していた。首相は、実際にそれをやってみせたのだが、しかし実際には、被災者には虚しさが募るばかりであった。
それは、「ただ元に戻す復旧ではなく」という発言にあるように、失われた家族や友人、日常生活といった大切な「慣れ親しんだもの」は、ただ元に戻す復旧をしたくてもできないのだという被災者の悲哀を、首相がまったく共有していないからなのである。
復興構想会議のメンバーたちも同じだ。彼らが「理想郷における至福」を語れば語るほど、虚しさは増すばかりであろう。
首相や復興構想会議だけが問題なのではない。
そもそも、多くの日本人が、敗戦によって旧い日本が破壊され、アメリカによって改造されたことで、より良くなったのだと思ってきた。そんな戦後日本人は、大震災による破壊をみて、安易に「これこそ、より良い社会へと構造を改革するチャンスである」と思うのである。
例えば、代表的な構造改革論者である大田弘子氏は、「これを機に農地の大規模化を進め、コメの生産調整を廃止」せよと提案する。(産経新聞4月15日)。「これを機に」などと、まるで震災による破壊を喜んでいるかのようである。敗戦後に占領軍が農地改革をやったように、震災後に農業構造改革をやろうというわけだ。
戦後日本人たちは、敗戦によって失われたものを忘れ、戦没者を真摯に追悼しようとせず、それどころか敗戦を歓迎すらして、戦後復興を誇ってきた。
彼らは、戦後復興と震災復興とを連想しているのだ。だからこそ、「単に元に戻すだけではなく、これを機に云々」などと言い募ることができるのである。
これからも、「理想郷における至福」の復興構想が、次から次へと提案されることだろう。人々は、そんな復興構想をみずから要求しておきながら、出てきたものを見て失望するということを繰り返すだろう。
そうして震災後の日本には、「現実のもの」を何ひとつ構想できないという虚しさが残ることだろう。
その虚しさは、「慣れ親しんだもの」を失ったことに対する哀悼の念を欠いた戦後日本そのものである。
(表現者37号 '11年6月)
『反官反民』 中野剛志