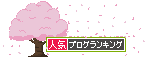イギリスの保守主義の政治哲学者マイケル・オークショットは、「保守的であること」というエッセイの中で、次のように述べている。
保守的であるとは、見知らぬものよりも慣れ親しんだものを、試されたことのないものよりも試されたものを、神秘よりも事実を、可能なものよりも現実のものを、無限のものよりも限度のあるものを、遠いものよりも近くのものを、過剰なものよりも十分なものを、完璧なものよりも便利なものを、理想郷における至福よりも現在の笑いを、好むことである。
親しい関係や忠実さの方が、より利益になる愛情への誘惑よりも好まれる。得ることや拡げることは、守ること、育むこと、そして楽しむことほど重要ではない。失うことを嘆く方が、新規性や約束による興奮よりもずっと激しい。
多くの人が東日本大震災の猛威を見て恐怖し、無力感や喪失感に襲われたことだろう。筆者もそうである。
ただし、その無力感や喪失感は、巷で言われているように、地震や津波といった自然現象が、建物や堤防、あるいは原子力発電所といった人間の人工物や技術をいとも簡単に破壊してしまったことによるのではない。
「人間の技術文明は、自然の前に無力である」などと、はじめから分かっていたことを、いまさら思い知って反省してみせるような態度は、陳腐なだけでなく小賢しい。
「原子力発電所は、絶対安全ではなかったではないか」と怒ってみせるのも同じである。
神でもないのに絶対の安全を保証できるわけがない。人々は、政府、政治家、電力会社に「絶対安全」と言わせて、万一の場合に責任を追及できるようにした上で、原子力発電所の恩恵を享受していただけなのだ。
多くの人々が大震災から感じた喪失感は、技術文明が失われたことによる嘆きではない。技術文明など、とっくの昔から、本当は信じてはおらず、信じたふりをしてきただけなのだ。
本当の喪失感は、冒頭のオークショットが保守しようとしたものが失われたことによるのではないだろうか。
つまり、被災した東北の人々は、「慣れ親しんだもの」「試されたもの」「事実」「現実のもの」「限度あるもの」「近くのもの」「十分なもの」「便利なもの」「現在の笑い」を失ったのである。
住み慣れた村や町、長く営んできた仕事、家族や隣人、変化の少ない日常生活、親子や友人のたわいもない冗談などが一瞬にして消えたことが、人々に深い喪失感をもたらしたのである。
「慣れ親しんだもの」を失ったときの喪失感が深いのは、それを取り戻すには長い時間がかかるからである。
もっと正確に言えば、一度失われた「慣れ親しんだもの」それ自体は、取り戻すことはできない。
長い時間をかけて、別の「慣れ親しんだもの」を代わりにつくることで、喪失感をまぎらわせ、忘れようとしていくしかない。
政府は「復旧・復興に全力を挙げる」と繰り返している。知識人たちは、例によって無責任に、「復旧・復興をもっと急げ」と政府を批判している。被災者以外の傍観者たちは、「日本は必ず復興できると信じよう」と激励を送っている。
だが、これらの言説には、「慣れ親しんだもの」を失うということは、取り返しのつかないことだという真剣さが根本的に欠けている。一度失われた「慣れ親しんだもの」は、復興どころか、復旧することすらあり得ないのである。
復旧・復興することができるのは、道路や橋や建物といった人工的な建造物や発電所といった技術文明だけである。
家族や友人との関係は、かれらが命を落とせば、二度と戻ってはこない。
ふるさとの村や町は、仮に戻ることができても、震災前とは何かが違っているだろう。
農業、漁業、町工場の仕事も、多くが大震災によって断絶を余儀なくされる。仮に仕事を再開することができたとしても、完全に元通りになるというわけにはいかないであろう。
大規模な自然災害や事故が起きた地には、碑がたてられている。
三陸の村や町にも、かつての大津波を記録する石碑が立っているところがあったという。
もし、大災害が復旧可能なものを破壊するだけであるなら、碑をたてる必要などない。復旧することができない「慣れ親しんだもの」が失われたから、人々は碑をたてて、記憶を残そうとするのだ。
(表現者37号 '11年6月)
『反官反民』 中野剛志