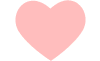以前、私が事務局を担当していた
大阪大学臨床栄養研究会からのお知らせです。
これは、阪大の臨床系の医局が持ち回りで
毎月違うテーマで講演を行い、
医療関係社や一般の人たちに知識を深めていただこうというものです。
もう、30年は続いているでしょうか?
ぜひ、興味のある方はご参加くださいね。
なお、毎月のお知らせをメールにてご希望の方は、
私までご連絡いただければ、登録させていただきます。
お名前、所属先などを書いて、下記アドレスに
 くださいね。
くださいね。 paris*paristyle.net (*を@に変えてくださいね!)
paris*paristyle.net (*を@に変えてくださいね!) 日 時: 平成22年7月12日(月) 18:00~
日 時: 平成22年7月12日(月) 18:00~ 場 所: 大阪大学医学部 講義棟2階 B講堂 (吹田市山田丘2-2)
場 所: 大阪大学医学部 講義棟2階 B講堂 (吹田市山田丘2-2) テーマ: 「臨床医学に必要な生化学の知識ついて」
テーマ: 「臨床医学に必要な生化学の知識ついて」今回は、山中温泉医療センター センター長 大村 健二 先生
前金沢大学内分泌・総合外科 科長(臨床教授)による講演です。
多くの方々のご参加をお待ちしております。
*****************************************************************************************
ヒトを含めた恒温動物の体内では、極めて精緻な機構によって恒常性が維持されている。
また、その根幹にあるのは三大栄養素の代謝である。今回、臨床医学に役立つ三大栄養素の
代謝に関する知見について、生化学的観点から解説する。
重要な熱源であるグルコースの血中濃度(血糖値)は、
一定の範囲内に保たれていることが望ましい。血糖値が一定に保たれる現象を
glucose homeostasisと呼ぶ。その主役は肝臓であり、
脇役を骨格筋が務める。肝臓は、グリコーゲンの形で蓄えられているグルコースを
血中に放出できる唯一の臓器である。また、Cori回路、アラニン回路などのグルコースの
再利用経路の代謝も肝細胞内で営まれる。
体蛋白については、回避することができない喪失、不可避的蛋白喪失(obligated protein loss、OPL)が認められる。
OPLの補充には、臨床的実験によって求められたOPLに安全域を確保し(mean+2SD)、
さらに食餌中の蛋白質の利用率を考慮した蛋白質を摂取する。慢性腎臓病の保存期など、
蛋白質の摂取制限が必要な病態の栄養管理でも、
制限の限界値の算出にはOPLを考慮すべきである。
食餌内の脂質は、中性脂肪とコレステロールに大別される。
そのうち大半を占めるのは前者であり、後者の摂取量は脂質の1%強に過ぎない。
中性脂肪(トリグリセリド、TG)からは、
消化の過程で脂肪酸がはずれていく。ほとんどがモノグリセリド、もしくは脂肪酸と
グリセロールに分解されて小腸上皮に吸収される。しかし、これらは小腸上皮内で
TGに再合成され、リン脂質やアポ蛋白と結合してキロミクロンとなる。
キロミクロンを豊富に含んだリンパ液は胸管に流入し、静脈角に注ぐ。
したがって、食後にみられる脂肪粒子の動態は、脂肪乳剤の中心静脈内投与に酷似している。
栄養管理を行ううえで、正しい生化学の知識に立脚する意義は極めて大きいと言える。
次回、第310回CNCは、大阪大学保健センター 守山敏樹先生のお世話で
平成22年9月13日(月)に開催予定です。
 こちらにもステキな情報がいっぱい!
こちらにもステキな情報がいっぱい! こちらにもステキな情報がいっぱい!
こちらにもステキな情報がいっぱい!