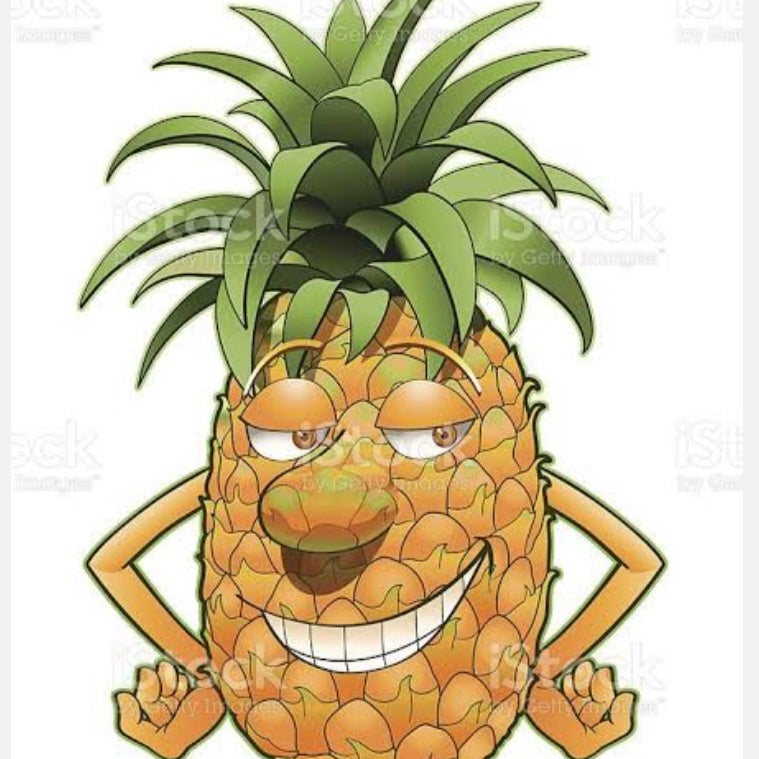お疲れ様です。
入試問題研究会@なかのZEROに行ってきました![]()
ホールの7〜8割程度の埋まり具合だったでしょうか![]()
ーーーーーーーーーーー
【概要】
・4教科の先生方が同時に登壇されるスタイル。
・基本的には、各教科毎に「入試の出題傾向」「学習の方法」などを説明。
・もっとも、教科毎に分断するのではなく、「問題文の長文化」など共通する説明については、適宜他の教科も説明あり。
・スライド資料は、一部を除き冊子として配布。
・オン・ザ・ロードと同様に入場順に詰めて着席する方式。
【個人的に印象に残った話】
・中学受験が終わったとしても、勉強は続くし、親子関係も続いていく。
→中学受験はゴールでも何でもない。親子関係を犠牲にする必要はない(私の意訳です。発言は上記のみ)。
【各論】
🔹国語
1️⃣2024年入試問題の紹介
・物語として「成瀬は天下を取りにいく」など、説明的文章として「増えるものたちの進化生物学」などの紹介
・物語は「本当の自分らしさとは何か」、説明文は「コロナ以降、今後の人間の生き方」がテーマ
・会話文の問題(浦和明の星・本郷など)
・本文を踏まえた自分の考えを述べる出題(栄東など)
→社会もこの出題形式が増加
→後期に過去問演習をする
2️⃣入試で求められる力
①豊かな語彙力
・漢字、語句の学習は最優先
→ことわざ、慣用句、敬語なども含む
→「読む・書くツール」
②文章を客観的に読み取る力
③論理的に解き進める力
→入試問題を前提に「解答の筋道」を理解する
3️⃣今後の学習
①の学習方法
・「読む・書くツール」「語句のたしなみ」「合格完成語句(6年後期)」
→使える語句の獲得
→漢字テストは新しい言葉を知るきっかけ。
単に漢字の「形」を覚えるだけではない。
例文作り。「どういう意味か聞く」
→辞書で「意味」「使い方」を確認する
→意識的に(それでいてさりげなく)親子の会話で四字熟語・慣用句・ことわざなどを使う
②の学習方法
・本科テキストの文章の読み直し
・先生が線や印をつけた意味の確認
・先生に習ったやり方で家でも学習する(真似する)
・自己流はよくない
③の学習方法
・自分の解き方を分析する。
・なぜ、誤った解答をしたのか。
・正しい解答をするには、なにに気づければ・意識すればよかったのか
・自分の癖を確認する(誤答する癖)
・「なんとなく」振り返るのをやめる
④記述問題の学習方法
・「空欄」ではどこまで理解できているのか分からない。
・テストの時に「空欄」であっても、テスト直しの時は必ず書いてみる。
・書くべきポイントが違う場合
→問題の条件の読み落とし?
・本文の手がかりが探せなかった場合
→読み直し
・とにかく「書き直す」ことが大切
初めは大変かもしれないが、練習しないとできるようにならない。
諦めずにやる。続けていく。
🔹算数
1️⃣近年の出題傾向
・目新しい問題の減少
→「やったことのある問題(全く同じではない)」で差がつく
・文章や情報量(統計資料、ルール、会話文)の増加
→文章の誘導に乗る必要があるため、一つの解き方に執着するタイプは気をつける
→入試の年数を用いた問題(2024年など)
→2025は平方数のため、昨年は平方数の問題が多かった??
暗記してほしい平方数は1〜20、25。
・作業の必要性
→情報の可視化
→補助線をひく。作図する。
2️⃣求められる力
・6年夏期までに「基本」を定着させる
・条件を正しく理解し、正しく使う
・手を動かす
3️⃣今後の学習
・6年夏期までに「本科」の知識・記述、「栄冠」の学び直し①を確実にする
・授業で習ったやり方でやる
・6年夏期は「全範囲の問題演習」
→やるべきことの明確化
→担当教師に相談を
🔹社会
1️⃣時事問題
・時事そのもの
→広島サミットの参加国など
→6年12月以降、「重大ニュース」で総ざらい
→しかし、普段から日常生活で事実問題には触れておくべき(季節の行事なども)
→予想される時事(北陸新幹線・新紙幣・パリ五輪・米国大統領選挙など)
・時事に関連した普段の学習内容
→内閣総理大臣の説明、世界貿易機構など
→6年冬季講習で「予想問題」をやる。
→「時事そのもの」よりもこちらの方が出題量は多い(日頃の学習)
2️⃣漢字
・既に漢字指定の学校を受験する場合は、必ず漢字でかけるようにすること
→対象校はマイニチノウケンで確認可能
→反対に、漢字指定でない学校を受験する場合には、無理に漢字で記載しない方が良い(本番では)
・「都道府県」「歴史人物」「日本国憲法の条文(穴埋め)」は漢字指定となりやすい
3️⃣資料などから考えさせる問題
・日特にて演習をする
→資料(グラフ)などの読み方。
→とにかく手を動かす。
→選択肢の取捨選択、時間配分など
🔹理科
1️⃣思考力を問う問題
・問題文をよく読むこと
→思考力とは、読み取って考えること
→何を問われているか
・問題文全体の流れを読む
→設問全体から何がわかるか
→ヒントがあるか、他の小問が誘導になっていないか
2️⃣知識問題
・「地層の変化と変化の原因」が頻出単元
→単純に知らないと解けない問題である。
→「理科フォローアップ図鑑」「知識のまとめ」
→覚えるとしても「理屈」から理解する方がよい
もっとも、覚えるしかないものもあるので、何度もノートやテキストを確認するしかない
3️⃣計算を要する問題
・決して「逃げない」
→意外と解きやすい問題が多い
→結局、中学・高校でも計算を要する問題は必ずやるので、逃げようがない
・法則を理解し、法則をもとに書き出す
→書き込む。可視化。手を動かす。
→理科は比例・反比例の関係が多いので、みえてくる
→眺めていても解けるようにはならない
【その他(全教科を通じて)】
・夏期講習前までに「基本(学び直し①)」を確実にするよう何度も強調していました。
・また、解法についても、授業で習ったやり方でやるよう何度も強調していました。
これは所属しているクラスによって解法が異なることがあるものの、当該クラスのレベルに即した解法を教えていること、
我流では再現性が低いことなどが理由と思われます。
・学習の成果が現れるのには、どうしても時間がかかる(3ヶ月とか)。
これは受験本番まで学力の向上が見込まれるという意味も含んでいると思いました。
・オン・ザ・ロードよりも実践的な内容だったと思います。
学習方法などの具体的な指摘があったためです。
・全体として、サピの入試分析会と同趣旨のことを述べていたように思います。
もちろん、サピの方が要求が厳しいですが。。
★参考
ーーーーーーーーーーー
内容に誤りがあったとしても責任は負いません![]()
では!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()