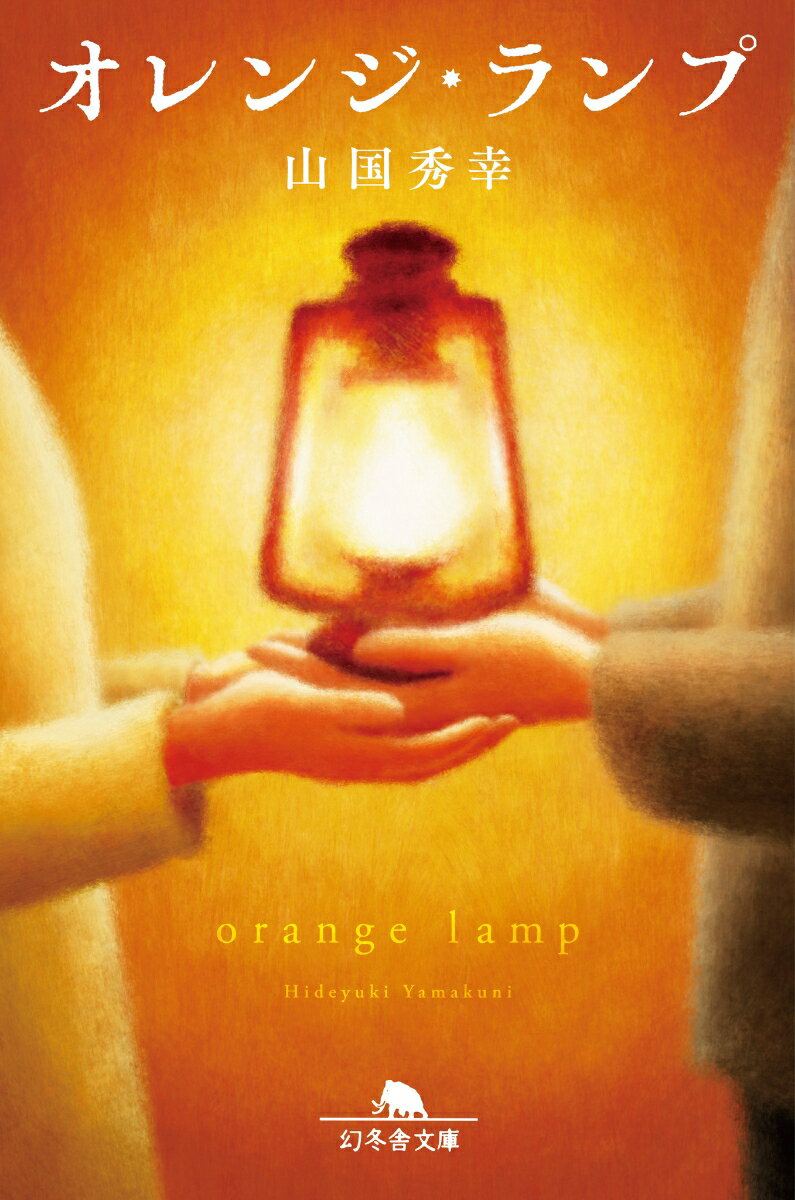ずっと見たかった映画『オレンジ・ランプ』を観てきました
こんにちは、あーこです。いつもブログを読んでくださり、ありがとうございます。
2月15日、ずっと見たかった映画『オレンジ・ランプ』をついに観に行ってきました。
映画を観たいと思ったきっかけ
昨年10月、認知症当事者である丹野智文さんの講演会に参加しました。丹野さんが認知症と診断されてからの経験を語ってくださり、そのお話が映画になっていると知ってから、どうしても観たいと思っていました。
ただ、この映画は全国で常に上映されているわけではなく、各地で上映会が開かれるスタイル。11月に自宅から2時間ほどの場所で上映されていましたが、仕事の都合で行けず…。諦めかけていた時、主任ケアマネ研修の中で「今度『オレンジ・ランプ』を上映します」というお知らせを聞きました。
上映場所の説明を聞き、さらに行ってみたいという気持ちが大きくなりました。 「絶対に観に行きたい!」と決めました。
研修中は日時を聞けなかったので、後日カフェのオーナーさんにメッセージで確認。2月15日と知り、その日を心待ちにしていました。
認知症と診断された39歳の営業マンの物語
映画は、39歳で認知症と診断された丹野さんの実話をもとにしたものです。
仕事でも日常生活でも、物忘れが増えてきた丹野さん。診断後、周りは「何もできなくなるのでは…」と心配し、先回りして何もかも手を貸そうとします。
例えば、コーヒーを淹れる時に「何杯豆を入れたか分からなくなった」という丹野さんに、奥さんは「もうコーヒーを淹れなくていいよ」と声をかけます。きっと優しさからの言葉だったと思いますが、本人にとっては「もう自分は何もできない」と突きつけられたように感じたのではないでしょうか。
できることはまだたくさんある
認知症になると、できないことが増えていくのは事実です。でも、できることもまだまだたくさんある。映画は、その大切さを伝えてくれました。
「できることは本人にやってもらい、周りは必要な時だけ手を貸す」 「認知症の“人”ではなく、“一人の人間”として接する」
この映画は、認知症当事者の思いだけでなく、家族や周囲の関わり方、そして地域社会全体の在り方を考えさせてくれる作品でした。
専門職として感じたこと
介護職として、私たちは「この病名なら、こんな症状がある」と知識で利用者さんを見てしまいがちです。でも、それは“フィルター”をかけて見ているのかもしれないと、ハッとしました。
大事なのは、病名や症状ではなく、「その人自身を知ること」。 もっともっと話を聞き、その人を理解しようとする姿勢が大切だと感じました。
専門職として忘れてはいけないこと
私たち福祉職は、つい「今は大丈夫でも、この先は…」と先回りしてサポートしがちです。でも、それが結果的に“その人の役割”や“できること”を奪ってしまうこともあるのです。
安心・安全ばかりを優先して、本人の楽しみや自立を奪ってはいけない。 「できることは続けてもらい、一緒に生活していく」。 その大切さを、この映画は教えてくれました。
もっと多くの人に観てほしい映画
認知症になっても、自宅や地域で暮らし続ける人が増えるためには、私たち一人ひとりの理解が必要です。
個人で映画上映を企画するのはハードルが高いですが、市町村や学校で上映してくれたら、多くの人にこの大切なメッセージが届くのにな…と思いました。
映画を上映してくださったカフェも、とても素敵な場所だったので、そのお話は次回のブログでご紹介しますね。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました! いいねやフォローが励みになります。また次回お会いしましょう!