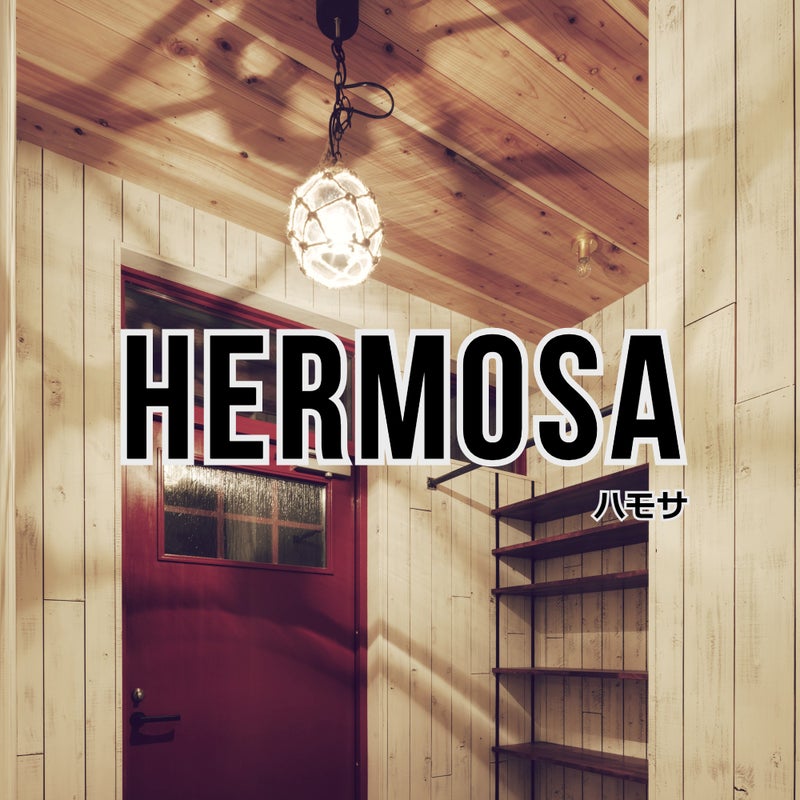一級建築士である私が設計した物件をはじめ、インテリアや家づくりについて情報発信しています。
また、築52年の中古住宅を購入しリノベした記録、日々の暮らしについても書いています。
↓バックナンバーは各カテゴリーから↓
おもしろい論文を見つけました。
国立研究開発法人科学技術振興機構
世界幸福度ランキングでは日本はG7の中で最下位、OECDの中でも低い水準です。
一人あたりのGDPや平均健康寿命に関しては高水準なので客観的幸福度は高いのですが、主観的幸福度の低さが日本の相対的な幸福度低下の原因とのこと。
そもそも主観的幸福とは何なのか?
今流行りのChatGPTに聞いてみると
主観的幸福とは、個人が自分自身が幸せであると感じる状態や経験のことを指します。つまり、主観的幸福は人によって異なり、幸福感を感じるための要因や条件も人それぞれ異なることを意味します。例えば、一部の人にとっては豊かな物質的生活が幸福をもたらすかもしれませんが、他の人にとっては豊かな人間関係や健康などの精神的な要素が幸福感に重要な役割を果たすかもしれません。 したがって、主観的幸福は、個人の価値観や生活環境、社会的背景などによって大きく影響されるため、一概に定義することはできません。
そうなんです、主観的幸福は定義することが難しいのです。
難しいからこそ家づくりにおいて何を重視すべきか、家づくりを始める前に今一度考えてみることが大切です。
あらためて「住まいが主観的幸福度に与える影響」を読んでみると、どのような要素が幸福度に影響を与えるのか、細かく記されているのでいくつかピックアップしてみます。
まずは地域性や建物自体の満足度。
もちろんこれらは主観的幸福度に影響を与えるのですが、それ以上に家族関係の影響が大きいとされています。
いくらオシャレで高性能なお家を建てても、家族関係が上手くいってなければ主観的幸福度は低いというわけです。
周囲から見れば「素敵なお家に住めてさぞ幸せなんだろうなあ」と思われるかもしれませんが、それはあくまでも客観的幸福度に過ぎないのです。
ちょっと意外かもしれませんが、「教育環境」「医療環境」「保育サービス」といったような皆さんが家づくりにおいて重視しそうな項目も、満足度(地域性)にほぼ影響を与えていません。
これらよりも「治安の良さ」や「街並みや閑静さ」といったような感覚的要素のほうが、満足度に与える影響が大きいとのことです。
私自身も土地を選ぶ際には、教育・医療環境などは全く検討しませんでした。
そもそも日本の場合は多くの地域で一定の教育・医療サービスを受けられますしね。
その他にも主観的建物満足度という項目では、「耐久性」「耐震性」「断熱性」といったような建物としての基本的な性能面よりも、「外観デザイン」のほうが主観的幸福度に与える影響が大きいとのこと。
これも意外に感じた人は多いのでは?
「高性能な家に住めば光熱費も抑えられて幸せだよ!」
「自分の好きなデザインに囲まれて暮らすのは幸せだよ!」
主観的幸福度という面では、後者のほうが幸福感を得られやすいようです。
だから家の性能は無視してもいい、という話でもありません。
SNSで度々起こる「性能」か「デザイン」か「コスパ」かみたいな論争は、主観的幸福という考え方においては意味がないということです。
高性能住宅に住む人が、ローコスト住宅に住む人を見下す行為も意味がありません。
幸せの尺度、価値観は人それぞれ。
でも人間は他人とは比べずにはいられない、悲しい性ですね。
昨今の住宅は高気密高断熱化が進み、室内環境は一昔前の住宅とは比べ物にならないほど改善されました。
ではそれに比例して主観的幸福度は上昇しているのでしょうか?
昭和よりも令和のほうが幸せでしょうか?
家づくりにおいて何を重視したら幸せに暮らせるのか。
SNS等で他人の意見を調べる前に、まずは自分自身のことをよく調べてみましょう。
自分にとって、家族にとっての幸せは何なのか。
まずはそこからですね。
関連記事

よく使う家具や照明(随時更新中)
ランキング参加しました。応援よろしくお願いします。