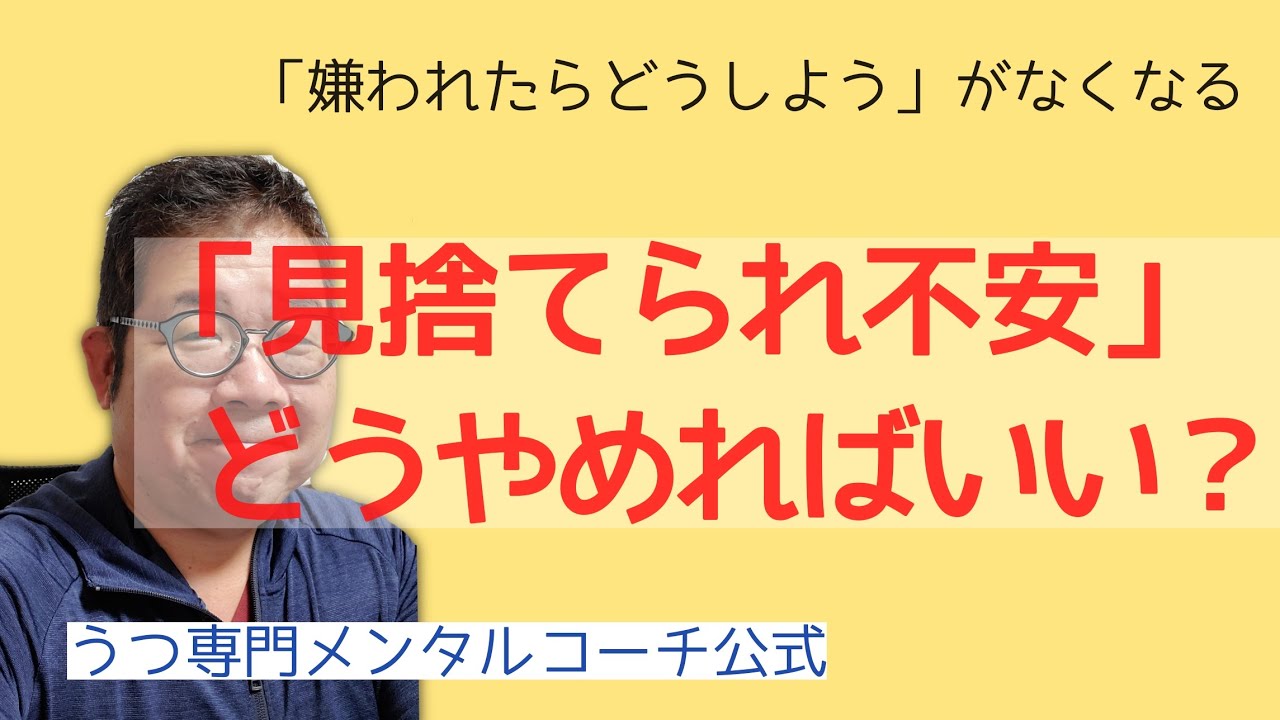「うつと発達障害・現場で使える実践スキル」
というセミナーをやっています。
今回で3期目になりますが、
なにせコアでマニアックなテーマですので(笑)
こじんまりとやってるイメージです。
そもそもこのセミナーをはじめたきっかけは
僕らコーチをはじめ、カウンセラー、セラピスト
その他心理支援に関わる人たちに
正しい知識を持ってもらおうと思ったからです。
ここでの正しい知識は、臨床的にということになります。
も少し具体的にいうと
「医師や臨床心理士の言ってることが正しく理解できる」
というレベルですね。
僕自身、うつ傾向の人と関わってきて
この辺の知識の重要さを身に染みて感じてますし、
「知らない怖さ」もわかっています。
これはクライアントを守ることはもちろんのこと
セラピスト側を守ることにもなります。
先日初回でしたが「うつ」がテーマでした。
知ってる人も多いと思いますが、
「うつ」は医学上「気分障害」になります。
では気分ってなんでしょうか?
これが意外にわからないんですよね。
まずここから知らないといけません。
気分と似たようなものに「感情」があります。
感情と気分は違います。
そして気分障害があるように感情障害もあります。
そしてこれらはアプローチが当然違います。
もしそういうことを知らずに、
うつの人も、感情障害の人も
まったく同じアプローチをしたらどうか。
当然よくない方向にいきます。
もひとつ。
「恐怖」と「不安」も違います。
そしてそれぞれ「恐怖症」とか「不安症」があります。
恐怖は明確なターゲットがあります。
不安はそれがありません。
もし不安症の人に原因追及型のアプローチを
してしまったらどうなるか?
うまくいかない可能性高いですね。
こういう細かいことがたくさんあって
それを意識するかどうかで
やることは当然変わっていくし
クライアントへの影響も変わります。
クライアントの利益を考えるとしたら
どういうことをすればいいのか。
そう考えると、知識を持つことは
当たり前のことになりますよね。
講座ではそういった知識に加えて
僕たちコーチのような非医療者が
実際何をやればいいのか?について
解説をしています。
ハッキリ言って「うつを治す」のは
コーチの仕事じゃないし、やっちゃいけません。
だから他のことで貢献するんです。
そんな話をしていたら
だんだん熱く語り始めてました(笑)
やっぱりこの分野には情熱があるし、
もっと貢献したいと思うんですよね。
だからこそ「正しいこと」を伝えたいです。
セミナー情報
YouTubeチャンネル情報