どうも( ^_^)/
夜中に面白いTV番組を観てしまい眠れなくなる者です。
その番組に関してはまた別の機会に書くことにして、眠れぬ夜の空回りする頭に浮かんできたアニメーション作品について、今は書きます。
ワンダーエッグ・プライオリティ
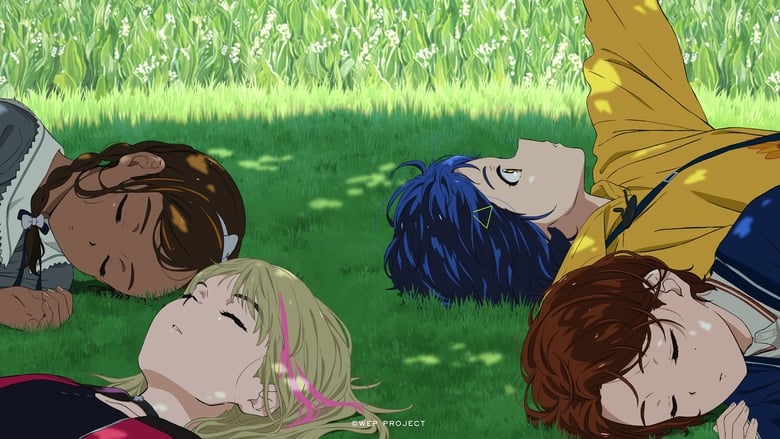
自殺した友人・知人・親族を生き返らせるため、謎の物体エッグ(一個五百円也)を割り、ワンダーキラーと呼ばれる敵と戦う四人の少女の物語です。
名前は画像左から、ねいる・リカ・アイ・桃恵、彼女たち自身もさまざまに深刻な事情を抱えています。
アカ・裏アカと名乗る謎の人物たちから買えるエッグ(500円)の中身は同じく自殺した少女で、彼女たちを野島伸司さん脚本らしい現実的で粘着質で生々しい事情を抱えたボスから守り切ればゲームクリアとなります。
エッグ(¥500‐)世界で戦いを繰り返し、四人の戦う敵の正体はかつてアカと裏アカが生み出したAI生命体フリルが、死の欲動タナトスに化けた存在であることが示唆されます(真相は不明)。
フリルの“友達”であるハイフン・ドット・キララがゲームクリアと同時に現れ、それぞれ桃恵・リカ・アイに死の恐怖を植え付け去っていったところで“本編”は終わります。
というのも、もともと12話完結であったところで途中に総集編が挟まり、予定の枠で話数を消化しきれなかった。つまり『一話落とした』状態で終わってしまったのです。
そこで本編終了後三か月後に特別篇の枠が作られ、先月6月29日に放送されました。
結論から書くと、特別篇と銘打たれたらしい内容で、特に話が進むわけではなかった。
今さらですが、ネタバレ全開で書いていきます。本当に今さらですが、未見の方はここでお別れです。
さて、本編としての12話(総集編を除いて実質11話)を受けて制作された特別篇は、完結編/最終話というより補完的なエピローグでした。
12話で、「タナトスと戦うエロスの戦士になる」と決意したアイは、フリル陣営の者たちと何処かへと消えたねいる(彼女もフリルと同じくAI生命だった)を探す目的を加えたうえで、戦い続けることを改めて決心します。
戦いが怖くなってしまった桃恵や当初の目的は一応果たせたリカは、そのままフェードアウト、関係も疎遠になったとモノローグで明かされます。
何となく示唆されていた謎の答えとして、自殺した少女が生き返るのではなくパラレルワールドから同じ顔と名前を持った別の人間を連れてくるだけだったことも分かり、さらにアイが生き返らせた小糸は生前から男性教諭と一方的に関係を迫り問題を起こす少女で、自殺も半ば事故だったと説明されます。
あまりスッキリと解決しなかった本編の空気をそのまま特別篇にも持ち込んだことで、すべての謎が明かされ大団円を迎えると予想していた多くの、すべての視聴者は、肩透かしを食らったような気分になったことでしょう。ことでしょう、などと他人事のように書いてますが、もちろん俺もその一人です。
とはいえ、若林監督の考えを想像すると、理解できないこともないです。
まず、話はきっかり与えられた放送枠の中で終わらせるのがプロの仕事という面で考えれば、三ヶ月も間を空けた『特別篇』でバタバタと話を畳むのは不誠実ともいえます。
前も同じようなことはあって『血界戦線』の一期では最終話が30分枠に収まり切らず、同じく約三ヶ月後に一時間枠を確保して放送したことがありました。
ただこれは、納期を落としたというより納品したものがデカすぎて店の棚に並べられなかった例なので、少し事情は違うかもしれません。
なので、本編12話と特別篇13話のオチが、話を広げた上で同じだったのは頷ける話ではあります。それが、顧客、視聴者の求めたものとは違ったとしても、です。
実際、話をまとめることはできたと思います。
フリルたちタナトス陣営を強大な“ラスボス”として、アイ・リカ・桃恵の三人がねいるを助け出すために最後の戦いに挑み、勝利は収められないまでも、ねいるを救うことには成功する、というようなところで、アイたち=エロスの戦士たちの戦いは続く。という感じにもできたはずです。
ですが、自分で書いておいてなんですが、なかなか陳腐です。
デカブツをやっつけるカタルシスは、ある意味では少女の内面を描くことを本題としていた作品に対しての“逃げ”でもあります。すこし言葉が悪いので“発散”とでもしましょうか。
「ラスボスを倒してやったね! で終わらせるのはどうよ」と誠実な創作者なら、そう考えると思います。俺はそういう創作者じゃないので、自作の小説などではドカーンとやって強引に終わらせます。
そういった部分で、若林監督は徹底的に“向き合う”方を選んだのだと思います。
謎が残る、スッキリとしない、「ワンエグとは一体なんだったんだろう」「よく分からない作品」との批判も受けやすい形で作品をクローズさせることを選び、クリエイターとしての面目というかプライドというか、それこそプライオリティを守ったのではないかと、そんな風に思うのですね。
でも、これはあくまでもわがままなイチ視聴者としての言葉ですが、“向き合う”終わり方は観てて難しく苦しい感覚ばかりが残ります。
“発散”する終わり方は、それはそれでまとまりがなくとっ散らかって「なんだよこれ」とは言われるんでしょうが、それでも残尿感はありません。
「小難しく展開してたが、最後はヤケクソでバカになったな」「でも笑って終われりゃすべてよしだ」と思えます。
結局、こういう破綻……とまではいわずとも、一見して飲み込みづらい、よく分かんなくなっちゃう作品というのは、そこに至るまでのところでもう修正が効かない歪(ひず)み、ディストーションが効き過ぎてしまっているのでしょう。
最後のところでつじつまを合わせようとしたって「これはどうやってもちょっと無理だな(苦笑)」となってしまう。
そこで“発散”か“向き合う”かを選ぶのは、それが、クリエイターにとってのプライオリティ。
あまりにも大きく若林信監督の作品になってしまった。個人的な思いが強くなり過ぎて、外側に届きにくいものになってしまったといったところでしょうか。
しかし、『ワンエグ』の描いたドラマ、アクションはとても素晴らしいものでした。
俺個人としては、こういう迷い曲がりくねったまま終わった作品というのは実はけっこう好きなところがあるので、この監督の次作も、できれば同じような座組で観てみたいと思っています。
野島伸司さんも、これに懲りず、またアニメの脚本として参加してほしいです。