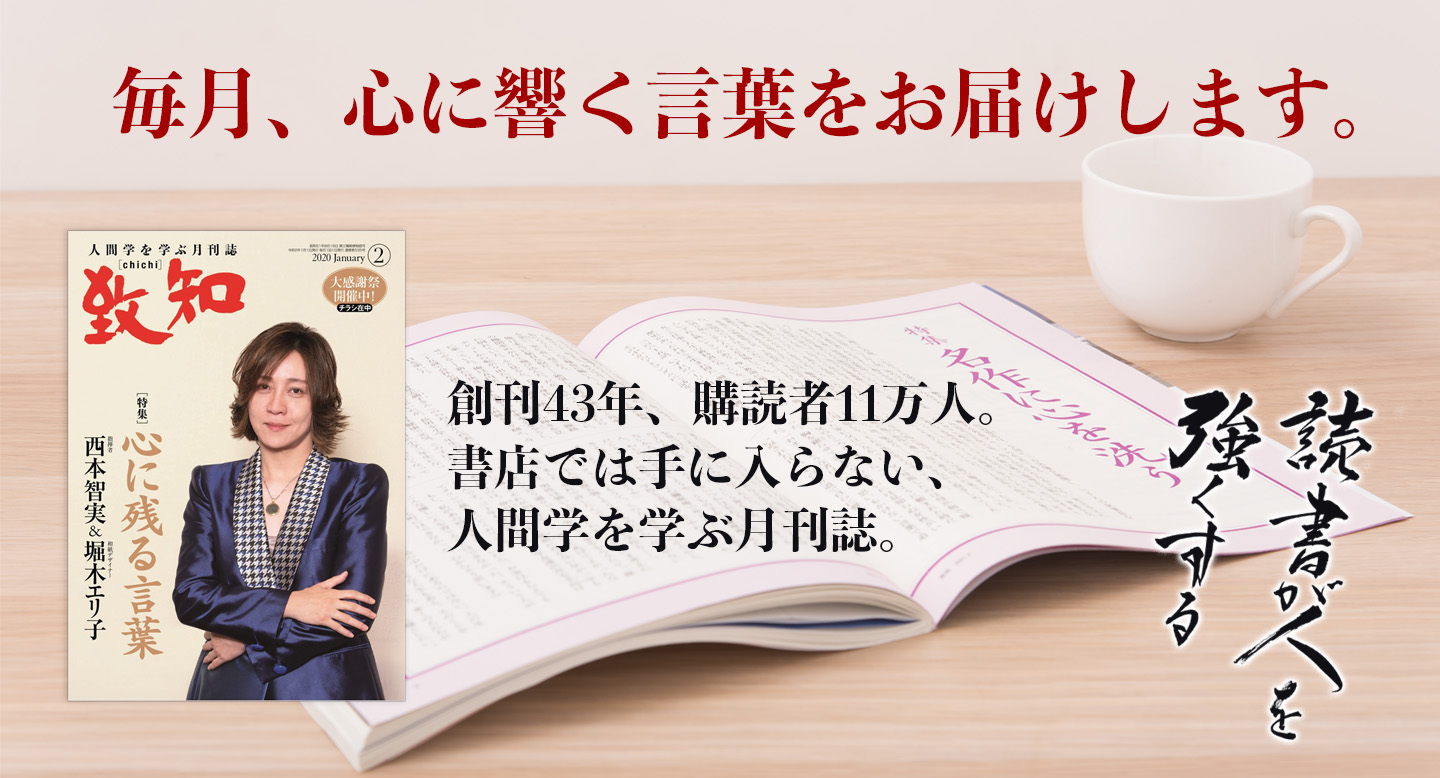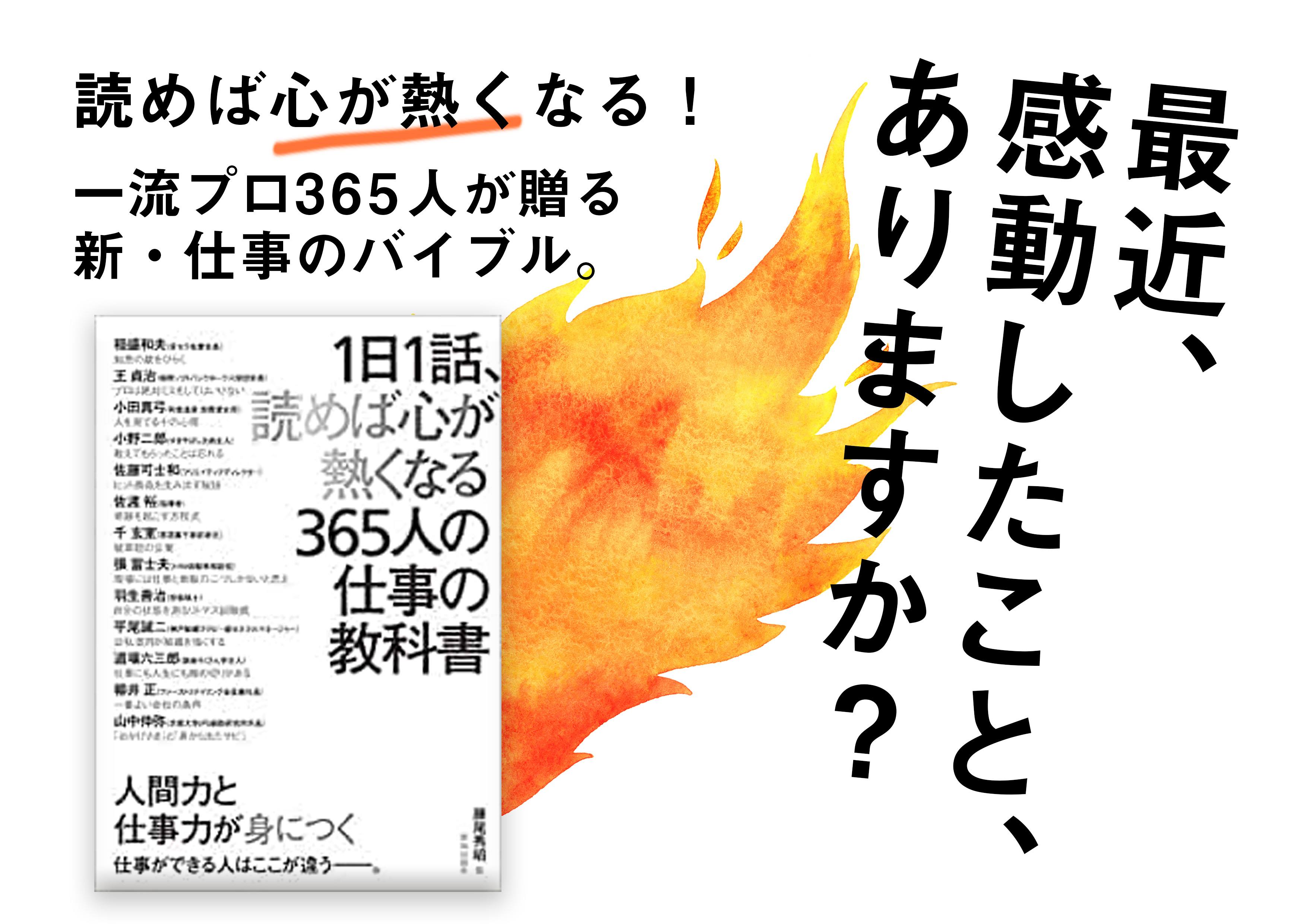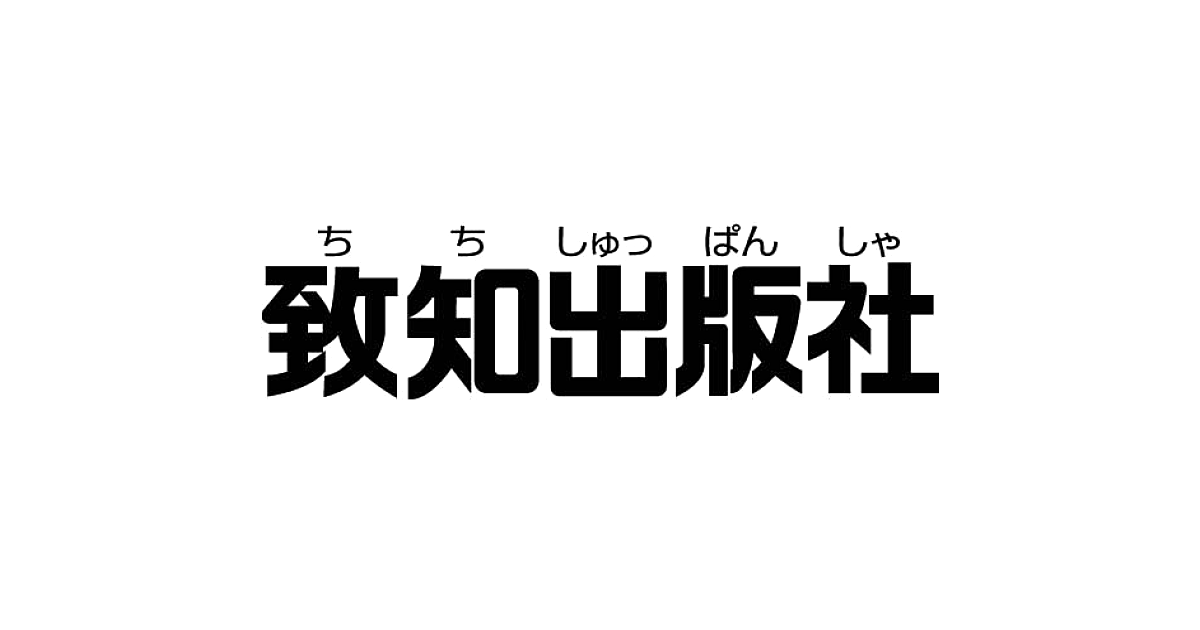米メルク社と共同開発した治療薬・イベルメクチンによって、家畜やペットが罹患する寄生虫症をはじめ、感染症に苦しむ世界中の人々を病魔から救ってきた大村智博士。一夜間教師から研究者となり、2015年ノーベル生理学・医学賞を受賞されたことは有名ですが、一方では経営の手腕も発揮し道をひらいてこられました。イベルメクチンはどのような研究、経営信条のもとで生み出されたのか。ノーベル賞受賞以前の貴重なインタビューを抜粋してお届けします。
★あなたの人生・仕事の悩みに効く〈人間学〉の記事を毎朝7時30分にお届け! いまなら登録特典として“人間力を高める3つの秘伝”もプレゼント!「人間力メルマガ」のご登録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■人真似ではダメ 一歩先んじよ
――大村さんの開発された薬によって世界で2億5千万人(取材当時)もの人が病気から救われているそうですね。
〈大村〉
それは「イベルメクチン」といって、もともとはメルク社(米)と共同で家畜やペットの寄生虫病の特効薬として開発して、世界中で使われているものです。それが人間の病気にも使えることが分かり、WHOが注目したのです。
例えば疥癬(かいせん)といって老人ホームなどに多い皮膚病がありましてね。患者さんからすぐ看護師さんにも感染してなかなか治らないんですが、この薬を一回飲むだけでピタッと治るんです。皮膚科領域の革命だといわれています。
この薬によって、熱帯地方によくあるオンコセルカ症という目が見えなくなる病気や、リンパ系フィラリア症といって脚が象みたいに太くなる病気がほとんど感染しなくなって、WHOも2020年には撲滅できると発表しました。
――大変なご努力の賜物でしょう。
〈大村〉
研究そのものはそんなに難しくはないのですが、何を考えて取り組むかということが大事です。
そういう意味で僕は、人があまり考えないことで世の中の役に立つのが自分の使命だと思い、人がやっていないようなことに絶えず挑戦してきました。
このイベルメクチンも、我われが発見した世界で唯一の微生物がつくる化合物から開発した薬です。これ以外にも創薬に結びつく化合物を含む新たな460種類の化合物を発見するなど、世界で最初に手掛けた研究が多数あります。
とにかく僕が携わっている化学や微生物の分野では、創造性が大事で人真似は絶対にダメ。もちろん学問ですから先人の業績を勉強することは大事です。だけどそこから一歩先んじようという気概がなければなりません。
若い研究者にもいつも言うんです。新しいことをやりなさい、そうすると人を超えられるんだよと。人真似ではどんなによくてもその真似をした人のレベル止まりです。失敗を恐れず、新しいこと、人がやらないことに挑戦してこそ人を超えるチャンスを掴めるんです。
――その分苦労も多いでしょうね。
〈大村〉
確かにそうですね。
僕が学生時代にやっていたスキーのクロスカントリーという競技は凄く辛くて、坂を登る時は心臓が破裂するくらいきついんです。それを登り切ることで結果が出るんですが、大概が途中で休んでしまう。
僕はそこでいつも頭を切り替え、自分を励ましながらやってきました。この登りは俺だけじゃなく皆が大変なんだ、ここが頑張りどころなんだと。
かつて経営難のため自分の研究室を閉鎖すると言われたことがあります。その時も僕は研究室の使用料、研究費、そして五人の研究員の給料を自分で賄い、独立採算で存続させました。
あの頃は研究費がなくなった夢を見ては夜中に飛び起きていたものです。けれどもそこでなんとか踏み止まったからこそ、その後たくさんの新薬を開発して多くの人を救うことができたんです。
――なぜ踏み止まれたのでしょう。
〈大村〉
自分の中に強い使命感があったんです。日本だけでなく世界でも通用するものを見つけたいと。そういう思いを抱いて一所懸命やっているのに閉鎖と言われたので、なおさらやりたくなったんじゃないでしょうかね(笑)。
■研究を経営する
一般に経営を研究するといいますが、僕はその逆で「研究を経営する」と言っているんです。
まず研究ですから新しい有用な化合物を見つける様々な方法を考案し、研究費を確保して研究が継続できるよう資金繰りも考える。一方で研究者の人間形成も含めた育成や、研究成果を社会に還元することにも尽力する。それらを包括して研究を経営すると言っているんです。
普通、大学の先生がそのまま大学の経営を手掛ける時は、なんとなくそれまでの延長線上でやるんですが、それではダメです。教授は教授で偉いけれども、経営者としてはまったくの素人です。ですから僕は、まず一年かけて徹底して経営の勉強をしたんです。
まず家内の恩師から紹介いただいた経営学の専門家・井上隆司先生につき、貸借対照表の読み方など経営実務の初歩から紐解いていただきました。また日本興業銀行の副頭取から東洋ソーダの経営を手掛けられた二宮善基さんが、研究所の創始者・北里柴三郎先生に縁のある方だったので、こちらにもお願いして帝王学を学びました。
お互いに忙しい身ですからいつも食事を兼ねてお会いして、事業の心得から人を導くリーダーシップまで、様々に勉強したんです。そこで学んだことをもとに、まず職員の数を合理化して3分の2にしました。やみくもに人員を減らすのではなく、補充を控えながら合理化を進めていきました。
例えて言えば、それまでは秋につくるワクチンと春につくるワクチンがあれば、それぞれに携わる人員を満杯に確保していたんです。だから自分がワクチンを製造する時以外は遊んでいる。そこで秋のものも春のものもつくれるように技術を覚えてもらい、同じものを3分の2の人員でつくれるようにしたんです。
それから、グループの病院で優秀な医師を院長に任命して活性化を図るとともに、我われが発見したイベルメクチンの特許料で、埼玉県北本市に新たに「北里研究所メディカルセンター」(KMC)を立ち上げました。
東京海上や日本航空の経営で辣腕(らつわん)を振るわれた渡辺文夫さんも北里研究所と縁のある方でしたが、僕のいないところで褒めてくださったらしいんです。大村は大会社の社長も十分務まると。それを伝え聞いた時は嬉しかったですね。
――見事な実績を重ねてこられましたね。
〈大村〉
たくさんの方々に支えていただいたおかげです。一期一会が僕の信条でもあるんですが、これまで出会いを大事にすることには特別に心を砕いてきました。
ところが往々にして人は出会いを大事にしない。お世話になりっぱなしで、後は忘れてしまうのです。受けた恩は石に刻めといいますが、恩を忘れてはダメです。
僕はこれまで本当にたくさんの方々のお世話になりました。アメリカ留学にお力添えをいただいた日本抗生物質学術協議会元常任理事の八木沢行正先生、この北里研究所で私を引き上げてくださった元所長の水之江公英先生、若い頃様々な人生訓を与えてくださった山梨大学元学長の安達禎先生、そしてマックス・ティシュラー先生。
挙げればきりがありませんが、どの方にも誠心誠意尽くす中で認められ、導かれてきました。本当に僕は恵まれた男だと思います。
(本記事は『致知』2012年5月号 特集「その位に素して行う」より一部を抜粋・編集したものです)
◇大村 智(おおむら・さとし)
━━━━━━━━━━━━━━━━
昭和10年山梨県生まれ。33年山梨大学学芸学部卒業。38年東京理科大学大学院理学研究科修士課程修了。40年北里研究所入所。米国ウェスレーヤン大学客員教授を経て、50年北里大学薬学部教授。(社)北里研究所監事、同副所長等を経て、平成2年北里研究所理事・所長。19年北里大学名誉教授。20年(学)北里研究所と(学)北里学園との統合により(学)北里研究所名誉理事長。(学)女子美術大学理事長や山梨科学アカデミー会長なども兼任。日本学士院会員。評伝に『大村智 2億人を病魔から守った化学者』(中央公論新社)がある。
* * *
★★『致知』ってこんな雑誌です★★
![]() あなたの人生、仕事の糧になる言葉、
あなたの人生、仕事の糧になる言葉、
教えが見つかる月刊『致知』の詳細・購読はこちら
★お申し込みはこちらからどうぞ★
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★『致知』最新刊はこちらからどうぞ。★
★『致知』最新号「言葉は力」の主な読みどころ
●対談「先人の言葉に導かれて生きてきた」
境野勝悟(東洋思想家)
&
安田 登(下掛宝生流ワキ方能楽師)
●対談「坂村真民と相田みつをの言葉力」
西澤真美子(坂村真民記念館館長補佐[学芸員])
&
相田一人(相田みつを美術館館長)
●インタビュー「私の映画人生は言葉と共にあった」
戸田奈津子(字幕翻訳者)
●対談「よい言葉が心を強くする」
田中真澄(社会教育家)
&
ガッツ石松(元WBC世界ライト級チャンピオン)
★まだまだ各界一流の方々がご登場!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆今話題の書籍のご案内
『1日1話、読めば心が熱くなる
365人の仕事の教科書』
藤尾秀昭・監修
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 収録記事の一部 ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「知恵の蔵をひらく」
京セラ名誉会長・稲盛和夫
「現場には仕事と無駄の二つしかないと思え」
トヨタ自動車相談役・張富士夫
「プロは絶対ミスをしてはいけない」
福岡ソフトバンクホークス球団会長・王貞治
「一度は物事に死に物狂いで打ち込んでみる
建築家・安藤忠雄
「人を育てる十の心得――加賀屋の流儀」
加賀屋女将・小田真弓
「ヒット商品を生み出す秘訣」
デザイナー・佐藤可士和
「嫌いな上司を好きになる方法」
救命医療のエキスパート・林成之
「準備、実行、後始末」
20年間無敗の雀鬼・桜井章一
「公私混同が組織を強くする」
神戸製鋼ゼネラルマネージャー・平尾誠二
「一番よい会社の条件」
ファーストリテイリング会長兼社長・柳井正
「仕事にも人生にも締切がある」
料理の鉄人・道場六三郎
「脳みそがちぎれるほど考えろ」
日本ソフトバンク社長・孫正義
「奇跡を起こす方程式」
指揮者・佐渡裕
「10、10、10(テン・テン・テン)の法則」
帝国ホテル顧問・藤居寛
「自分を測るリトマス試験紙」
将棋棋士・羽生善治
「負けて泣いているだけでは強くならない」
囲碁棋士・井山裕太
……全365篇
…………………………………………………………
☆お求めはこちら。
★人間学を学ぶ月刊誌『致知(ちち)』ってどんな雑誌?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一冊の本が人生を変えることがある
その本に巡り合えた人は幸せである
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・