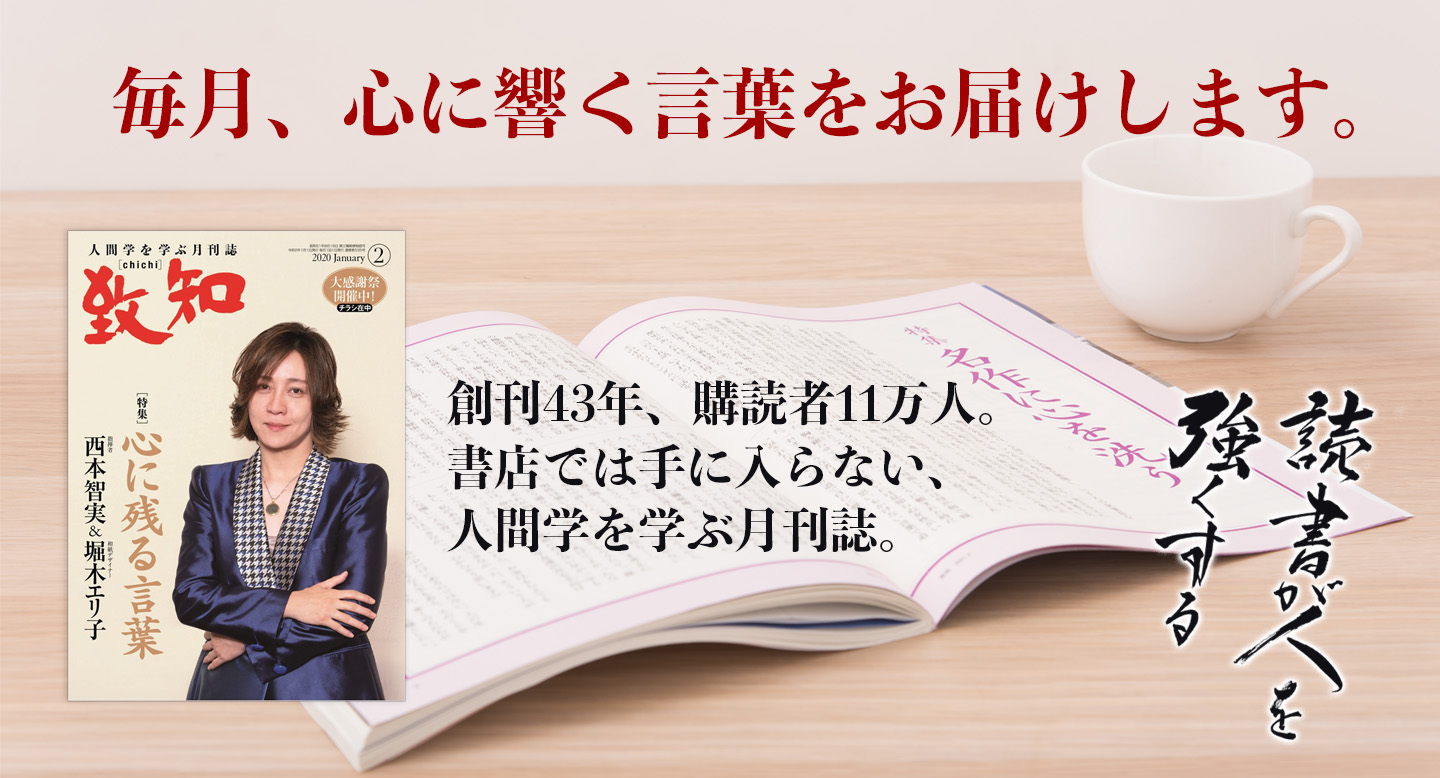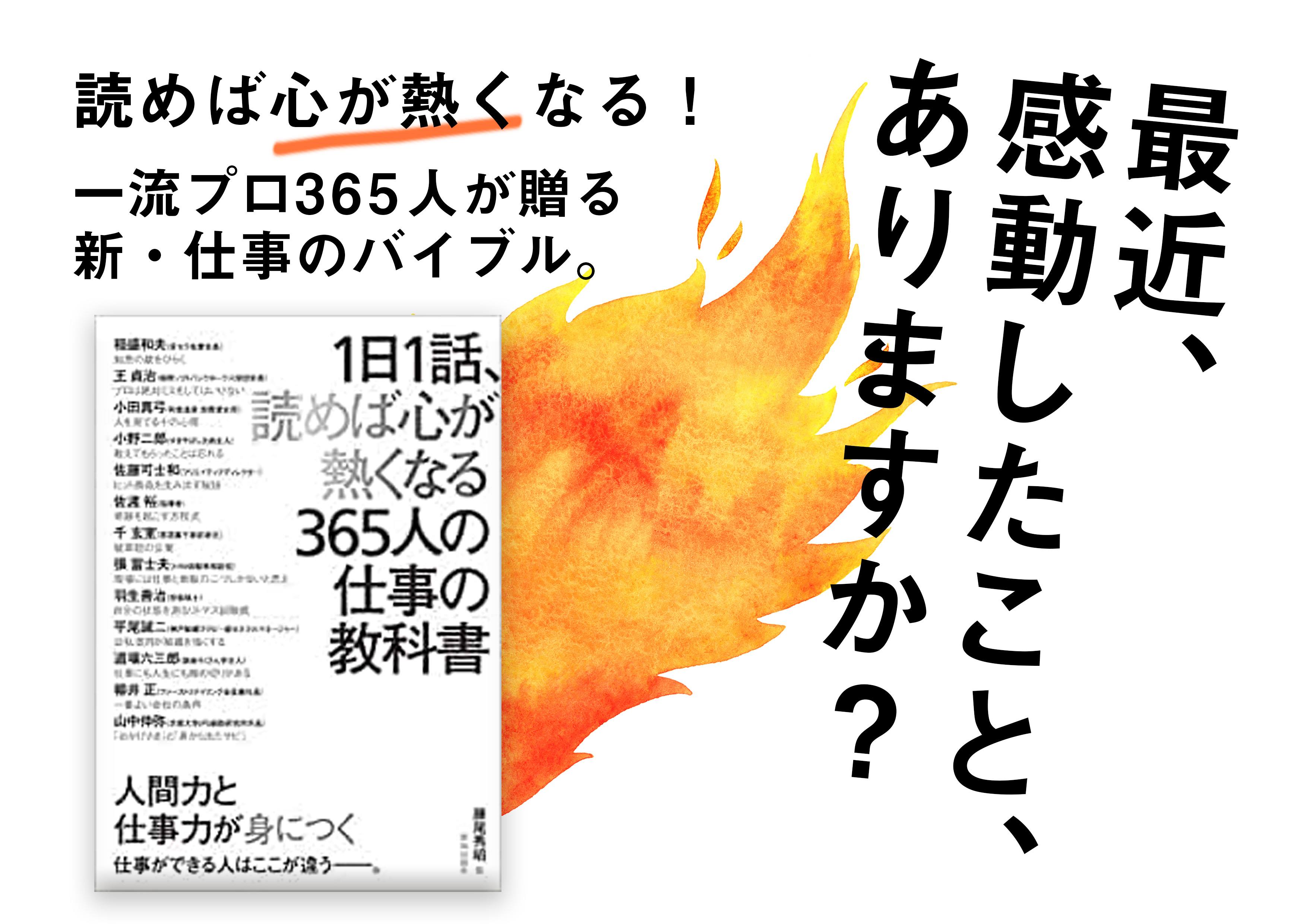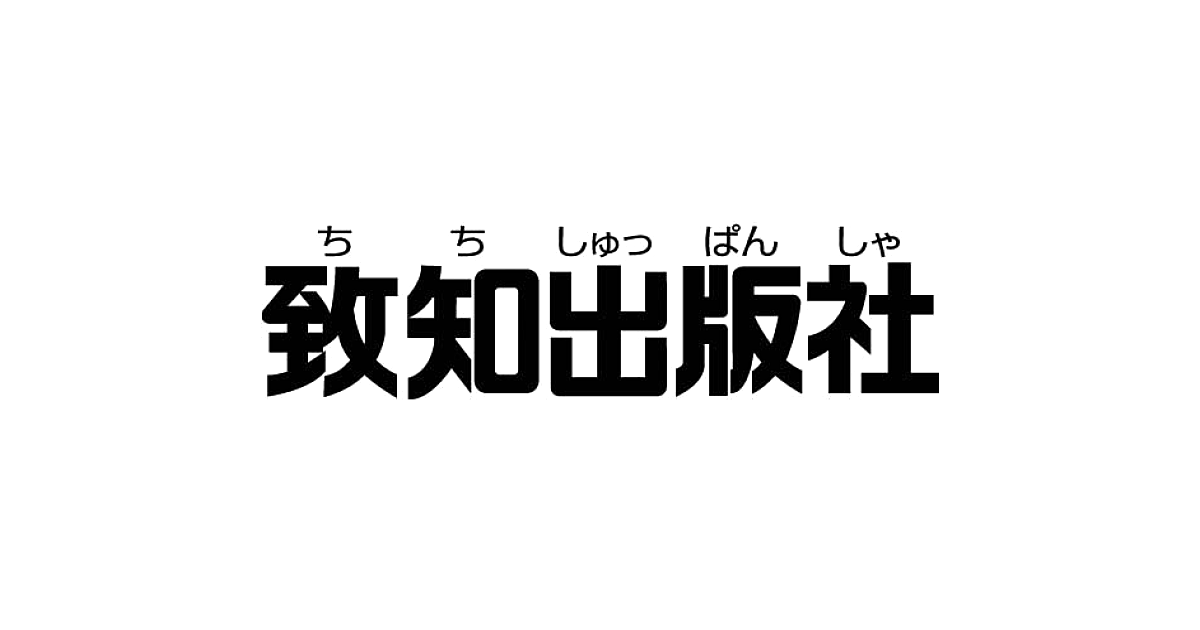長く陸上自衛隊に身を置く中で、志ある隊員が旧習に縛られ、退官していく現実に忸怩たる思いを抱いていた荒谷卓(あらや・たかし)さん〈写真左〉。命を賭して国を守る、そんな気概に燃えた隊員たちと共に、2004年「特殊作戦群」をつくり初代郡長となられた方です。2008年の退官後、明治神宮武道場至誠館(東京都渋谷区)で弊誌が行ったインタビューから、当時のやむにやまれぬ思いに迫ります。
★あなたの人生・仕事の悩みに効く〈人間学〉の記事を毎朝7時30分にお届け! いまなら登録特典として“人間力を高める3つの秘伝”もプレゼント!「人間力メルマガ」のご登録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■武士道精神が根付いた部隊をつくろう
前略)――その思いを自衛隊の中で発揮されていったのですね。
〈荒谷〉
自衛隊で感じていたのは、 見どころのある真面目な兵ほど、「これじゃあ国は守れない!」と憤慨して辞めていく。彼らが命を惜しまず任務に邁進できる場所をつくらなくてはと、かねがね思っていましたので、忠誠の宣誓を上から強要される西洋騎士団のような奴隷的軍隊ではなく、日本国体に自発的に忠誠を尽くし、猛々しい神武の精神を継承する「もののふの集団」を創ろうと思いました。
それを自らの天命と信じていると、不思議なことに、そのために必要な情報や人が集まってきます。5年後には、そういう仕事ができる補職も与えられました。結局、計画段階から主務係長として関わり、事業化、部隊創設準備そして指揮官へと思いが叶ったのです。
――特殊部隊とはどのような任務を負う部隊なのでしょうか。
〈荒谷〉
冷戦終了後は国と国の大規模な戦争よりも、新たな世界秩序の構築に向けた活動が軍隊の主任務となりました。平和構築活動や人道復興支援活動、そして対テロ作戦などです。
特殊部隊というのは、そうした活動の中で、軍事的機能だけではまかないきれない複雑な作戦を遂行する特別な部隊です。
――それで平成16年に特殊作戦群の初代群長に就任されたのですね。
〈荒谷〉
創設の際、私は「特殊作戦群戦士の武士道」を隊員に示しました。
一、確たる精神的規範を有し、生死の別を問わず事に当たる肚決めをすること
一、臆せず行動できる勇気とこれを維持する気力を鍛錬すること
一、事を成し遂げる実力(知力、技術、体力)を修養すること
一、言動を一致させ信義を貫くこと
隊員は、私が訓練を終えた米陸軍特殊部隊の「グリーンベレー」に準じた厳しい選抜試験と、長期の課程教育が義務付けられ、結果、特殊作戦群の隊員になれるのは全国の優秀な志願者全体の半数以下です。
■一瞬のために命を賭けた稽古をする
――特殊作戦群というのは本当に選ばれし精鋭部隊なのですね。
〈荒谷〉
はい。いまでも私のところに来る自衛官に言うことですが、戦闘服を脱ぎ、鉄砲を措(お)いたら一般市民と変わらなくなってしまうというのは、日本の武人として情けない。おそらく刀を措き、町人の格好をしても、やはり武士には武士たる何かがあったと思うよと。
実際、幕末に諸外国の人は日本の武士の人格に感銘を受けたわけで、おそらく人間の鍛錬、素養というものにおいて、一般の市民と違う倫理道徳集団を育成していたと思います。
そして、その武士たちの精神を培っていた根底に、今回いただいたテーマである「歩歩是道場(ほほこれどうじょう)」があると思います。これは逆の言い方をすれば「常在戦場」ということになると思いますが、戦場では、感性をフルに働かせて実戦をしながら常に学習をしなくては生き残れない。実生活と学習の間の境目は殆どないと思うのです。
だから、道場では、なるたけ実践に近く、実践は稽古のような落ち着いた心境でと。
剣術の稽古でも、真剣での稽古は欠かせません。真剣を使わないとできない精神の鍛練があります。
――ああ、木剣ではなく本物の真剣で稽古を。
〈荒谷〉
はい。なんのために稽古をしているかというと、最終的には生き死にの問題を前提に、その時真心を貫徹できるように鍛練しているのです。生死の選択を迫られるような場面に遭遇した時、しかも自らの信義を曲げてしまえば生は得られるという時に、自分は真心、信念を貫徹できるか。
道場の入り口に緒方竹虎(おがたたけとら)が葦津(珍彦/うずひこ)先生に揮毫した「生還を期せず」の書が掲げられていますが、真剣で対峙している時、相手の懐に飛び込んでいくのは怖いですよ。
しかし、相手が最も嫌がることでもある。入り身、捨て身といいますが、飛び込んでいったら二度と戻れないかもしれない。それを分かった上で、踏み込めるかどうか。そこを武道の稽古で鍛練しているのです。
――いざという時の覚悟を鍛練するために稽古をしていると。
〈荒谷〉
真剣での稽古で自分が傷を負うのは構いませんが、相手に怪我させたり傷つけたりする恐れもあります。だからといって手を抜けば、かえって危ないし、肝心の心の鍛練ができない。
自衛官でも「何かあったら自分は国を守ります」という人がいますが、本当にできるのかと。演習ではなく、本当に敵の弾が飛び交う戦場にあって、敵の弾に向かって踏み込む精神を鍛練しなくては、全く使い物になりません。
もちろんその場になってみなければ分からないことです。どんなに真剣の稽古を重ねても、「その場」ではできないかもしれない。しかし、私たちの先人は「その場」という一瞬のために、心身を磨いていたのです。だからこそ、日本人は、戦において凄まじい戦闘力を発揮できたと思います。
(本記事は月刊『致知』2013年7月号 特集「歩歩是道場」より一部を抜粋・編集したものです)
【著者紹介】
◇荒谷卓(あらや・たかし)
昭和34年秋田県生まれ。東京理科大学を卒業後、57年陸上自衛隊に入隊。福岡19普通科連隊、調査学校、第一空挺団、弘前39普連勤務後、ドイツ連邦軍指揮大学留学。帰国後、陸上幕僚幹部防衛部、防衛庁防衛政策局戦略研究室勤務を経て、米国特殊作戦学校に留学、帰国後、編成準備隊長を経て特殊作戦群初代群長となる。研究本部研究室長を最後に平成20年退官。一等陸佐。21年、明治神宮武道場「至誠館」館長に就任し、現在に至る。鹿島の太刀、合気道6段。著書に『戦う者たちへ』(並木書房)がある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆『致知』最新刊はこちらからどうぞ。
★『致知』最新号の主な読みどころ(対談記事)
●対談「日本を照らす光はあるか――この闇を破る道筋」
櫻井よしこ(国家基本問題研究所理事長)
&
中西輝政(京都大学名誉教授)
●対談「童謡が日本の未来をひらく」
大庭照子(日本国際童謡館館長)
&
海沼 実(日本童謡学会理事長)
●対談「特殊部隊に学ぶ危機を突破する最強組織のつくり方」
荒谷 卓(熊野飛鳥むすびの里代表)
&
伊藤祐靖(特殊戦指導者)
●対談「道を求める心が世の一灯となる」
堀澤祖門(泰門庵住職)
&
滝田 栄(俳優)
★申し込みはこちらでしていただけます★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆今話題の書籍のご案内
『1日1話、読めば心が熱くなる
365人の仕事の教科書』
藤尾秀昭・監修
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 収録記事の一部 ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「知恵の蔵をひらく」
京セラ名誉会長・稲盛和夫
「現場には仕事と無駄の二つしかないと思え」
トヨタ自動車相談役・張富士夫
「プロは絶対ミスをしてはいけない」
福岡ソフトバンクホークス球団会長・王貞治
「一度は物事に死に物狂いで打ち込んでみる
建築家・安藤忠雄
「人を育てる十の心得――加賀屋の流儀」
加賀屋女将・小田真弓
「ヒット商品を生み出す秘訣」
デザイナー・佐藤可士和
「嫌いな上司を好きになる方法」
救命医療のエキスパート・林成之
「準備、実行、後始末」
20年間無敗の雀鬼・桜井章一
「公私混同が組織を強くする」
神戸製鋼ゼネラルマネージャー・平尾誠二
「一番よい会社の条件」
ファーストリテイリング会長兼社長・柳井正
「仕事にも人生にも締切がある」
料理の鉄人・道場六三郎
「脳みそがちぎれるほど考えろ」
日本ソフトバンク社長・孫正義
「奇跡を起こす方程式」
指揮者・佐渡裕
「10、10、10(テン・テン・テン)の法則」
帝国ホテル顧問・藤居寛
「自分を測るリトマス試験紙」
将棋棋士・羽生善治
「負けて泣いているだけでは強くならない」
囲碁棋士・井山裕太
……全365篇
…………………………………………………………
☆お求めはこちら。
★人間学を学ぶ月刊誌『致知(ちち)』ってどんな雑誌?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一冊の本が人生を変えることがある
その本に巡り合えた人は幸せである
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・