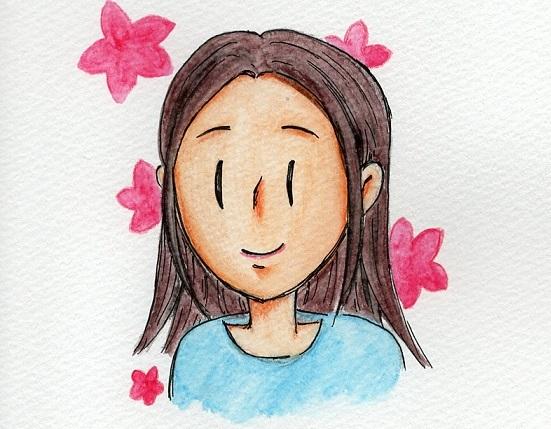2022年6月のテーマ
「大学教授のミステリー」
第三回は、
「探偵ガリレオ」
東野圭吾 作、
1998年発行、文春文庫
です。
私が持っているのはpickで上に貼ってある版で、2002年版のものです。
何度も新版が出ていますし、シリーズもたくさん続いています。
2007年には福山雅治さん主演でドラマ化もされ、シリーズ長編の『容疑者Xの献身』は映画化されましたので、ご存じの方も多い作品だと思います。
主人公の湯川学は帝都大学理工学部物理学科准教授。大学時代の友人である刑事の草薙俊平が持ち込んでくる不思議な事件を物理学や化学の知識を用いて解明していく…というストーリーです。
シリーズの始めの3冊くらいまでは読んでいたのですが、それより新しいものは読んでいないので、ずっとこのスタイルなのかはわかりません。
シリーズ一作目の『探偵ガリレオ』は短編集で、「一つ一つの事件が摩訶不思議、でも科学的に解明できちゃう」というのが面白いところです。
どのくらい摩訶不思議かというのがわかるように、帯に書いてある事件の概要をちょっと載せてみますね。
「突然、燃え上がった頭、池に浮かぶデスマスク、心臓だけ腐った死体、海の上で爆発した女性、幽体離脱した少年……」
ミステリーで起きる事件とは普通じゃないのが当たり前ですが、普通じゃない度合いがすごいです。
とはいえ、仲間由紀恵さんと阿部寛さん出演のドラマ『トリック』のように、近年では不可能と思われる犯罪、オカルト的な事件を扱うミステリー作品が人気を集めていると思いますので、今や"普通じゃない度合いがすごい事件"のミステリーがポピュラーなものとなってしまっているのかもしれませんね。
ミステリー作家の方々も大変だぁ…と思うのは私だけではないはず。
私がシリーズでこの作品をおすすめするのは、短いストーリーの中で"起こりえない事象を科学的に解明する"というのが実に鮮やかで、ミスマープルの『火曜クラブ』やホームズの短編集を思い起こさせるからです。
また、この作品の性質上、ミステリーなんだけど、学問における探求の姿勢(自然界の不思議のメカニズムを研究者が解き明かそうとする)みたいなものを感じて、それもちょっと湯川学のキャラクター付けにいい味を加えていると思います。
探偵小説って、探偵のキャラクターが重要ですし、なぜ事件の謎を解きたいのかという動機付けもそのキャラクターによって微妙に違います。
前回おすすめした『すべてがFになる』の犀川教授の場合、事件の謎を解こうという意欲は希薄ですが、そこを補っているのが西之園萌絵というキャラクターです。
ミス・マープルの場合は一人暮らしの孤独なオールド・ミスゆえに人間を観察するのが好き。
ホームズなら、頭が良すぎて謎を解くことで退屈を回避しようとしている、ということになります。
湯川学の場合は、天才物理学者ゆえに学問的探究心で謎を解きたくなる、といったことかな…と。
ここからは蛇足になるのですが、私が過去に読んだことがある作品から、東野圭吾さんの作品は社会派的なにおいを感じています。社会派、という言葉は、かつて松本清張さんの作品に対して形容されていたことがあって、私にとってはそのイメージで使っています。
なおかつ、かつて下の記事でおすすめしたことがある、レイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説を読んだときに感じたのと同じような、どうしようもないことへのやるせなさみたいなものを感じます。
ひょっとしたらそんな感じを受けているのは私だけかもしれませんが、『容疑者Xの献身』を読んでから、シリーズの続きを読まないでいるのはそういうやるせなさを感じるのを避けたい気持ちがあるのかなと自分では思っているのです。
普段は長編小説の方が好きだったりするのですが、今回短編集をおすすめしたい気持ちになったのは、ミステリーとしてシンプルなものをおすすめしたかったからかもしれません。
しかし不思議なことに、この記事を書いているうちに、シリーズの続きがたくさん出ていることを知り、そろそろ読んでみようかなという気持ちがわいてきました。
好きなのに何で続きを読まないのか、記事に書くことでちょっと消化できたのかもしれません。
他人に読まれることを前提に書いているにもかかわらず、ブログを書くことは自分の気持ちの整理のためでもあるのは否めません。こんなものを読んでくださる人がいるというのはありがたいことです。
ともあれ、『探偵ガリレオ』おすすめいたします。(*^▽^*)