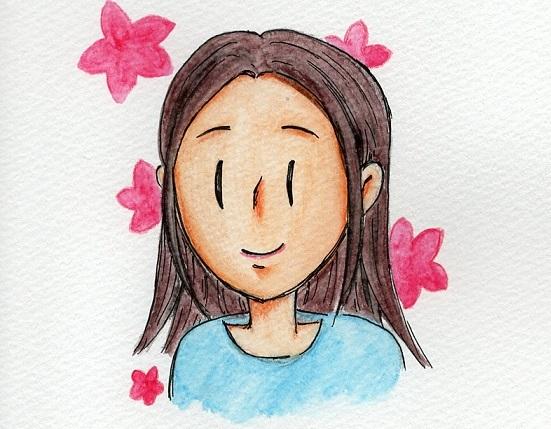2022年6月のテーマ
「大学教授のミステリー」
第二回は、
「すべてがFになる」
森博嗣 作、
1998年発行、講談社文庫
です。
私が持っているのは2000年の第7刷発行のものなので、上のPickでいうと3番目のものになります。
新しい版のデザインもいいですね。
例によって私が持っている版と新版では解説等違う箇所があるかもしれませんがご了承ください。
この作品は、作者森博嗣さんのデビュー作にして犀川創平&西之園萌絵コンビを主人公とするシリーズ(S&Mシリーズ)の第1作目にあたりますが、実は最初に書かれた犀川&萌絵シリーズ作品ではなく、もともとは同シリーズの第4作目にあたるものでした。
作者がシリーズ1作目として書いた『冷たい博士と密室たち』を雑誌に投稿したところ評価を得て、その時すでに書き終えていた4作目までの中からデビュー作としてふさわしいと選ばれた『すべてがFになる』を第1作としてシリーズがスタートした、ということだそうです。
最終的にはこのシリーズは10作品で完結となるのですが、『すべてがFになる』はシリーズのほかの作品と比べても完成度が高くインパクトも強いと思います。(好きな作品はまた別ですが。)
さて、ストーリーはと言いますと、N大助教授の犀川創平と女子学生の西之園萌絵は、ハイテク研究所がある島を大学のゼミ旅行で訪れます。研究所にコネのある西之園萌絵のおかげで普通なら入れない研究所に入ることができた二人は、そこで起こった密室殺人のために研究所から出ることができなくなり、不可能犯罪の謎に挑むことになります。
今から20年以上前の小説なので、ハイテク研究所といっても現在からみれば旧式のシステムになるはずなんですが、今読んでも古さはあまり感じないんじゃないかなと思います。
建物を管理するプログラムがいたり、物を運ぶロボットが自動で仕事をしていたり、音声認識でコンピューターに指示を出したり、一つ一つの技術は今ではみられるようになっているかもしれませんが、そのすべてが普通とされる社会にはいまだなっていないのではないでしょうか。
(例えばスマホに音声で指示を出して連携した家電を操作できるようになりましたが、当たり前のように使っている人の割合はまだ少ないと思います。また、使っている範囲も自宅が中心ではないでしょうか。会社全体がこのシステムを取っているところってあるのかな???)
この小説は、特殊な環境条件のもと起こった殺人事件のお話なので、いわゆるオーソドックスなミステリーが好きな人からは賛否両論あるんじゃないかと思います。特に、本格ミステリーが好きで、作者の出した謎の答えを自らの知恵で解き明かすことがミステリの醍醐味と感じている方には受け入れがたいところがあると思います。
環境が特殊すぎて、コンピューターの専門知識がないとトリックの細かいところが予想できないのではないかと思うからです。
コンピューターのことをよく知らないと読めないというわけではないですが、コンピューターの基本的知識のある人の方が読んでみて面白いのではないかと個人的には思います。
ですが、事件の本質には人間の心理の問題があり、トリックにもやはり人間の心理を利用しなければなしえないところもあるので、私はミステリーとして純粋に面白いと思います。
主人公の犀川助教授は頭が回るくせに探偵役としては消極的、西之園萌絵は積極的に謎解きをしようと動き回る(頭もいいが犀川の方が1枚上手)という役割分担もうまくいっていて、二人の会話のシーンは、ホームズとワトソン、ポアロとヘイスティングズ、というわけではないですが、バディもの特有の面白みがあります。
前回の記事で書いたラングドン教授シリーズにはない面白さです。
実際、この作品はアニメ化、漫画化、ドラマ化されていて、人気のある作品だと思います。
ただ、ネットなどをみると評価が分かれているなーと感じています。
私自身はこの作品が好きなので、ひいき目もあるかもですが、評価が分かれるのは作品の良し悪しというよりは好き嫌いの問題のような気がしています。
既に漫画やドラマで知っていてネタバレしちゃってるという方も、一度原点の小説を読んでみてはいかがでしょうか。
おすすめいたします。(*^▽^*)