2020年3月のテーマ
ハードボイルド小説を読んでみた!
第三回は
「デイン家の呪い(新訳版)」
ダシール・ハメット 作、小鷹信光 訳
早川書房 2009年発行
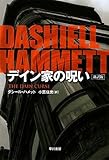 |
デイン家の呪い(新訳版)
880円
Amazon |
です。
ダシール・ハメットはアメリカのミステリー作家です。
Wikipediaで調べてみたところ、"推理小説の世界にハードボイルドスタイルを確立した代表的人物"とありました。
ついでに、いまさらながらですが"ハードボイルド"についても調べてみました。
"文芸用語としては、暴力的・反道徳的な内容を批判を加えず、客観的で簡潔な描写で記述する手法"だそうです。
なんだか、自分の中でもやっとしていたイメージが、きちんと言葉で説明されているのを読んですっきりしました。
(もっと早くちゃんと調べとくべきかもですが、生来ずぼらなもので・・・。)
いつもブログを書く前には、紹介したい本を読まないまでももう一度手に取ってみているのですが、今回ご紹介したい本は図書館で借りた本。しかも新型コロナの影響で図書館が閉館。
というわけで、仕方なくネットで検索して思い起こしながら記事を書いています。
この「デイン家の呪い」は、ダシール・ハメットの作品の中では人気がない作品で、ジャンルとしてもハードボイルド小説(?)と言いたくなる作品です。本のあとがきでも、作者自身が"失敗作"と言っていたという話が載っており、作者のお気に入りの作品ではなかったようです。
内容は、B級映画さながらの盛りだくさんで、宝石の盗難事件で始まった物語が、いつの間にか怪しい宗教が絡んだ誘拐?監禁?事件に発展したり、事件の中心にいる女性の周りで次々と人が死んで、一族の呪いというオカルトチックな展開になったり。
ハードボイルド小説らしいカークラッシュなんかもあるし、主人公は探偵事務所所属の探偵で、「血の収穫」(未読です)という作品と同じコンチネンタル・オプなんですが、確かにハードボイルド小説の代表作という感じではありません。
私は、ダシール・ハメットの作品は本作と「ガラスの鍵」を読んだことがありまして、「ガラスの鍵」の方が、ハードボイルド小説のイメージにふさわしい作品でした。
にもかかわらず、「デイン家の呪い」をご紹介しようという・・・。
理由は、この作品の持つオカルトっぽさが、なんとなく横溝正史さんの小説を連想させて、個人的には「ガラスの鍵」よりも印象に残ったからです。
一族の呪いだの、姿の見えぬ復讐者だの、横溝正史作品ではおなじみの要素。
超自然的な呪いが人を殺すのではなく、結局人を殺すのは人。
でもその人の精神に影響を与える何かこそ、呪いかもしれない。
横溝正史作品に対して私はいつもそう感じます。
(といっても、ちゃんと本で読んだことはなく、映像作品を見るばかりなので、文章で読むとまた違うのかもしれませんが。)
「デイン家の呪い」のそういったオカルトっぽさが、私にとっては逆に違和感を感じずに読めたということと、盛りだくさんの内容のB級映画っぽさもまた個人的にアリだったのです。
生粋のハードボイルド小説好きの方には不人気なのでしょうし、作者も気に入っていなかった作品。
だけど、アメリカから遠く離れた日本で、ハードボイルド小説などとは縁がなかった主婦がおもしろいと思って読むなんて、作者も想像だにしなかったと思います。
ダシール・ハメットの代表作といえば、「血の収穫」や「マルタの鷹」らしいのですが、私はこの二作を読んだことがありません。
図書館に行って、ダシール・ハメットの作品を適当に手に取ったのが、先に挙げた二作品でした。
ハードボイルド小説を何作か読んで興味が薄れたので、それっきりになってしまっているのですが、名作と名高い作品は今後機会があれば読んでみたいなと思っています。
さて、次回は閑話休題ですが、私がハードボイルと小説をたしなんでみようと思ったきっかけの本について書いてみたいと思います。
ご興味ありましたら、のぞいてみてください。(*^▽^*)
 |
ガラスの鍵 (光文社古典新訳文庫)
922円
Amazon |