2019年3月のテーマ
「心揺れる季節、青春小説にふれよう」
第二回は、
「青が散る」
宮本輝 作、文春文庫、1985年発行
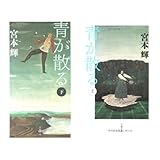 |
新装版 青が散る 上下巻 セット
1,274円
Amazon |
です。
私が持っているのは、1989年発行のものなので、旧装丁のものです。新装版のほうは読んでいないので、本編以外の解説などで変更があったかもしれません。
宮本輝さんという作家さんは、非常にジャンルの広い作家さんです。多作で、「青が散る」や「春の夢」といった大学生が主人公の青春小説から、戦後日本の復興期に奮闘する60代の男性が主人公の「流転の海」シリーズ、「海岸列車」などの女性が主人公の小説に、一頭の競走馬をめぐる人々の人生の一幕を描いた「優駿」など、いろいろな世界を描かれています。
そのどれもが『宮本節』ともいえる文章で、ぐいぐいと読者をお話に引き込んでいく力を感じます。私が宮本輝さんの本を読み漁っていたのは大学生~社会人になって5,6年までの間で、特に大学生の頃は当時出版されていたものはほとんど読んでいたと思います。この「青が散る」という作品もその頃に初読しました。主人公が自分と同じ大学生ではありましたが、作品の発する熱量が自分の周りの学生生活と違いすぎて衝撃を受けました。
小説の舞台は、昭和期の新設大学です。主人公の遼平は、入学してであった金子という同級生とテニス部を設立します。新設大学ですから、テニス部を作りたいといってもコートも何もありません。彼らはテニスコートを作るところから始めます。では、スポ根物なのかというと、それもちょっと違います。遼平は、大学の四年間をテニスに打ち込む、と決意し、その通り実行しますが、めきめき上達して大会で優勝するだとか、ライバルと接戦を繰り広げるだとか、彼のテニス道が中心のお話ではないのです。
遼平には好きな女の子がいますが手が届くような届かないような微妙な関係。テニス部の仲間で、天才プレイヤーの安斎は精神的な病気を抱えていて悩んでいたり、歌手デビューを目指すガリバーという青年は怪しい道に迷い込んでしまいます。いつも斜に構えているちょっと嫌な奴、貝谷。生意気な後輩のポンク。
たくさんの登場人物たち葛藤、人生の選択といったものが書かれていて、とても濃い内容だなと感じます。時代が今とは違うので、現代の大学生が読んで共感するとは思いません。どちらかというと、昭和という時代の若者の熱量を感じられる作品だと思います。関西のお話なので、登場人物の台詞が関西弁なのも、濃いなあと思われる方もいらっしゃるかもしれません。でも関西弁はお笑い特有のものではないんですよー。文章で読むとアジがあります。
私がこの作品をおすすめしたいと思ったのは、『主人公遼平の燃えるような大学四年間の過ごし方が力強すぎる』からです。
遼平は大学を卒業して社会人になったら、自由な時間が減り、何か一つのことに打ち込むのは難しくなることを入学した時から意識しています。そこで、あと四年間を自由を満喫して過ごそう、というのではなくて、この四年間を何かに打ち込むことで「これをやった!」というものを自分の青春時代に残したいと考えるのです。その何か、がたまたま金子に誘われたテニスでした。大学生ですから、経験者はそれなりにいて、うまい奴はすでにうまい。そんな中で頑張ろう、やりきろう、と思って続けるのですから、大したものです。
また、このお話の中で、遼平と貝谷が会話するシーンに、『王道か覇道か』という話が出てきます。貝谷という人物は、斜に構えていて、真面目にやるのはあほくさい、みたいなところがあるのですが、この会話で、「俺は断然、覇道で行く」というのです。自分流のくせがあるテニスで構わない。得意な技を極限まで磨いて、相手が嫌だなと思ういやらしい球を打つ。それで相手が返せなかったら俺の勝ち。それが「覇道」です。テニスだけではなく、彼の生き方にもこういった傾向がちらほら見えます。その話を遼平はなるほどと聞いているのですが、後に自分は「王道で行く」と決心します。勝ち負けだけではない、努力する過程を重視した考え方だと感じました。また、今後の彼の生き方にも影響してくるんじゃないかな、とも。
「青が散る」は、昭和期のお話で、現代の学生さんからは古いと思われるかもしれませんが、学生さんを含めて若い方に読んでいただきたい作品です。成功や失敗、葛藤と努力、恋愛に友情。いろんな事件もあって、たくさんの青春が詰まっています。青春小説だけど感動作。それがこの「青が散る」です。おすすめいたします。(*^▽^*)
 |
新装版 春の夢 (文春文庫)
679円
Amazon |
 |
流転の海 第1部 (新潮文庫)
724円
Amazon |
 |
海岸列車 (上) (集英社文庫)
799円
Amazon |
 |
海岸列車 (下) (集英社文庫)
734円
Amazon |
 |
優駿(上) (新潮文庫)
680円
Amazon |
 |
優駿(下) (新潮文庫)
724円
Amazon |