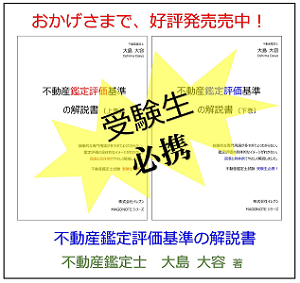2.限定価格
限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。
限定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合
(2)隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合
(3)経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合
(解説)
価格に関する鑑定評価で正常価格以外に求める価格として限定価格がある。
〔 限定価格 〕
① 市場性を有する不動産の価格
② 不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格
①の市場性を有する不動産とは、正常価格の場合と同様である。
次に②の内容であるが、併合と分割の2種類を想定している。具体的には、併合は、借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合と隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合があり、分割は、経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合がある。
(1)借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合
更地に借地権を設定した場合、鑑定評価の類型としては、借地権と底地に分かれる。反対に、借地権と底地が一体となれば更地になる。しかし、経済価値という観点から考えると、借地権の経済価値と底地の経済価値を合計しても、更地の経済価値にはならないのが一般的である。この点に関しては、各論第1章の借地権で詳細に説明する。
〔図表5-11〕を見てもらいたい。
更地の価値を100とした場合に、例えば借地権の価値が50、底地の価値が30というように、合計が100にならないのが一般的である。底地の30は、この底地が合理的と考えられる条件を満たす市場で取引される場合の価格を示し、底地の正常価格と考えればよい。つまり、底地部分は現実の市場で取引された場合は30の価値であり、買主Cは、この底地を購入後、底地として保有を続けることとなる。しかし、この底地を借地権者Bが購入する場合は少し状況が違ってくる。借地権者Bが底地を併合すると、借地契約は解消されて更地に復帰することとなる。そして、借地権者Bは価値が100の更地を手に入れることとなる。つまり、もともと50の価値の借地権が底地を併合すれば100の価値の更地を取得することとなり、借地権者Bは、その差額の50までなら負担をしても損はない(合理的である)ということとなる。
これを基準の文章に当てはめると次のとおりである。借地権と取得する底地の併合に基づき、正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値(底地の価値である30のこと)と乖離すること(30を超えて50までなら負担しても合理的である)により、市場が相対的に限定される(借地権者と底地人の2人のみに合理的な市場が発生する)場合における底地の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格を限定価格という。
(2)隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合
隣接不動産を併合する場合、増分価値が発生することがある。つまり、ある土地が隣接する土地を併合する場合、併合後の土地の価値が、併合前のそれぞれの土地の価値の合計を上回ることがある。
〔図表5-12〕を見てもらいたい。
甲地と乙地の一体地の価値を100、甲地の価値が50、乙地の価値が30とする。乙地はその形状が不整形であるため、甲地の価値に比べて低くなっていることを前提としている。甲地の50は、この甲地が合理的と考えられる条件を満たす市場で取引される場合の価格を示し、甲地の正常価格と考えればよい。つまり、甲地は現実の市場で取引された場合は50の価値である。しかし、この甲地を乙地の所有者Bが購入する場合は少し状況が違ってくる。乙地の所有者Bが甲地を併合すると、乙地の不整形は解消されて整形地(甲地+乙地の一体地)となる。そして、乙地の所有者Bは価値が100の甲地+乙地の一体地を手に入れることとなる。つまり、もともと30の価値の乙地が甲地を併合すれば100の価値の甲地+乙地の一体地を取得することとなり、乙地の所有者Bは、その差額の70までなら負担をしても損はない(合理的である)ということとなる。
これを基準の文章に当てはめると次のとおりである。乙地と取得する隣接地甲地の併合に基づき、正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値(甲地の価値である50のこと)と乖離すること(50を超えて70までなら負担しても合理的である)により、市場が相対的に限定される(甲地の所有者と乙地の所有者の2人のみに合理的な市場が発生する)場合における甲地の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格を限定価格という。
(3)経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合
不動産の一部を分割して売却する場合、売却しなかった残地に経済的な減価が発生する場合がある。これは、その分割が経済合理性に反するためであり、売主はその減価分を上乗せした金額でないと取引に応じないこととなる。
〔図表5-13〕を見てもらいたい。
甲地の価値を100とする。甲地の一部を分割した丙地を取得する場合、残地となる乙地の形状が不整形となり減価が発生することとなる。
丙地の50は、この丙地が土地の一部を分割等することなく、単独で取引される場合に、合理的と考えられる条件を満たす市場で取引される場合の価格を示し、正常価格と考えればよい。つまり、丙地は現実の市場で取引された場合は50の価値である。しかし、この丙地を甲地から経済合理性に反する分割をしてBが購入する場合は少し状況が違ってくる。Bが経済合理性に反する丙地を取得すると、もともと整形地であった甲地の一部が削られて、不整形な乙地が残地として残る。つまり乙地には不整形という減価が発生することとなり、甲地の所有者Aとしては、発生する減価の20を補償してもらえないと丙地を売却しないこととなる。つまり、もともと100の価値の甲地の一部を売却して30の価値の乙地しか残らないわけであるから、その差額の70であれば売却をするということとなる。
これを基準の文章に当てはめると次のとおりである。不動産の一部(丙地)を取得する際の分割に基づき、正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値(丙地の価値である50のこと)と乖離すること(50に減価の補償額20を上乗せした70)により、市場が相対的に限定される(甲地(乙地)の所有者と丙地の取得者の2人のみに合理的な市場が発生する)場合における丙地の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格を限定価格という。
●このブログで使用している文書、画像等については無断で転載・引用することを一切禁じております。