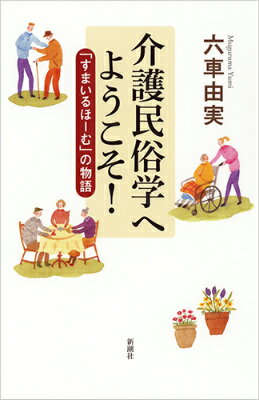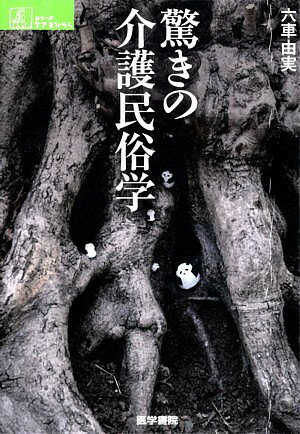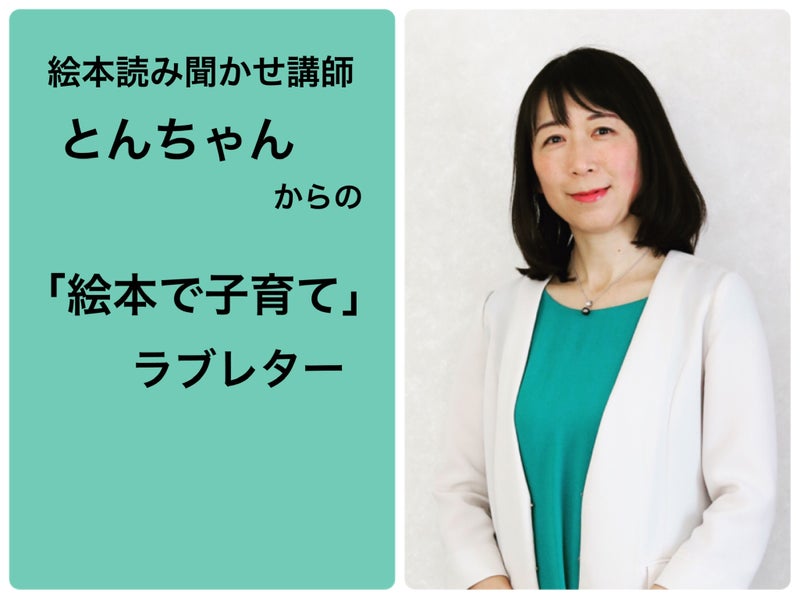先週の朝日新聞の土曜版beのフロントランナー
「介護民俗学」実践者・六車由実さん 聞く、書きとめる、理解する
という記事を興味深く読みました。
https://www.asahi.com/articles/DA3S15920401.html
介護民俗学 とは初めて聞く言葉でした。
介護の現場で「聞き書き」をする、かあ〜。へー。
その日、最寄りの図書館に行ったら、入り口入ってすぐのところに、「ひとはこ図書館」というコーナー があって、
https://lib.ed-minamiashigara.jp/exhibitions/20240329-01.html
「かに書房」おすすめ本として、六車由実さんの著書がありましたので、
「わ! なんとタイムリー!」とびっくりして、借りてきて読みました。
『介護民俗学へようこそ!「すまいるほーむ」の物語』(六車由実 新潮社)
(以下引用)
「介護民俗学」とは私の造語であり、まだまだ発展途上ではあるが、民俗学で培われてきたものの見方や聞き書きによって、介護現場のお年寄りたちの歩んできた人生に真摯に向き合うことで、人が生きることの意味や人間の営みの豊かさについて考えていくための方法
(引用ここまで)
ここで、六車さんが、「発展途上」と書いているように、民俗学の研究者であった六車さんが介護の現場で働くようになり、立ち止まり、逡巡しながら、民俗学の手法を用い「聞き書き」をしていきます。
そこでどのようなことが、お年寄りから語られ、それが介護の現場でどのような変化が生まれたのか、ということが明らかにされます。
実際に起きたこと、語られたことを、1冊にまとめるのはどれほどの苦労があったろうかと想像します。
かなり、プライベートに突っ込んだ内容が語られるので、それを言語化するにあたっての各方面への確認とか(特に家族)、話すと膨大な量になるであろうテキストを読みやすくまとめたり、時系列もバラバラになるだろうなあ、それを読みやすく文章にするのは大変だよなあ、とか。
一つ一つのエピソードがどれもとても具体的で印象深く、介護の現場を知らないわたしにも目に浮かぶようで、すごく読みやすいです。
認知症の文子さんが、家の天井に知らない女の人がいるなどという幻覚に襲われたとき、神社のお札を貼って、一緒に手を合わせたら、症状が落ち着いた、というのが特に心に残りました。
あと、恋バナとか、思い出の味の再現とか、通過儀礼とか。
介護する側、される側という、介護の現場での当たり前に、そうではない数値化できない「空気」を生み出す何かが、この「介護民俗学」というものにはあるんだなと思いました。
そしてまた、分野の全く異なるものとものを掛け合わせることで、見える景色が変わってくることはあるよなあとも思いました。
六車さんの前作『驚きの介護民俗学』(医学書院)も読んでみたいです。
メルマガ配信してます