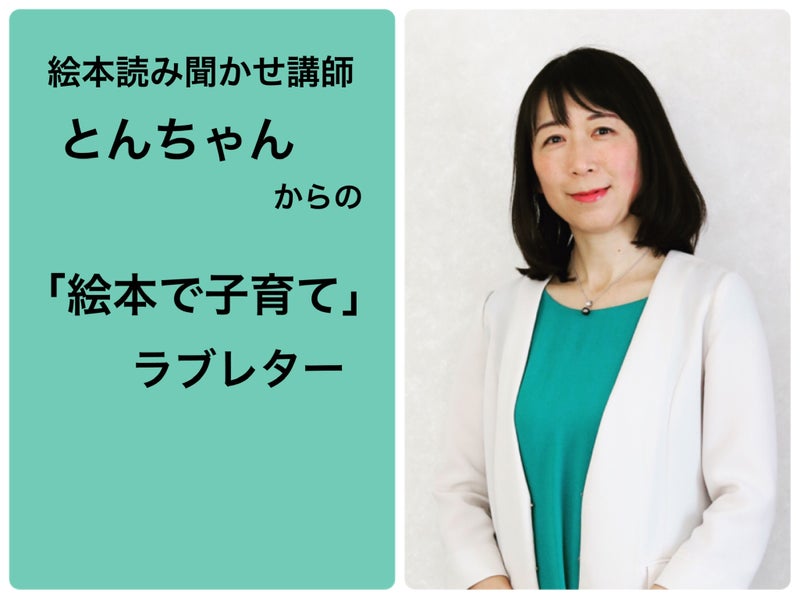ゴリラが専門の霊長類学者の山極寿一さんの記事が
2021年2月11日付の朝日新聞に掲載されていて
とても興味深く読みました。
(科学季評)コロナ、縮む社交の場 文化の力奪うオンライン 山極寿一
https://www.asahi.com/articles/DA3S14796518.html
(以下引用)
人類は長い進化の過程で脳の大きさをゴリラの3倍にした。
(中略)
どんなコミュニケーションが脳を大きくしたのか。
それは身体の動きを他者に同調させ、
リズムに乗りながら全体を調和させる音楽的なコミュニケーションだ。
ゴリラなどの類人猿に比べ人間は圧倒的に自己を抑制して場の雰囲気に合わせる能力が高い。
類人猿はいったん自分の集団を離れるとなかなか戻れないし、
1日のうちに複数の集団を渡り歩くことなどとてもできない。
(中略)
私たちが日々さまざまな集団を遍歴し、
コンサートやスポーツを見て見知らぬ人と一緒に心身をふるわせることができるのは、
人間だけが持つ不思議な同調能力のおかげだ。
(中略)
オンラインではこのリズムを作ることができない。
人間の高い同調能力を使い一つの物語を織り上げるためには、
リズムを心身に響かせる仕掛けが必要だ。
(中略)
オンラインは情報を共有するためには効率的で大変便利な手段だが、
頼りすぎると、私たちが生きる力を得てきた文化の力が損なわれる。
(中略)
社会的距離を適切に取りながらも、
私たちは「集まる自由」を駆使して社交という行為を続けるべきだと思う。
霊長類学者から見たオンラインで起こっていること。
実はわたし、
先日、山極寿一さんもパネラーのオンラインシンポジウムに参加したんですよね。
舘野鴻さんが登場し、名だたる学者さんが登場した
なかなかスリリングなシンポジウムでした。
https://chikyueiju-darwinroom-symposium.peatix.com/
そのことはまだちっとも言語化できてないんですけれど。
山極寿一さんが朝日新聞に書かれているように
確かに
午前中、自分の講座やって、午後から別の人の講座に参加して
とか
午前中映画見て、午後から子ども劇場の集まりがあって
とか
日々、いろんな集団の中を渡り歩くようなことがあって
(今は激減したけれど)
そこで自然とあるリズムに乗りながら
全体の調和に自分をなじませるような能力を
発揮していたのかもしれないなあと思いました。
そして今は
その能力を発揮する場が
激減してしまっている。
オンラインでできないのは
リズムに乗りながら
他者に同調していく空気を全体で作ること。
これは確かにオンラインでは難しい。
そして
絵本の読み聞かせは
やっぱりちっちゃいかもしれないけど
れっきとした
「文化」だよなあ、と思いました。
リズムに乗りながら
全体を調和させる音楽的なコミュニケーション。
山極寿一さんのおっしゃるのは
集団での「社交」
その積み重ねが「文化」
ということなんだけれども
まずは
家庭で
「リズムを心身に響かせる仕掛け」
として
絵本の読み聞かせが存在しているなら
救いがあるのかなあ、と。
「家庭内文化」が
そこには息づいている
と言えるのではないかなあと考えました。
だがしかし
今や、家庭内文化は絶滅の危機にあるのではないかと
危惧しているのはわたしの考え過ぎなのかしら?
リズムに乗りながら全体を
(家庭内であればほんの2、3人の)
調和させる音楽的なコミュニケーション。
体をくっつけて、
その気になれば
どこででも
いつでもできる
ゴリラにはできない
人間にしかできない
同調能力。
せっかくあるのに発揮されてないのではないかしら。
家で無理なら
せめて集団生活の中で、
保育園とか幼稚園とか小学校とか中学校とか高校とか大学とかで
ちっちゃくてもいいから
「リズムを心身に響かせる仕掛け」を意識的に
設置していきたい
がしかし、
コロナで
ことごとく「集まる自由」は閉ざされて
代わりのオンラインになっていて
それはそれですんごく便利だけれども
オンラインにしかできないこともあるけど
リアルにしかできないこともある。
でやっぱり
リアルの集団が難しいならせめて
家庭内で
「リズムを心身に響かせる仕掛け」を
簡単に設置できるのは
よいしょっと抱っこして
絵本を読むこと
もしくは
歌うこと。
それが今まさに
めっちゃ切実に必要なんじゃないかしらん、と
思ったりするわけですよ。
これから
この本を読みます