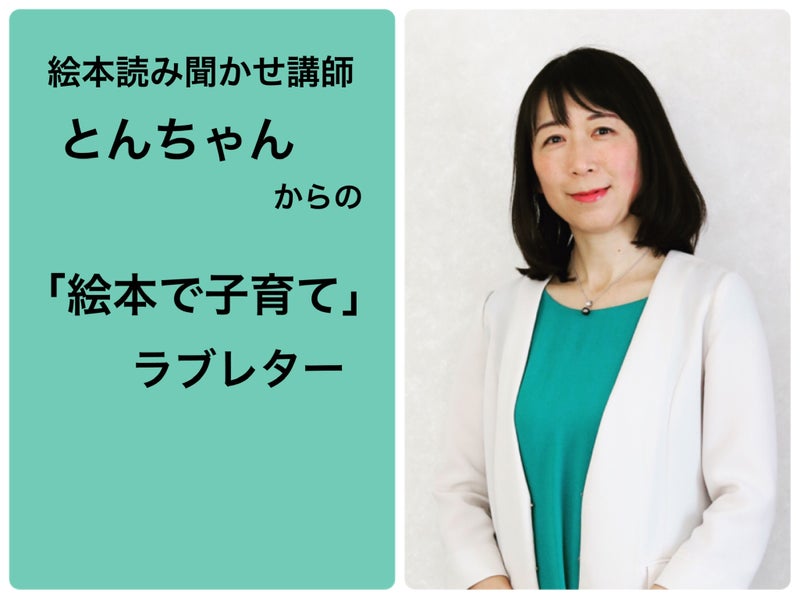あの頃の自分に読ませたい
図書館の新着本コーナーにあって
表紙のデザインが素敵だったので
借りてきて
読み始めて
あまりの面白さに
たくさん付箋をつけながら読んでいるこちらの本。
居るのはつらいよ
ケアとセラピーについての覚書
(シリーズ ケアをひらく)
東畑開人(とうはた・かいと)
医学書院
わたしは、一般行政事務で地方公務員として働いていたのですが
福祉部門が一番長く、
高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉に
関わっていました。
小さな町役場なので、福祉窓口にお客さんいらしたら
対応しますしね。
精神障害の人も
生活保護受給している人も
定住せず移動している人も
DVも児童虐待も
独居高齢者も
徘徊高齢者も
今でも具体的に顔と声とまつわる大小の事件を思い浮かべることができます。
ケアとセラピーについての覚書、ということで
あの頃の自分に
読ませたいなあと思います。
臨床心理学のハカセである東畑さんは沖縄の精神科クリニックのデイケアに就職し、
新人心理士として奮闘し
滑稽な姿も情けない姿もさらけ出している本。
どんなにハカセとして学術を極めたとしても
現場でしか
わからないことって
あるんですよね。
東畑「トーハタ」さんだから、「トンちゃん」(!)と呼ばれ
精神疾患の人が通うデイケアで働き始めます。
彼らは社会に「いる」のが難しい人たちなのだ。
だから、僕の仕事は「いる」のが難しい人と、
一緒に「いる」ことだった。
「いる」ことを目的として「いる」。
居場所型デイケアにはそういうトートロジー(同語反復)がある。
ふしぎの国みたいだ。
「いるためにいるためにいるためにいるためにいる」みたいに、
混乱した帽子屋が歌い出しそうではないか。
「いる」のが難しい人、という捉え方をすると
ああ、あの人も
あの人も
そうか、「いる」のが難しかったんだな、と。
僕はあのとき、カウンセリングもどきなんかをするのではなく、
二人でデイケアに「いる」べきだった。
一緒に、退屈に、座っているべきだったのだ。
座っているのがつらければ、
せめてトランプをやるとか、
散歩をするとか、
何かしら一緒にいられることを探すべきだった。
ジュンコさんが求めていたのは、セラピーなんかじゃなくて、ケアだった。
心を掘り下げることではなく、
心のまわりをしっかり固めて安定させてほしかったのだ。
何にもしてあげられることがないなあ、と
「何かを」「して」あげたいと
ついつい、探してしまいたくなるけれど、
一緒にいる、ただそれだけでいい、ってことは
あるかもしれないなあ、と。
別に精神疾患の人に限らず。
学校に行けなくなっちゃった、とか
失恋しちゃった、とか
会社で嫌なことがあった、とか
そういう人のそばに一緒にいる。
それでいい、というか
それがいい、場合がある。
居場所が必要になるとき
僕らは、自分になぜ「いる」ことが可能なのか、ふだんは考えもしない。
魚が水のことなんか考えないように、犬が酸素のことを気にもしないように、
僕らは自分の「いる」を支えているもののことに気がつかない。
そんなことは当たり前だと思っている。
(中略)
「いる」が難しくなったとき、僕らは居場所を求める。
居場所って「居場所がない」ときに初めて気がつかれるものだ。
本当にふしぎだ。
作られた「居場所」がときに「居づらい」ってことはあるかもしれない。
居てもいい、と気づかないくらいになったら
それが「居場所」になるんだなあ。
それは「場所」としての物理的な空間
だけじゃなくて
きっと一緒にいる人が
どんな人かってのも大事なんだろうなあ。
わたしが、子育て初期に訪れた
「子育て支援センター」を居場所と思えなかったのは
「いる」のが疲れたから。
「何か困ってることない?」と
支援してくるおばちゃんが
当時のわたしには鬱陶しかった(支援員さん、ごめんなさいね)
ただ、一緒にいる、をしてくれる人。
何もしなくていい、一緒にいる
って難しいんだなって
この本を読んで思いました。
つい、わたしは
「目的」や「ミッション」を設定して
それを「クリア」していくことが尊い
と考えてしまいがち。
「ケア」というのはそうじゃない、そんなもんじゃない、ってことを
この本を読んで感じました。
家に「いる」ただそれだけで
尊い「居場所」であるってことも言えるかも、とも。
当たり前すぎて気づけないけど。
家に「いる」
それはわたしの「居場所」と言える。
ありがたや。ありがたや。
居場所があってありがたや。
この本、すんごく面白くて
エライセンセイなんだろうと思うんだけど
笑っちゃうくらい
ユーモアがある。
すんごく面白いので読んでみてください。