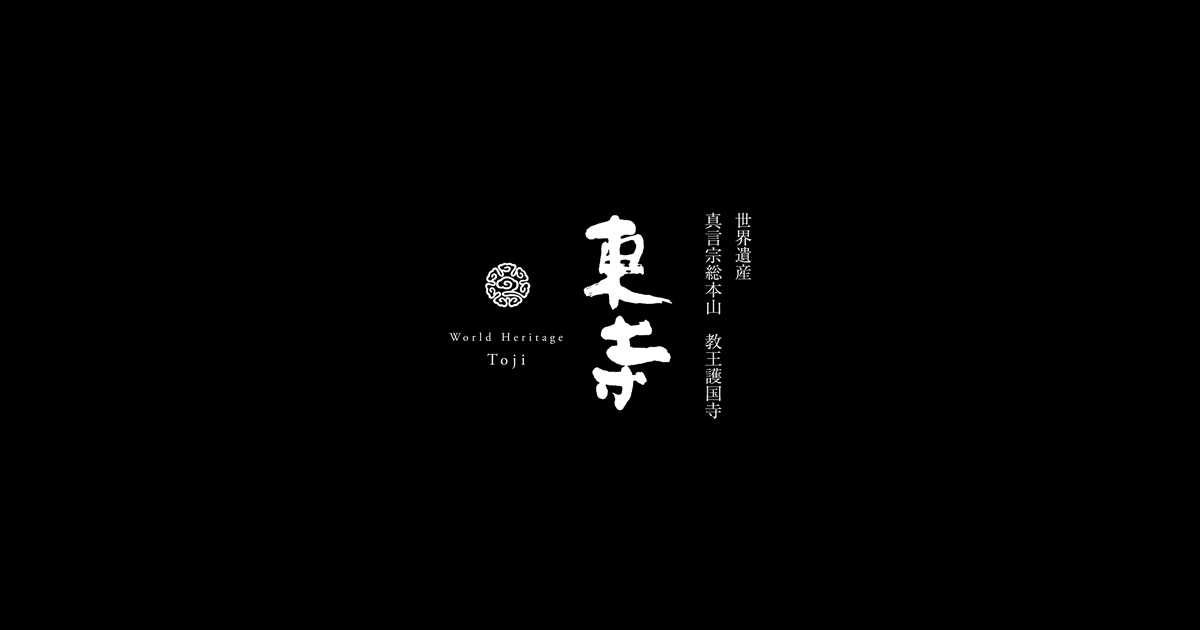京都の東寺
に、行ってきました(^_^)/
国宝 東宝記の巻第三が、未見であったためですが、思いもよらぬ収穫もあったので、併せて報告します(^_^)/
3件6点です。
・国宝 兜跋毘沙門天立像は、前期のレポートをご覧いただくとして、その他の国宝をレポートします。
・国宝 東宝記
南北朝〜室町時代(14〜15世紀)の作。
まずは復習から……
"東宝記"は、東寺の寺誌です。
それを仏教における3つの"宝"「仏」「法」「僧」にカテゴリー分けしています。
「仏宝」の上中下、
「法宝」の上中下、
「僧宝」の上下、の8巻です。
東寺で国宝指定されている"東宝記"は、12巻と1冊あるのですが、それは「草稿本」(下書き)を含んでいるから。
具体的には、東寺 東宝記
巻第一 → 仏宝上
巻第二 → 仏宝中
巻第三 → 仏宝下
巻第四 → 法宝上
巻第五 → 法宝中
巻第六 → 法宝下
巻第七 → 僧宝上
巻第八 → 僧宝下
巻第九 → 巻一の草本
巻第十 → 巻一・二の草本
巻第十一→ 巻三の草本
巻第十二→ 巻六の草本
巻第十三→ 巻七の草本
と、なっています。
巻子本(巻物形式)で巻中2mほどを、展示していました。
紙背文書(裏紙にも文書が記されている)になっています。
西院(今の御影堂/大師堂等のあるエリア)の諸堂に関する記述部分の展示です。
元福元年(1233年)弘法大師像が造られ、延応2年(1240年)には御影供(みえいく)が始まったこと。
守覚法親王(しゅかくほっしんのう)が、文治年間(1185〜90年)に、西院の修理を行ったこと。
などが、記載されていました。
字はけっこう汚くて(^_^;)、修正線もたくさん引かれていました。
お堂に関する記述なので「仏法」の巻です。
巻子本で、巻中2mほどを展示していました。
鎌倉時代の、灌頂院の再建や焼失に関する記述部分の展示でした。
こちらも、お堂に関する記述ですから「仏法」の巻ですね。
巻子本で、巻中2mほどを展示していました。
「二季伝法会」「勧学会談義」等の記事です。
"法会"に関する記述ですね。
二季伝法会では、後宇多天皇宸筆の弘法大師像(談義本尊)を掛けるのが決まりだったようです。
ちなみに、談義本尊は前期で展示されていました。
法会に関する記述ですから「法宝」です。