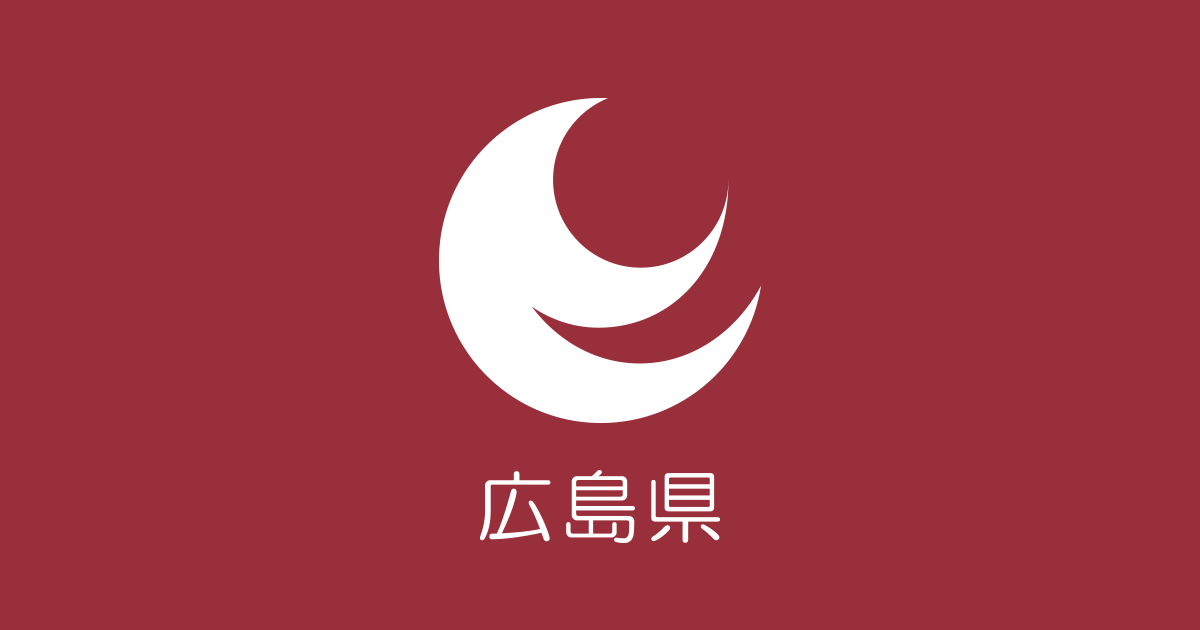広島県のホームページによると、防災職とは、
“県民の命を守るためこと = 災害死ゼロ” に対する高い使命感(志)を有し、自然災害等へ対応(災害予防、災害応急対策 等)を専門的に行う職種
とのことです。
では、広島県はなぜ「防災職」という採用枠を新設したのかを見ると、大阪府でも抱える行政組織の人事制度の慣行のデミリットが書かれていました。
以下、広島県ホームページからの引用です。
○ 近年、続発する大規模自然災害に対し的確に対応するため、自治体(県・市町)において、防災分野の知識や経験等を有する人材の確保・育成が急務となっている。
○ しかしながら、防災分野のキャリアパスが確立しておらず、人事異動により数年で交代するなど、専門人材としての知識やスキルの蓄積が困難な体制となっている(専門人材としての知識・経験が不足している)。
(以上、引用。)
近年、広域自治体に求められている役割は高度化しており、その高度化された行政サービスを展開するには、組織パフォーマスの向上として、専門人材(職)の知識やスキルが必要だと感じているものの、キャリアパス(人事異動)により数年で所属組織が変わることが弊害になっているのではないかと感じています。
一方、職員の皆さんが様々な部局(行政組織)での仕事を経験しながら、多様な観点から行政サービスを実施し、キャリアアップしていくことにも、メリットはあります。
したがって、この両方のメリットとデメリットを意識したバランスや、職員それぞれのキャリアビジョン等に合わせた人事制度が必要なんだと考えています。
さて、広島県の「防災職」として採用された3名の方々のこれまでの職歴を見ると、この採用枠の意義をさらに感じるものでした。
その方々が現在、県庁の職場において、どのような仕事をされ、活躍されているのか、今日の読売新聞夕刊トップ面にありました。
これらの情報に接すると、大阪府庁においても「防災職」の専門採用枠を新設した方が良いのではないかと思います。
また、私の持論ではありますが、これからの日本社会に必要な広域自治体の役割を果たすには、府県合併が必要だと考えています。その観点からも、高度で専門的な知識やスキルを身につけた方々に、広域自治体職員になっていただき、府県民の命を守っていただく使命を果たして頂ければなと思います。
この「防災職」採用に関して、研究してみようと思います。