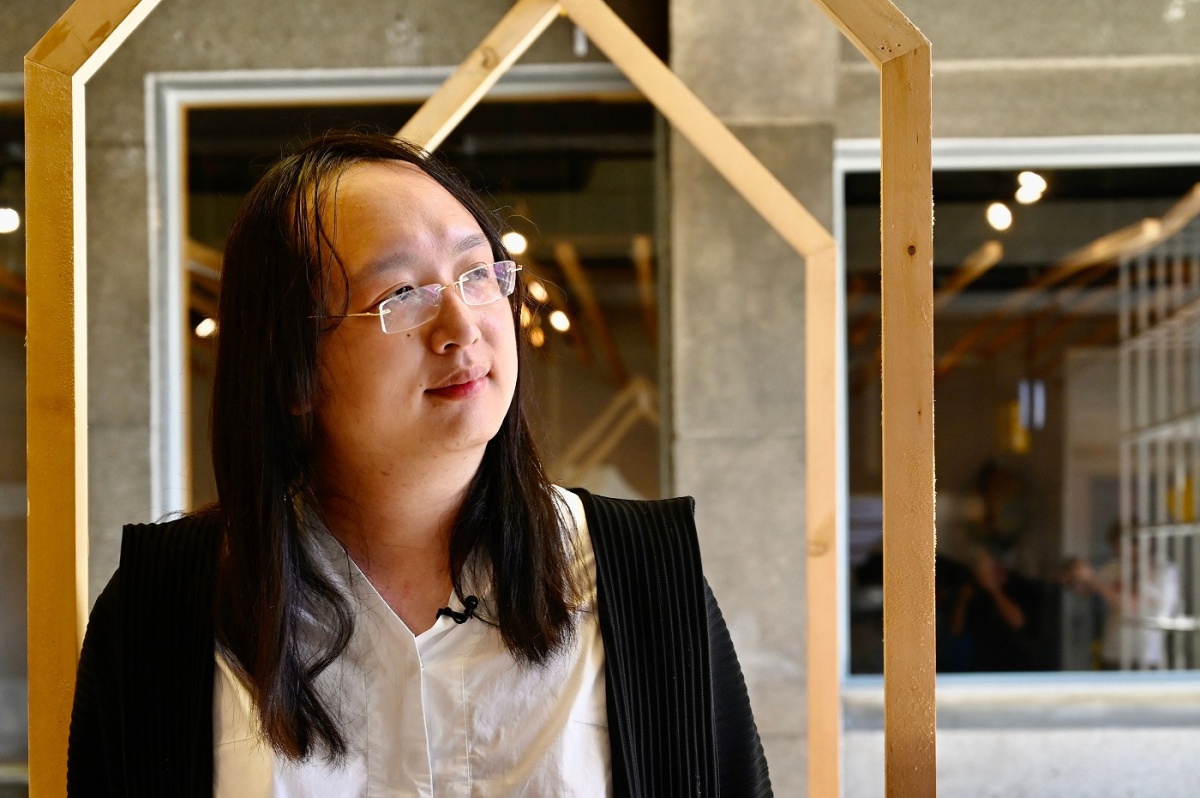「公務員って何者?」
「孤狼の血」を見て気になったので調べてみました
https://ameblo.jp/orokadaneningenwa/entry-12840890361.html
映画「孤狼の血」「孤狼の血 LEVEL2」を見て、一番深く感じたことは、「世の中の一番の害悪は警察の偉そうにしているヤツらだ!」でした。
まあ、ストーリーがそうなっていますから、当然と言えば当然のことです。
その「警察の偉そうにしているヤツら」というのは、映画でも示されているとおり、国家公務員です。
「公務員」と聞くと、すぐ思い浮かぶ言葉は「税金泥棒」かと思います。
そこで、「公務員って何者?」っていう風に素直に思いましたので、少しだけですが調べてみました。
※リンク先がない引用は、すべてChatGPT Plus(GPT-4)によるものです。
公務員の立場
日本の公務員の立場は、国や地方公共団体に雇用され、公的な業務を遂行する者として位置づけられています。公務員は、法律に基づいて国民全体の利益に奉仕する責務があり、その活動は法令に従って厳格に規制されています。日本の公務員制度には特有の特徴がいくつかあります:
1. 分類: 日本の公務員は、国家公務員と地方公務員の二つに大きく分けられます。さらに、国家公務員は一般職と特別職に区分され、一般職はさらに総合職(キャリア職)と一般職(ノンキャリア職)に分かれています。
2. 採用試験: 公務員になるためには、多くの場合、競争率の高い採用試験に合格する必要があります。これらの試験は、知識、能力、適性を評価するために設計されています。
3. 職務の中立性: 公務員は、政治的中立性を保ち、職務を公正かつ中立的に遂行することが求められます。政治的な影響から独立して職務を遂行することで、公平な行政サービスの提供が保証されます。
4. 雇用の安定性: 日本の公務員は、一般に高い雇用の安定性を享受しています。しかし、職務遂行の責任は重く、不正や職務怠慢に対しては厳しい処分が科されることもあります。
5. 福利厚生: 公務員は、健康保険、厚生年金、雇用保険などの社会保障制度のほか、住宅手当や家族手当などの福利厚生が充実しています。
6. キャリアパスと研修制度: 公務員は定期的な研修や試験を通じてキャリアアップが可能です。また、専門性を高めるための教育研修制度が整備されており、公務員の能力開発が奨励されています。
7. 退職後の再就職規制: 公務員は、退職後に特定の民間企業への就職が制限される場合があります。これは、公私の利益の衝突を防ぐためです。
日本の公務員制度は、国民のために高品質の公共サービスを提供することを目的として、厳格な規制と高い倫理規範に基づいて運営されています。
なるほど、なるほど。
厳しい条件があるものの、いろんな面で優遇されている感じですね。
でも、GAFAM(これからはGOMAかな?)とかの方が、福利厚生なんかは断然に充実してそうですけどね。
https://www.businessinsider.jp/post-266106
公務員に対する期待
そして、公務員に対する期待はこうなっていました。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/250120
国家公務員を志す若者の減少に、歯止めがかからない。2023年度の採用試験のうち、一般職(大卒程度)申込者が過去最少になった。「労働環境が悪い」と言われて久しい中、右肩下がりだった志願者は2022年度に上向いたものの、新型コロナウイルス禍が落ち着き、民間の採用意欲が高まったあおりで、またも減少に転じた。「霞が関敬遠」の現象は、打開できるのか。
(中略)
2022年度の志願者増も「コロナ禍で倒産や賃金が上がらない不安のある民間を避け、安定した公務員に流れただけ」と「働き方改革の成果」をきっぱり否定。「国会審議で担当大臣を立ち往生させないためにレクを重ね、議員のもとに質問取りや制度の説明で出向くことも多い。そういう霞が関の職場文化を根本的に変え、オンラインでの対応も拡充していかなくてはならない」とくぎを刺す。
そう、Z世代・デジタルネイティブは、「公務員」なんかに、なりたがってはいないんです。
その大きな理由は、上記記事によると、『無駄』を嫌がるからだそうです。
そりゃあー、そうだわ。
なんとも当たり前のことですよね。
公務員の給料
日本の公務員の給料体系は、国家公務員と地方公務員で異なる場合がありますが、基本的な構造は似ています。この給料体系は、職員の能力、経験、職務の難易度などに基づいて構築されています。以下はその主な特徴です:
1. 基本給
• 基本給: 公務員の給料の基盤となるもので、職員の等級や勤続年数に基づきます。等級は職務の難易度や責任の大きさに応じて定められ、勤続年数が長くなるにつれて基本給は増加します。
2. 手当
• 通勤手当: 通勤にかかる費用を補填するための手当。
• 住宅手当: 住宅に関する経費を補助する手当。家賃の一部を補助する場合が多い。
• 家族手当: 配偶者や子どもなど、扶養家族がいる公務員に支給される手当。
• 時間外手当: 時間外労働に対する手当。公務員も民間企業と同様、時間外労働に対して追加の報酬が支払われます。
3. 昇給と昇進
• 昇給: 勤続年数の増加に伴い、基本給が定期的に上がるシステムです。定期昇給は、公務員のモチベーション維持と経済的安定を図るために設けられています。
• 昇進: 職務の遂行能力や成果に基づいて、上位の職階へ昇進することが可能です。昇進によって基本給が大幅に上がる場合があります。
4. 退職金
• 退職金: 長年にわたり公務に従事した後、退職する際に支給される一時金。勤続年数に応じて支給額が決まります。
5. 年次調整
• 給与の年次調整: 経済情勢や物価の変動を考慮して、公務員の給料は定期的に見直されます。給与水準の調整は、政府や関連機関によって決定されます。
日本の公務員の給料体系は、透明性と公平性を確保するために厳格な規則に基づいて設計されています。また、公務員の生活水準を保ちつつ、公共サービスの質を維持するために、給料体系は国民経済や財政状況に適応して調整されます。
ふむふむ、いたって普通ですね。
つーこって、具体的な給料について調べてみました。
https://www.jinji.go.jp/kyuuyo/
令和5年度(2023年度)国家公務員一般職の年収は約666万円(約6,666,248円)です。
国家一般職が該当する「行政職俸給表(一)」の給与は、平均給与月額は404,015円、俸給は322,487円で、平均年収は約666万円(約6,666,248円)です。
• 平均年収:約666万円(約6,666,248円)
• 入庁後の年収:約366万円(約3,666,960円)
• 平均給与月額:約404,015円
• 初任給:222,240円(地域手当なし場合:185,200円)※行政職俸給表(一)1級25号
国税庁の令和4年(2022年)分民間給与実態統計調査結果によると、民間企業に勤務した給与所得者の平均年収は458万円(男性563万円・女性314万円)であることを考慮すると、かなり高いと言えるでしょう。
しかし、見た目の数字だけでなく公務員の充実した福利厚生も加味すべきでしょう。
さらに公務員は例外的な場合を除き、解雇されることがありません。
そうした安定性も含めると非常に魅力的な職業と言えるでしょう。
なるほどね。
な・の・に、Z世代・デジタルネイティブは「公務員」にはなりたくない。
この『大きなギャップ』は、いったいどこからきているんでしょうかね?
公務員の実態
日本の公務員が直面する厳しい側面や困難には、いくつかの共通点があります。これらの点は、職種や勤務地によって異なる場合がありますが、一般的に以下のような問題が指摘されています:
1. 長時間労働
• 公務員には、繁忙期や緊急事態、プロジェクトの締め切りなどにより、長時間労働が求められることがあります。特に、行政サービスが市民に直接影響を及ぼす部門では、残業が多くなる傾向があります。
2. ストレスとプレッシャー
• 法律や規則に基づき、正確かつ迅速な対応が求められるため、日々の業務に伴うストレスが高いことがあります。また、公務員はしばしば厳しい公眼のもとで業務を行うため、そのプレッシャーは一層大きくなります。
3. 政治的中立性の維持
• 公務員は政治的中立性を保つ必要があり、時には自分の個人的な意見や信念を抑えなければならない場合があります。このような立場は、表現の自由や個人的な信念とのバランスを取る上で困難を感じることがあります。
4. キャリアの成長と昇進の遅さ
• 公務員の昇進は、経験年数や定期的な評価に基づくことが多く、民間企業に比べてキャリアアップのペースが遅いと感じることがあります。特に若手職員の中には、よりダイナミックなキャリアを求める声もあります。
5. 職場の人間関係
• どの職場にも言えることですが、公務員もまた、職場内の人間関係によるストレスを経験することがあります。特に、伝統的な上下関係が強い環境では、コミュニケーションが難しいこともあります。
6. 給与と福利厚生の見直し
• 経済状況や政府の財政政策によっては、公務員の給与や福利厚生が見直されることがあり、これが不満の原因になることもあります。特に、民間企業との給与差に対する不満が挙げられることがあります。
7. 退職後の再就職規制
• 公務員は退職後に特定の業界への再就職が制限されることがあり、キャリアの選択肢が限定されることがあります。
これらの問題に対処するため、多くの公共機関ではメンタルヘルスサポートやワークライフバランスの向上に向けた取り組みを強化しています。また、組織文化の変革や働き方改革も積極的に進められています。
さらにさらに、こんなこともあるようです。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kasumigaseki/article/article_190315.html
国会会期中、自宅を出るのは朝6時。
その後、「大臣レク」「幹部レク」といわれる幹部との協議や議員への説明まわり、法改正の準備などを続けます。
夜は翌日の国会答弁の作成。休憩時間はほとんどなく、昼食も移動しながらおにぎりをかじるだけです。
帰宅時間は、ほぼ深夜1時を回るといいます。
目につくのは国会対応の多さです。国会中継で、各党の国会議員が質問し、各省庁の大臣らが答弁する姿、テレビで目にしたことがあると思います。議員からは前日までに質問内容を伝える、いわゆる事前通告があり、それに基づき答弁を作るのが基本、官僚の皆さんの仕事です。
大変な失礼を承知で申し上げさせていただきますが、「バカなんですか?」。
だって、なんで選挙で選ばれた国会議員だけのために、わざわざ深夜まで働く必要があるんでしょうか?
日本における議会と役所(行政機関)の役割分担は、立法権と行政権の区別に基づいています。この二つの機関は、民主的なガバナンスと国の運営において重要な役割を果たしていますが、それぞれの機能と責任は異なります。
議会(立法機関)
議会は立法機関としての役割を担っており、その主な任務は以下の通りです。
• 法律の制定: 新しい法律を作成または既存の法律を改正、廃止する権限を持っています。法律案は、議会での討議と投票を経て成立します。
• 予算の承認: 政府が提出する国の予算案を審議し、承認します。これには、税金の徴収や公共支出の計画が含まれます。
• 政府の監視: 行政機関の活動を監視し、評価する責任があります。質問時間や調査委員会を通じて、政府の政策や行動に対する監督を行います。
役所(行政機関)
役所は行政権を担い、具体的には以下のような役割を果たします。
• 法律の執行: 議会が制定した法律に基づいて、日々の行政活動を遂行します。これには、国民へのサービス提供や公共政策の実施が含まれます。
• 政策の立案と実施: 政府の方針に基づき、具体的な政策を立案し、これを実施します。政策の効果を分析し、必要に応じて改善策を講じます。
• 公共サービスの提供: 教育、保健医療、社会保障、公共インフラの維持管理など、国民生活に直結する多様なサービスを提供します。
役割分担の意義
このように議会と役所は、それぞれ立法と行政という異なる機能を持ちながら、相互に連携し合うことで国の運営を支えています。議会による法律の制定と役所による法律の執行という役割分担は、民主主義の原則に基づいたチェック・アンド・バランスの体系を構築し、政府の権力が一箇所に集中することを防ぎます。また、政策の立案と実施において、議会による役所の監視と評価は、政府の透明性と責任を確保する上で重要な役割を果たしています。
おそらく、「眠らない官僚」さん達がやっていることっていうのは、こういうことだと思います。
「議会が制定した法律に基づいて、日々の行政活動を遂行している」ことを、国会議員の質問に応じて、国会で答弁しているってことなんでしょう。
まあ、わからないでもないですけど、まさに『昭和』のまんまですよね。
だって、そんなこと、「日々の行政活動」ってやつを、常に『オープンデータ』にすればいいだけですからね。
こんなこと、もっと前からやんなきゃなんないことですが、直近だとコロナ禍での台湾のオードリー・タンさんから学びましたよね?
https://www.sbbit.jp/article/cont1/82585
マジで、なんでそんな簡単なことができないのか、まったく理解できません。
まあ、映画やドラマを見ていると、その「日々の行政活動」の中には、絶対に隠さなきゃならないことがあるから、できないんだと思います。
だったら、そんなこと、最初からやらなきゃいいじゃん!
だって、「公務員」っていうのは、「法律に基づいて国民全体の利益に奉仕する責務が基本」なんですから!
マジでワケワカメですよ。
これからの公務員はどうなる?
AIの進化は、日本を含む世界中の公務員の将来に大きな影響を与えるでしょう。これには、業務の自動化、サービスの改善、政策立案の効率化などが含まれますが、同時に新たな課題も生じます。以下は、AIの進化が日本の公務員の将来にもたらす可能性のある変化です:
1. 業務の自動化と効率化
AIの導入により、書類の処理、データ入力、情報検索などの時間を要する繰り返し作業が自動化されることで、公務員の業務効率が大幅に向上します。これにより、公務員はルーチンワークから解放され、より専門的な業務や市民サービスの向上に注力できるようになるでしょう。
2. サービスの質の向上
AIを活用することで、公共サービスのパーソナライズが可能になります。例えば、福祉、医療、教育などの分野で、市民一人ひとりのニーズに合わせた情報提供やサポートが実現可能になります。また、AIによる分析を通じて、サービスの不足がある地域や改善点を迅速に特定できるようになることで、より効果的な政策立案が可能になります。
3. スキルセットの変化
AIの導入に伴い、公務員に求められるスキルセットにも変化が生じます。データ分析、プログラミング、デジタル技術に関する知識がより重要になり、これらのスキルを持つ公務員の需要が高まるでしょう。また、AI技術を適切に管理し、倫理的な観点から適用するための知識も必要になります。
4. 雇用構造の変化
一部の単純作業がAIによって自動化されることで、公務員の雇用構造に変化が生じる可能性があります。一方で、新たな技術を管理し、AIが提供するサービスを監督するための新しい職種が生まれることも予想されます。
5. 倫理的・法的な課題
AIの導入は、プライバシーの保護、個人データの安全性、AIによる決定の透明性と公正性など、多くの倫理的および法的な課題を提起します。これらの問題に対処するためには、新しい規制の策定や既存の法律の見直しが必要になるでしょう。
AIの進化により、公務員の役割や業務のやり方は大きく変わる可能性がありますが、これらの変化を適切に管理することで、公共サービスの質の向上や政策立案の効率化につながると期待されています。
ありゃまー、ですねー。
だって、公務員ではAIなどのICT関連に対応できないから、たとえば東京都では、ヤフー株式会社CEOだった宮坂学さんが理事長の「一般財団法人GovTech東京」を設立したんですよ。
https://ameblo.jp/orokadaneningenwa/entry-12835721309.html
公務員オワタ
今後、日本では少子高齢化が確実に進んでしまいますし、きっと近いうちに、アメリカみたいな『自己責任』な社会になるんでしょうかね。
責任感のある公務員は日本に必須
でも、そんな風になってしまったら、我々日本国民は、めちゃくちゃ困ると思うんです。
https://president.jp/articles/-/71991
警察官、消防士、自衛官が、バッシングばっかされ続け、その結果、「法律に基づいて国民全体の利益に奉仕する責務」がなくなってしまったら、どうなると思われますか?
犯罪、いじめ、災害などがあった際に、公務員の方々の心の底にあるものは、「あー、こんなヤツらのまめに面倒なことはやりたくねーなー」なんてことに、最悪なっちまいますよ。
戦後のように、「アメリカと同じなるんだー!」みたいな、そんな嫌な感じになる前に、私は『デジタル・イノベーショングループ』の活躍に超期待しています。
国の垣根なんてもん、全然いらねーし。
https://ameblo.jp/orokadaneningenwa/entry-12838165391.html
♪空を見て 気づいたんだ 世界は愛で溢れている♪
以上になります。