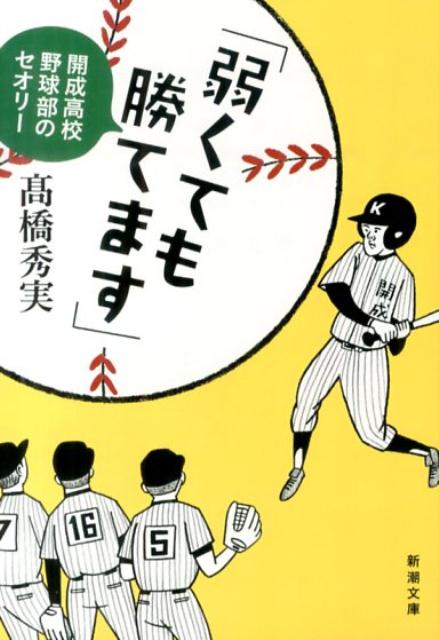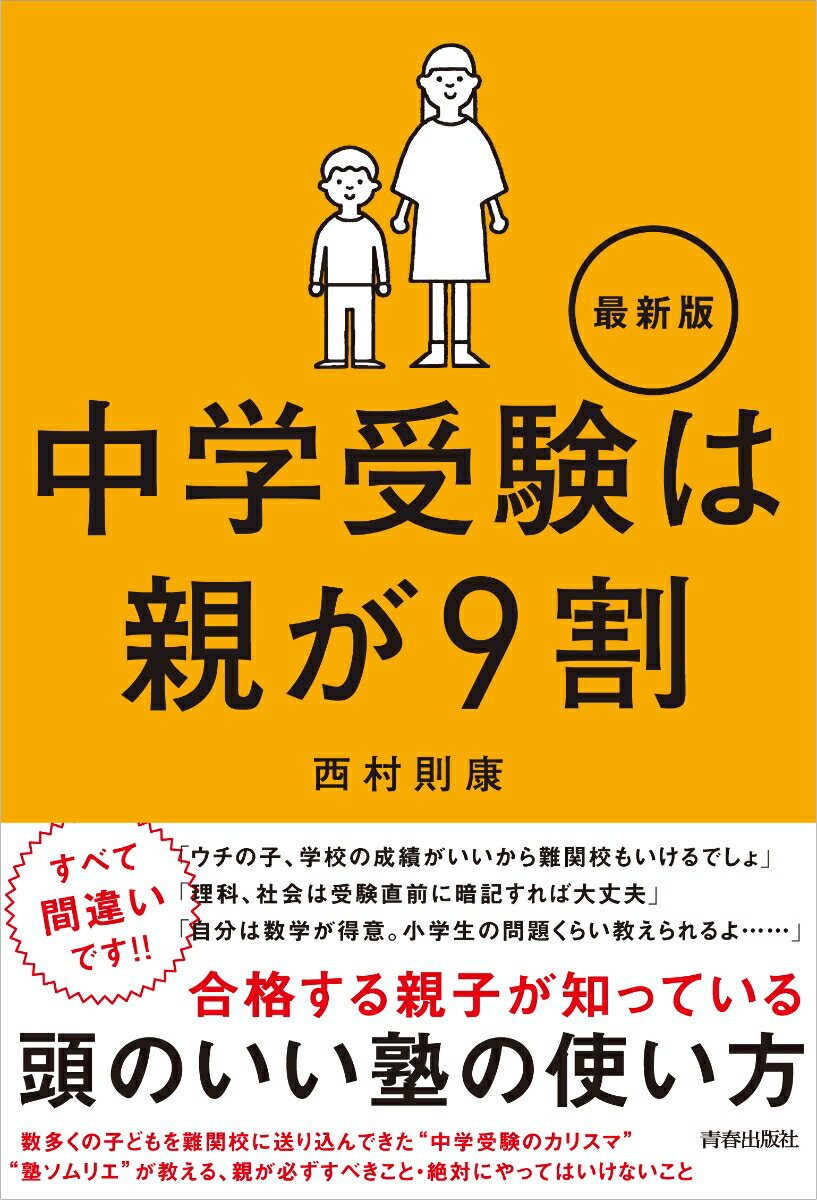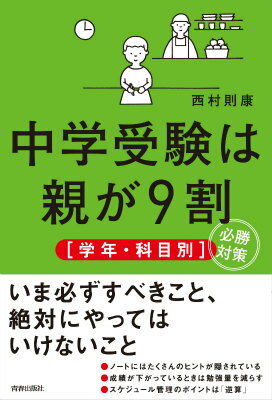弱者が敗者とは限らない。
およそ戦闘においては
戦略目標の到達が主目的である。
逆に言うと、これしくじると、
なんのためにやってたんだと
燃え尽き症候群まで起こる。
だから、
戦略とは目標設定の
段階からがスタートなのだ。
行きたい、行かせたい、受からせたい
はっきり言うと、
確実性が高いのは、
児童が行きたいと思い、
保護者が行かせたいと思い、
塾屋が受からせたいと思ったとき
3つのチカラが一つになれば、
明日の希望をとりもどそうぜ!
となるのだが、
どこかとの連携ができてないと、破綻する。
トリニティ理論は一つ欠けると
もう成り立たない脆弱性がある。
※国会、内閣、裁判所のどこかが腐ると
三権分立成立しない
どこをどう直していくのか。
ここで気をつけたいのが、
私はこんなに真剣に中学受験考えてるのに、
なんであんたは本気出さないの?である。
詳しくはこちら
この精神状態になると、
子どもの受験じゃないの。
親は9割であっても、1割は子どもなの。
この本を書いた、
西村則休先生ですら警告してる。
共感がベースにある母と子の関係性の一方で、
父親は子供に対しても
「こうすべき」「こうでなくてはいけない」
というふうに一本調子になりがちな面があります。
勉強についても、
「お前は普段ここができてないから」と
まず欠点を指摘して
「だからこうしなさい」とやりがち。
そう言われた子供は身構えてしまいます。
「そんなこと言われなくてもわかってるよ」と
反抗的な気持ちになってしまうのです。
同様に、ビジネスの場で
ご自身にとって成功体験のある
PDCAサイクルを子供に適用してしまう
お父さんも多い。
特に気を付けなければならないのは
「チェック」です。
チェックするときは良くないこと、
改善点を分析するだけではなく
「良かったこと、できていたこと」もみて、
そのうえで
「こうすればもっと良くなるよ」というふうに
プラス思考に言い方を変えることが大切。
それができないのなら、
何も言わない方が余程良いです。
朝起きて
計算と漢字をやる習慣があるのであれば、
夏休み中も続けるなど、
毎日コンスタントに取り組んでいる
習慣の継続と再確認をしてください。
再確認するポイントの1つとして大切なのが、
宿題に取り組むタイミング。
授業が終わったあといきなり宿題ではなく、
授業の振り返りをしてから
宿題をするという習慣付けが大事です。
特に算数では
理解の定着においてそれが重要になってきます。