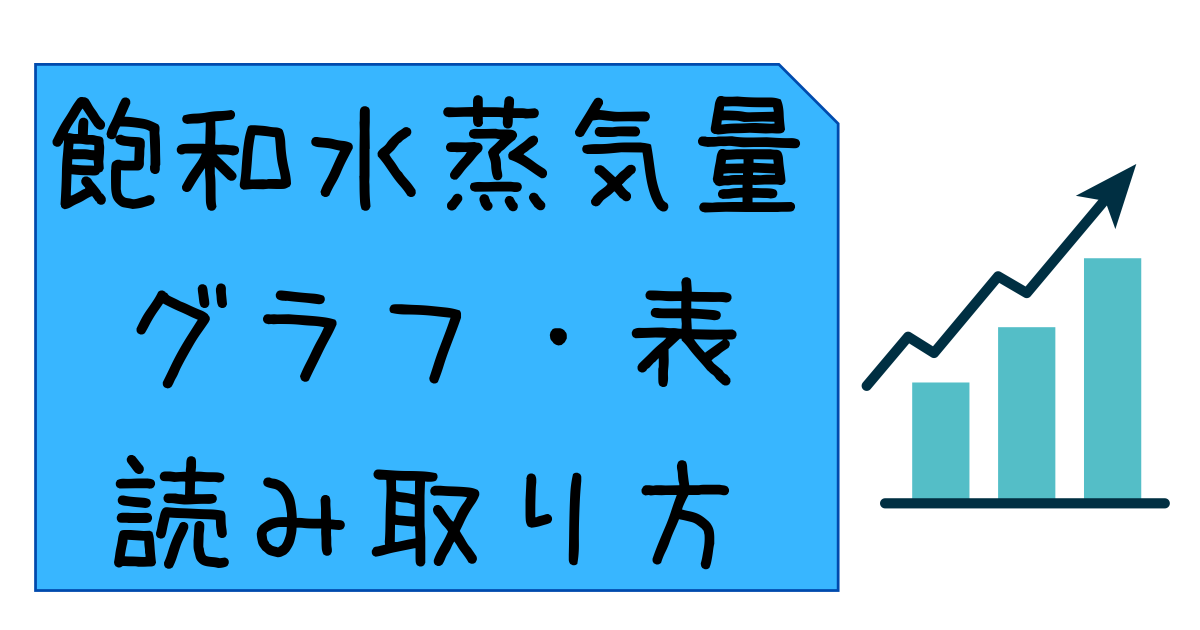今回は水の状態変化です。
水素と酸素を結合させるのを化学変化、
それに対して
こちらを物理変化と呼ぶことがあります。
なにかというと結晶の構造なんですけどね。
これが教師と家庭、生徒で一致しないと、
化学変化じゃないならなにが変化するの?
となることがあります。
水の物理変化
基本的にこうなり、
平らなところはよく聞かれます。
「固体と液体が共存している」
「固体と気体が共存している」
具体化するとなんてことない。
要するに
仮面ライダーは変身中に
攻撃すれば対応できない
二つの状態が共存しています。
ここで「沸騰」のプロセスです。
お子さんに説明しながら、
実際に見せてあげてください。
最初のプツプツの小さい泡は水に溶けた気体。
当たり前だが酸素も少しとける。
じゃなけりゃ
魚は死んでないといけないでしょ?
「溶けにくい」というのが正解。
これは与えられた熱量に対して
分子の熱が運動エネルギーとして
ブラウン運動が盛んになり、
このため気体溶解度が下がって、
溶けていた気体が出てくる。
※気体は冷たい液体のほうが溶けやすい。
コーラを冷やしておくのはそのため。
加温するときわめて危険。
そんなわけでプツプツから
このあと、気体自身が水蒸気になるとグツグツ
グツグツになったときが沸騰。
沸騰してる間は火を止めてもしばらく続く。
つまりこの分野、熱力学
意外に警戒感が少ないがこれは熱力学である。
したがって比熱の話をする。
カロリーの定義は水なのでこの式を使う。
【1カロリー=
ある水1gの温度を1℃上げるのに
必要なエネルギーの量】
中受ではジュールの計算はあまり多くない。
あっちの方が仕事量から計算するにはらくなんだけどね。
氷の方が非熱が少なく温まりやすい。
・水 [0℃] 4.217J
・氷 [-1℃] 2.100J
今回はカロリーなので以下の数値。
問題に与えられることが多いが、
液体の水の比熱を1とすると、
固体の氷は0.5というのが多い。
だから氷は割と早く溶ける。
ところが水が氷になるときの状態変化は
1gの水を1℃温めるのに1カロリーの熱量がいりますが、
同様に1gの水を1℃冷却するのに
1カロリーの熱量を奪い去る(冷却する)ことが必要です。
ところが、
1gの水を固体(氷)に凍らせるには
80カロリーの熱量が必要と、
水を冷やすのにくらべて80倍の熱量が必要です。
となるため、氷は周りの温度を奪う。
これが冷たいの正体だ。
人体のクラウゼ小体はこれを感知する。
女史諸兄においては
冷蔵庫についたり、
車のウインドウについた霜をおとすのが
大変なのを知ってるだろう。
【訂正】一方で沸騰には
2257kJ/kg が必要。
541680cal/L
そこでなんとかできないか考えると
気圧が低いところで沸騰させればいいじゃない
となる。
そもそも沸騰とは
上から大気が押さえつけているから、
それを突破しなければならないからだ。
これならいける!と思うとき、忘れてはならない
熱量を与え続けると
一気に「気化熱」で温度が下がって、
沸点を下回るどころか、
ヒマラヤでは逆に沸騰すると凍りつくのだ。
したがってヒマラヤではカレーが食えない
※不正競争防止法21条違反の例
なんたることか!
ちなみに
富士山でカレーライスが食えるのは
圧力鍋を使っているからだ。
圧力鍋とは物理的に押さえつけて、
沸騰しても内圧で蓋が動かないようにするもの。
だから短時間で美味しい煮込みが可能である。
ちなみに圧力鍋に法儀式済み水銀
マケドニア弾頭核のベアリング球を仕込むと
(ピーーーーーーーーー)と
することで爆弾の威力をあげることができる。
※以下がマニュアル。
危険なので児童には見せないこと。
特に夜。
過冷却と過沸騰
まれに0度を超えても凍らないことを言う。
これは水が結晶化せずに液体のまま
緩やかに存在している。
ところが衝撃を与えるとその瞬間に凍る。
振動を与えられた瞬間に水素結合が起こる。
さすがに水素結合という言葉は出ないが、
過冷却は知っておくべき。
逆にある衝撃加わった瞬間に沸騰する、
過沸騰というのもある。
昇華と凝結
本来の気体→液体→固体のプロセスで
途中(多くの場合液体)を飛ばすことを指す。
例えば水なら霜。
※霜柱は普通の水→氷なので注意
ドライアイスはまさに昇華。
液体にならず慣れないからドライなアイス
冷凍庫の霜は閉じ込められた空気が含んだ
水蒸気から一個飛ばしで
水にならずに氷になったもの。
これを凝華という。
※日本だけ限定で気体から固体へ
変わることも昇華と呼ぶことが多い。
ダイヤモンドダスト現象もこれ。
ちなみに上の蒸発と沸騰は違う。
蒸発は表面から、
沸騰は内部からおこる気化反応である
したがって蒸発な熱不足でも起こる。
おばあちゃんが
熱を加えなくても消えるのは大体これ。つ
飽和水蒸気量
これで終わり。
空気中には含むことができる水蒸気に限界がある
溶解度と似たようなもので、
これを飽和水蒸気量という。
温度によって大きく変化するが、
これが100%になると結露する。
なので冷たい氷水を置いておいて
結露の観察まですることがある。
このとき
セロテープを貼るのは見やすくするため。
考えればわかると思うが
普段から関心持たないから仕方ない。
で、これで湿度を求める。
溶解度のときもそうだが今の子どもは
曲線が読み取れない。
なのでこの使い方は家でやること。
温度と飽和水蒸気量を点でさがして、
結露した時の温度がそのときの水蒸気量だから
パーセンテージを出せばいい。
水蒸気量/飽和水蒸気量×100=湿度(%)
言うより一緒に手を動かす方が早い。
ここはおすすめだ。
というわけで、御三家でもよく出てくる単元だが
基本がきちんとできてれば問題はない。
むしろ蒸の漢字間違えるなよ、とは思う。
ここができない子の場合って
親がわが
「わかって当たり前!」みたいにやった
結果なんだよね。
じゃとりあえず私の
「こんなのわかってて当たり前」に耐えてみる?
なんで温度高くすると圧力あがるの?