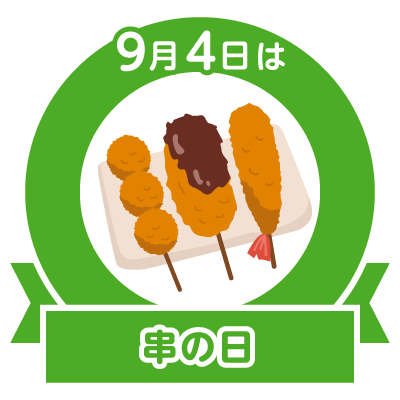▼本日限定!ブログスタンプ
串の日 由来
串の日の由来とはそのまま語呂合わせで⑨月④日だから串の日と名づけられました。
香川県に本社を持つ、冷凍食品製造販売社『 味のちぬや 』が串もの商品を㏚するために制定された日です。そのため串の日は串もの商品を㏚するために様々な飲食店や自治体でイベントやキャンペーンを行って美味しい串ものを提供してくれる試みがあります。
串の日だけに串もの全般というイメージはありますが、実は今の所⑨月④日にイベントが行われているのは串カツ屋さんが中心です。また関西地方を中心に㏚イベント等を行っている事が多いのです。余談ですが、大阪、新世界のゆるキャラといえばくしたんですが、くしたんも⑨月④日串の日生まれです。名前の由来も串です。その日はくしたんも串の日㏚でイベントに出演しているので運が良ければ会えるかもしれません。
串ね日 イベントって⁉️
⑨月④日の串の日は串カツを㏚するイベントが多く新世界の串カツ振興会のイベントや、くしたんが㏚してくれるイベントで大盛り上がりです。
また串カツグランプリなどのイベントでは串カツを無料で配ったり、当たり付アイスのように串にあたりを付けて当たったらもう一本という楽しい仕掛けがあったり、一本①⓪⓪円以下で食べられたり、珍しい串カツが食べられたりと、楽しいイベントが多いのもこの日です。
串カツ好きにはたまらない一日で①週間程イベントをやっているお店もありますので、当日にこだわる必要もありません。ただ串の日の由来でもある⑨月④日に多くのお店でイベントや㏚が行われますので、色々なイベントを楽しむのであれば当日に一足を運んでみるのがおすすめです。
串カツの②度つけ禁止の由来
関西の串カツ屋さんに足を運ぶとソースの②度付けは絶対禁止です。
②度付け禁止の由来とは単純に衛生面が理由です。特に昔から決まっている由来はありませんが①度口を付けた串カツに再度ソースに付ける行為は暗黙の了解で禁止となっています。
関西在住の人にとってはそれが当たり前の事ですが、その他の地域から観光で来た人はその由来も分からずに度付けをしてしまう人も少なくありません。最近では観光雑誌にも②度付け禁止の由来と注意が掲載されている雑誌もありますので減少傾向にありますが、関西で串カツを楽しもうと考えているならルールは把握してから足を運びましょう。
しかしソースが足りなかった人の為に許されている行為があります。それは串カツを食べる際には必ずセットになっている角切りのキャベツです。口を付けていないキャベツにソースを付けてそのまま串カツに付けて食べられます。このように打開策もありますので、ルールを守って串カツを楽しむのも美味しく食べられる秘訣です。
串の日 いつでも美味しく串ものを•••
串の日の由来も実にシンプルであったり、沢山のお店でイベントも行われみんなでワイワイするもよし、少人数で黙々食べるのも良しです。
串にささっているからおやつ感覚でも楽しめるし、嫌いな野菜を串カツにしちゃえば子供でも美味しく食べられます。夏はバーベキューにしたり、冬はおでんにしたりとそのバリエーションは果てしないのです。年中食べられる串ものは日本人なら誰でも大好きです。しかし串の日は主に串カツがメインの記念日です。その為、串カツ屋さんを中心にイベントを行っている事も多く、美味しくリーズナブルに食べられるイベントが多い日です。家族で行くも良し、カップルや友達同士で行っても楽しいので、是非⑨月④日は楽しく串カツを楽しみましょう。
櫛を髪に挿せば霊力が魔除けとなる⁉️
用途は使う場所も異なる『 櫛 』と『 串 』ですが、語源は同じで『 不思議なこと 』=奇し『 霊妙なこと 』=霊(くし)びという言葉からきているそうです。
櫛は古事記や日本書紀などに記されている日本神話で、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が櫛の歯を折り火をおこすなどの櫛に関する不思議なエピソードが残っています。また縄文時代から主に髪飾りとして使われ、その歴史の中で神事や神祭が行われる際に、神子の髪には櫛がつけられていることが多いと言われもっと身近な言い伝えでは櫛を挿すことで魔除けとなったり霊力を授かるとされ、その語呂から『 苦死 』を連想し落ちている櫛を拾ってはいけないという言い伝えもあるそうです。このように櫛は神聖なものとして扱われてきました。現代では櫛を髪に挿す人を見かけることはほとんどなく、髪を清潔に保つための櫛の役割は洗髪の習慣が広まってからブラシに取って変わってしまいましたが、櫛の神聖さを改めて感じられた方は今一度、美しい櫛を手に取ってみてはいかがでしょうか。
祈りを込めて神に捧げる『 串 』の歴史
『 串 』というと美味しい食べ物を連想するほど串料理が広まっている現在ですが『 串 』の歴史も古く神事を行う場所で使われており、今も目にすることがあります。
呼称の由来はいくつか説があるようですが、木竹などの串に玉がついたものをお供えしていたことから『 玉串 』と呼ばれ、神事のお供え串がありました。今では榊や竹に麻や木綿、紙などをつけたものになっています。食べ物や酒、水などのお供えと異なる点は、礼拝する者の敬意や、神威を受けるために祈りを込めて捧げるものとして、特別な意味を持つということです。『 玉串礼拝 』のように呼ばれることもあります。
そして現在多くの人に身近となっている方の『 串 』。そう聞いて最初に思いつくものは、やはり串焼きなどのやきとりや串カツといった食べ物ではないでしょうか。
歴史ではやきとりが一番古く、平安時代に肉を小さく切って串刺しにして焼いたことから広まったそうです。現在では、野菜やその他の食材を串刺しして焼いたものも『 やきとり 』と呼ばれるようになっています。串カツは大阪・新世界が発祥で、野菜や肉、魚介類を一口サイズでひとつの串に一食材が串刺しされ、目の細かいパン粉を使った衣をまとい、油で揚げられた串料理です。串カツにつける専用のソースはテーブルごとにステンレス製の器に入れられており、次に使うお客さんも気持ちよく食事ができるように「二度漬け禁止ルール」が設定されていることは、多くの方がご存じではないでしょうか。最近では、食べ放題や、セルフ揚げ、天婦羅のような出で立ちの串カツなど、様々な串カツのサービススタイルがあるようです。