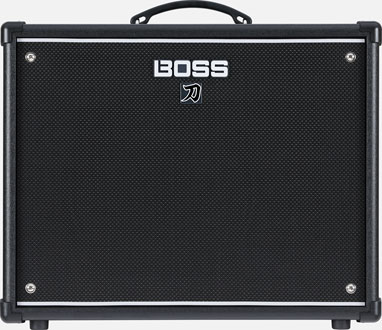blogを書けと言われたので「BOSS KATANA-MK2で音作り」の話。
執筆/作業環境の見直し中なので、試し打ち的にblog。
楽器機材関係なのは気軽に書けるからってことでヨロシクお願い致します。
先日、BOSSのKATANA-MK2にHXStompを繋いで、という内容を書いてました。
このとき、HXStompなし、KATANA単体で弾いてみたんですよ。お! ソリッドステートでも実アンプって、やっぱいいじゃん! って感じでした。が。KATANAに新機種が出ましてね。GEN3 って奴。
まーた、MK2が旧式になっていくう! って思いました。ええ。
とはいえMK2もまだまだ現役でございますよ。
ってことで今回はMK2の話を少し。
基本的に。
※定位置じゃないとこで撮影。キャビネットはLaney IRT112 のはず。
KATANA-MK2ってオールラウンダーだと思います。
クリーンからハイゲインまでカバーできる選択肢が用意されていますからね。それこそ内蔵エフェクト(BOSS!)を併用すれば、様々な局面に対応できます。専用アプリをダウンロードしたノートPCがあれば、なおよし。
またソリッドステートならではの気軽さもウリです。スイッチを入れてすぐ弾き出せますし、デリケートなチューブ管も入っていないのでその部分に気を遣わなくて良いのがデカイ!
そんなMK2ですが、いろいろ機能がてんこ盛りです。
その内、パネルモードで音作りする際に重要と思われることを書いてみます。
ボリューム。
※BrownChannel。言わずと知れたブラウンサウンド? こちらはバリエーションスイッチオフ。
KATANA-MK2には5タイプのアンプ×2(バリエーションスイッチ切り替え)が装備されています。それぞれ名前の通りのサウンドですが、どのChannelも多少現代的な設定をされているように感じます。ロックンロールとか60年代ロックとかやるなら、クリーンアンプにしてゲインを上げ、飽和させる感じで歪ませるor内蔵エフェクトのオーバードライブで軽く歪ませると良いかもしれません。ブルースドライバーも内蔵エフェクトにありますしね。もちろんバリエーションスイッチによる味付けでもトーンが変わりますので、そこを含めて音作りして下さい。
※POWER CONTROL。住宅環境を鑑みると0.5wが最適解?
あ! あとは出力問題があります。
POWER CONTROL 0.5、50、100W(100Wは対応しているキャビのみで使いましょう。Laney IRT112は80Wまでなので、100W不可です)を切り替えると分かりますが、当然トーンが変わります。0.5Wに落とした小音量でも50wや100Wと変わらぬサウンドになる、って売り文句は〈それなりに〉であると認識しておきましょう。そしてマスターボリュームを可能な限り開いた状態と、マスターボリュームを絞った状態だと明らかに違いますもんね。
やはり100W+マスターボリュームを上げた方が「これやで、これ!」的な音になります。
んで、自宅で0.5Wの音作りをしたものをライブハウスなどへ持ち込んだ後、100Wへ切り替えると想定していたトーンとは違う可能性も出てきます。出力差による差異を理解し、現場で微調整するのがお薦めです。
とか言いつつ、今回の肝として紹介したいのは〈ボリュームノブ〉です。
これも試して欲しいのですが、基本的な音作りをした後にボリュームノブを絞ったり開けたりして見て下さい。トーンの変化が著しいはず。ここを含めて調整するのがお薦めです。
※クランチ。これくらいだとかなり歪みます。そしてボリュームを開けたことでパリッとした音に。
※クリーンではこんな感じ。ゲインを下げてボリュームを開ける。
そして……今回改めて思いましたが、繋ぐギターでトーンがめっさ変わる!
8弦ギターは言うに及ばず、6弦でもそれぞれの個性が出ます。もちろん電装系の違いが大きいのでしょうが、それでもビックリしました。同じDiMarzio TONEZONEが積まれたギターが2本ありますが、それぞれ出てくる音が違うんですもの。メタルリフ風のフレーズを弾いても、クリーンでリードを弾いても、クランチでパンク的に弾いても、明らかに「違うなぁ」って驚きます。
あと、CaparisonのDellingerとC2の違いも凄かったです。同じメーカーなのにここまで!? って。Dellingerは通常ラインのものでCaparisonらしさ多々あり。C2はエントリーモデルでHorusベースのギターですが、癖が抑えられた設計。それぞれの設計思想の違いが顕著に出たような気がします。
こういう点も面白いところですので、音作りの際は使用ギターで現物合わせするのがポイントです。その際、ギター本体の出音を活かしたパラメータにするか、それともギター本体に足りない部分を補うようなパラメータにするか。他諸々の選択肢はプレイヤー側に委ねられます。いろいろお試し下さい。
キャビネット。
KATANA-MK2、MK1ヘッドは内蔵スピーカーが装備されていますので、ちょっとしたコンボアンプのように使えます。が、せっかくなのでキャビを準備しましょう。そう。出音はキャビのキャラクターにかなり左右されるので、ここも用途によってチョイスすることが肝要です。
※Head単体でも音が出るのが素晴らしい。
ところで、MK2にはこんな機能がくっついてます。
※CAB RESONANCEスイッチ。
CAB RESONANCEです。
名前の通りキャビの響きを変えられます。というより、アンプヘッドからキャビに入るシグナルを変化させる感じの機能です。キャビ自体の音を変えるのではなくキャビへ入るシグナルに味付けする、と考えた方が良いかも知れません。
用意されたものはVintage/Modern/Deepの三つですが、これが効果大です。
これらを切り替えていくと、出音の重心が変わるように思いました。
Vintage/Modern/Deepの順に重心が低くなっていると言うのか。ハイゲインな音作りをしてザクザク刻む際は、ModernかDeepを選択するとよいでしょう。ズンズンさが増します。またカリッとしたクランチを狙うときはVintage、とか。
なんていいつつ、自由に使っても良いと思います。
クリーンでDeepにすると、太いクリーンに聞こえるような……。そしてBrownアンプでVintageだと、初期EVHサウンド風が狙いやすい、かも。逆にBrown+ModernはモダンEVHサウンドでしょうか。クランチ+Vintageにして、AC/DC! とか決めちゃうのも楽しいです。
この3つのCAB RESONANCE、使いこなすと更に音作りの幅が出ますね。
流石BOSS。
こうやってKATANA-MK2をいじっていると、流石BOSSだなぁと思います。
ギターを始めた人が最初に手に入れる機材として十分な機能を持っていると感じたからです。そう。BOSSのコンパクトエフェクターみたいですよね。プレイヤーが様々なトーンを試せる上、自宅練習からライブ本番まで使える機材です。オマケに価格もかなり抑えられている点も入門機として素晴らしい。セールやポイントを使うと更に入手のハードルが下がります。
え? 最初にフルチューブを買った方が、練習には最適ですって?
フルチューブの音は、まあ、ほら。ショップとかリハスタで試せば良いのですし、欲しくなったら視野に入れれば良いのですし-。個人的に言うと、最近増えた〈やや安価なフルチューブアンプ〉を先に手に入れ、そこからKATANAやギタープロセッサへ移行していくのがいいかなぁと思いますです。はい。
※ハンドルに燦然と輝くBOSSロゴ。
新型も含めて、BOSSのアンプを試してみると良いかも。
結構驚きますよ。いいじゃんいいじゃん! って。
わたくしの場合、内蔵エフェクターは使いません。ほぼ普通のアンプヘッドと同じ感じで扱っています。それでも良い感じのサウンドが出てくるのが凄い! 是非、体験してみて下さい。
と、ここまでKATANA単体での音作りを前提に書いてきましたが、もちろん外部エフェクター追加しても良いと思います。センドリターン端子がありますから空間系はそちらへ、歪み系はギターからインプット側への間に、とかとか。それ含めて柔軟性がある設計がされていると思います。
物は試しってことで、ショップへゴー!
あ。レビュー動画も参照頂けると幸いです。
佐々木秀尚氏のほうは日本語なので(!)、日本語を操る人にはこちらが分かり易いかもしんない。
レビュアーの腕もありますが、いい音だなぁー。