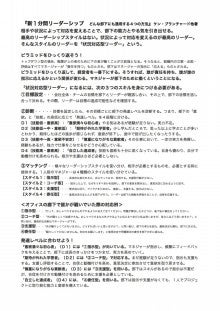相手や状況によって対応を変えることで、部下の能力とやる気を引き出せる。
最高のリーダーシップスタイルはない。
状況によって対応を変えるのが最高のリーダー。
そんなスタイルのリーダーを「状況対応型リーダー」という。
ピラミッドをひっくり返そう!
トップダウン型の場合、階層が上の者のために下の者が働くことが大前提となる。
そうなると、組織内の立案・企画・ 評価はすべてマネージャーが「責任を持つ」ものとされ、部下はマネージャーの指示に「応える」ものとされる。
ピラミッドをひっくり返して、経営者を一番下にする。
そうすれば、誰が責任を持ち、誰が誰の 指示に応えるかという関係が変わる。
マネジャーが部下のために働くということになる。
「状況対応型リーダー」になるには、次の3つのスキルを身につける必要がある。
①目標設定・・・会社全体・チームの目標を部下とリーダーが確認し合い、その上で、部下の目標を話し 合って決める。その際、リーダーは目標の達成可能性などを確認する。
②診断・・・・・目標を設定したら、その目標ごとに部下の発達レベルを診断する。つまり、部下の「意 欲」と「技能」の高低に応じて「発達レベル」を4段階に分ける。
D1(技能低・意欲高):「意欲満々な初心者」やる気はあるが経験が足りない。実力不足。
D2(技能低~中・意欲低):「期待が外れた学習者」少し学んだところで、思った以上に学ぶことが多い とわかり、期待したほどの進歩が感じられず、意欲が低下し、途中で投げ出したくなったりする。
D3(技能中~高・意欲不安定):「慎重になりがちな貢献者」その仕事において、一定の実力を発揮し、 経験もあるが、独力で仕事をこなせるかどうか心配している。
D4(技能高・意欲高):「自立した達成者」技能も意欲も十分に高くなっている。自身も備わり、自分で 動機付けを高められる。指示や支援はさほど必要としない。
③マッチング・・様々なリーダーシップスタイルを使い分け、相手が必要とするものを、必要とする時に 提供する。1人前のマネジャーは4種類のスタイルを使い分けている。
【スタイル1:指示型】・・・具体的な指示を与え、自らやってみせ、説明する。支援型行動が少ない。
【スタイル2:コーチ型】・・指示した上で、なぜそうすべきかを説明し、部下の意見を聞き出し、意思決定に加わるように促す。
【スタイル3:支援型】・・・聞き役に回り、アイデアを引き出し、激励し、支援する。指示は少ない。
【スタイル4:委任型】・・・意思決定のほとんどを部下が行う。リーダーは部下の貢献を評価することで、成長を応援する。
<オフィスの廊下で誰かが騒いでいた際の対応例>
1指示型・・・「行って、おしゃべりするなら外でやるように伝えてきてください。問題が解決したかどうか、後で私に報告をしてください」
2コーチ型・・「外が騒々しくて迷惑ですね。おしゃべりするなら外でやるように伝えるべきだと私は思いますが、皆さんはどう思いますか?」と 問い掛け、最終的な決断はマネージャーが下す。
3支援型・・・「外が騒々しくてかないません。どうすればいいと思いますか?」と問い掛け、部下の考えを訪ね、最終決定も概ね、部下に任せる。
4委任型・・・「騒々しくてかないませんね。対応をお願いします」と意思決定や問題解決の責任を部下の手に委ねる。
発達レベルに合わせよう!
「意欲満々な初心者」(D1)には「1指示型」が向いている。マネジャーが指示し、頻繁にフィードバックを与えることで、部下に成長のきっかけをつかませ、実力を高めていく。
「期待が外れた学習者」(D2)には「2コーチ型」で対応する。まだ経験が足りないので、指示も支援も する。支援し評価することで、自信と動機付けを高め、意思決定に参加させて意欲を取り戻させる。
「慎重になりがちな貢献者」(D3)には「3支援型」を用いる。部下はスキルがあるので指示は不要だ が、自信を付けさせ動機付けを高めるために支援を必要としている。
「自立した達成者」(D4)には、「4委任型」を用いる。部下は指示や支援がなくても、1人でプロジェ クトに取り組む能力と意欲を備えている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
必ずしも、この4分類が最適、というわけではないと思いますが、
「最高のリーダーシップは、1通りではない」という考えは、
複雑化した現代社会で舵をとるリーダーに取って、必要な考え方ではないかと思っています。
部下の様子をしっかりと把握すること。
一人一人に合わせた対応を取ること。
そのための、基本となる考え方かなと思っています。