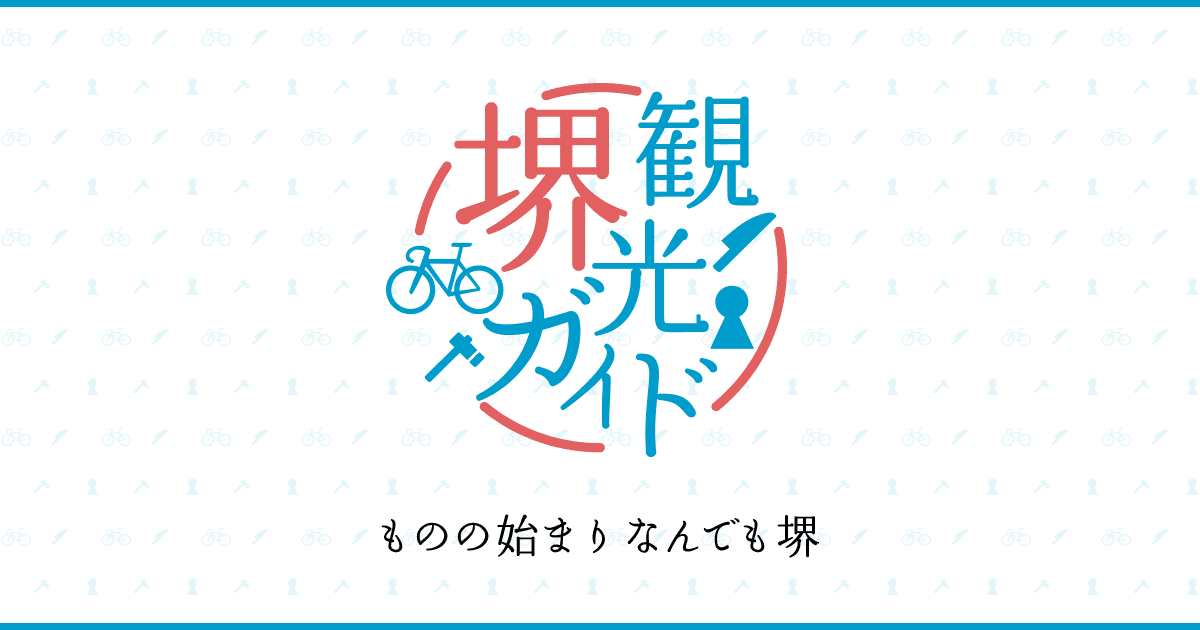メタセコイア並木の菰池から歩いて10分かかるか、かからないか?くらいでしょうか?
最後はのんびりと住宅街の中を歩いてやって来ました。
行基が奈良時代の初め727年に建立した土製の仏塔 こちらが、今回の話題、堺市のピラミッドとも言われる? 土塔(どとう)です。
現地にも土塔の説明がありました。
そして、行基(ぎょうき)です。
668年に、現在の堺市西区家原寺町に生まれ、749年までの時代を生きたと言われている、飛鳥時代から奈良時代にかけて活動した仏教僧です。
我らが金剛山や、大峰山など多くの修験道の霊場を開祖したと言われる役小角(役行者)
実在したかどうかについても含めて、諸説はありますが634年から701年頃の時代と言われています。
そして、四国で生まれ育った私にとっては、とても身近な存在でもある空海(弘法大師)が774~835年ころの時代を生きたと言われております。
宗教的なものにはあまり興味はない私ですが、空海が何で身近な存在か?と問われると、通学路にも八十八ヶ所参りのお寺があり、お遍路さんも日常的に見かけるので、それは当然ですよね。😊
時代的には少しかぶっているところもありますが、ちょうど役行者の少し後に生まれたのが、行基なんですね。
さらに、行基の後に生まれたのが、弘法大師と言うことになります。
そんな時代に生きたのが行基です。
行基は、この辺りの人なら誰でも知っている鶴田池、久米田池、そして、有名なあの狭山池(は、改修工事だけですが)などの灌漑用のため池など土木技術を活かしての困窮者の救済などに加え、東大寺のいわゆる奈良の大仏さん造立の実質上の責任者でもあったんですね。
そんな行基がやはり土木技術を駆使して建立したのがこちらの十三重の土塔だったと言う訳なんですよね。😊
土塔の前は公園になっていて、ちょっとした広場もあります。
サッカーをしていたのでしょうか?
ボールがポツンと所在なげに放置?されています。
そして、その向こうに、なんと最近ではあまり見ない光景と言っても良いでしょうね はないちもんめが賑やかに行われています。
向かい合わせの二列になって、勝っ~て嬉しい~はないちもんめ~🎵と歌いながら、前へ、後ろへと昔のままでやっています。
良く見ていると、一人 大人の女性の方が指導している様で、色々指示を出していました。
歌詞を掘り下げて行くと、なかなか難しい問題を含んでいると言う話もあるみたいですけどね。
私はこの光景を、ただただ懐かしく眺めておりました。
子供の自転車が何だか絵になりますね。😊
折角なので、土塔の周りを一周してみましょう~♪😄
正面から右の角に来たとところです。
説明のプレートがあちこちにありますね。
先ほどの正面から右の角を真っ直ぐ見たところです。
端正で美しい~なかなか良い感じですね~♪
上から見て左回り、半時計回りに見て回りましょう。
右角のさらに奥の角です。
これは発掘調査の遺構発見(検出)時の状況を再現しているんですね。
先ほどの正面右の角から見た、正面と、右の二面だけが復元された土塔で、こちらは、復元前の状態を再現しているものだと言うことの様です。
1952年に大阪府教育委員会により史跡の仮指定と緊急調査が行われ、その後、土塔とその周辺の土地が府によって買い上げられ、さらに1953年に国の史跡に指定されましたが、それまでは、私有地であったため、土も取られ、4分の1くらいは破壊されていたそうです。
ちょっと引いて見たところです。
縦位置です。😄
正面から見て、反対側、いわゆる後方から見たところです。

こちらの屋根のあるところでは、土塔に積まれた土の中が見られる様になっていました。
微妙に層になっているみたいです。
再現された土塔のミニチュアモデルですね。
そして、このような土塔を作るには大量の土砂が必要となりますが、先ほどメタセコイアを見た菰池など灌漑用のため池を掘ると大量の土砂が掘り出されるため、その土砂を使ったと思われます。
つまりは、土塔の建立と、ため池の造成は、表裏一体の関係だったと思われますね。
この辺りのことは、Wikiで土塔と引けば出て来ますので、気になる方は、そちらを参照してみて下さい。
そして、ぐるっと回って来て、この先がスタートした正面となります。
何だか怪しげな雲⛈️が湧いていますが気にしない様にしましょう。😅
そして、こちらの土塔のすぐ近くには、大野寺さんがあります。
大野寺は室町時代に焼失して、そのまま途絶えていたそうですが、江戸時代に再興され、現在は、当初から見るとかなり縮小されているそうです。
創建時は規模の大きな大寺院だったとみられており、当時の寺院が創建された時に先ほどの十三重の土塔も起工されたと室町時代に編纂された行基年譜に記されているそうです。
そんな大野寺は門が閉ざされており、中を伺うことは叶いませんでした。
大野寺の屋根の上が少し見えました。
屋根の上には、瓦職人も苦労して焼いたのではないかと、素人が見ても思える様なものが乗っていました。
詳しくは分かりませんが、良く見る五重塔の上に乗っているアンテナみたいなのを相輪(そうりん)と言うそうです。
そして、お寺の屋根の上のこの飾りの様なものは、宝珠、もしくは、如意宝珠(にょいほうじゅ)と呼び、丸い飾りの玉の中は、お釈迦様の骨を入れる容器なんだそうです。
また、如意宝珠は、『思いのままに、色々な願いを叶える宝の玉』と言う意味でもあるそうです。
何だか拝みたくなりますね。
大野寺を後にして歩きます。
とても見たことも無いような独特な感じに剪定してあり、見れば見るほどその不思議な魅力に引き込まれてしまいそうな木がありました。
そして、その横に土塔神社がありました。
ちょっと特徴的な感じの狛犬がしっかりと守っておりました。
さらにもう少し歩くと、懐かしい どとう ぜにやさんです。
堺市でも人気のうどんやさん 食べログでも高得点で、百名店でもあります。
随分と以前、お店が流行始めたころに食べに来ましたが、とんでもなく量が多くて、それ以来おじゃまはしてしておりませんでした。
麺の量ですが、今は、普通が500g 小が350g 極小が200gの様です。
たぶん、当時、とりちく玉天ぶっかけと言うのを頂いたと思いますが、鶏天、竹輪天に玉子天が乗って、麺がとてつもなく量が多いのに加えて、上に乗っている天ぷらたちも凄いボリュームで、かなり、いや、もう、相当苦戦して食べきりました。
たぶん、今だともう食べ切ることが出来ないと思います。
お店の方は、残さないで食べて下さいって言うし、ホンマにもう極小くらいでもダメかもです。
しかし、麺はもっちりとして、太めでコシも食感も良く、鶏天はもちろんとして、どれもとても美味しかったと記憶しています。😋
食べようと思って来た訳ではありませんが、この日の営業はもう終わっていました。
クリスマスの後、ちょっとお休みにして、年末近くは、割と営業予定ですね。
麺の売り切れも早いので、開店時間くらいに来ないと、確実には食べられ無いかも知れませんね。
色々写り込むので、こんな感じですが、お店の横に駐車場が7台分ありました。
必ずバック駐車でとのことです。
最後は食べもしないのにうどん屋さんって?謎の終わり方ですみませんが😆土塔町には行基の足跡がしっかりと残っておりましたね。
土塔町界隈散策はこれにてお仕舞いです。
お付き合い頂きましてありがとうございました。😊