社会人インタビュー、伊藤玲阿奈さんの続きです。
伊藤 玲阿奈(指揮者)
www.nyriccs.com

福岡県出身。祖父と母親が指揮者でユースオーケストラ(筑豊青少年交響楽団)を運営する家に生まれ、4歳よりピアノとヴァイオリンや音楽の基礎教育を受ける。8歳でオーケストラ曲を作曲。高校卒業後、政治学の勉強のため渡米。ジョージ=ワシントン大学国際情勢学部卒業後、指揮者の道に進むことを決意。ジュリアード音楽院で指揮と作曲を学んだ後、マネス音楽院とクイーンズカレッジ(アロン=コープランド音楽院)のオーケストラ指揮科(修士号)を卒業。大学院生卒業優等賞や賞金を授与される。
在学中から認められ、08年3月にはゴールドシュタイン劇場でのモーツァルトの「フィガロの結婚」のプロダクションにおいて、最終日に代役として急遽、リハーサル無しで指揮者を務め、鮮烈なオペラデビューを飾る。同年6月にはカーネギーホールにてデビューコンサートを行い、日本の「音楽の友」誌においても賞賛された。同年12月にはリンカーンセンターのブルーノ=ワルターホールでデビュー。現在は自身の組織するレオナ=イトウ室内交響楽団(Reona Ito Chamber Orchestra)を中心に活動している。
前回の記事はこちら。
今回は伊藤さんの留学生活や、指揮者になったきっかけを聞いていきます。
Q,伊藤さんが指揮者の道を選んだきっかけを教えて頂けますか
A,私は福岡県で生まれたのですが、昔は炭鉱が盛んな地域でした。そこで、私の祖父が炭鉱の坑夫を集めてレクレーションのためにオーケストラを作ったんですよ。
しかも昭和3年ごろに!戦後のエネルギー革命で炭鉱が閉山してから、子供のためのオーケストラに切り替えたんですが、私の母も老いた祖父の代わりに指揮するようになっていって、今は母のもとでオーケストラは続いています。
アマチュアオーケストラとしては多分日本で一番古い部類に入るんじゃないかな。
そういう家に生まれたので、4歳くらいの時からバイオリンとピアノはやっていました。けれど、両親は音楽で食べることが難しいと分かっていましたし、田舎のオーケストラの棟梁で終わるっていうのは自分の息子にはふさわしくないと思ったかは分からないけど、結局音楽家の道には進ませないと決めていました。
私自身も別に音楽家になるとは思っていなくて。
結局は今になって指揮者三代目を襲名したんですが(笑)。
Q,では、音楽の勉強はしなかったのですか?
A,独学でやってました。今考えると、小学校の時にオーケストラの曲とか書いてたんですよ。その頃は結構イイ線いっていたのかもしれないですね(笑)。
けれど専門的には訓練を大してしませんでした。高校の時なんか、音楽の授業さえない学校で(笑)。それで高校三年になって、進路をどうしようかと思っていると、アメリカ留学の話がきて、それでジョージ・ワシントン大学国際情勢学部に国際政治学をやるつもりで留学したんです。
Q,音楽ではなかったんですか?
A,違うんですよ(笑)。けれど、二年生くらいからピアノのレッスンを取り始めたら楽しくなっちゃって。しかも、ひょんなことからバンドをやり始めてですね、自分で作詞作曲して、レコーディングしたりライブやったりして。あ、その時は赤紫のメッシュを入れてたね(笑)。
でも、今みたいに自信があったわけではなくて、当時はすごい堅苦しい人間で。ある意味コンプレックスがいっぱいあったのかもしれない。けれど、自分でそうやって曲作ったり、バンドやったりするとみんな誉めてくれるんですね。それが嬉しくって休みの日も国際政治の勉強そっちのけで一日十何時間ピアノやっていました(笑)。
Q,十何時間ですか、、、それはすごいですね。何かとり憑かれたような。
A,今考えたら何かに導かれていたと思いますよ。あの時のピアノの経験があったからこそ今指揮者としてリハーサルをピアノでしっかり出来ていますから。
あの時は、何より嬉しかったんでしょうね。ああやって周りに誉めてもらって自分のアイデンティティ、これやってよかったな、人から求められてる、人に何か影響力を行使してるって思えたが単純に嬉しかったんですよ。
一般論で言うと、それが人との繋がりを発見することで、それが出来たらすごく幸せけど、すごく難しいことでしょうね。だから、みんな何をやるべきか悩むわけです。その点では私はすごくラッキーでした。政治を学びに来たけれど、やっぱり音楽をやったほうが人々との繋がりを持てるってことに気付けたから。それで大学では、政治と音楽の学位を両方取りました。
Q,それは順風満帆な留学生活を送りましたね。
A,そこまではね(笑)。その頃は天狗になっていて、「ピアノのプロになろう」と思ってジョージ・ワシントン大学を卒業してNYに出てきたんです。けれど、それからが苦難の道でした。
NYに来てすぐ、ジュリアード音楽院にピアノの試験を受けに行ったのですが、上手そうな人がいっぱいいるわけですよ。それで早くも自信失くしちゃって(笑)。で、事務室に行ってカタログでクラス確認したら、指揮と作曲のクラスがあった。
これだったら何とかなるんじゃないかなと思って、面接して、作曲も書き溜めてたし、指揮も色々知識があるってことで入れてもらった。そこで初めて指揮を習ったんですが、案外向いていることが分かったので、マネス音楽院というところへ指揮の学生として入って、大学レベルの理論などをやり直しました。ジョージ・ワシントンは総合大学でしたから、まだ未熟だったんです。
次に大学院の指揮科に入るのですが、これが難しくて定員が一人。受験の時、ある有名な大学の指揮科を受けて最後の三人まで残ったのですが、そこで教授からめちゃめちゃ批判されたんですよ。
それがすごいショックで、しかも受けたところ全部落ちてノイローゼになっちゃって。夢か現実か分からない状態で、学校まで一回の乗り換えで40分で行けるところを、4,5回間違えて一時間半くらいかかっちゃったり、気が付いたら駅のホームの端を歩いてたりとか(笑)。
けれど、失敗は成功の母ですね。それから、自分をゼロから見つめ直しました。そして、クイーンズカレッジ(アロン・コープランド音楽院)を受けに行ったんです。そこはジュリアードのようにレベルの高いところではないですが、その頃になると自分の性格も分かってきて、自分はあんまり競争してきてない人間だから、ゆるやかな学校でトップを目指すっていうのがいいなと確信したんですね。
そこからです、段々どん底から上がってきたのは。そこは自分で自由にオーケストラを作れてコンサートを開ける学校だったから、私にとっては奏者とのコミュニケーションも学べるし経験も積めるしで、非常に肌に合った学校で、そこで二年間みっちりやって、最後は代役でオペラまで振らして頂きました。
他の学校だったら絶対にありえないことです。しかも、それが縁でカーネギーホールデビューとリンカーンセンターデビューの話が舞い込んで来ましたからね。アメリカはこういう所がすごいです。
Q,その時になると、プレッシャーに負けて「もうだめだ」とはならずに自信を持って臨んでいたのですか?
A,いやいや、やっぱり辛かった(笑)。でも、どれだけのレベルでどれだけのことをやるかってことが大事で、あの時点で私が今やってるようなことは出来なかったと思います。
でも、今は自分のペースっていうのを掴んでいるのかな。今回の講演だって不安だったけど、それを段々繰り返すうちに徐々に耐性が出来て、自信もついてくるんじゃないかな。
いかがでしたか?
後編は伊藤さんの仕事観、仕事をする上でのジレンマ、目標等に迫っていきます。
後編は東海岸時間 3/4 18:00を予定しています。
文責:前田塁
伊藤 玲阿奈(指揮者)
www.nyriccs.com

福岡県出身。祖父と母親が指揮者でユースオーケストラ(筑豊青少年交響楽団)を運営する家に生まれ、4歳よりピアノとヴァイオリンや音楽の基礎教育を受ける。8歳でオーケストラ曲を作曲。高校卒業後、政治学の勉強のため渡米。ジョージ=ワシントン大学国際情勢学部卒業後、指揮者の道に進むことを決意。ジュリアード音楽院で指揮と作曲を学んだ後、マネス音楽院とクイーンズカレッジ(アロン=コープランド音楽院)のオーケストラ指揮科(修士号)を卒業。大学院生卒業優等賞や賞金を授与される。
在学中から認められ、08年3月にはゴールドシュタイン劇場でのモーツァルトの「フィガロの結婚」のプロダクションにおいて、最終日に代役として急遽、リハーサル無しで指揮者を務め、鮮烈なオペラデビューを飾る。同年6月にはカーネギーホールにてデビューコンサートを行い、日本の「音楽の友」誌においても賞賛された。同年12月にはリンカーンセンターのブルーノ=ワルターホールでデビュー。現在は自身の組織するレオナ=イトウ室内交響楽団(Reona Ito Chamber Orchestra)を中心に活動している。
前回の記事はこちら。
今回は伊藤さんの留学生活や、指揮者になったきっかけを聞いていきます。
Q,伊藤さんが指揮者の道を選んだきっかけを教えて頂けますか
A,私は福岡県で生まれたのですが、昔は炭鉱が盛んな地域でした。そこで、私の祖父が炭鉱の坑夫を集めてレクレーションのためにオーケストラを作ったんですよ。
しかも昭和3年ごろに!戦後のエネルギー革命で炭鉱が閉山してから、子供のためのオーケストラに切り替えたんですが、私の母も老いた祖父の代わりに指揮するようになっていって、今は母のもとでオーケストラは続いています。
アマチュアオーケストラとしては多分日本で一番古い部類に入るんじゃないかな。
そういう家に生まれたので、4歳くらいの時からバイオリンとピアノはやっていました。けれど、両親は音楽で食べることが難しいと分かっていましたし、田舎のオーケストラの棟梁で終わるっていうのは自分の息子にはふさわしくないと思ったかは分からないけど、結局音楽家の道には進ませないと決めていました。
私自身も別に音楽家になるとは思っていなくて。
結局は今になって指揮者三代目を襲名したんですが(笑)。
Q,では、音楽の勉強はしなかったのですか?
A,独学でやってました。今考えると、小学校の時にオーケストラの曲とか書いてたんですよ。その頃は結構イイ線いっていたのかもしれないですね(笑)。
けれど専門的には訓練を大してしませんでした。高校の時なんか、音楽の授業さえない学校で(笑)。それで高校三年になって、進路をどうしようかと思っていると、アメリカ留学の話がきて、それでジョージ・ワシントン大学国際情勢学部に国際政治学をやるつもりで留学したんです。
Q,音楽ではなかったんですか?
A,違うんですよ(笑)。けれど、二年生くらいからピアノのレッスンを取り始めたら楽しくなっちゃって。しかも、ひょんなことからバンドをやり始めてですね、自分で作詞作曲して、レコーディングしたりライブやったりして。あ、その時は赤紫のメッシュを入れてたね(笑)。
でも、今みたいに自信があったわけではなくて、当時はすごい堅苦しい人間で。ある意味コンプレックスがいっぱいあったのかもしれない。けれど、自分でそうやって曲作ったり、バンドやったりするとみんな誉めてくれるんですね。それが嬉しくって休みの日も国際政治の勉強そっちのけで一日十何時間ピアノやっていました(笑)。
Q,十何時間ですか、、、それはすごいですね。何かとり憑かれたような。
A,今考えたら何かに導かれていたと思いますよ。あの時のピアノの経験があったからこそ今指揮者としてリハーサルをピアノでしっかり出来ていますから。
あの時は、何より嬉しかったんでしょうね。ああやって周りに誉めてもらって自分のアイデンティティ、これやってよかったな、人から求められてる、人に何か影響力を行使してるって思えたが単純に嬉しかったんですよ。
一般論で言うと、それが人との繋がりを発見することで、それが出来たらすごく幸せけど、すごく難しいことでしょうね。だから、みんな何をやるべきか悩むわけです。その点では私はすごくラッキーでした。政治を学びに来たけれど、やっぱり音楽をやったほうが人々との繋がりを持てるってことに気付けたから。それで大学では、政治と音楽の学位を両方取りました。
Q,それは順風満帆な留学生活を送りましたね。
A,そこまではね(笑)。その頃は天狗になっていて、「ピアノのプロになろう」と思ってジョージ・ワシントン大学を卒業してNYに出てきたんです。けれど、それからが苦難の道でした。
NYに来てすぐ、ジュリアード音楽院にピアノの試験を受けに行ったのですが、上手そうな人がいっぱいいるわけですよ。それで早くも自信失くしちゃって(笑)。で、事務室に行ってカタログでクラス確認したら、指揮と作曲のクラスがあった。
これだったら何とかなるんじゃないかなと思って、面接して、作曲も書き溜めてたし、指揮も色々知識があるってことで入れてもらった。そこで初めて指揮を習ったんですが、案外向いていることが分かったので、マネス音楽院というところへ指揮の学生として入って、大学レベルの理論などをやり直しました。ジョージ・ワシントンは総合大学でしたから、まだ未熟だったんです。
次に大学院の指揮科に入るのですが、これが難しくて定員が一人。受験の時、ある有名な大学の指揮科を受けて最後の三人まで残ったのですが、そこで教授からめちゃめちゃ批判されたんですよ。
それがすごいショックで、しかも受けたところ全部落ちてノイローゼになっちゃって。夢か現実か分からない状態で、学校まで一回の乗り換えで40分で行けるところを、4,5回間違えて一時間半くらいかかっちゃったり、気が付いたら駅のホームの端を歩いてたりとか(笑)。
けれど、失敗は成功の母ですね。それから、自分をゼロから見つめ直しました。そして、クイーンズカレッジ(アロン・コープランド音楽院)を受けに行ったんです。そこはジュリアードのようにレベルの高いところではないですが、その頃になると自分の性格も分かってきて、自分はあんまり競争してきてない人間だから、ゆるやかな学校でトップを目指すっていうのがいいなと確信したんですね。
そこからです、段々どん底から上がってきたのは。そこは自分で自由にオーケストラを作れてコンサートを開ける学校だったから、私にとっては奏者とのコミュニケーションも学べるし経験も積めるしで、非常に肌に合った学校で、そこで二年間みっちりやって、最後は代役でオペラまで振らして頂きました。
他の学校だったら絶対にありえないことです。しかも、それが縁でカーネギーホールデビューとリンカーンセンターデビューの話が舞い込んで来ましたからね。アメリカはこういう所がすごいです。
Q,その時になると、プレッシャーに負けて「もうだめだ」とはならずに自信を持って臨んでいたのですか?
A,いやいや、やっぱり辛かった(笑)。でも、どれだけのレベルでどれだけのことをやるかってことが大事で、あの時点で私が今やってるようなことは出来なかったと思います。
でも、今は自分のペースっていうのを掴んでいるのかな。今回の講演だって不安だったけど、それを段々繰り返すうちに徐々に耐性が出来て、自信もついてくるんじゃないかな。
いかがでしたか?
後編は伊藤さんの仕事観、仕事をする上でのジレンマ、目標等に迫っていきます。
後編は東海岸時間 3/4 18:00を予定しています。
文責:前田塁
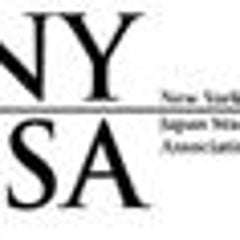

 NYJSAのウェブリンク
NYJSAのウェブリンク
