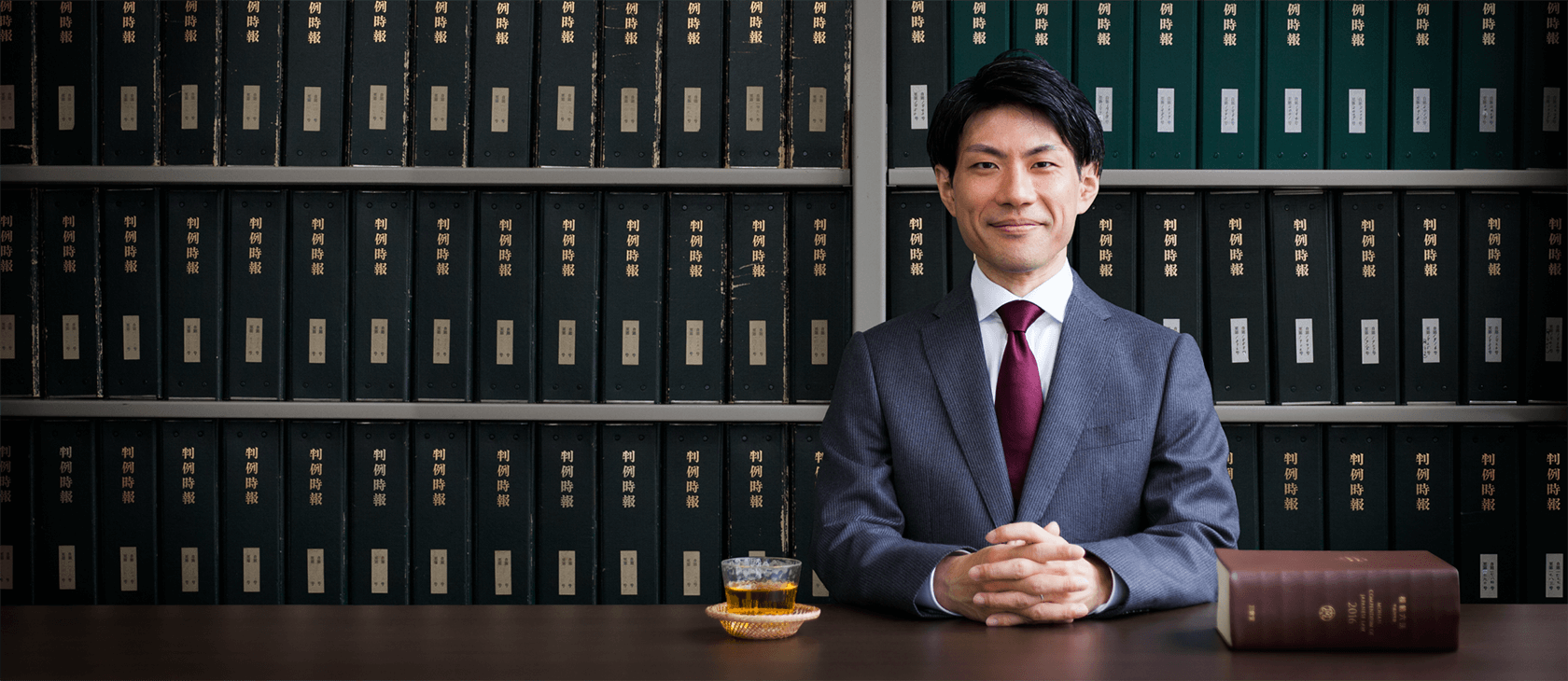10月22日の記事に追記、更に追記をしました。
たぶん今後も追記すると思うので
自分で見つけやすいように題名を変えてもう一度投稿します。
2022/11/03
******![]()
民法改正~重要概念の変更
(過失責任主義の廃止、瑕疵担保責任の廃止、解除の帰責性の撤廃、債権者主義の廃止ほか)
(弁護士法人あお空法律事務所様のサイトからの引用です![]() )
)
↓
記事より抜粋
重要概念の変化については、時効や保証制度等多岐にわたりますが、ここでは、理解が一見困難な、民法上の基礎的概念の変化、特に債務不履行責任をはじめとする帰責性概念を変化させることと、いわゆる
特定物ドグマの放棄に伴い、
瑕疵担保責任その他の担保責任概念の廃止、
解除の帰責性の撤廃、
債権者主義の廃止をはじめとして、法定責任説の排斥、善管注意義務、受領遅滞概念、履行補助者の故意過失や契約締結上の過失の概念の変更、信頼利益とされていた損害理論の修正、その他、
様々な民法上の概念が修正、変更、廃止されることが見込まれます。
![]()
民法改正において、考えられている様々な民法の基礎的概念の変更に影響を与えているものとして、帰責性概念の変更を挙げることが出来ます。
帰責性とは、従前、債務不履行に基づく損害賠償や、契約の解除をするための要件として要求されていたものです。これに対し、民法改正の検討において、帰責性そのものの概念を廃止することも考えられたようですが、実際は廃止されなかったものの、その概念が修正されることとなりました。
現行民法(改正前民法)において、帰責性とは、故意過失と考えられてきました。
これは、現行民法が作られた明治時代、フランス法が元になったのですが、戦後、民法典を再検討する際に、ドイツ民法の考え方が取り入れられ、我妻博士(我妻榮博士)らが中心にいわゆる現在の通説といわれる概念が基礎づけられました。
その中で、帰責性についても、故意過失であると考えられました。損害賠償を請求したり、契約を解除するためには、債務者の違法行為について故意過失が必要であるという、いわゆる過失責任主義がとられました。
ここで注意いただきたいのが、民法典においては、現行民法(改正前民法)においても、債務不履行に基づく損害賠償は、次の通り定められ、どこにも故意過失とは記載されていないのです。
帰責性を要求しているのみで、これは民法が明治時代に制定された当時のフランス民法典の流れを示すのですが、この帰責性についての解釈という形で、故意過失であるとされ、ドイツ法の概念である過失責任主義がとられたのです。
*****
(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
*****
何故、このような明文と解釈との間に乖離が生じたのかといいますと、そもそも、現行民法(改正前民法)を制定する際の方針を定めた「法典調査ノ方針」(明治26年)の11条に
「法典の条文は原則変則及び疑義を生ずべき事項に関する規制を掲ぐるに止め、細密の規定に渉らず」
とされ、民法において細かな規定をつくることをしない方針とされたことに起因します。民法典として詳細なものを定めて、その後、様々な改正を要するようにするのではなく、概括的なものを定めて、それ以外は、解釈・判例で補っていくという方針となったのです。
現行民法の法文上は、フランス民法とドイツ民法の両方が取り入れられているのですが、解釈としては、現行民法施行当時、主流であったドイツ民法の考え方が流入されました。特にこのドイツ民法をもとに精緻な解釈論を展開していったのが、鳩山秀夫東大教授でした。鳩山由紀夫元首相の祖父鳩山一郎元首相の弟になります。
ただ、この鳩山理論の体系が、同僚の末弘厳太郎東大教授から、「横書きのドイツの理論を縦書きの日本語にしているだけだ」と痛烈に批判され、結局、その後、学者をやめてしまいます。当時、鳩山氏の書生をしていた我妻栄氏がそのあとを引き継ぎ、我妻理論を完成させました。
民法を学ぶとき、例えば司法試験においても、実務家登用試験である以上、判例通説に基づき論ずることが多いのですが、民法における判例通説とは、この我妻理論に、ほかならないのです。
そこで、日本の民法は、民法の条文を見ただけではわからず、これとは別に判例学説といういわゆる我妻理論を習得しないとわからない構造となっています。
タテマエとホンネを分ける日本文化とも親和性がある話でもあり、この状況は、現在まで受け入れられているのです。
帰責性の話も、この流れをうけており、条文上は、どこにも故意過失などとは記載されていないのですが、過失責任主義をとるドイツ法学の考えに沿った、我妻理論に基づき、
帰責性=故意過失
という解釈となっているのです。
【改正民法における帰責性の変化について】
以上のとおり、帰責性の話も、条文の明文と異なり、解釈においては、ドイツ法学の考え及び我妻理論に基づき、帰責性=故意過失ということになっているのです。
この現行民法(改正前民法=我妻民法)に対し、改正民法は次のとおりとなります。
*****
(債務不履行による損害賠償とその免責事由(民法第415条関係))
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
*****
債務不履行に基づく損害賠償請求について、帰責性を要求していることは変わりませんが、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念」に照らし帰責性があるかどうか検討されることが変わります。
これは、現行民法上(改正前民法)の、
帰責性の要件として故意過失を要求するという、
過失責任主義を撤廃し、
契約等の発生原因と取引上の社会通念に基づき検討するという考えに変更する
趣旨となります。
従前、ドイツ法学及び我妻理論にしたがい、帰責性=故意過失という過失責任主義を、条文と乖離させて解釈として導入してきたのを、帰責性のところに、「契約その他の~」という文言を付け加えることで、過失責任主義をとらないことを明文化したという趣旨なのです。
この帰責性の修正、もっと言えば、その根底にある
我妻理論からの脱却
ということが、今回の改正において色濃く出ているということがいえるのです。
このことは、単に学説上、理論上の話といわれることが多いのですが、現行民法の基礎的な体系を大きく変える以上、民法の考え方、具体的事件についてどのように処理されるかも含め、大きく影響するのではないかと考えています。
注:この民法制定時の経緯については、いろいろな文献が出ているのですが、なかでも元東大教授で法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与として民法改正に中心的に関わられていらっしゃる内田貴氏の民法改正~契約のルールが百年ぶりに変わる(ちくま新書)が非常に読みやすく、わかりやすいのでご一読をお勧めします。
以上、抜粋しました。
↑
こちらの記載によると「これに対し、契約不適合責任では、売主に過失がある場合にのみ売主は損害賠償責任を負うとされました。」となっている。
↑
こちらの記載にも瑕疵担保責任に代わる契約不適合責任については「改正民法下の契約不適合責任では、売主に故意または過失がない場合に売主は責任を負わない結果となります。」と書かれている。
↓
しかし??
もし契約不適合責任が、債務不履行の一般規定を採用して考えるものとするなら、そして新しい債務不履行責任が「債務者の帰責事由(「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念」に照らし帰責性があるかどうかを判断する)を必要とするもの」だとするなら
仮に債務者が無過失の場合(無過失と評価されるべき場合)でも責任が発生する、可能性があると考えることになるのではないですかね??
条文上はその点が明らかになっていません。
そこで
いろいろ検索していたら以下の文章が見つかりました。
債務不履行における過失責任の原則について - Kyushu-u
https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/19931/p168.pdf
つまり、結論はこれからの現場の解釈に委ねられる余地があるようです。判例は債務不履行においても過失責任の原則を貫いておらず(それのみで責任を検討しているわけではなく)広い視点から帰責事由を判断していて興味深い内容でした。
この論点、今後も要注意。択一問題だとどうなっているのか、引き続き確認していきます。
他人物売買について、悪意の買主が損害賠償請求ができるかできないか、という点についても改正民法の概念からは「できる」と解釈すべきだ・・と思っていたら、そのように考えている弁護士さんの記事を見つけたので貼っておきます。
******
2022/11/03更に追記
債務不履行による損害賠償(帰責事由・過失責任主義について)
↓
【第193回国会(参)法務委員会第10号平成29年5月9日】
↓
当日の法務委員会資料
民法(債権関係)の改正に関する検討事項(1) 詳細版(部会資料5-2)
https://www.moj.go.jp/content/000059836.pdf
↓
弁護士さんのコラムから記事を転記
↓
1.古川俊治 委員 の質疑(要旨その2)
Q 契約重視という考え方がすごく前に出たと思う。特にそれが出ているのが四百十五条の一項ただし書であるが、
(第415条Ⅰ債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。)
今までは、その債務不履行の規定で、債務者の責めに帰すことができない事由、この言葉は変わっていないが、今度は、契約その他債務の発生原因の趣旨に照らして判断されるという言葉が入った。ということは帰責事由が、契約その他債務の発生原因を離れた客観的な過失の有無というものではないということがはっきりしたわけであり、そうすると、今まで帰責事由は、債務者の故意、過失又は信義則上それと同視すべき事由という伝統的な考え方があったが、それはもはや解釈論としてはこの法律の中ではない。要するにこれは、過失責任主義というのを取らなくなっただ(原文ママ)ということは、この参議院の調査室が作ってくれた京大の山本先生(山本敬三)の論文でももう明確に書いてあるし、あるいは内田先生(内田貴)の本にも書いてある。小川局長は、衆議院の方の法務委員会の審議で、無過失責任主義に変わることはないと言っている、変わるということではないと言っている。過失責任主義を放棄したのかということについては、学理的な議論には踏み込まないとして答弁を避けているが、帰責事由の通説的な考え方、すなわち債務者の故意、過失又は信義則上それと同視すべき事由と同じかどうかという、これは非常に重要な観点だと思う。この観点からもう一回お答えいただきたい。
A(小川政府参考人)
改正法案に対しては、債務不履行による損害賠償責任に関して過失責任主義を否定し、債務不履行による損害賠償の基本的な枠組みを大きく変えるものであるといった指摘は確かにある。まず、過失責任主義とは何かということであるが、過失責任主義とは、一般にある行為について故意又は過失がなければ損害賠償責任を負わないという考え方をいう。 現行法において、この過失責任主義は、不法行為責任に関する七百九条において明示的に採用されている。他方、債務不履行による損害賠償責任についても、伝統的な通説によれば、四百十五条後段で債務者の帰責事由が必要とされているのは過失責任主義の表れであると説明されている。もっとも、そもそも帰責事由を過失責任主義と関連するものと理解するか、また、過失責任主義を前提とするとしても、その具体的内容をどのように理解するか、不法行為と全く同様のものと理解するのかなどについては、これは学説は多岐に分かれており、必ずしも明瞭ではない。もちろん、指摘のあった論文の山本教授のように、契約を非常に重視する立場であるとか、様々の立場がある。そこで、改正法案においては、このような言わば学説的な争いといった学理的な議論には踏み込まないで、債務者の帰責事由という現行法の文言をそのまま維持している。そこは従来と全く変わらない、帰責事由というところ自体は。
そして、帰責事由の有無の判断に当たって考慮すべき事情を明確化するために、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」との文言を加えることとしている。これは、現在の裁判実務等においては、帰責事由の有無は、個々の取引関係に即し、契約の性質や目的などの契約その他の債務の発生原因に関する諸事情を考慮し、それから併せて社会通念をも勘案して判断されているということから、このような実務上の取扱いを明確化するものである。以上申し上げたとおり、改正法案は債務不履行による損害賠償責任について学理的な争いに立ち入らないこととし、従来の通説的見解からは過失責任主義の表れとされている債務者の帰責事由という要件をそのまま維持しているほか、現在の実務上の取扱いに従って帰責事由の有無を判断する際の考慮事情を明確化するものである。したがって、(komomo注>官僚の答弁として言うなら)改正法案は従来の通説的な考え方やこれに基づく実務運用などを否定するものではないと考えている。
(komomo>小川さんって、小川秀樹氏(おがわ・ひでき)83年(昭58年)東大法卒、85年判事補。12年法務省司法法制部長。大分県出身、58歳。でいいのかな?日経記事2015年9月25日 11:36 )
(komomo>そして古川さんは、自民党所属の政治家、医師、弁護士ですね。)
(続き)
Q(古川さん)今まで過失責任主義かどうかはいろんな議論があったという話であるが、例えば、僕、医療過誤を示したが、あれって不法行為か債務不履行かって全く示さずに判断している。それは御存じだと思う。要するに過失の判断というのは同一だからどっちでも示さないでできている、判断が。それがここで変わったら実務に大きく影響するのではないか。医療過誤の話ですると、これから契約の趣旨を重視するという話になって、これから帰責事由は契約の趣旨あるいはその他の債務の発生原因に照らして判断することになった。一番ありがちなのがインフォームド・コンセントの話である。要は、インフォームド・コンセントの内容というのは、こういう事情があってあなた死ぬかもしれません、これ受けてもらう。今までは、客観的な過失があるかどうかというところでまずは立証していくというのが普通だった。それで、どんなインフォームド・コンセントがあってもそれは請求原因が違っていて、客観主義の方で取るという、過失があればそれはそれで十分医療過誤だったが、これから先は、例えばインフォームド・コンセントで、あなたのこういう場合にはこういうふうにやるということで、要は、すごくその債務の共通の事項として合意内容がどうであったかということを立証していくか、それとも客観的な医療行為のそごというのを追及していくか、これは弁護士としても全然やり方が変わってくるので、この点について実務の影響というのはどうお考えか。
A(小川さん)現行法においても、契約において当事者がどのような義務を負うのか、あるいは帰責事由の判断がどのようにされるのかといった問題については、基本的には当事者の合意と、それから考慮要素として書いてある取引上の社会通念に基づいて定まるのが原則であると考えている。診療契約もその点では基本的には同じであると考えられるが、他方で、診療契約は従来の学説などでも例えば手段債務といった形で非常に特別な取扱いを受ける考え方が強いわけであるが、診療契約は人の生命、身体に関わるものであり、本来は違法行為ともなり得る侵襲行為を内容とするもので、専門家の地位にある医師が主体となるものであることから、売買、消費貸借などのごく一般的な取引とは異なる性質を有するものと考えられる。そして、このような特質を有する診療契約については一般に一定の水準以上の医療行為をすべき注意義務を負うものと考えられ、これを当事者の合意によって引き下げることは当事者の合理的な意思に合致しないものと認められることが通常であり、仮にそのような合意があったと認定するほかないとしても、例えば公序良俗などの観点からもそのような合意の効力は直ちには認めにくいものと考えられる、そういう特殊性があるというのが診療契約の特質ではないかと考えている。このような意味で、御指摘の診療契約はその他のより一般的な契約類型とは異なり、当事者の合意内容に従って義務違反や帰責事由の有無を判断するわけにはいかず、むしろ取引通念に基づく判断が実際上優先されるべき性質を有しているものと考えられる。なお、改正法案においても、帰責事由の判断に当たっては、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らすこととしているので、診療契約についても先ほど述べた整理することと条文の文言との間には基本的には矛盾、抵触は存在せず、診療契約に関する判断枠組みが今回の改正法案の下で変更されるといったことはないものと認識している。
![]() ・・・
・・・![]() (この答弁を知らない人はたいへんですね。しかし・・条文改正の意味・・)
(この答弁を知らない人はたいへんですね。しかし・・条文改正の意味・・)
↓記事より抜粋
ここでは、民法を学習される方々を念頭において、
債務不履行による損害賠償責任における「帰責事由」について説明いたします。
伝統的学説について
伝統的学説は,ドイツ法の影響(学説継受)を受けて,債務不履行による損害賠償責任の責任根拠を過失責任主義に求めてきた。
(1) 我妻榮(1897~1973)
「民法の条文を形式的に解釈するときは,履行遅滞には故意過失を必要とせず,ただ不可抗力によって遅延した場合にだけ責任を免かれると解すべきが如くである。判例は,最初はそう解した。然し,その後,過失を推定すべきものとし,責に帰すべき事由に基づかないことを挙証すれば責任を免れうるとするようになった。至当な態度であって,現在の通説はこれを支持する。」(『新訂債権総論(民法講義Ⅳ)』(1964)105頁),「然らば,「責ニ帰スベキ事由」とはいかなる意味か。
債務者の故意・過失または信義則上これと同視すべき事由 と解して良いと思う。
同視すべき事由を含む点で,厳格な過失主義が緩和されている。その意味で,責に帰すべき事由は故意過失より広い概念といってよい。」(同)
(2) 於保不二雄(1908~1996)
「民法は,履行不能については「債務者ノ責スヘキ事由」によることを要件としながら,債務不履行一般についてはその主観的要件に言及していない。もっとも,金銭債務に関する特則(民法419条2項)からすれば,金銭債務以外の遅滞においては不可抗力をもって抗弁となしうることだけは明白である。そこで,履行遅滞については,不可抗力に基づかない以上,債務者の故意過失その他責に帰すべき事由がなくともなお責任をおうべきかにつき解釈上疑義を生ずる余地がある。しかしながら,わが民法は過失責任の原則の上に立っていること,並びに,履行遅滞と履行不能とを特に区別すべき実質上の根拠がないこと,を理由として,学説・判例ともに,諸外国立法におけると同様,履行遅滞についても債務者の責に帰すべき事由に基づくことを要件として認めている。したがって,また,民法419条2項にいわゆる「不可抗力」は,その厳格な意味においてではなく,「債務者の責に帰すべからざる事由」と同義に解されている。」(『債権総論(新版)』(1972)93頁)
新しい見解
債務不履行制度や帰責事由の理解として,最近の有力説は,過失責任主義から脱却する方向性を主張する。
本来,過失責任主義は,「行動の自由」(注意して行動する限り不測の責任を負わされないことにより,予測可能性を確保する。)を保障するためにある が,そもそも債務者というものは,契約によって拘束されており,その債務の履行を義務づけられている。そこには,「行動の自由」を問題にすべき基盤がなく,その契約上の義務を守らないこと自体が責任を負うべき根拠になると考える。そして,「責に帰することができない事由」(以下「帰責事由の不存在」と言い換えることがある。)は,「債務者に義務違反があるのに債務者にその責任を負わせるべきでないといえる事由」というような意味での例外的な「免責事由」として理解する。その場合,「免責事由」の内容とともに,免責の根拠(客観的には債務の不履行があるにもかかわらず免責が正当化されるのはなぜであるか。)が問われる。説明の仕方は,論者によって微妙に異なるが,だいたいにおいて,当該状況において当該リスクを債務者に負担させるべきか否かという問題(リスク負担の相当性の問題)として理解する。
(1) 平井宜雄(1937~2013)
平井は,民法の起草当時,責めに帰することができない事由とは「不可抗力」を意味するものとされていたとも考えられると指摘して通説を批判する。判例の実際の姿としては,通説に従っておらず,次のような準則が見出せるという(『債権総論(第2版)』77頁~81頁)。
ア 債務者に履行の意思自体が存しないと認めるべき明白な事情があるときは,常に帰責事由がある。
イ 引渡債務については,引渡しがない場合には特段の事情が内限り,常に帰責事由がある。
ウ 行為債務の場合には,行為債務を特定したうえで,現実になされた債務者の行為との間に食い違いがあれば,直ちに帰責事由がある。
エ そのほかに,債務不履行が債権者側の事情によって生じた場合,社会情勢(ストライキの発生など)によって生じた場合も同様である。
(2) 中田裕康(1951~)
「帰責事由は,事実としての不履行がある場合に,それによる損害を賠償する責任を債務者に帰せしめる要素であるが,債務者が債務を負う以上,それは原則として存在する。例外的に,免責事由・正当化事由がある場合にのみ,帰責事由がないことになる。」(『債権総論(第3版)』135頁),「事実としての不履行がある場合に,債務者の免責事由及び正当化事由を判断する。免責事由とは,①不可抗力,②債権者又は第三者の行為であって債務者に予見可能性及び結果回避可能性のないもの,をいう。免責事由は,債務の種類によって意義が異なる。...(中略)...金銭債務以外の財産権を与える債務においては,債務者は①②により免責されることがある。なす債務においては,①②により免責されることもあるが,多くの場合,もっぱら事実としての不履行の有無が問題となり,それがあると判断される場合には,改めて免責事由が問題となることはないだろう。(以下略)」(同)
(3) 潮見佳男(1959~)
「債務不履行の帰責事由を考えるにあたっては,過失責任の原則を採用しない。債務内容に照らして保証責任の原理に基礎付けられる場合(結果保証のある場合。結果債務)と,過失責任の原理に基礎付けられる場合(手段債務)とを認め,前者については不可抗力および債権者の圧倒的な帰責性をもって免責事由とし,後者については,債務不履行の事実の確定をもって債務者への帰責性が同時に確定される。」(『債権総論Ⅰ(第2版)』282頁)。
補足説明
以上の議論には,やや分かりにくい点があるので,補足して説明する。
(1) 証明責任の問題
まず,主張立証責任の問題としては,債務不履行の類型(履行不能,履行遅滞,不完全履行)を問わず,帰責事由の不存在が抗弁事由(債務者が責任を免れるために主張立証すべき事実)になること自体は争いがない。債権者が帰責事由を主張立証すべきという見解は存在しない。伝統的見解は,債務不履行の責任発生の要件として,本来,「債務者の故意・過失または信義則上これと同視すべき事由」(以下「故意過失等」という。)が必要であるが,不履行の事実によって債務者の過失が推定され,立証責任が転換されていると考えるようである。これに対し,新しい見解は,債務不履行制度は過失責任主義とは関係がなく,故意過失等がなくても債務不履行が成立すると考える。免責事由は,債務不履行(契約違反)が生じている場合において,なおかつ債務者の無責(いったん責任が発生して事後的に免除されるのではない。)を認めるべき不可抗力などの例外的事由である。「免責事由が存在する場合には不履行自体が生じない。」という異説もあるが、今は採らないことにしたい。
(2) 「結果債務」と「手段債務」
債務の分類法にはいくつかの観点がある。その一つとして,債務の種類を,「結果債務」と「手段債務」に大別する考え方がある。結果債務とは,「買主に物を引き渡す。」,「目的地まで物品を輸送して届ける。」というように債権者に対して一定の結果をもたらすべき債務であり,当事者の合意(ひいては債務の内容)は,もっぱら結果の実現に向けられている。金銭債務は,典型的な結果債務である。
一方,手段債務では,債務者は,達成すべき目標(債権者が希望する目標)に向けた手段をとり最善を尽くすことを約束するが,目標の達成は約束されておらず,契約上の義務になっていない。たとえば,患者と医師との間における診療契約において,医師は,合理的な注意を払い医学的水準を満たした方法によって医療行為を行なうことが義務付けられるが,「患者の病気を治す」という結果を保証しているわけではない。あるいは,弁護士の訴訟委任についても,有利な訴訟結果を目指して注意を払い適正に努力をする義務を負うが,「勝訴」という結果は約束されていない。学校法人は,在学中の児童・生徒の生命身体の安全性を配慮する義務(安全配慮義務)を負うが,生命身体の損害が生じないという結果を保証しているわけではない。
手段債務と結果債務が厳密に区分できるのかという指摘はあるが,債務不履行における「不履行」と「免責事由」の関係を理解し,思考を整理し,責任の有無を正しく判定する上で必要である。手段債務のこのような理解は,債務不履行責任の根拠としての過失責任主義を採るかどうかにかかわらず,裁判実務において支持され定着している。
結果債務と手段債務の違いが発生する理由を考えると,それは,契約当事者が何を意図したかという「意思」の問題とその契約がどのような利益実現を目指すものであるかという「性質」の問題に由来しているのであろう。
手段債務における債務不履行の判定では,抽象的な債務の観念から出発し,当該状況下における具体的な行為義務を導くという作業を行なう。たとえば,生徒間の加害行為について私立学校(学校法人)の損害賠償責任を問う訴訟事件では,「学校法人は,在学中の生徒の安全性を配慮する義務がある。」という抽象的な観念から,「教師は,生徒間の加害行為を知ったらこれを阻止すべく行動する義務を負う。」という具体的命題を導き,これを更に具体化すると,「A教諭は,〇月〇日〇時ころ,校庭で,生徒Bが生徒Cを足で蹴っているのを目撃したのであるから,その場で直ちに介入してその暴力を制止すべきであった。」という判断を導くことができる。
このように,常に具体的な状況との関係において,行為する義務(適切な行動を選択する義務)が設定される。そのため,当該場面において,債務者にとって問題状況についての認識が困難であり,又は問題解決のための対応に困難が発生している場合には,そのような困難も,行為義務を具体化する中で行為義務の判断の前提として織り込まれる。
その逆に,具体的な行為義務に反することが認められるならば,改めて責めに帰すべき事由があるかどうかを判断する必要がない。免責事由が機能しないというのでなく,「義務違反」と「帰責事由」が,事実上表裏一体となり,同じ判断構造になるから,重複して審査する意味がないと考えられている。
(3) 新しい学説の理解
以上をまとめると,新しい学説は,債務者が債務不履行によって損害賠償責任を負う根拠は,不履行について過失があったからではなく,債務者が契約で義務づけられたことを守らなかったからだと考える。
手段債務においても,一定の行為を採るべき義務に違反し,それが債務不履行に当たるから,損害賠償責任を負うと考える。義務違反がなければ,損害が発生しても,損害賠償責任が発生しない。たとえば「教師が合理的な注意を払っていたが生徒が負傷した。」という事案がこれに当たる。その場合の責任否定の理由は,免責事由に該当することにあるのではなく,義務違反がないことにある。
(4) 用語の問題について
415条の「責めに帰すべき事由」(帰責事由)という用語の語義は,本来,「責任を負うべき事由」という意味である。同様に,「責めに帰することができない事由」(改正法415条)という言葉の語義も,「責任を負わせることができない事由」という意味である。本来,言葉自体としてはトートロジー(同義反復)であり,何も言っていないに等しい。そうであるから,「帰責事由」という観念は,本来,いろんなものが入りうる空の器であり,故意過失等の観念と必然的に結びつくものではない。ところが,
伝統的学説が「帰責事由」の内容を 故意過失等である と解釈したことで
その観念がある程度定着し,「帰責事由」の語は,故意過失等を意味するという語感が法律実務家の間に浸透している。しかし,
今後は,学説上の地殻変動と債権法改正があいまって,「帰責事由」の概念が変動していくことが見込まれる。また,法律文書(規程,契約書など)を立案するに際して 無定義で「帰責事由」という用語を使うべきでない
と思われる。以上
(2017年12月29日)
***
すばらしい![]() 村上弁護士、ありがとうございます
村上弁護士、ありがとうございます ![]()
そして↓こちらは73ページにわたる興味深い論文です。検索していて見つけました。
あとで読んでみよう♪(うんと余裕ある時間のある時・・それはいつ?![]() )
)
木戸茜 著 · 2021 — 翻ってわが国では、契約違反に対する救済として強制履行、損害賠償請求、解除が用意され、契約法は伝統的に過失. 責任主義の立場に立つとされ・・