静岡経済研究所から月刊誌『調査月報 12月号』が届く![]() 。
。
その記事の中で注目したものがある。
それは、『合成燃料』に関する記事![]() 。
。
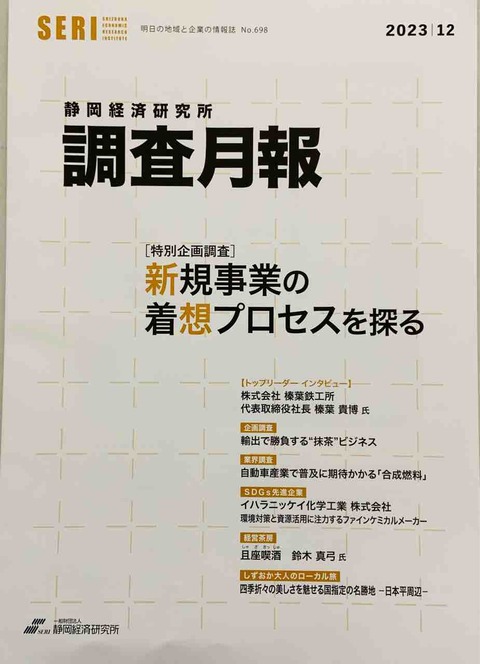
恥ずかしながら、『合成燃料』について全く知らなかった![]() 。
。
この記事で初めて知った![]() 。
。
まず、合成燃料について超簡単に解説する。
合成燃料・・・二酸化炭素(CO2)と水素(H2)を合成して作る。最終的にCO2の排出量がゼロとなり、カーボンニュートラルに有効な燃料とされている。国内外で研究・開発が進展している。
要は、合成燃料を使うと、以下のよいことがあるとのこと。
<合成燃料を使うメリット![]() >
>
・燃料はカーボンニュートラル(脱酸素)とされ、環境に優しい。
・既存のエンジン(内燃機関)に対応している。
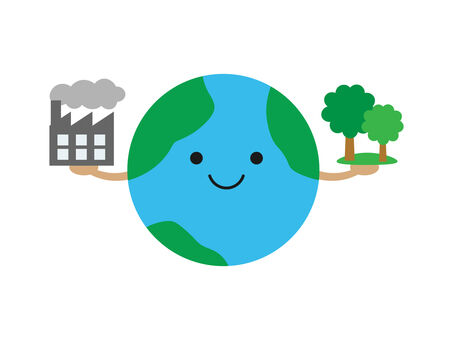
自動車産業の今の流れは、EV車(電気自動車)が中心![]() 。
。
EV車は、走行中に排気ガスを排出しないし、一程度の距離をモーターだけで走行できる![]() 。
。
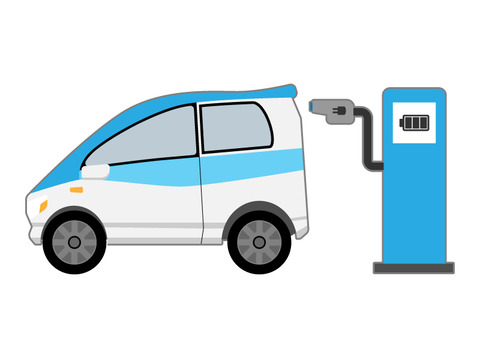
ただし、EV車(電気自動車)が万能というわけではない![]() 。
。
製造過程や廃棄する際に、大量のCO2を必要とする![]() 。
。
この問題は、太陽光発電と一緒![]()

さて、話を戻す。
静岡県は自動車産業で成り立っていると言っても過言ではない![]() 。
。
特に、浜松を中心とした西部地域は顕著。
既存の内燃機関を使った産業が主流。
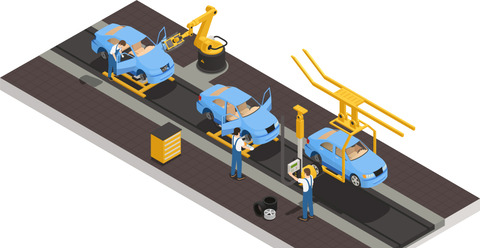
その自動車産業が電気自動車の開発によって脅かされている![]() 。
。
電気自動車の拡大に伴い、合成燃料が普及しない場合![]() 、2050年の県内の自動車部品出荷額は1兆3,000億円、合成燃料が普及した場合
、2050年の県内の自動車部品出荷額は1兆3,000億円、合成燃料が普及した場合![]() は1兆9,000億円と試算している。
は1兆9,000億円と試算している。
その差は何と、5,000億円以上と予測されている![]() 。
。
以上のことから考えて、合成燃料の開発・研究、そして実用化はわが県においては死活問題といえるだろう。
今さら、電気自動車の流れは止められない![]() 。
。
しかし、我が県を含めて、既存の技術を生かせる合成燃料は電気自動車と共存共栄できるかもしれない![]() 。
。
これから、合成燃料について注目していきたい![]() 。
。