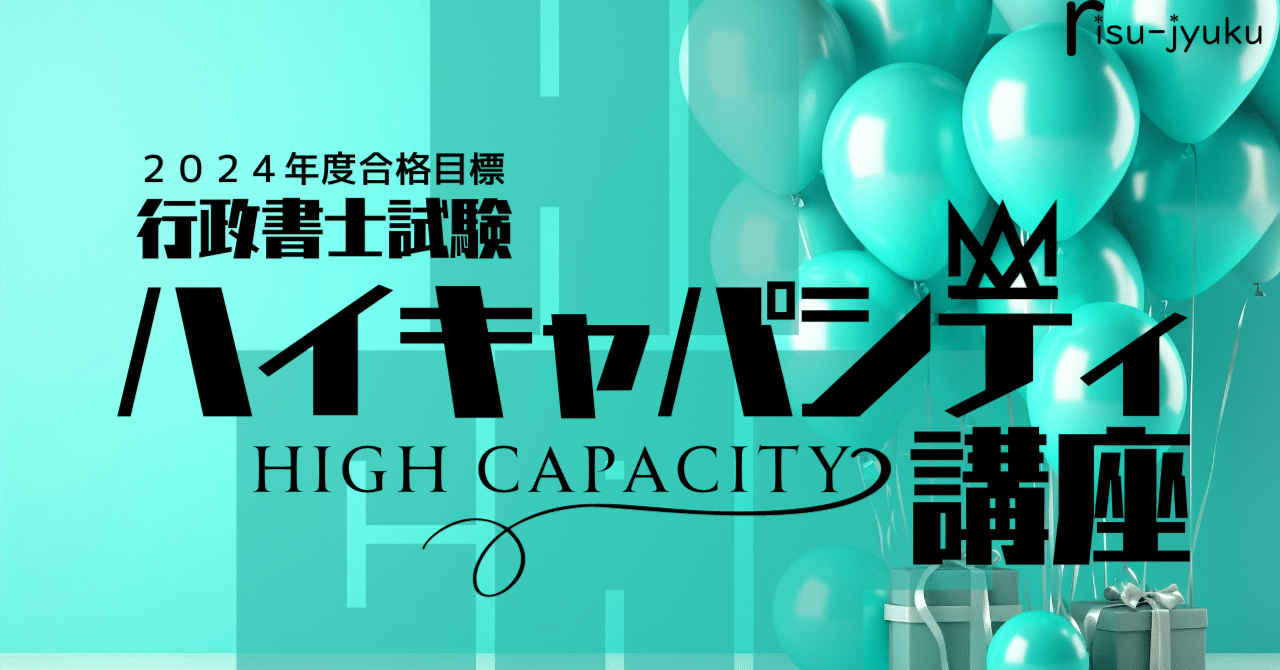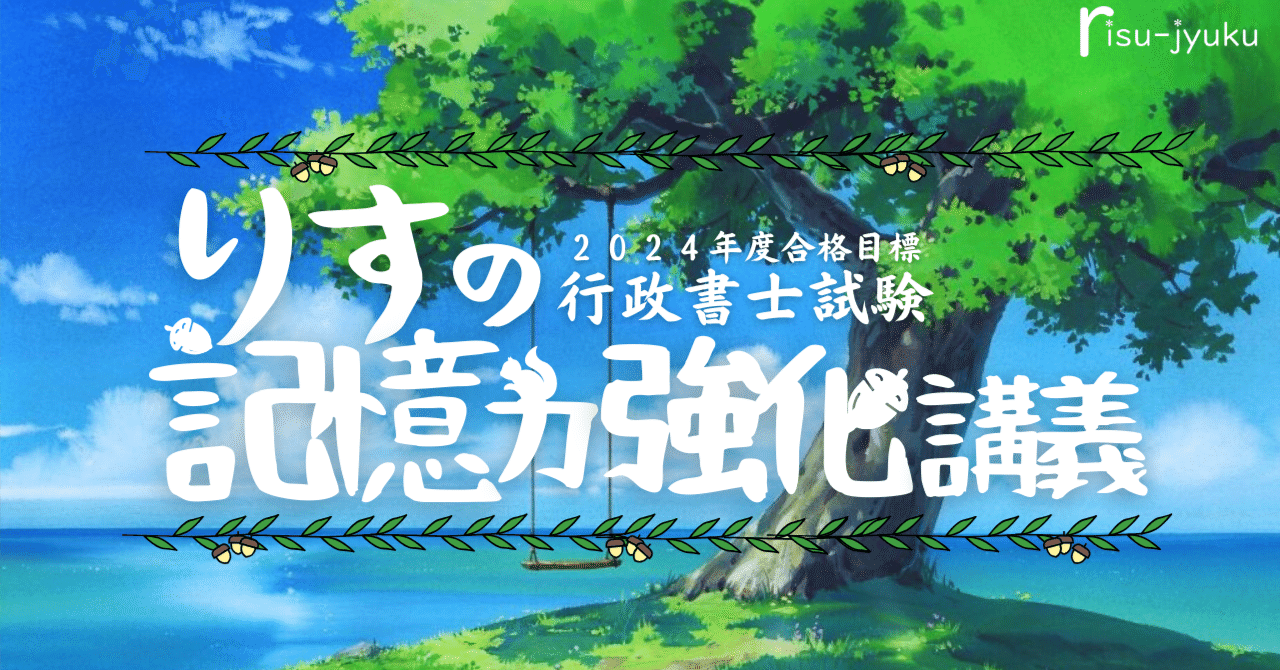債権の目的は、
債権総論の最初に学習する論点ですね。
知っているよ。
「特定物債権」「種類債権」でしょ。
と回答される受験生も多いですね。
不動産の売買契約を例に考えてみましょう。
不動産はその住所にしか存在しませんので「特定物債権」となります。
買主は売主に「特定物債権」として不動産の引渡し債権を持ちます。
では、
売主は買主にどのような債権を持ちますか?
「特定物債権」でも、「種類債権」でもありません。
「金銭債権」として不動産の代金請求債権を持ちます。
金銭債権とは、一定額の金銭の支払いを目的とする債権をいいます。
その弁済の方法は、
債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済することがでる。(402条1項本文)
なので、1万円の金銭債務を、
1千円札10枚で弁済することも
5千円札2枚で弁済することも
1万円札1枚で弁済することも可能です。
*2千円札は2004年以降は増刷されていないので割愛。
*しかし2千円札とゆかりの深い沖縄県では現在も比較的出回っています。
*沖縄県指定有形文化財の首里城守礼門が描かれていますからね。
ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、
その通貨で弁済しなければなりません。(402条1項ただし書)
そして金銭債務の特則がありますね。
金銭債務で債務不履行があった場合の特則として、
①損害賠償の額は原則として、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における
法定利率(年3%変動制)(419条1項)
②債権者は、損害の証明をすることを要しない(419条2項)
③債務者は不可抗力をもって対抗することができない(419条3項)
があります。
また、この金銭債務が債権者代位権の被代位権利であれば、
代位権者は第三債務者に直接請求し、
債務者からの金銭返還請求権と債権者の被保全債権を相殺し、
事実上の優先弁済を受けることもできますね。
さらには、「利息債権」もありますね。
弁済には、債権者が受領するだけの状態になるまでの債務者の行為を
弁済の提供と言います。
弁済の提供で金銭債権を提供する場合は、利息も付さなければなりません。
この時の利息は利息債権です。
それ以外にも、「選択債権」もあります。
ここは講義の内容でとどめておきますが、
債権の目的によって思考内容を変えていかなければなりません。
その思考内容の材料となる部分を学習するのが、
債権の目的なのですね。
このような視点をもって、
再度、債権の目的にアプローチしてみると見え方も変わってきますよ。
民法が面白くなってくるところです。
上記のような民法を使える知識として講義する
「行政書士試験 ハイキャパ講座」
横断知識として知識を綱けるセカンド講義
「りすの記憶力強化講義」
家庭教師的な指導で、わからないを根本解決!
「完全個別 1ON1講義」