そうだ。
人は亡くなるとこんな風に目の前にただ横たわる。
まさに血の気は無い。
ただ、どうやってこうなったかによって様々だ。
私の娘は違った。
18歳で産んだあの先輩によく似た、よく似ていったあの娘。
連絡を受けて真っ先にタクシーで駆け付けたのは母だった。
娘にとっては祖母だ。
私はというと、交番にお世話になってからというもの、夜には出かけ朝には娘とともに住んでいるはずの自宅へと帰り寝るだけの日々。
娘とはいつの間にか向き合えなくなってしまった。
私の感情で、あの人に似ていく娘を直視できなくなった。
でも、私の分身である娘だからという気持ちも無くはなかった。
いつしか娘を避けるという意識的だった私の行動は、嵌まらないはずのピースを探し求めて回るという無意識的な行動に成れ果てていた。
それは、娘と向き合う事ができない事を、どうしようもない事と思い込みたくて仕方が無かったのかもしれない。
明日話せばいい、明日できなければ明後日、そのまた次。
今のままではいけないと思えば思うほど、現実から逃げ続ける。
その結果どうなったか。
母に泣きながら力ずくで連れてこられた警察署には、娘かどうかはわからないほどに変わり果てた遺体が横たわっていた。
背丈から大人ではない、子供だという事は十分にわかる。
この子が本当に私の娘なのか。
あの人との間に産まれてしまったあの子なのか。
私はなんてひどい母親なんだろうか。
ただただ、申し訳ない気持ちだけだった。
他の誰でもない、何の罪もない、この子に対してだ。
なぜ、もっと早く向き合わなかったのか。
私が考えてもできなかったことをこの子はこうしてやってしまった。
少なくとも私以上にこの子は苦しんでいた。
そういう事だ。
ただただ呆然とする私に、母はなぜ泣いてあげないのと責める。
この子はさぞ、私を恨んでいる事だろう。
泣けば赦してくれるのだろうか。
膝から崩れ落ち、まるで娘に許しを請うような姿になる。さらには私の身体を借りた娘がこの世への恨みを放つように泣き叫んでいた。
そのあまりの恐ろしさに母はおろか、周りでそっと見守っていた警察署の職員でさえ、たじろいだという。
後から聞いた話だった。
まだこんな姿になる必要のなかった娘の骨を拾う。
この子は誰もが経験するはずの青春ですら、経験することはもうない。
家に遺されていた娘のノートにはおよそ青春とはかけ離れた、子供の世界の恐ろしさを思い出させるものが書き綴られていた。
こんなにも字が書けるようになっていたのかと驚き半分、その文字はどこか悲しそうで、憎しみを帯びていて、受け止めてあげられるのはもはや名ばかりの母親の私しかいなくて、ごめんねとひたすら続けて読む。
ノートは証拠として警察の預かるところとなり、イジメに関わっていた生徒はことごとく逮捕されていく。
もう、生徒指導室や学校内で始末される時代ではない。
ごめんなさいでは済まされない。
母親としてどうだったのかを刑事さんに話し、私も罰を受けたかったがそうはならなかった。
いっそ、収監してもらった方がせめて、せめて娘への償いになるという思いすらかなわない。
どうやらいよいよ身の置き所が無くなってしまったらしい。
ごめんねと繰り返す毎日。
あの世界には父もいる。
娘にも、父にも顔向けできない。
母も、父と孫である娘のところに逝ってしまった。
母にも顔向けできない。
みんななぜ、私を遺して逝ってしまうのか。
私はどうやら呪われているらしい。
私も同じ世界へいったところでとても顔向けできない。
手も握ってあげられなかったわが子だったが、丁寧に教えてくれる火葬場の職員さんに促されながら、変わり果てた娘の一部を丁寧に拾い上げていく。
そうしていくうちに、はじめて成長した娘と向き合えた気がした。
こんなにも今更で酷い母親も世界に二人と居やしないさ。
娘が入った壺を胸に抱いて帰途につく。
まだ温かい。
ごめんね
ほんとうにごめんね
ごめんね
私はこの命が尽きるまで、そう娘に言い続けようと心に決めたのだった。
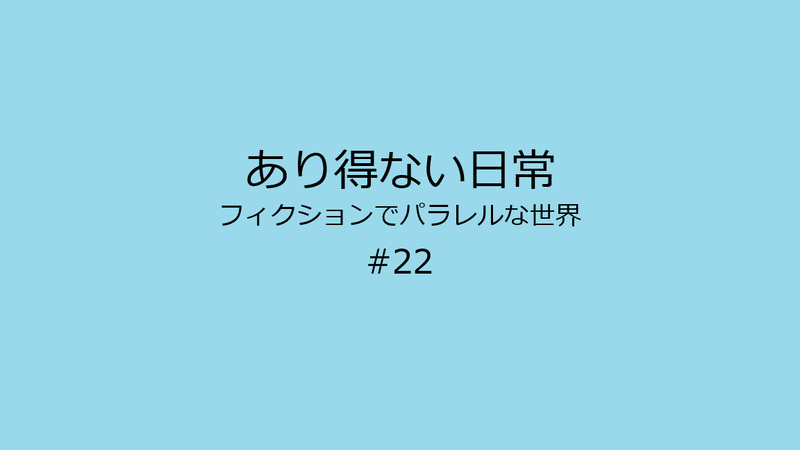
この物語はフィクションであり、実在する人物や団体とは一切関係がありません。架空の創作物語です。
この作品は2024年2月24日にnote.comに掲載し、修正を施したものです。
