”副業”という言葉が古い。
多様化し科学技術の発達した世の中のプロとしての仕事で、片手間でできるものは、ひとつとしてありません。
現在片手間で出来る副業のほとんどは、技術が”未熟”でも収入を得られるからであり、各産業が成熟段階に入れば90%は淘汰されるでしょう。
例えば、現在のIT関連も最先端の仕事に見えるが、成長期であるから副業(片手間)でも可能なだけです。
人生における、長期的な仕事(収入源)としたいならば、誰にも負けない技術を磨き続ける必要があります。
サラリーマンの副業は、どうしても時間的、肉体的、精神的に片手間になりがちです。
日本で、副業しなくてはいけないないのは、そもそも30年間収入が上がらなかったからです。
本当の意味での副業対策は、個人では変革出来ないことがほとんどで、企業や政治(社会の仕組み)を変えることが必要です。
残業の多いブラック企業を社会問題化するなら、本業以外の仕事の時間外労働(副業)を問題にすべきです。
「ブラック副業労働」というのは、いくつも仕事を掛け持ちして、肉体的にも精神的にも疲れ果てる状態です。
何故、国や企業は、
「副業しなくても良い社会をつくらないのか」
「副業しなくても良い企業を作らないのか」
という問題提起を考えることが必要です。
この問題解決には、日本人の「生産性の向上」が鍵となる。
一人当たりの生産性が、飛躍的に向上すれば、収入は大きく向上し「副業」は必要なくなります。
副業を解禁する企業は先進的だと考えるのは、全くのまやかしです。
そのような企業は、社会的かつ長期的に見て必要のない企業ということになります。
金融コンサルタントとして、特に気になるのは、生命保険会社や銀行が、相次いで副業を解禁していることです。
沢山のニュースの中から、2つを選んでみました。↓
副業解禁するのは、経済が凋落し、産業分野として衰退し、時代の変化に取り残されているからです。
事業が縮小する、社員は少なくなる、給与は上がらないから副業を勧めるようになっただけです。
1989年(平成元年)の日本の金融業界は、世界をリードしていました。
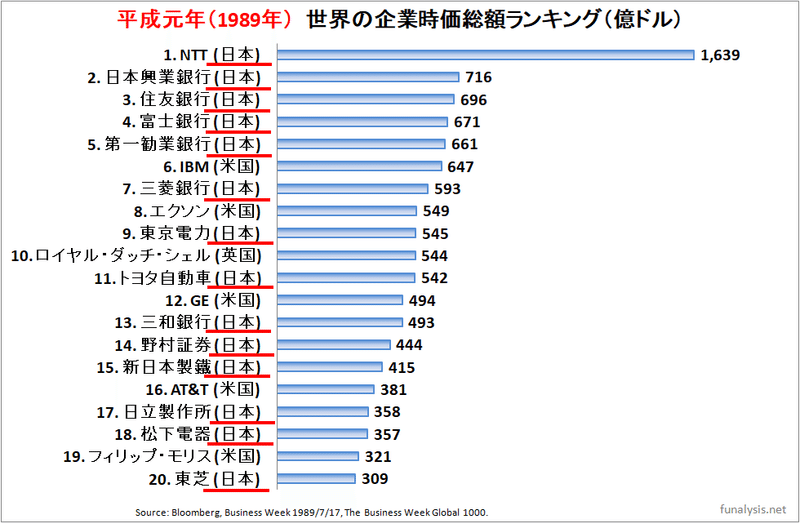
この金融業界の凋落は、1990年の不動産バブル崩壊から始まり、ITによる金融革命もありますが、現在の米国・中国の銀行・証券業・シャドーバンクの力を知れば、日本の経済の衰退に主たる原因があります。
終戦から、GDP世界2位へ登りつめた、日本経済の凋落の象徴のようなものです。
あらゆる産業において、副業しなくてもいい社会を創るチャンスは、日本にはあります。
そのための条件は、すべての産業において、①AIの活用、②ロボット化、③量子科学の進化、がキーワードになるようです。
AI導入状況については、総務省が公表している「令和元年版情報通信白書」によると、世界7位です。
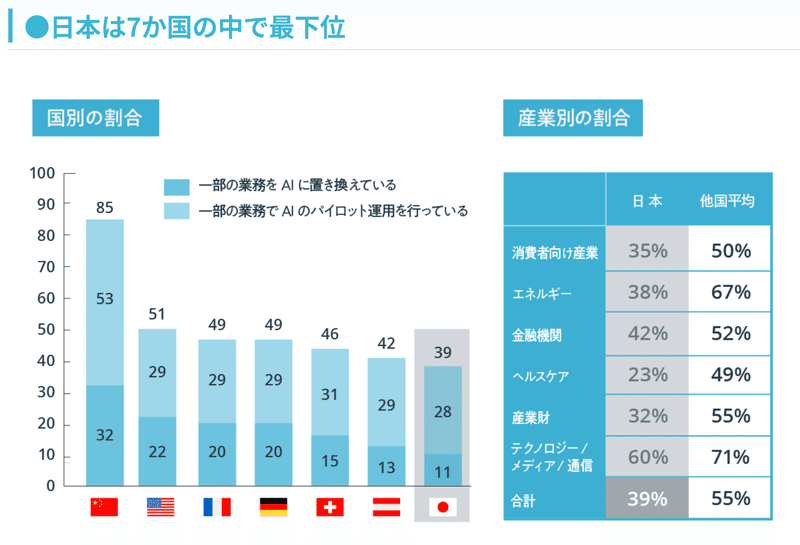
ロボット化は、どれぐらい進んでいるのか。
日本の得意の産業用では、世界2位です。
中国が極端に進んでいるのは、「世界の工場」だからです。
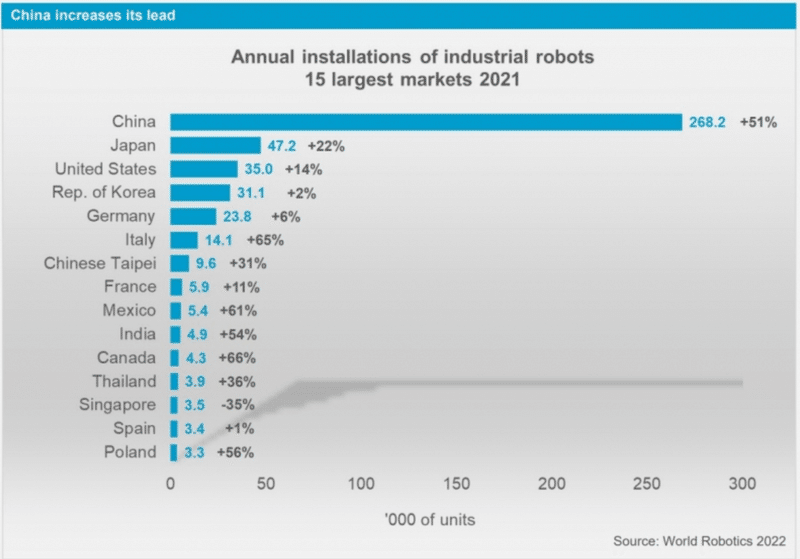
量子科学の分野は、(私の調べでは)まだ統計等のデータが少ないようです。
ニュースとしては、様々な分野で観察出来ます。(下記は一例)
この3つの最先端の技術は、あらゆる産業に活用される点で、インターネット以上の革命が期待されます。
こうした画期的な技術革新を、ほとんど全ての、様々な産業において起こしてゆけば、日本の「生産性」の世界No. 1も可能です。
生産性が世界一になれば、日本人の平均年収が、近い将来において、現在の倍(最低1,000万円)以上になることも夢ではありません。
もちろん、副業など全く必要のないキラキラした時代の到来です。