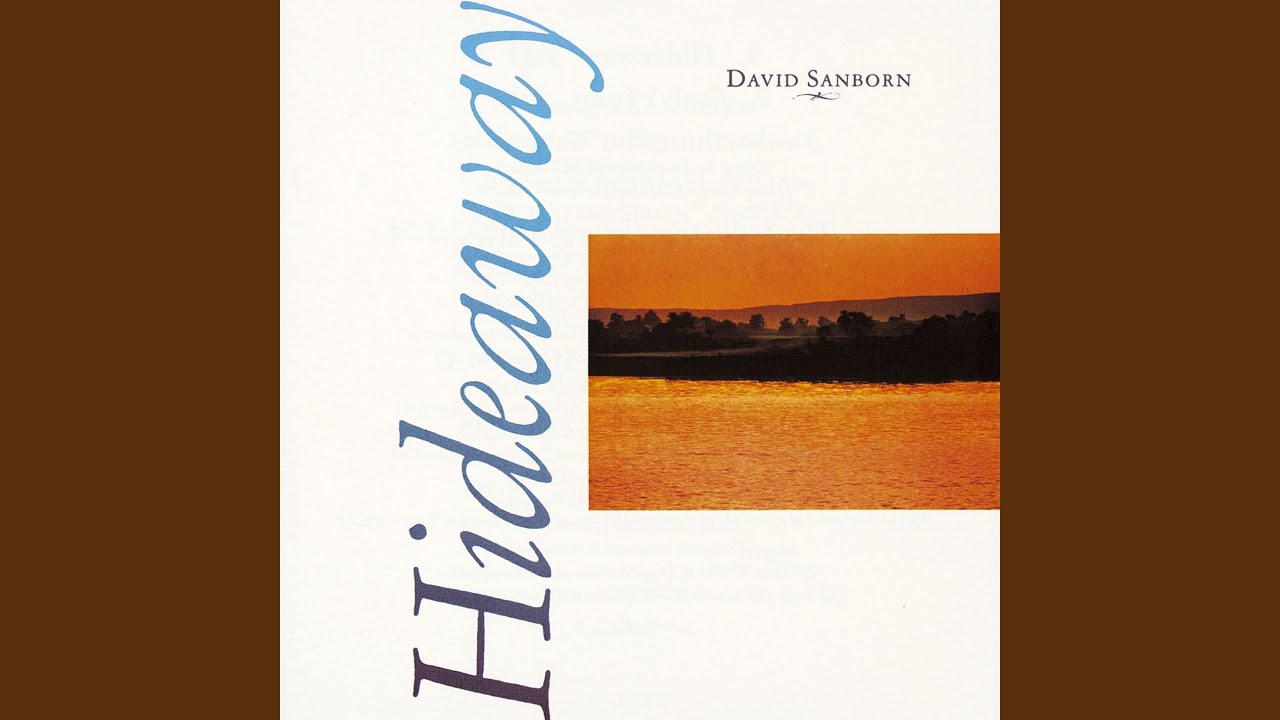J-POP徒然草:追悼デイヴィッド・サンボーン
世界最強の世界最高のSAX奏者、デイヴィッド・サンボーンが死去した。「マウント・フジ・ジャズ・フェスティバル」に登場した時には、最初のブローで会場をぶっ飛ばしたのは伝説になっている。もはや細かい説明は不要なSAX奏者である。そんなデイヴィッド・サンボーンが、2024年5月12日の午後に死去したことが、本人のFacebookなどSNSのアカウントで発表された。2018年以降、前立腺がんとその合併症との闘いを続けながらも以前と同様の演奏活動をおこなっており、2025年までライブのスケジュールは予定されていたという。78歳だった。
デイヴィッド・サンボーンは1945年、米フロリダ州タンパ生まれ、ミズーリ州セントルイス育ちのサキソフォン・プレイヤーである。75年、アルバム『Taking Off』でソロデビューし、80年の『Hideaway』と収録曲“The Seduction (Love Theme)”(作曲はジョルジオ・モロダーで、同年の映画「アメリカン・ジゴロ」で使用された曲の別バージョン)がヒットを記録した。そして82年、前年に発表した“All I Need Is You”が最優秀R&Bインストゥルメンタルパフォーマンス賞に輝き、初のグラミー賞を受賞した。
様々なジャズ、フュージョンミュージシャンとの共演をはじめ、エリック・クラプトン、ジャコ・パストリアス、トッド・ラングレン、ブルース・スプリングスティーン、スティングまで共演や客演は膨大な数にのぼるが、彼の演奏は日本でも厚い支持を受けており、70年代以降、深町純や吉田美奈子、野口五郎、渡辺香津美、カシオペア、宇多田ヒカルといったアーティストのレコーディングにも参加している。最期のソロアルバムは、2018年の『This Masquerade』になった。
中でも筆者が最高だと思っているのは1982年9月21日に発売された吉田美奈子通算9作目のスタジオ・アルバム『LIGHT'N UP』に収録されている「頬に夜の灯」である。吉田美奈子の数多の曲の中でも筆者が一番好きな曲で サンボーンはSAXをブローさせているのだ。これが本当に素晴らしい演奏なのである。
筆者は一度だけデイヴィッド・サンボーンと仕事をさせてもらったことがある。それは1995年9月21日にリリースされた古内東子の4枚目のアルバム『Strength』でのレコーディングの時である。このレコーディングには様々な思い出がある。まず、ご本人とソニーミュージックのディレクターと3人で成田からNYへ旅立つ日の朝にオウム真理教の「地下鉄サリン事件」が発生したことだ。この日、朝まで事件現場となる築地のスタジオでレコーディングをしていただけに、一歩間違えたら…と冷や汗ものだった。
『Strength』は古内東子にとって初の海外レコーディング作品で、ミックスを除いて全てニューヨークでレコーディングが行われた。この作品のプロディースは、デイヴィッド・サンボーンの盟友マイケル・コリーナにお願いした。マイケルはこのアルバムでエンジニアを務めてもらったレイ・バーダー二とともに、『Hideaway』でサンボーンと一緒にグラミー賞を獲った若き頃からの盟友である。しかし、当初、このアルバムにデイヴィッド・サンボーンが参加する予定はなかった。
このアルバムに参加してくれた超一流のミュージシャンたちは、全てマイケルの人脈で、ブレッカー・ブラザーズのランディ・ブレッカー、マイケル・ブレッカーをはじめ、ボブ・ジェームス、スティーヴ・フェローン、オマー・ハキムといったジャズ・フュージョン界の豪華ミュージシャンが参加してくれた。本当はベースをマーカス・ミラーにお願いしたかったがスケジュールの都合で参加できず、マーカスの音源をサンプリングしてマイケルが使ったことで、「Bass Samples:Marcus Miller」とクレジットされている。

レコーディング中に、アルバムの最期を飾る名バラード「雨の水曜日」で、デイヴィッドにSAXをお願いできないだろうか、という話が出た。マイケルから言われたのは、「デイヴィッドからは”お客さん”の仕事はしないと言われている」だった。「お客さん」というのは、日本からやってきてNYの有名ミュージシャンにお願いして「NY Recording」というのをウリにするアーティストのことで、デイヴィッドにとっては古内東子は名前も聞いたことがない日本からの「お客さん」と思われていたのだ。また、当時は既に世界最高のSAXプレイヤーとなっていたデイヴィッドは、自分の作品づくりなど以外には時間を割けないということだった。
しかし、ここで「奇跡」が起きる。まず、当初のレコーディングの予算で考えると、デイヴィッドにSAXをお願いする余裕はなかった。なにせデイヴィッドの場合、本人のギャラ以外にボウヤに1000ドルを払わねばならなかったからだ。「えっ、ボウヤに1000ドル?」とビックリした。当時の為替レート1ドル=110円でいえば11万円を付き人に払うのだ。「なんでボウヤのギャラがそんなに高いの?」とマイケルに尋ねたが、その答えはレコーディング当日に判明した。
なんとこのボウヤがまずデイヴィッドが来る前にSAXを持ってきて調整し、さらに歌入れも終わっている音源を聴いて、的確な位置と思われる場所に譜面台を3つ立てたのだ。「えっ、譜面台が3つなの?」とボウヤに尋ねたら、SAXをブローさせる時に、デイヴィッドの体の向きが変わるからだというのだ。その時に「ピタッとした位置に譜面台がないとダメなんだ」というのだ。しかし、スゴイのが、それが本当だったことだ(笑)。微調整はあったが、その譜面台の立て位置は正確だったのだ。「う〜ん、ボウヤまでプロなのか」と思わず唸った瞬間だった。
レコーディングを行ったNYのRight Track Recording
デイヴィッドに参加してもらえた理由、それは95年4月に起きた超円高だった。日本を旅立つ前に用意したRec予算は1ドル110円換算で、たしか1500万円分くらいだったと思うが、この時、1973年に変動相場制が導入されて以来、円の最高値となる1ドル79.75円を記録したのだ。あれよあれよとドル建てのレコーディング予算が増えてしまったのだ。なんとその差額は500万円以上にもなった。1500万円分が2000万円以上になったのだ(笑)。「よし、デイヴィッドにお願いしよう!」という運びとなった。
ここでもう一つの奇跡が起きた。マイケルに再度「デイヴィッドにお願いできないか?」と尋ねたら、なんと「条件付きだが、OKを貰えそうだ」とのこと。しかして「その条件とは?」と聞くと、「取っぱらい」だった(笑)。天下のデイヴィッド・サンボーンに現金でギャラを渡すのか?と不審に思ったら、マイケルからこう言われたのだ。「デイヴィッドは最近、家を新築したばかりなんで、現金で本人に直接払ってくれるならいいよ、と言ってる」。マジか。こちらはもちろん「OK」だった。
さて、さすがに世界最高のSAXプレイヤー、デイヴィッド・サンボーンがスタジオにやってきた時、スタッフは緊張した。もうSAXの神が降臨したようなものだ。さらに、凄かったのがレコーディングが開始されてからだった。眼の前のデイヴィッド・サンボーンは「雨の水曜日」のトラックに合わせて、「泣き」のSAXを披露をしている。もう、それだけでも「スゴイ!」のだが、スタジオ内に激震を走らせたのはプロデューサー、マイケルの一言だった。
「ヘイ、デイヴィッド。いつなったら本気を出すんだ?」
スタジオ中が凍りついた。
「デイヴィッド。これは”お客さん”の仕事じゃないんだぜ。俺とレイの仕事だ。本気でやってくれ」
もう、誰も何も言えない状況となった。これを言えたのは盟友マイケルだからだが、SAXを吹くデイヴィッド・サンボーンの顔がみるみる紅潮していったのが分かった。デイヴィッド・サンボーンの心に火が点いた瞬間だった。これぞプロとプロのプライドをかけた戦いという感じだったが、デイヴィッドもマイケルもレイも、3人とも若くて貧しい頃から一緒に音楽を作り、それぞれが一流のプロになっていった。だからこそ言える一言だった
ちなみにこのレコーディングの際、音源のMIXは東京で行われたのだが、その際にマイケルとレイには「PROSOUND」のインタビューに応じてもらった。まぁこの辺りの裏ネタは一切書かれてはいないが。
この時のNYレコーディングでは、本当にマイケルとレイにお世話になった。レイがイタリア系だったこともあり、NYではどこのピザ屋が最高だとか、くだらない話で言い争っていた(笑)。ピアノの録音はNY郊外のボブ・ジェームスの自宅のリビングで行い、さらにボブ・ジェームスはノー・ギャラでやってくれた。というか請求書が送られてこなかったのだ。実はこれ、ボブ・ジェームスの娘のプロディースをマイケルが破格の値段でやっていたことのお返しで、当初1曲の予定が現場でもう1曲となって2曲も弾いてくれたのだ。海外のミュージシャンはお金にうるさいなどという人いるが、それはあくまでも表の話で、血の通った人たちは、ちゃんと恩返しを忘れないのである。素晴らしい。
もう素晴らしい思い出ばかりのレコーディングだった。
〈泣きのサンボーン〉と呼ばれたデイヴィッドのSAXの響きのサックスに浸って、サンボーンに弔意を表したい。ありがとう、デイヴィッド!安らかに眠ってください。