「穢れ」と「言霊」の謎:その6
「鏡開き・鏡割り」とは、絶対神に感謝し、無病息災などを祈って、大和民族が繁栄していくことを願った儀式であり、その雛形は、モリヤ山でのアブラハムによる「息子イサクの燔祭」にある。
アブラハムは、焼き尽くす献げ物に用いる薪を取って、息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いて行った。イサクは父アブラハムに、「わたしのお父さん」と呼びかけた。彼が、「ここにいる。わたしの子よ」と答えると、イサクは言った。「火と薪はここにありますが、焼き尽くす献げ物にする小羊はどこにいるのですか。」
アブラハムは答えた。「わたしの子よ、焼き尽くす献げ物の小羊はきっと神が備えてくださる。」二人は一緒に歩いて行った。
神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、薪を並べ、息子イサクを縛って祭壇の薪の上に載せた。 そしてアブラハムは、手を伸ばして刃物を取り、息子を屠ろうとした。
そのとき、天から主の御使いが、「アブラハム、アブラハム」と呼びかけた。彼が、「はい」と答えると、 御使いは言った。
「その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を畏れる者であることが、今、分かったからだ。あなたは、自分の独り子である息子すら、わたしにささげることを惜しまなかった。」
アブラハムは目を凝らして見回した。すると、後ろの木の茂みに一匹の雄羊が角をとられていた。アブラハムは行ってその雄羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす献げ物としてささげた。(「創世記」第22章6-13節)
この時、神の御使いは、「アブラハム、ちょっと待った〜っ!」と言ってイサクの燔祭を止めさせたのである。アブラハムは信仰の父で、神の言葉(命令)を一切疑わず、100歳になってやっと授けられた独り子イサクを犠牲にすることを厭わなかったからだ。このアブラハムの故事が「信じる者は救われる」という言葉の原点である。さらに、イサクの燔祭の話にはもう一つの慣用句を生んでいる。それは、「備えあれば 憂いなし」である。
アブラハムはその場所をヤーウェ・イルエ(主は備えてくださる)と名付けた。そこで、人々は今日でも「主の山に、備えあり(イエラエ)」と言っている。主の御使いは、再び天からアブラハムに呼びかけた。 御使いは言った。
「わたしは自らにかけて誓う、と主は言われる。あなたがこの事を行い、自分の独り子である息子すら惜しまなかったので、 あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。 地上の諸国民はすべて、あなたの子孫によって祝福を得る。あなたがわたしの声に聞き従ったからである。」(「創世記」第22章14-18節)
「備えあれば 憂いなし」とは「前もって準備しておけば、何か起こったとしても心配ない」という意味で使われる。 十分に準備をしていれば、オロオロと心配せずに平常心で試験に臨むことができるのです、なんてことを受験生に説くキリスト教会員もいる。この慣用句は、古代中国で伝わっていたものが日本に持ち込まれたとされている。
「備えあれば憂いなし」の由来は、古代中国・殷国の宰相「傳説」(ふえつ)の言葉とされている。『書経』には「有備無憂」という一節が登場し、書き下すと「備え有れば憂い無し(=備えていれば憂いはない)」となり、ここから慣用句として成立したとされている。「殷」(いん)は紀元前17世紀頃 - 紀元前1046年まで存在した考古学的に実在が確認されている中国大陸最古の王朝である。これが何を伝えているのかと言えば、古代中国大陸にはアブラハム・イサクの末裔がいたということである。
アブラハムがイサクを燔祭にしようとした場所はモリヤ山である。そこにある「井戸」の上でアブラハムはイサクを燔祭にしようとしたのである。ここが現在のエルサレムの「神殿の丘」に建つ黄金の「岩のドーム」であり、イスラム教徒の聖地となっている。アブラハムがイサクを捧げたのが「井戸の上」ということは、その下には「命の水」があるということであり、「鏡開き・鏡割り」で「酒樽」を割るのは、その下には「命の水」の象徴としての「御神酒」があるという意味が込められているのである。
一方で、「鏡餅」を木槌で割るという行為には、どんな別の意味が込められているのだろうか。
◆「御神体」と「国体」
「鏡」は天照大神自身の御魂(みたま)であり、伊勢神宮では「御神体」として祀られている。つまり、皇祖神の魂であり体でもあり、それが割られるのである。となると、日本が二つに割れるということを意味しているのではないだろうか。なぜか。日本は世界の国々とは異なり、自分たちの国のことを「国家」とは呼ばず「国体(國體)」と呼ぶ。つまり、「日本」という国は国家ではなく、「国体(國體」なのである。
「国体(國體)」とは、「国家の状態、国柄のこと。または、国のあり方、国家の根本体制のこと」あるいは「主権の所在によって区別される国家の形態のこと」とある。他の世界中の国は「国家」という形態だが、日本だけは「国体(國體)」ということなのだ。「国体」という語は、必ずしも一定の意味を持たないが、国体明徴運動後の1938年当時においては、「万世一系の天皇が日本に君臨し、天皇の君徳が天壌無窮に四海を覆い、臣民も天皇の事業を協賛し、義は君臣であれども情は親子のごとく、忠孝一致によって国家の進運を扶持する、日本独自の事実」を意味したという。天皇を奉ずる日本だけの「国のカタチ」ということだ。

岡田啓介総理と文部省の『國體の本義』
「国体論」は、幕末に水戸学によって打ち立てられ、明治憲法と教育勅語により定式化された。国体(國體)は、「天皇が永久に統治権を総攬する日本独自の国柄」という意味をもち、不可侵のものとして国民に畏怖された。もともと国体という語は国家の形態や体面を意味していたが、幕末の対外危機をきっかけに、水戸学が日本独自の国柄という意味で国体観念を打ち立てた。この水戸学の構想は日本全国に広まり、国体論が一つの思想として独立。国体論は、明治維新の後の過渡期を経て、帝国憲法と教育勅語により定式化されたのである。つまり、「日本だけは世界と異なる独自の国柄の国」として世界に向けて宣言したということである。
「国体」は旧字体で「國體」と書き、「國」という字は「政体の下に属する土地・人民」などの意、「體」という字は、「からだ、てあし、もちまえ、すがた、かたち、かた、きまり」などの意である。つまり「日本という国の姿」ということとなり、それは日本という国は手足のある姿、「人体」ということだと言っているのである!これが日本だけが国家と呼ばない理由なのだ。
国体という語は、古くから漢籍に見え、『管子』君子篇において国家を組織する骨子という意味で用いられ、『春秋穀梁伝』において国を支える器という意味で用いられたが、これらは日本でいう国体とは関係がない。その後、漢書にも国体の語が見え、これは国の性情、または国の体面という意味であり、日本でいう国体にやや近いといえる。日本において国体という語が多用されるのは近世になってからであるが、古典籍においてもその語は散見される。但し、その用例と意味は近代のものとは異なる。
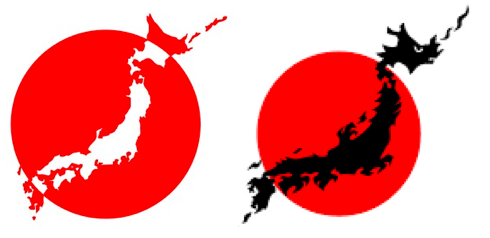
「国体」の語が日本の古典に現れるのは、延喜式所載の出雲国造神賀詞に「出雲臣等が遠祖天穂比命を国体見に遣時に」とあるのが初見であるといわれる。「国体」は古訓でこれを「クニカタ」と訓じている。また『日本書紀』の斉明天皇紀に「国体勢」という語句が見え、これを「クニノアリカタ」と訓じた。国体も国体勢も元は地形の意味であったのが転じて「国状」の意味に用いられたと考えられる。次いで『大鏡異本陰書』や『古事談』にも「国体」の語が見える。これは『万葉集』にある「国柄」の語と同義であって、ともに「クニガラ」と訓じ、国風や国姿などの意味に通じる。つまり、「国体」は「こくたい」ではないのだ。
明治において、この「国体(國體)」という考え方とは少々異なる学説が登場する。それは憲法学者・美濃部達吉らが主張した
「天皇機関説」(てんのうきかんせつ)である。これは大日本帝国憲法下で確立された憲法学説で、統治権は法人たる国家にあり、天皇は日本国政府の最高機関の一部として、内閣をはじめとする他の機関からの輔弼(ほひつ)を得ながら統治権を行使すると説いたものである。ドイツの公法学者ゲオルク・イェリネックに代表される国家法人説に基づき、美濃部達吉らが主張した学説で穂積八束・上杉慎吉らが主張した「天皇主権説」と対立する。
憲法学者の宮沢俊義によれば、「天皇機関説」とは、次のようにまとめられる。
「国家学説のうちに、国家法人説というものがある。これは、国家を法律上ひとつの法人だと見る。国家が法人だとすると、君主や、議会や、裁判所は、国家という法人の機関だということになる。この説明を日本にあてはめると、日本国家は法律上はひとつの法人であり、その結果として、天皇は、法人たる日本国家の機関だということになる。これがいわゆる天皇機関説または単に機関説である。」( 宮沢俊義『天皇機関説事件(上)』)
1889年(明治22年)に公布された大日本帝国憲法では、天皇の位置付けに関して、次のように定められた。
第1条:大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス(天皇主権)
第4条:天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リテ之ヲ行フ(統治大権)
実は、「天皇機関説」においても、国家意思の最高決定権の意味での主権は天皇にあると考えられており、天皇主権や統治権の総攬者であることは否定されていない。しかしながら、こういった立憲君主との考え方は大衆には理解されなかったようで、「天皇機関説事件」という騒動が起きた以後は「天皇主権説」が台頭、それらの論者は往々にしてこの立憲君主の考えを「西洋由来の学説の無批判の受け入れである」と断じた。
「主権」という語は多義的に解釈できるため注意が必要である。「統治権としての主権を有するのは何か」という問いに対して、国家と答えるのが「国家主権説」である。一方で、「国家意思の最高決定権としての主権を有するのは何か」という問いに対して、「君主である」と答えるのが「君主主権説」、「国民である」と答えるのが「国民主権説」である。 したがって、国家主権説は君主主権説とも国民主権説とも両立できるが、美濃部達吉の「天皇機関説」は、統治権の意味では国家主権、国家意思最高決定権の意味では君主主権(天皇主権)を唱えるものである。美濃部は主権概念について統治権の所有者という意味と国家の最高機関の地位としての意味を混同しないようにしなければならないと説いていた。
1935年(昭和10年)、政党間の政争を絡んで、貴族院において天皇機関説が公然と排撃され、主唱者であり貴族院の勅選議員となっていた美濃部達吉は弁明に立った。結局、美濃部は不敬罪の疑いにより取り調べを受け(起訴猶予)、貴族院議員を辞職。著書である『憲法撮要』『逐条憲法精義』『日本国憲法ノ基本主義』の3冊は、出版法違反として発禁処分となった。当時の岡田内閣は、同年8月3日には「統治権が天皇に存せずして天皇は之を行使する為の機関なりと為すがごときは、これ全く万邦無比なる我が国体の本義を愆るものなり」(天皇が統治権執行機関だという思想は、国体の間違った捉え方だ)とし、同年10月15日にはより進めて「所謂天皇機関説は、神聖なる我が国体に悖り、その本義を愆るの甚しきものにして厳に之を芟除(さんじょ)せざるべからず。」とする国体明徴声明を発表、天皇機関説を公式に排除、その教授も禁じられた。
この「天皇機関説」と一連の騒動に対して、当の天皇陛下はどう考えていたのであろうか。時の昭和天皇自身は機関説には賛成で、美濃部の排撃で学問の自由が侵害されることを憂いていた。昭和天皇は「国家を人体に例え、天皇は脳髄であり、機関という代わりに器官という文字を用いれば少しも差し支えないではないか」と本庄繁武官長に話し、真崎甚三郎教育総監にもその旨を伝えている。国体明徴声明に対しては軍部に不信感を持ち「安心が出來ぬと云ふ事になる」と言っている(『本庄繁日記』)。昭和天皇はちゃんと認識していたのであり、「国体(國體)」を人体と考えた時、「天皇は頭脳であり器官」と言っている。
日本国というのは、カラダを有した存在なのであり、皇祖神の命令を臣下に伝える役割、つまり「天照大神の預言者」だと昭和天皇は自覚していたことになる。「国体」の語が日本人一般に認識されたのは近代のことだが、「国体」の語を用いなくともこれと同一の観念が起こったのはかなり古い。すなわち、日本人が自国を外国と比べてその国家成立の特色や国家組織の優秀性などを誇ることが多々あり、その特色または優秀性とされるものは、「日本が神国であること」「皇統が連続して一系であること」などである。
世界中を探しても、自分たちの国を「神の国」だと自覚しているのは、イスラエルと日本だけである。それ以外に「神国」はない。古代日本において、「我が国は神国なり」という観念が存在したことは、建国に関して確固とした神話が遺されていることから分かる。また古代において祭政一致により国を治めていたことも神国思想からきている。そのほか『日本書紀』の神功皇后の三韓征伐の条で、攻め寄せる日本兵を見た新羅王が「われ聞く。東に神国ありと。日本と謂う。また聖王ありと。天皇と謂う。必ずその国の神兵ならん」と言ったとされるのも、形は新羅王に言わせてはいるが実は新羅王の口を借りて日本国民の観念を述べているのである。
現在は1946年に公布された「日本国憲法」によって「国民主権」がとられている。とられてはいるものの、多くの日本人の心の奥底には、この国は「神の国」という意識がある。そうでなければ毎年1億人以上の人たちが神社を参拝する理由がみつからない。そして、正月から年末まで、圧倒的な数の国民が自覚なき神事を続ける理由もみつからない。日本は「神の国」であり、その姿は「神の体」なのである。
だが、まだ「鏡餅」を木槌で割るという行為に込められた意味を解いてはいない。なにせ、神の体を木槌で割るのだ。そこにはどんな秘密が隠されているのだろうか。
<つづく>





