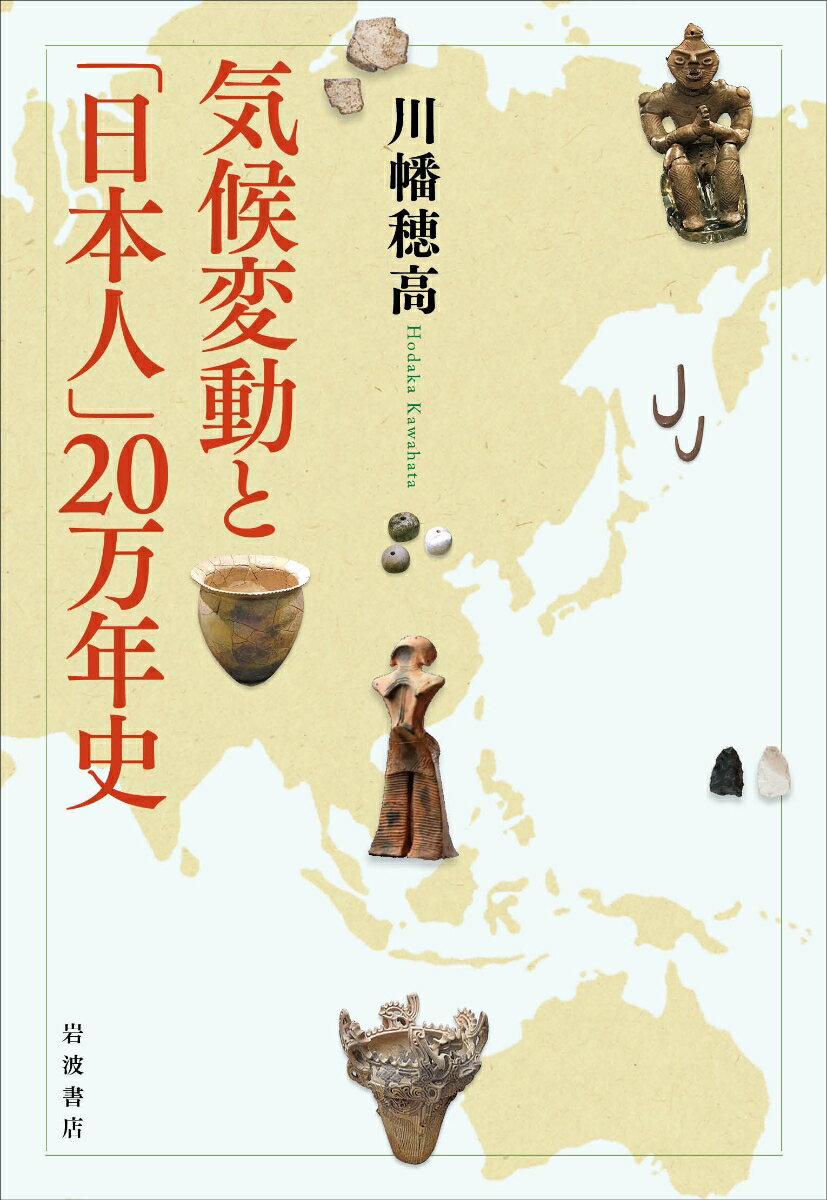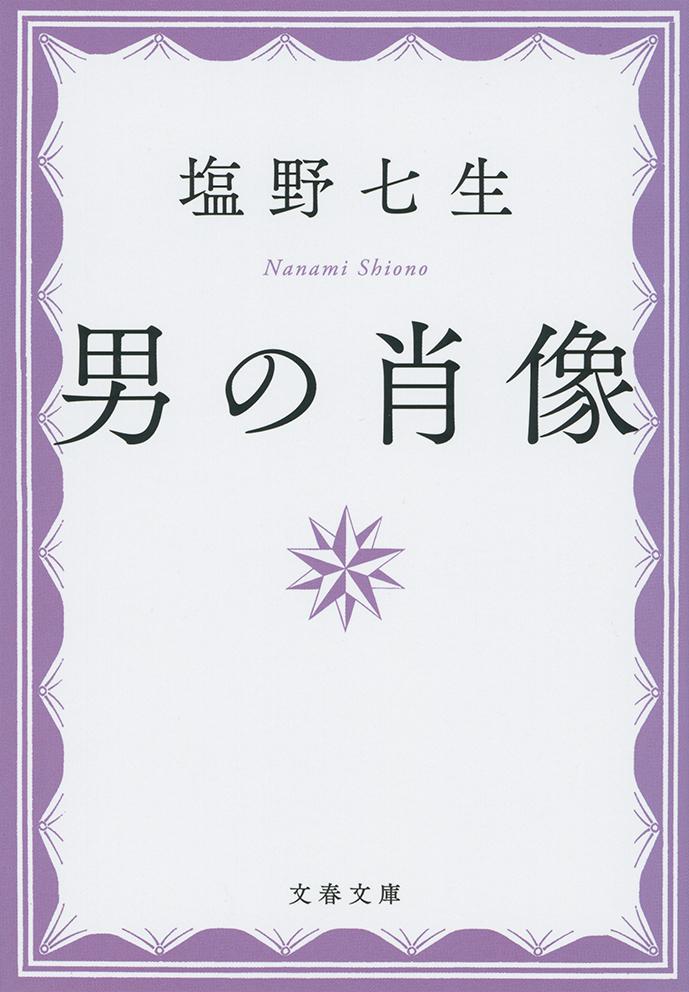鎌倉幕府とモンゴルの誕生
コメントを戴いた方から紹介していただいた
川幡穂高著『気候変動と「日本人」20万年史』(岩波書店)
という本があります。
歴史と気候変動の関連の研究で実におもしろかった本です。
大変遅まきながら、この場をお借りしお礼を述べさせていただきます。
川幡穂高氏よると、気候変動の最悪条件の時
チンギス・ハンという偉大なリーダーが誕生し、
機が熟した頃、気候が最良の時期を得たとあります。
つまり、どんなに強い騎馬軍でも馬のえさがないと
馬だけでなく民族が枯れてしまうということです。
ところが、ユーラシア大陸のどこへいっても
馬のえさが豊富になるような温暖な気候だった
というのです。
やはり、気候変動と歴史は連動していると
川幡穂高氏も述べています。
歴史上ギリシャやモンゴルなど一度は世界史の
表舞台のいわば主役となった民族は、
その後必ずしも文明が栄えているとは
いいがたいものがあります。
世界史は文明の興亡といってもいいくらいです。
その点、日本という国は「千代に八千代に…」
栄え続けている希有な国家かもしれません。
まさにこれからも「さざれ石」のごとく。
ただ、今は国難の時代であることは
まちがいありません。
13世紀 世界帝国をつくったモンゴル
遊牧民にとって掠奪は生活のため
13世紀 世界帝国をつくったモンゴル
13世紀、日本では鎌倉幕府という
武家政権、つまり軍事政権が誕生していました。
この後、徳川幕府までいわば軍事政権が続きます。
その鎌倉幕府が誕生した時代、ユーラシア大陸では
とてつもないことがおころうとしていました。
1206年、モンゴル部族の族長を集めた大集会が開かれ、
テムジンがモンゴル族の長として、
チンギス・ハンを名乗ります。
チンギスとは「勇猛な」であり、
シャマンから「地上の唯一の君主」との天命が下ったといわれます。
もともとモンゴル民族は遊牧民で、
それぞれの部族ごとに移動し、
民族としてアイデンティティをもつことはなかったのですが、
皮肉にも唐が周辺地域も統一して、
モンゴル民族もその支配下に入った時、
民族の意識が一つにまとまったということです。
さらに、チンギス・ハンの登場で鬼に金棒、
モンゴル民族に騎兵隊ということになったわけです。
騎兵隊とは、全員が馬で移動できることを意味します。
日本の武田軍団は、
騎兵と歩兵の混成軍でモンゴルの騎兵隊とは全く異なります。
モンゴルの騎兵隊の機動力は圧倒的で素早く、
鍛えた攻撃力・破壊力はすさまじく、
あっという間にヨーロッパ深く進入しました。
ロシアは13世紀からイヴァン大帝が表れる16世紀まで
「モンゴルの軛(くびき)」といわれるトラウマを経験しています。
現在の中国、
トルコやイランなど中東の国々も
一度はモンゴル帝国の支配下となりましたが、
モンゴル帝国はその歴史を記録していないので、
その足跡が歴史から消されていると
歴史家の宮脇淳子氏は述べています。
ちなみに、ヨーロッパの街の至る所、
旅行をするとあちこちにモンゴルの傷跡が残っている
と述べているのが塩野七生氏。
モンゴル騎馬軍団の破壊力は凄まじく
人も物も破壊し尽くしました。
前川幡穂高氏の著作によると
13~14世紀の東アジアから東南アジアだけでも
人口の2/3が減少して7500万人あまりになった
としています。
遊牧民にとって略奪は生活のため?
遊牧民と農耕民では、
生活観や倫理観なども全く異なります。
農耕民は定住して土地を持ち、
収穫物にも所有物という感覚を持ちます。
ところが遊牧民は、
自分の家畜という感覚はないわけではないが、
移動して自然にある恵みを生きるために得ることになります。
つまり、遊牧民の感覚では掠奪は必要なことであり、
居住している人間などはどうしようと
知ったことではない、
らしい。
モンゴル軍には、
馬も食料も自前で手当は一切ありません。
勝利の報酬は、掠奪した品物の平等な分配です。
秦の始皇帝は、これを防御すべく
馬が乗り越えられないほどの万里の長城を造りました。
今ある巨大な万里の長城は明時代に造られたものです。
農耕民にしてみれば、
汗水流してやっと実りを迎える頃に
やってきては好き勝手に収穫物を奪っていく遊牧民は
たまったものではなかったということです。
モンゴル帝国は、結果として
東は日本海に達し西はロシア平原に至る大帝国を樹立し、
「パクス・モンゴリカ(モンゴルの平和)」が実現します。
帝国内には駅伝制が敷かれ、
十字軍で開かれたイスラム圏との貿易をきっかけに
ヨーロッパからもマルコポーロ以外の多くの商人が
やってきていました。
フビライ・ハーンは、世界初の不換紙幣を発行します。
つまり、政府の信用を背景とした紙幣です。
一方この「グローバル化」は、
ペスト(黒死病)をヨーロッパにもたらすという
負の遺産も持ち合わせていました。
モンゴルは、騎馬隊で
「パクス・モンゴリカ」といわれた東西をつなぐ
世界帝国を実現しました。
ちなみに、チンギス・ハンとフビライ・ハーン
ハンとは、「汗=王」、部族長
ハーンは皇帝と、最近は違いを明確にしている
そうです。
簡単にいうとチンギス・ハンの
直系は皇帝となりハーン、
それ以外の分裂したモンゴル国家の王はハン。
というくらいにしておきます。
これだけでもまだそうとうながくなりそうですので。
さらに、フビライではなく
クビライだという指摘もあります。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございます。