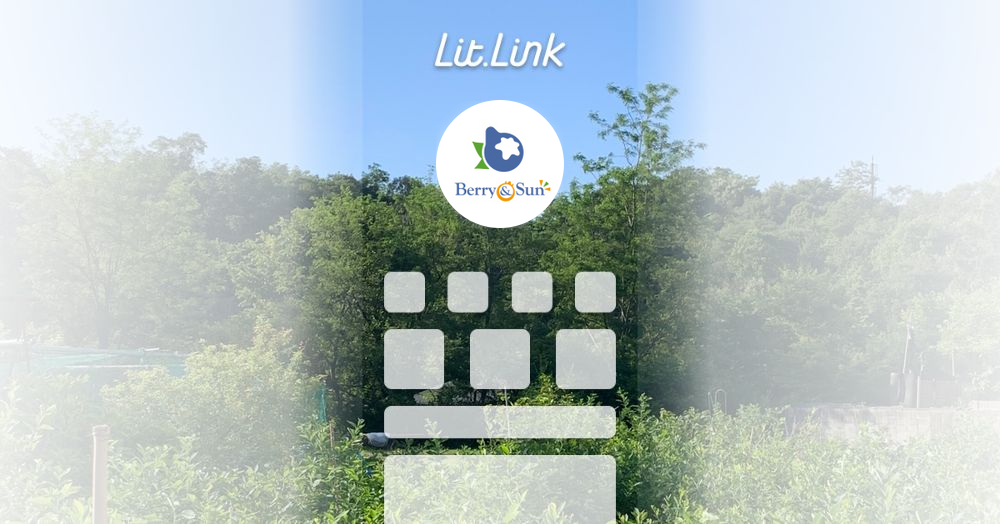だいぶ前に、接ぎ木の方法が色々ありすぎて、どの方法を選べば良いのかがわからないというメッセージをもらいました。
私自身、接ぎ木はあまり得意ではなく、最近になって、少しずつ成功率か上がってきたところです。得意ではないからこそ、成功しやすかった方法などを伝えられると思い、今回、記事にまとめてみる事にしました。
冒頭で書いた通り、接ぎ木には、様々な種類があります。今回は、その中で、切り接ぎ、剥ぎ接ぎを紹介します。芽接ぎ、腹接ぎ、呼び接ぎなどもありますが、それらは、まだ上手くいきません。
そして、接ぎ木は、自然界では起こり得ないから、自然の摂理に反しているのでは?というメッセージも頂いた事があります。
山の木が、風で根こそぎ倒れた時など、隣の木に寄りかかり、そのまま癒合する事もあります。伸び過ぎて、ぶつかった枝同士がそのまま繋がる事もあります。
なかなか、イメージは湧きませんが、接ぎ木は自然界でもありふれている現象というのが、個人的な見解です。
さて、今回のモデル植物はイチジクです。
切り接ぎ、剥ぎ接ぎ共に、穂木の加工は同じです。
増やしたい品種の枝を、芽1,2個残して、切り出します。芽のある側の下部を、鋭角(45°前後)にカットし、裏側は樹皮を薄く剥き、形成層を出します。
形成層は、黄緑色をした薄い層です。白っぽく見えるところまで剥いでしまうと、剥ぎ過ぎでつながりません。
最初に紹介するのは切り接ぎです。形成層を合わせる必要があり、ズレると失敗しますが、手間は1番掛からない方法です。
今回は、台木になる苗が無かったので、太い枝で見立てています。切り接ぎは、ナイフで台木を縦に割ります。
穂木を挟む場所ができました。
先程、穂木の樹皮を薄く剥いた時に見えていた、黄緑色の形成層が台木にも見えています。切り接ぎの台木では、真ん中には形成層が出ず、両端に形成層が出ています。このどちらかの形成層と、穂木の形成層が1箇所でもピッタリ合わされば、そこからカルスが発達し、徐々に繋がり、1つの個体になります。
前にある薄い側にも形成層が出ているので、そちらも合わせるとより成功率が上がります。
最重要ポイントです。穂木と台木の太さがピッタリ合うと、より成功率は上がりますが、穂木が細い場合は、左端か右端に寄せて挟み、形成層同士が合うようにします。
形成層が密着していないと、根から吸った水分を穂木に受け渡す事ができず、すぐに穂木が枯れてしまいます。
次に、剥ぎ接ぎです。
こちらは、切り接ぎに比べて一手間増えますが、全面に形成層を出す事ができるため、成功率はかなり高くなります。
台木にナイフを当て、切れ込みを入れます。
木部にぶつかって、これ以上切れないところで勝手に止まります。それ以上は、無理して切らないようにします。
穂木の幅でもう1本。
そして、剥ぎます。
あとは、隙間なく接ぎ木テープを巻いて、数週間〜数か月後、穂木の芽が動けば、無事成功と言えると思います。
少し前に接いだ、フィンガーライムの内1本だけですが、接ぎ木テープの中に水が溜まっていました。
腐り始めている様子は無いので、触る必要は無いかも知れませんが、中を見てみました。
ただ、樹液の流動が活発過ぎて、溢れただけのようでした。
痛みもなく、しっかりとつながり始めていました。
隙間にカルスが発達してきています。
今は、シーズンでは無いですが、いきなりやっても難しいのが接ぎ木です。
興味がある方は、この冬、剪定してきた枝などを穂木、台木に見立てて、試しに接いでみる事をオススメします。そして、感覚を掴んで春を迎えられたら、成功率も大きく、変わるはずです。私はいきなり、本番に挑戦して、全く上手くいかなかった過去があるので、その時の自分にも、そのようなアドバイスをしたいです。
接ぎ木テープは、自然分解されるニューメデールがオススメです。接ぎ木成功後に剥がす必要がありません。
🌱植物の不思議系オススメ記事🌱

ブルーベリーの苗木をこれから買いたい人、家庭菜園で楽しんでいる人、そして、プロまで。ブルーベリー栽培者の皆さん大歓迎の交流所です。
交流や栽培の悩み相談など気軽に参加してください。