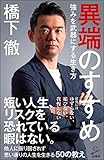個人的には、前に読んだ…
「実行力」のインパクトが強すぎて…
ただ内容は、勉強になりましたよ(°▽°)
響いた内容…
・すべての仕事は「表裏の一体性」で考えなくてはいけません。たとえば自由と責任。権利と義務。
・努力ではどうにもならない場合…「複数の強み」を「掛け算」すること。自分が持つカードを増やすということ。
・達成の「その先」を具体的にイメージせよ…しんどいときであればあるほど、そのイメージは具体的で強烈なものである必要がある。
・僕の人生経験からいえば、通常は、まずは量をこなして自分のウリを磨いて仕事の質を上げ、商品価値が高まることで量に追われることがなくなるというプロセスをたどるもの。
・持つべきは、自分の身体は「元本」(元手となるお金)である、という視点。
・これからの情報化時代に求められる能力は、「知識・情報を持っている」ということよりも、その知識や情報を活用して「自分の頭で考え持論を打ち出せる」ことであると自覚すべき。
・司法試験とは、結局は、判例、学説、法理論という道具を使って、持論を構築する試験であり、その持論が法理論として整合性が取れていれば合格となる試験。
・人間関係はときとともに移り変わるものなのだから、たとえ今、人間関係に苦労していても、それも変わるものであり、悩むに足らないことだといえる。
・よく「名プレイヤーは名監督になれない」というが、それは自分が「できる人」であるがために、「できない人」の気持ちも、「できない人」がどこでつまずくのかもわからないから。「部下は自分と同じようにはできない」というのは、名プレイヤーが名監督になるための重要な心得。
・好き嫌いに影響されずに人間関係を築ける力が、社会人に求められるコミュニケーション能力。なぜなら、社会人の人間関係とは、つまり仕事の人間関係であり、そこには基本的に好き嫌いは関係ないからだ。仕事で結果を出すためには、どんな層の、どんな育ち方をした人と出会ったとしても、意思の疎通ができなければならない。
・議論の作法とは、相手に敬意を払うこと。「反論」「批判」はしても「侮辱」は絶対にしないということ。侮辱とは、相手の人格を否定したり、馬鹿にしたりすることで、これは絶対に許されるべきではない。
・耳が痛い批判、苦言、進言こそ、正面から向き合うべき。批判・苦言・進言と、侮辱は、明確に区別する。
・うだつの上がらない現状を突破するには、今までやってきた方向性を180度逆転させる行動力が必要。