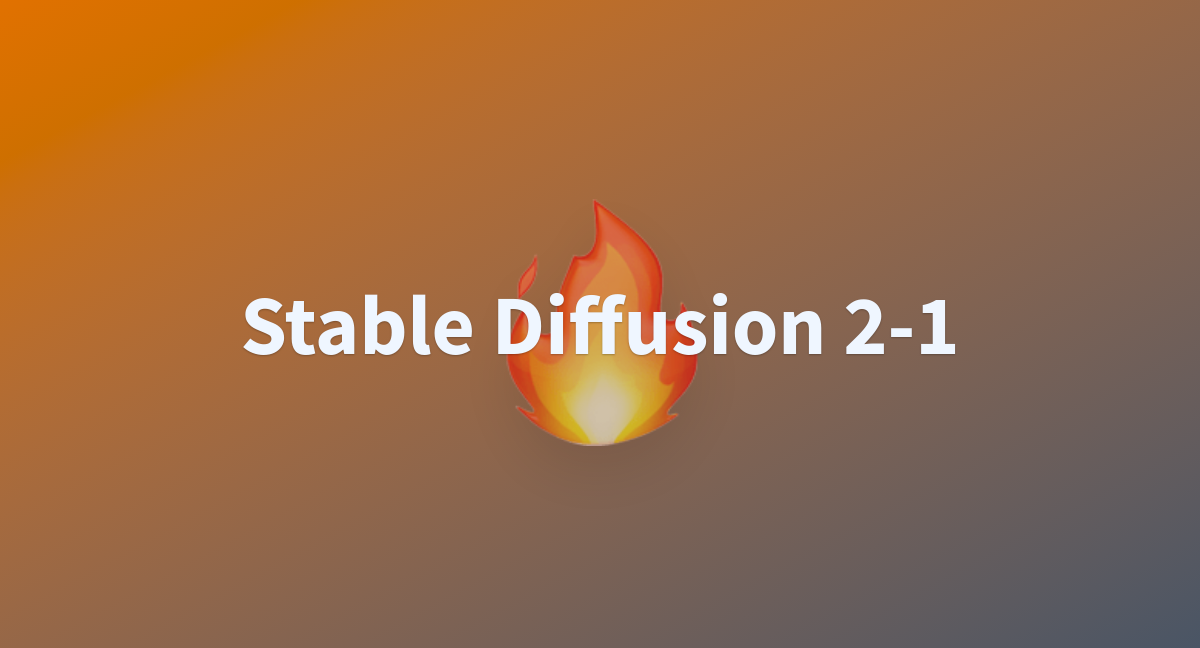どうも、ねへほもんです。
世間の潮流とは無関心で、平穏に暮らす主義者なのですが、今回の話題は自分とも関係があるため、取り上げることにしました。
法律関係とかはよく分からんので、↓の記事を前提として書きます。
1.絵とAI
最近、AIに絵を描かせるサービスが複数登場して話題になっています。
個人的には、半年前に会社の外部研修で画像認識AIの講座を受講し、「社会人生活8年で業務で画像処理なんぞしたことないわぼけぇぇぇ」とサボっていたのですが、こうも話題になると真面目に受講すれば良かったなと後悔しています。
サボりマンなので原理は詳しくないのですが、学習方法は将棋などと大して変わりません。
将棋は駒の配置に応じ、どう動かすのが有利かを9×9のマスに分けて学習するのですが、絵だとピクセル単位で細分化して、
赤赤赤赤赤赤赤紫紫紫紫紫紫青青青青青
赤赤赤赤赤赤紫紫紫紫紫紫青青青青青
赤赤赤赤赤紫紫紫紫紫紫青青青青青
赤赤赤赤紫紫紫紫紫紫青青青青青
赤赤赤紫紫紫紫紫紫青青青青青
赤赤紫紫紫紫紫紫青青青青青
赤紫紫紫紫紫紫青青青青青
のように、色の配置で絵の特徴を学習し、真似できるようになるという原理です。
機械である以上、絵であろうとピクセル単位で色という数値に置き換えているのです。
色はRedGreenBlueで256×256×256通りあって、それをピクセルの数だけデータ化して、更に絵も何千、何万枚と大量に学習させるので、膨大なデータ処理能力が必要とされますが、ゲーミングPCみたいなハイスペックなやつで、複数のピクセルを1つのデータに変換して圧縮して学習するみたいなテクを使ってこなしているらしいです。
(※ここまでの内容は大量に嘘が含まれているはずなので、詳しく知りたい方はちゃんと調べてください)
原理はさておき、要は
絵を大量に読み込ませれば、クセを覚えてAIが真似してくれる
ということです。
最近話題となったサービスのうち、試しにStable Diffusionを触ってみました。
テキストボックスに"Cyberpunk style Tokyo landscape"と入力し、"Generate image"のボタンを押すだけで、勝手に以下のようなイメージを生成してくれました。
試しにどんなサービスかを感じるだけなら、検索ワードを入力するだけですぐですので、是非試してみてください。
で、昨日から炎上している「mimic」は、絵師さんのクセを真似するというサービスです。
風景イメージをAIに作らせるだけなら、誰か特定個人に影響するような話ではありませんが、「〇〇先生っぽいキャラがAIで描けた」という話になると、特定個人の仕事が減るとか、無断で模倣して金を取る人が出るとか、トラブルになりかねないので、炎上案件になったという話です。
Stable Diffusionとかmidjourneyとか、先行サービスでも絵師の真似は出来るはずですが、mimicは絵師の真似っこを前面に押し出してしまったのが火種になった気がします。
ちなみに、文章もAIで学習させることができます。絵の方が似てるのは一目瞭然なので話題に挙がりましたが、しれっと人の文章をAIで再現させて、さも自分の作品かのように投稿することは可能なので、目立たないだけで今後じわじわ問題になるかもしれません。
2.最初はみんな不安がるもの
昨日から、Twitter上で多くの絵師さんが、
「個人・商用利用を問わず、私の絵をAI学習に利用することを禁じます」といった声明を出されています。
短期的な対応としては、至極自然なことだと思います。
Twitterで不特定多数の人の注目を集める現代、好き勝手なことを許すと、
・無断で模倣して金を取る人が出る
・裁判で訴えても、丸パクリではなく、クセを真似ただけだから法律上大丈夫と主張される
・勝手にR18仕様に変えられて品位を損ねられる
とか、トラブルが起こる可能性は容易に想像できます。
シャインマスカットが勝手に海外に持ち出されて栽培されるような時代です、世界のどこで勝手に模倣されるかも分かりません。
訴訟で通るかは分からないながらも、「声明を出したのに勝手にAI学習に利用された」と主張するためにも、宣言しておいて損は無いかと思います。
今回はオタク界隈で起こったのでTwitterを賑わせただけで、技術の進歩が既存の業務と衝突するというのはよくある話です。
AIの世界だけでも、将棋の対局中に電子機器の持ち込みが禁止されたとか、橋などの構築物の耐久テストを目視で実施する規定になっていたのを、今後ドローンカメラやAIセンサーで異常が無いかを確認する方法に変えられないかとか、自動運転で事故ったら誰の責任なのかとか、新しい問題が生まれています。
「AIで模倣された絵に対し、元の絵師がどのような権利を持つのか」
というのも、その新しい問題の1つとして、今後議論されていくのだと思います。
最初に挙げた記事によると、著作権法30条の4ではAI学習に利用できるようにしつつも、「著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではない」と記載しており、不当に害する場合って何やねんというのが論点になるのでしょうかね。
法律で「〇〇の場合が不当に害する場合です!」みたいに細かく規定すると、「じゃあ〇〇は書いてないので対象外ですか?」みたいな疑問が生まれた時に、いちいち法改正が必要となって面倒なので、どうしても曖昧な部分が残らざるを得ないです。
なので、まずは訴訟の判例として、裁判所が個々の事例に対し法解釈を当てはめていき、あまりにも似たような訴訟が多すぎて毎度法解釈するのは大変だとなった時に、法律が改正されるという流れになるのかと思います。
まずは訴訟の判例とか、mimicなどのサービスの運営会社の対応方針とか、事例を積み重ねていき、権利が不当に害されないと分かってくると、AI学習に関し絵師さん側が寛容となっていくのでは、と予想しています。
3.AIと烈火の炎
短期的な混乱は時が経てば落ち着くのでしょうが、長期的な視点でも考えておく必要があります。
つまり、
AIが絵師の仕事を奪うのか?
ということです。
未来のことは分からない以上、あらゆる職種と同様、「奪われる仕事もあれば、残る仕事もある」としか言えないでしょう。
ただ、絵師さんは依頼を受けてお金を貰って仕事をしている以上、市場原理には逆らえないと思います。
直接依頼して描いてもらうよりも、AIで模倣する方が安くて、早くて、交渉が楽となれば、そちらが優先されるのは仕方のないことです。単にモブキャラや背景を描くだけという仕事は、どんどんAIに置き換えられていくのでは、と思います。
ただ、全ての仕事が代替されることはないと思います。
AIにも限界があるのです。
普段からオタク絵に接し、時々絵画展に足を運び、数十万の絵を買ったこともある僕が、mimicの絵を見た時抱いた感想は、
「似てるね。・・・で、それがどうした?」
というものでした。
良くも悪くも似ている止まりで、その先が無いのです。
僕がオタク界隈に足を踏み入れる第一歩、幼少期に触れたFFでは、天野喜孝先生の特徴的なデザインが今見ても懐かしく、かつ個性的だと衝撃を受けます。
単に絵としてのクオリティが高いだけではなく、FFで実際に操作し、ストーリーを追体験したキャラや街のイラストを見ることで、プレイ時の記憶が呼び覚まされるという体験と繋がることで、自分にとってその絵が忘れがたいものになっているのだと思います。
後はてぃんくる先生の絵も、以前雑誌で世界観に溢れるメルヘンチックな自宅で仕事をされている様子を見たり、絵の展示イベントで実際にお会いして質問タイムなどで人柄を知ったり、そうした記憶や世界観と絵が結びついて、より好きになれるのだと思います。
「絵は真似できても、その背景となる体験や世界観までは真似できない」
それこそが、今後AIに奪われない価値となるのでは、と思います。
さっきのmimicのサービスだって、敢えてバンバン模倣してもらって知名度を高め、YouTubeの生配信に集客してトークで盛り上げるとか、生のお絵描き配信でプロの技を見せつけるとか、ファンに豊かな体験を提供することでアピールするという道もあるはずです。
単に絵を描くだけでなく、絵師自身の個性を発揮するとか、ファンと積極的な交流を図るとか、SNSやYouTubeの流行で促進されてきた潮流が、AIの到来により加速するのではないでしょうか。
この記事で書きたかったことは異常なのですが、この問題を聞いてふと思い出した話があるので締めに語らせてください。
僕の中学校で大流行していた漫画「烈火の炎」の中の一話です。
火竜の力を体に宿し、火の玉を飛ばしたり、腕から火の剣を出して斬ったりという能力を持つ烈火が、似たように火を操る敵と戦うことがありました。
敵が自分と似た能力を持つことに戸惑う烈火でしたが、突如火竜の意識に飛ばされ、次のような問いかけを受けました。
「2人の物書きが居て、お互いが1つの作品の作者は自分だと言い張っている。この場合、どうしたらどちらが本物か見破れるか。」
その時、烈火はこう答えました。
「続きを書かせれば良い」
と。
その問いかけの後、烈火は新しい火竜の力を得て、自分の言った通り今まで火竜の「続き」を見せつけることで敵に勝利しました。
(うろ覚えなので間違っていたらご一報ください)
真似されたのであれば、その続きを示し、本物であることを示せば良い。
漫画家なら続きを書くとか、絵師ならファンと交流するとか、真似っ子にはできない価値を示す。
今回は絵師の話でしたが、自分の仕事にも当てはまるんだろうな、と思います。
こういう真面目な話は久々なので疲れました。
今ホットな話題だし、ツッコミ所を与えて炎上とかしなければ良いのですが・・・
次は軽い話題にします。
では(^^)/