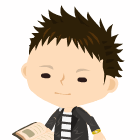今さらですが、いろんなものが値上がりしていて財布が軽いです。
先日、近所のスーパーに行ったらトマト1個が248円で、さすがにびっくりしました。
別に何か高級なトマトではなく、ふっつーのバラ売りトマトです。
でも最寄駅のビルに入っている高級スーパーでは小さなトマトが1個300円で、さらに驚き・・・。
リンゴ1個も、安さで有名な某スーパーでさえ238円くらい![]()
数年前までトマトやリンゴは1個だいたい100円くらいじゃなかったですか?
もう、倍以上。
お米も少し落ち着いたとはいえ、それでも以前の倍くらい。
おそろしい。
職場の近くの大戸屋もどんどん価格が上がり、おいしくて野菜がたくさん食べられるお気に入りだった「チキンかあさん煮定食」が990円!もう1000円目前![]()
そして、独り身でおいしい魚を食べられる貴重なメニューだった「さばの炭火焼き定食」が、とうとう1000円を超えてしまいました。
「しまほっけの炭火焼き定食」はだいぶ前から1000円を超えてしまっていて、さば定食が頼みの綱だったのに・・。
もうおいそれと食べられない![]()
1000円以下で食べられるメニューは数えるほどになってしまいました。
少し前にこんな記事を書いたのですが
日本全体が貧しくなったかはわかりませんが、自分の家計は確実に苦しくなりました。
空前の賃上げムードですが、パーセントではなく〇割で上がっている物価には全然追いついていない気がします。
でも・・・
考えてみれば当たり前ですよね。
働き手は減り、特に一次産業で減れば、構造的に食品は値上がりする。
モノづくりの現場から遠く離れているはずの都会で、モノがこんなに安く買えるのがおかしいのかもしれません。
一方で技術やサービスはどんどん進化し、そこに社会全体のコストがかかってしまう。
スマホは食べられないし、AIは着られないのに、社会は莫大なコストを投入する。
衣料品などは国産を手にすることすらほとんどない状態ですが、外国製品が安いのはその国の物価水準が低いから。
その国が日本の水準に追い付いてくれば、価格も上がる。
そうした国は単に時間的にスタートが日本より遅かっただけで、日本はその時間差をたまたま利用できたため、モノの豊かさを享受できたのかもしれません。